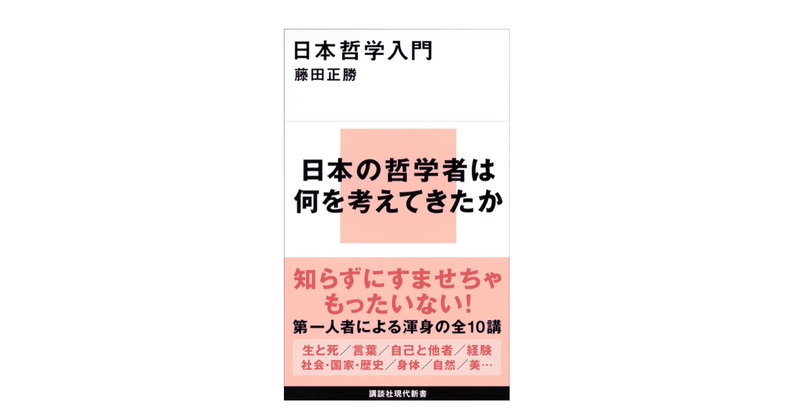
藤田正勝『日本哲学入門』
☆mediopos3366 2024.2.4
日本で最初の哲学の講義は西周によるもので
明治維新後の一八七〇年(明治三年)から
「育英舎」と呼ばれた私塾において
「百学連関」(Encyclopedia/百科全書の訳)という題目で
おこなわれたものだが
そこでは哲学だけではなく
学問全体にわたって説かれ
「致知学」(Logic/論理学)や「理体学」(Ontology/存在論)
をはじめとした哲学の諸領域や哲学史なども講義されたという
上記は日本語による明治維新後の哲学講義の始まりだが
一五八三年(天正十一年)に豊後の府内に設立された
イエズス会士の高等教育機関であるコレジオにおいて
人文課程を終えた神学生に対して哲学課程の講義がなされた
というキリシタン研究における資料があるとのこと
とはいえその講義はラテン語で行われ
しかもその講義はポルトガル人の神学生五名を
対象として行われたものなので
日本での哲学講義の始まりとはいえないかもしれないが・・・
その四百四十年余り前の哲学講義は別として
実質的に日本で哲学が講義されはじめてから約百五十年ほど経つ
かつて日本に哲学があるのか
日本の哲学というのは哲学といえるものなのか
といった議論がなされたこともあったが
(いまでもそういう議論はあるかもしれないが)
「世界哲学」ということがいわれはじめてから
(ちくま新書『世界哲学史』が刊行されたはじめたのが二〇二〇年)
その視点がふまえられながら「日本哲学」が
ようやくその全体として論じられはじめている
「世界哲学」という視点は
ギリシアの哲学からはじめる西欧の哲学こそ「哲学」である
というものではなく
「ギリシアの哲学もフランスの哲学もドイツの哲学も、
それぞれの言語を用いてそれぞれの文化・伝承の枠のなかで
なされる営み」であるという視点である
「日本の哲学」もその意味において位置づけることができる
本書では日本の哲学の歴史を辿るというのではなく
「①「経験」、②「言葉」、③「自己と他者」、④「身体」、
⑤「社会・国家・歴史」、⑥「自然」、⑦「美」、⑧「生と死」
という八つのテーマ」で「それぞれの問題をめぐって
日本の哲学者たちがどのような思索を重ねてきたのか、
そこにどのような特徴があるのかを見ていく」ものだ
コンパクトにまとめられてはいるが
どの項目もそれぞれのテーマが明確に論じられている
それぞれのテーマについては
あらためて見ていきたいと思っているが
日本の哲学者の思索の根底にあるものについて
藤田正勝はこう示唆している
「物事を正確に把握するために、私たちは、対象を固定し、
それを要素に分け、構造を明らかにしようとする。
その操作が学問には必須であることは言うまでもない。
しかし、そのように見る私と見られる対象とを分離し、
分離された対象を固定し、分割することで、
物事はほんとうに把握されるのだろうか
という問いもまた生まれてくる。
多くの日本の哲学者の思索の根底には、(・・・)
「知」の意義はもちろん認めつつ、その根源に立ち返って、
そこからあらためて「知」の成立を見直してみたい
という考えがあったように思われる。」
「西洋の哲学においてはたいていの場合、
知から身体や欲望、感情などが排除され
「その影響を取り除くことで知が知として成立すると考えられた」が
「日本の哲学者においては、知は身体や感情、
さらに行為と深く関わっている」と考える傾向があるのである
九鬼周造が『「いき」の構造』において
「生きた哲学は現実を理解し得るものでなくてはならぬ」
と記しているように
「哲学は論理の世界に閉じこもるのではなく、
現実に関わり、その脈動に触れなければならない。
そのことによって哲学ははじめて「生きた哲学」でありうる」
ということが日本の哲学が目指してきたものではないか・・・
そのためには
「変わらずにありつづけるもの、自己同一性を保持するものこそ
「ある」といえるものだという固定した観念」を問いなおし
「動いてやまないもの、変化してやまない」物事を
「その「動性」においてとらえることこそが必要」なのだが
往々にしてコンクリートブロックのように
固定化され記号化された概念や定義にしばられ
そのなかで議論がなされたりもする
そうしたありかたでは
「日本語」そしての文化・伝承という特性が生かされないまま
西欧の論理主義の猿まねに堕してしまうことにもなりかねない
「○○の哲学」というようにそれぞれの視点でしか
とらえることのむずかしい視点から学ぶためにも
私たちは「日本の哲学」でしか得られないだろう視点を
見直してみることが求められている
さらにいえば(かなり唐突になるが)
地球における人間の哲学をさえ離れた
○○の哲学という視点があるとすれば
そこから学ぶということもあり得るのかもしれない
■藤田正勝『日本哲学入門』
(講談社現代新書 講談社 2024/1)
*(「はじめに」より)
「本書では、日本の哲学の歩みを明治の初めから現代まで時間軸に沿って見ていくのではなく、①「経験」、②「言葉」、③「自己と他者」、④「身体」、⑤「社会・国家・歴史」、⑥「自然」、⑦「美」、⑧「生と死」という八つのテーマを設定し、それぞれの問題をめぐって日本の哲学者たちがどのような思索を重ねてきたのか、そこにどのような特徴があるのかを見ていくことにしたい。」
「そもそも日本の哲学を学ぶ意義はいったいどこにあるのだおるか。それを知ることで何を獲ることができるのであろうか。そのような疑問を抱く人もいるかもしれない。
(・・・)
たしかに哲学は、その成立以来、普遍的な原理の探求をめざしてきた。しかし普遍的な原理の探求であることは、ただちに使用される言語の制約から自由であることを意味しない。私たちの思索は、私たちの文化・伝承の枠のなかでなされるのであり、一つ一つのことばのズレ、その集積としてのものの見方や文化そのものの差異が、「真なる知」を問う問い方、答えの求め方に影響を及ぼさないとは、どうてい考えられない。
ギリシアの哲学と、それを受け継ぐヨーロッパの哲学こそが唯一の哲学であるという考え方もあるが、私はギリシアの哲学もフランスの哲学もドイツの哲学も、それぞれの言語を用いてそれぞれの文化・伝承の枠のなかでなされる営みであり、その制約から自由ではないと考えている。
どのような問題について論じるのであれ、それぞれの長い歴史のなかで形づくられてきた自然や神、人間や歴史をめぐる理解を踏まえて答えが探求されていくのであり、そうした前提からまったく離れた————言わば無菌の————時空間のなかで思索がなされるわけではない。
私たちの知は、つねにその視点からは見えないもの、あるいはその視点設定のゆえに覆い隠されるものが生まれる。そのとき重要なのは、異なった見方を否定したり、排除したりすることではなく、それと対話することである。
日本の哲学はその対話に大きな寄与をすることができる。伝統を背負いながら、自ら主体的に思索するからこそ、他の文化・伝統のなかで成立した哲学と対話することができるし、哲学のより豊かな発展の可能性を見いだしていくことができる。」
*(「おわりに」より)
「古代ギリシアの哲学者アリストテレスもその主著『形而上学』の冒頭で、「人間はすべて、生まれつき知ることを欲する」と述べているが、私たちには何かを知りたいという欲求がある。その欲求が私たちの日々の生活の根底にある。そして私たちは知を積み上げ、学問を作りあげてきた。何かを知るために求められるのは、私たちの思い込みや偏った見方を排除し、物を物として見ることである。見る私とみられる対象、主観と客観との分離がその前提となる。その上で対象をできるだけ正確に把握することが学問成立の条件となる。
物事を正確に把握するために、私たちは、対象を固定し、それを要素に分け、構造を明らかにしようとする。その操作が学問には必須であることは言うまでもない。しかし、そのように見る私と見られる対象とを分離し、分離された対象を固定し、分割することで、物事はほんとうに把握されるのだろうかという問いもまた生まれてくる。
多くの日本の哲学者の思索の根底には、このような問いがあったと言ってよいのではないだろうか。「知」の意義はもちろん認めつつ、その根源に立ち返って、そこからあらためて「知」の成立を見直してみたいという考えがあったように思われる。
というのも物事は動いてやまないもの、変化してやまないものだからである。私たちには、変わらずにありつづけるもの、自己同一性を保持するものこそ「ある」といえるものだという固定した観念があるが、はたしてそうであろうか。目の前にある樹木にせよ、「自由」といった概念にせよ、「私」というものにせよ、変わらずにありつづけるものであろうか。時間とともに変化し、違った層を見せるのではないだろうか。その変化するものを固定化し、分割することには意味があるが、しかしそのことによって私たちは物事をとらえそこなっているのではないか。むしろ固定化し、分割する以前の事柄そのもの、現前しているものそのものに立ち返り、それをその「動性」においてとらえることこそが必要なのではないか。そこからあらためて「知」の意義を考える必要があるのではないか。このような発想が多くの日本の哲学者の思索の根底にあったように思われる。
「知」を「知」の形でそのまま受け入れるではなく、その成立以前に立ち返って理解りようという思索の徹底性、あるいは根源性とも言うべきものがそこにはあった、あるいはあるように思われる。
この現前するものにおいては、見るものと見られるものの区別はない。むしろ両者は一体である。第3講で使ったことばで言えば、事柄は単なる「もの」ではなく、むしろ「こと」としてとらえることができる。たとえば野に咲くスミレを美しいと思い、ウグイスの声を心地よいと感じるとき、そこにあるのは単なる「もの」ではない。私が美しいと思い、心地よいと感じるという「こと」がそこにはある。
そこで私たちが経験しているのは、私から区別されたある「もの」の変化や運動が、やはり一つの「もの」と考えられる私に何らかの刺激を与えたということではない。そこにはスミレを美しいと思い、ウグイスの声を心地良いと感じるという「こと」だけがある。そこでは見る私とみられる花との区別はない。
「こと」において重要なのは、「こと」がさまざまなやすらぎや喜びを感じる。それが生きる意欲につながっていく。私たちから区別された「もの」にはそうした表情がない。しかし私たちの具体的な経験のなかでは、「もの」は単なる物体としてではなく、そうした表情をもったものとして現前している。この具体的な経験のなかに現前しているリアリティから出発し、そこから「知」がいかに成立してくるのか見ていこうという意図が、日本の哲学者の思索のなかに見てとれるように思われる。
それは日本の哲学者の思索のなかでしばしば知が行為と、理論が実践と深く結びついたものとして意識されていたことにも関わっている。
西洋の哲学においてはたいていの場合、知から身体や欲望、感情などが排除された。その影響を取り除くことで知が知として成立すると考えられた。しかし多くの日本の哲学者においては、知は身体や感情、さらに行為と深く関わっていると考えられている。
たとえば西谷啓治は「行ということ」と題した論考のなかで、私たちの知が本質的に、対象だけに向けられたものではなく、自己自身を知ることに、したがってまた自己自身が内から変化していくことに結びついていることを、つまり知が「全身心的な」ものであることを主張している。湯浅泰雄もまた、東洋思想と西洋の哲学とを比較したときに前者に見いだされる特質として、知が自己の身心全体による「体得」ないし「体認」を通して把握されるものとしてとらえられている点を挙げている。東洋の伝統的な思想で「修行」が重視されたのもそのことに関わっている。
本書では詳しく述べることができなかったが、九鬼周造は一九三〇年に発表した『「いき」の構造』という著作の「序」で、「生きた哲学は現実を理解し得るものでなくてはならぬ」ということばを記している。哲学は論理の世界に閉じこもるのではなく、現実に関わり、その脈動に触れなければならない。そのことによって哲学ははじめて「生きた哲学」でありうるということを述べた文章であるが、日本の哲学の特徴をよくとらえたことばでもあり、日本の哲学が目標とすべきものをよく示したことばであると思う。
以上で見たような、生きた現実に迫ろうとする姿勢、つまり、ものごとを固定したものとしてとらえるのではなく、絶えず変化するものとしてとらえ、そこにどこまでも迫っていこうとする姿勢、既存の「知」の枠組みを超えて、さらにその根源へと迫っていこうとする姿勢、知を単なる知としてではなく、つねに実践と深く結びついたものとしてとらえるものの見方は、過去の哲学者のなかだけに見いだされるものではなく。いまの時代を生きる私たちのなかにも息づいているように思う。それを眠ったものにせず、日々の生活のなかで考え、行動する糧にすることがいま求められているのではないだろうか。」
*****
「日本の哲学(・・・)の意義はどこにあるであろうか。たとえば第1講で述べた「世界哲学」への貢献ということが考えられるであろう。
そこで述べたように、「世界哲学」とはさまざまな哲学の営みを統合した唯一の「哲学」を指すのではない。それぞれの文化の伝統のなかで成立した哲学のあいだでなされる対話の営み、あるいはこの対話がなされる場所を指す。以上で述べたような特徴をもった哲学として日本の哲学はその対話の場所でさまざまな貢献を行いうるのではないかと私は考えている。」
【目次】
はじめに
第1講「日本の哲学」とは
第2講 哲学の受容
第3講 経験
第4講 言葉
第5講 自己と他者
第6講 身体
第7講 社会・国家・歴史
第8講 自然
第9講 美
第10講 生と死
おわりに
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
