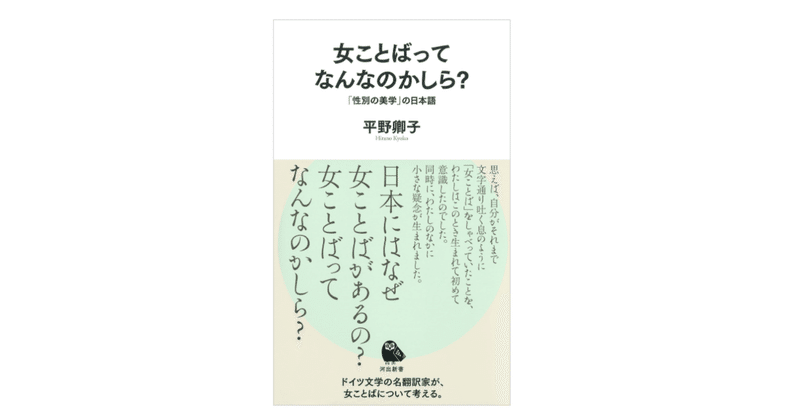
平野卿子『女ことばってなんなのかしら?/「性別の美学」の日本語』
☆mediopos-3158 2023.7.11
mediopos-3155(2023.7.8)で
友田健太郎『自称詞〈僕〉の歴史』をとりあげたが
おなじ河出新書に「女ことば」について書かれた
平野卿子『女ことばってなんなのかしら?』がある
著者はドイツ語翻訳家であり
「女ことば」のないドイツ語を日本語に訳すとき
その違いを意識しないわけにはいかない
西欧語に「女ことば」がないからといって
性差やそれに伴う差別がそこに存在しないわけではなく
名詞に性があったり
三人称の性別で動詞の形が変わったりと
別の形で「性差の呪縛」は存在している
「女ことば」は
古くから存在しているように思われがちだが
たとえば「だわ」「のよ」といった言葉づかいは
明治時代の「女学生のはやり言葉」で
そのときには「下品で乱れた言葉」だとされていた
それが朝鮮半島や台湾などの植民地での同化政策の際
女らしさの表現とされるようになったという
戦後もそうした女ことばが称賛されることとなり
それが「日本女性は丁寧で控えめで、上品だという
「女らしさ」と結びつけられ、
「女ならば女言葉を使うはずだ」という意識」が生まれた
そうした歴史的経緯は知っておく必要があるし
それがある種の「性差の呪縛」につながり得ることに
意識的である必要はあるだろう
個人的にも「女ことば」が強調されるのは
どこか不自然な感じがしてあまり好きではない
男女問わず丁寧語をベースに話しながら
必要に応じて謙譲語や敬語を織り交ぜて話すのが
いいのではないかと思うのだが
差異が差別につながらないのであれば
「使いたい人は使う、使いたくない人は使わない」
というのが基本ではあるだろう
ことばには歴史が刻まれている
そこには否応なく性別の差異や
それに伴う差別意識なども刻まれてきているが
それらをすべて中立的なことばに
人工的に置き換えていくことはできないだろう
重要なのは「性差の呪縛」という魔法から
じぶんを解き放つべく意識的であることだと思われる
■平野卿子『女ことばってなんなのかしら?/「性別の美学」の日本語』
(河出新書 063 河出書房新社 2023/5)
(「はじめに」より)
「『性別の美学』は、日地谷=キルシュネライトが日本の女性作家たちと対談した記録『〈女流〉放談————昭和を生きた女性作家たち』に収録されたもので、そのなかで彼女は、かつて日本で暮らしたときに味わった困惑について次のように回想しています。
日本に来て日々驚かされたのは、日本社会においては人々の行動規範や自己理解や世界観が当たり前のように性別の違いによって区別され、美学化されている様子であった。
このような日本人独特の意識・価値観を、日地谷=キルシュネライトは「性別の美学」と名づけました。でも・・・・・・彼女の困惑はこのときが初めてだったのでしょうか。いや、ずっと以前、日本語を学び始めたときにそれはすでに始まっていました・・・・・・ほかでもない「女ことば」の存在です。
長い間、なぜ、私は、クラスメートの男子と同じように「腹が減った」とは言えずに、「お腹が空いたわ」と女性用のやわらかい表現を使わなければならないのか、理由がまるで分からなかったのだ。
この論考に触発され、わたしはかつて自分の大きな関心事であり、いまも変わらず使っている女ことばについて、その歴史的背景をも含めてじっくり考えてみたいと思うようになりました。たしかに西洋には日本のような形での女ことばは存在しません。ですから、日地谷=キルシュネライトの気持ちはとてもよくわかります。けれども、(・・・)女性らしい話し方を強いられるのは日本だけの現象ではないのもまた事実なのです。」
(「第一章 女ことばは「性別の美学」の申し子」より)
「日本での経験を通して、日地谷=キルシュネライトはこの国に女ことばが存在する理由を理解し、やがて次のように思うに至ります。
「性差」というカテゴリーは、やはりここにおいても重要な、いやむしろ決定的とも言える基準であり、日本語を形成している他の重要な特徴である「年齢」や「社会的階級・上限関係」などと比較しても、より絶対的な要素であるといえるかもしれない。
そして、この論考を次のように締めくくります。
当たり前のように男性と女性を区別する発想は、日本の文化の中に深く根を下ろしている。それだけに、男女を区別しようとする発想を克服することは、日本社会にとってはひときわ困難なのではないかと考えずにはいられない。
(・・・)
しかし・・・・・・彼女があえてそこに「美学」というポジティヴな表現を与えたところに、この問題が一筋縄ではいかないこと、「克服することは日本社会にとってひときわ困難」だと結論づけた理由を見ることができるのです。」
「一般に女ことばと考えられているのは、次のようなことば遣いです。
・特有の終助詞(「のよ」「わ」「かしら」「わよ」)を使う
・なまった母音(「うるせえ」「知らねえ」など)を使わない
・卑語や罵倒後(「尻(ケツ)「畜生」など)を使わない
・接頭語「お」をつける(「お砂糖」「お花」など)
・感動詞は「まあ」「あら」など
・敬語をよく使う
女ことばは、古くから伝えられてきた日本の伝統のようにいわれてきました。でも、ほんとうにそうなのでしょうか。この点について、言語学者の中村桃子は次のように語っています(「朝日新聞」二〇二一年一一月一三日)。
いま、私たちが「女言葉」と認識している「だわ」「のよ」といった言葉づかいの起源は、明治時代の女学生の話し言葉です。ただ、当時は正しい日本語とは扱われず「良妻賢母には似合わない」「下品で乱れた言葉」だと、さんざん非難されていたのです。女言葉が正当な日本語に位置づけられたのは、朝鮮半島や台湾などの植民地でとられた同化政策の中でのことです。「女と男で異なる言葉遣いをする」のが日本語のすばらしさであるとされ、多様な言葉づかいの一部だけを「女言葉として語る」ことで、概念が生み出されました。
戦後は日本のプライドを取り戻すため、女言葉はさらに称賛されるようになります。その中で、「女学生のはやり言葉」だったはずが、起源を捏造され、「山の手の中流以上の良家のお嬢様の言葉」だったと喧伝されるようになります。日本女性は丁寧で控えめで、上品だという「女らしさ」と結びつけられ、「女ならば女言葉を使うはずだ」という意識も生まれました。
この話から、世間で女ことばだといわれているものが、日本の伝統ではないどころか、為政者の都合によって推奨され、広まったものだということがわかります。中村によれば「そのとき、はじめから標準語の定義にかなった女性の言葉だけが取り入れられた」ため、女ことばは標準語だけに存在するのです(『女ことばと日本語』)。
「西洋諸国が「カップル社会」なら、日本はさしずめ「男女棲み分け社会」といえるでしょう。けれども根底にある考えは同じです。どちらにも「女は愚かで弱い」という大前提があり、それが西洋では「だから、俺のそばを離れるな」となり、日本では「だから、ひっこんでろ」となっただけのこと。」
(「第二章 人称と性」より)
「性差がことばに表れているといえば、日本語にはもうひとつ重要なものがあります。それはバイナリーな一人称。
バイナリーとは、人間を生物的に女と男の二つに振り分ける立場のことで、日本語の一人称は「わたし(私〕」を除けば、性別により使い分けがはっきりしています。
これは日本語の大きな特徴です。」
「自分を僕という女の子、いわゆる「僕っ娘」が現れてからすでに長い年月が経っています(・・・)。自分のことを「僕」というわけは主として二つあるように思います。
ひとつは女らしさの規範かた脱して「男の子のように生きたい」という気持ち、もうひとつは「少女」から「女」への移行に対する恐れやためらいです。もっとも、この二つは厳密に分けられるものではなく、多くの場合分かちがたく結びついているといえます。」
「西洋人にとって一人称がひとつしかないことはまったく問題がないのでしょうか。
半世紀以上も前のこと。ドイツで暮らして半年ほどたったある晩、遠距離恋愛で悩んでいた友人のモニカがいいました。
「だから、自分にいったのよね、わたし。『モニカ、あなた(du)もっとしかりしなくちゃ』って」
このときはじめてわたしが、ドイツ語では自分のことをいうのに二人称を使う場合があることを知ったのでした(英語も同じ)。自分を他者としてながめて言い聞かせるのだ、と。」
「英語をはじめとする西洋語では、三人称単数代名詞はバイナリーであり、いちいち性を特定しなければなりません。このため、ノンバイナリーな性自認の人を指す三人称単数代名詞として、英語では「they」を使う動きが広がっています。動詞はそのまま「are」です。
文法的におかしいと感じる人もいるかもしれませんが、二人称の「you」も単数複数ともに動詞は「are」ですね。」
「そもそも、日本語の三人称は「彼」だけでした。森鴎外が「舞姫」で、踊り子エリスを一貫して「彼」と記しています。女性の三人称として「彼女」という訳語を作ったところに、男性優位の思想が現れているといえます。男は基本形(彼)で、女はその派生形だからです。
明治以降の西洋語の影響による日本語のめまぐるしい変貌を思うと、「彼女」「彼」がそんなに使われていないのはいささか意外な気がしますが、明治以降に生まれたこれらの三人称に、わたしたち日本人はいまでも心のどこかでなじめないものを感じているのかもしれません。」
(「第三章 日本語ってどんなことば?」より)
「日本語の特性について、ごく簡単にふり返ってみましょう。
まず、「主語がないとは、誰がやったのかいいたがらないことに、
「主観的」とは、事実より、自分はどう思ったかについて語りたがることに、
「遠回しに拒絶する」とは、はっきりものをいいやがらないことに、
「受け身が好き」とは、自分がやったのではなく、相手のせいだといいたがることに、
「自動詞が好き」とは、自分がやったのではなく、自然にそうなったといいたがることに、
「罵倒語や悪態が少ない」とは、品のないことばを使いたがらないことに、
それぞれつながります。
こうしてみてくると、日本語って、世間で「女性的」だとされてきた話し方に似ていると思いませんか。正確に言えば、「女性的だとされ、批判されてきた」特性を持つことばなのです。必ず主語を入れ、他動詞と能動文を好み、因果関係を明確に示そうとする西洋語とは、まさに対照的だといえるでしょう。
けれども、穏やかで丁寧ないっぽうで、日本語は権威主義的で差別的な一面を持っている言語でもあります。
なせか。それは、敬語が非常に発達していることもあって、いつでも、何気ない会話でも、相手との上限関係や年齢差による自分の立ち位置を意識せずにいられないから。さらに、物心つくかつかないうちに自分の性をいやおうなしに意識させられ、そのことが、その後の人生を陰に陽に規定するからです。」
(「第六章 女を縛る魔法のことば」より)
「「女らしさ」と「男らしさ」は一見対応しているように見えますが、その実意味合いが微妙に違います。含みのある「女らしさ」とは違い、「男らしさ」は、無条件に褒めことばなので、女らしさは過剰なときに、男らしさは足りないときに批判されるのです。」
(「第七章 女ことばは生き残るか」より)
「今後ますます使われなくなっていくと思われる女ことば。はたして女ことばが生き残るのか。
結論からいえば、なくなることはないと、わたしは思います。
その理由の一番大きなものは、言語学者金水敏のいう「役割語」としての働きです。「役割語」とは、特定の人物像(年齢、性別、職業、階層、時代など)うぃ思い浮かべることができる言葉遣いのこと。
女ことばはその代表的なもので、ほかに老人ことば「わし・・・・・・じゃよ」「・・・・・・でのう」、少年ことば「僕、・・・・・・なんだとよ」、男ことば「俺は・・・・・・だぜ」、方言「おら・・・・・・だべ」などがあります。
ただし、役割語は実際につかわれている(た)というより「それらしく聞こえる」いわばお約束の記号、虚構のことばであることが多い」。
「ここでひとつはっきりさせておきたいのは、日本語オリジナル・翻訳を問わず、女ことばがふさわしい場合があることです。
そもそも女ことばとは「女は丁寧で上品なことばを使うべき」という理念によって作られたものです。いいかえれば、そのような価値観が大手を振っていた時代の女性の発言なら女ことばがふさわしいことになります。
まずは時代背景です。」
「西洋語には「女ことば」はないという意見もありますが、翻訳はあくまでも「日本語で表現するとしたら」が原点です。たとえば、初対面の相手には日本では敬語を使うのが基本ですから、そういう場面ではたとえ原文がフラットな文章でも、敬語で訳すことが多いでしょう。」
「本書を閉じるにあたって、わたしは自分に問いかけてみました。日常の話ことばとしての女ことばは早晩消えていくだろう。わたしはそれを寂しいと思っているのだろうか。いや。なぜって、わたしはいま多くの女性たちが話している「中立語」を簡潔で気持ちがいいと思っているから。なんであれ、女と男を徒に「区別」しているものが、この国から減っていくことはわたしの心からの願いだから。
生粋の女ことば話者であるわたしは、これからも女ことばを使い続けます。そのことに少しも抵抗感はありません。(・・・)
女なのだから女ことばで話すようにと強制されることは、さすがにもうないでしょう。(・・・)使いたい人は使う、使いたくない人は使わない、それだけのことです。」
◎平野卿子
1945年、神奈川県生まれ。翻訳家。お茶の水女子大学卒。テュービンゲン大学留学。メアス『キャプテン・ブルーベアの13と1/2の人生』でレッシング翻訳賞を受賞。訳書にマン『トーニオ・クレーガー』他多数。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
