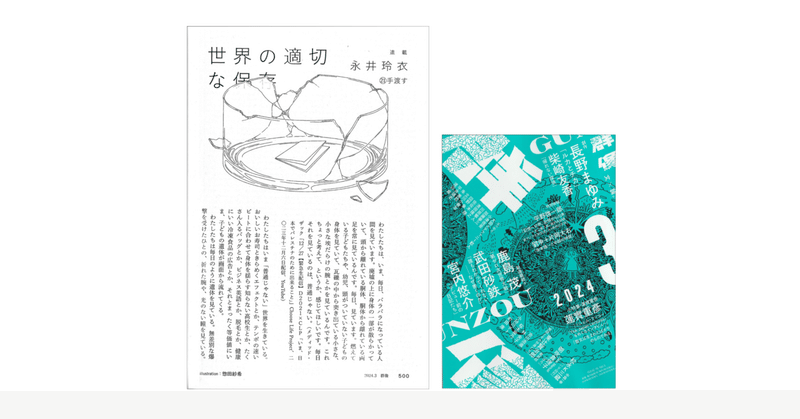
永井玲衣「世界の適切な保存㉑手渡す」(群像2024年3月号)
☆mediopos3371 2024.2.9
「わたしたちはいま
「普通じゃない」世界を生きている。」
永井玲衣はガザで起こっている現実の前で
「暗記は忘却である。」という
「わたしは「普通じゃない」毎日を過ごす前から、
パレスチナのことを暗記していた。
オスロ合意のなされた年号を、バルフォア宣言を、
ハマスを、暗記していた。
だがそれは適切な保存ではなかった。
頭の中に、置き去りにされてさえいなかった。
暗記することで、わたしは忘却した。
わたしたちは、忘却した。」
事はパレスチナだけのことではない
ウクライナのことはいうまでもなく
いまアメリカが分断されようとしていることなど
世界で起こっているさまざまなこと
さらにこの日本における
能登半島地震のような災害のみならず
戦争による死者をはるかに超えるような
ワクチン薬害による膨大な死者を前にしながら
知らぬ顔をしつづける政治家や官僚たちなど
さまざまな「普通じゃない」ことの前で
いやその渦中においてさえ
それらを「忘却」しようとしている
「忘却されているのは、感じることだ。
普通ではないと感じることだ。
埃まみれの小さな腕が、転がっていると感じることだ。」
というように
すでにいまはもう感じられないような
「記憶」あるいはデータが
<不適切に>保存あるいは消去されている
その感情はすでに死んでいる
生きてはいない
「感じること」だけではない
私たちは「考えること」についても
多くのばあい「いま考えている」のではなく
ただ過去暗記したものをアウトプットしている
その思考もすでに死んでいる
生きてはいない
生きた感情が
いままさに生まれながら
それを感受するものであるように
生きた思考も
いままさに生まれ
それを考えていることにほかならない
それはデータを使うことで
いわゆるエビデンスを示すことで
明らかにされるようなものではない
データはすでに死んでいる
しかも多くのばあい
データには多くのバイアスがかかり
都合のいい結果にむすびつけられている
どんなに当たり前に思える考えでも
かつて考えたことの「暗記」的な記憶と
いままさに生み出されているものとは
まったく異なっている
そして生きた思考は
生きた感情がともなってはじめて
あるいは
生きた感情は
生きた思考がともなってはじめて
いままさに生まれている
「適切な保存とは、それが生きたまま
手渡されることまで含むのかもしれない。」
と永井氏はいう
「生きたまま」ということは
そうした生きた感情・生きた思考を
ということだろう
私たちは日々
みずからの感情と思考が
死んだものになってしまっていないか
常に問い続けていなければならないのではないか
そうでなければ
実際に直面していているときでさえ
すべては「忘却」されてしまうから
そしてそれはまさに現在のような
「普通じゃない」世界にかぎらないだろう
私たちが「普通」だと思い
日々生きている世界も同じである
■永井玲衣「世界の適切な保存㉑手渡す」
(群像2024年3月号)
*「 わたしたちは、いま、毎日、バラバラになっている人間を見ています。廃墟の上に身体の一部が散らかっていて、頭から離れている胴体、胴体から離れている両足を常に見ているんです。毎日、見ています。燃えている子どもたちや、幼児、頭がついていない子どもの身体を見ていて、瓦礫の中から突き出ている小さな、小さな埃だらけの腕とかを見ているんです。これちょっと考えて、というか、感じてほしいです。毎日それを見ているのは、普通じゃない。(メディット・ザック「12/27【緊急配信】D2021×CLF「いま、日本でパレスチナのために出来ること」Choose Life Project、二〇二三年十二月六日配信、YouTube)
わたしたちはいま「普通じゃない」世界を生きている。おいしいお寿司ときらめくエフェクトとか、テンポの速いビートに合わせて身体を揺らす知らない高校生とか、たくさん入るバッグとか、ビジネス英語とか、脱毛とか、健康にいい冷凍食品の広告とか、それとまったく等価値にいま、子どもたちの遺体が画面から流れてくる。
わたしたちは毎日のように遺体を見ている。無差別な爆撃を受けたひとの、折れた腕や、光のない瞳を見ている。これは、普通じゃない。それが、カップ麺のアレンジレシピや、芸能人の噂まとめ投稿と、まるで同じ重さを持つように、並んでいる。これは、普通じゃない。
そして同じように、イスラエル軍の若い兵士が、ガザに生きるひとびとが住んでいた場所ではしゃぎまわったり、銃を振り回してダンスを踊ったり、金庫をこじ開けたりしている動画が、つるつると流れてくる。
人間なんて、世界なんて、しょせんそんなものだ、イスラエルによるパレスチナ占領が、パレスチナ人の虐殺が、そして長年にわたる世界の黙殺がある前から、世界はそうだったとあなたは言うだろうか。だが、構造を理解することは、現状を肯定することではない。やはりこれは、普通じゃない。確かめるように、摩耗していく心に言い聞かせるように、言う。これは、普通じゃない。」
*「 ガザは実験場です。
二〇〇七年当時で百五十万人以上の人間を狭い場所に閉じ込めて、経済基盤を破壊して、ライフラインは最低限しか供給せず、命を繋ぐのがやっとという状況にとどめておいて、何年かに一度大規模に殺戮し、社会インフラを破壊し、そういうことを十六年間続けた時、世界はこれに対してどうするのかという実験です。
そして、分かったこと————世界は何もしない。(岡真理『ガザとは何か————パレスチナを知るための緊急講義』大和書房、二〇二三年、一四二ページ)
岡真理さんは、これを「恥知らずの忘却」とあらわす。こうして忘却を繰り返すことによって、今回のガザでのジェノサイドを整えてきたと。」
*「暗記は忘却である。わたしは「普通じゃない」毎日を過ごす前から、パレスチナのことを暗記していた。オスロ合意のなされた年号を、バルフォア宣言を、ハマスを、暗記していた。だがそれは適切な保存ではなかった。頭の中に、置き去りにされてさえいなかった。暗記することで、わたしは忘却した。わたしたちは、忘却した。
私が最後に言いたい重要なことは、「感情を忘れないこと」です。感じるということを忘れないでほしいです。毎日毎分毎秒、私たちが今おかれている、この悲惨な状況や映像に触れても、人間性を忘れないでほしいです。(ハニン・シアム「【緊急配信】D2021×CLF「ガザで一体何が起きているか————民族浄化とは何か————」Choose Life Project、二〇二三年十二月六日配信、YouTube)
配信の中で、ガザ出身のハニンさんが、ガザで命をおびやかされているいとこのメッセージを読み上げたあとに、そう言った。
忘却されているのは、感じることだ。普通ではないと感じることだ。埃まみれの小さな腕が、転がっていると感じることだ。」
*「だが、わたしたちには言葉が足りない。あなりにも足りないと思う。悲しい、という言葉さえ、出てこようとして、頭を引っ込める。そうではない。そうあらわすのではないと思ってしまう。言葉は、わたしたちの感情をせおうことができず、からからに乾いた言葉がそこらじゅうにちらばっている。
わたし自身も、ここ数ヶ月何も書く気が起きない。言葉が出てこない。何もかもが違うと感じる。その違うと感じることもまた、違うと感じる。わたしは言葉を必要としている。
ハマースと名付けた者たちを非人間化する言葉が氾濫する中で、パレスチナ人が人間であるということを私たちが理解するために、私たちは文学を、文学の言葉を必要としています。文学は、人間にヒュー何ティを取りもどさせます。
誤解しないでください。文学によって人間性を取り戻すのはパレスチナ人ではありません。私たちです。
パレスチナ人が私たちと同じ人間である、それは当たり前のことです。[・・・]そのことを私たちが理解することによって、私たち自身が人間になります。(岡『ガザとは何か』四五ページ)」
他者の言葉を食べるように読み、パレスチナ人の詩を目にうつし、わたしたちが人間になろうとする。パレスチナについて倦怠感しか感じることになかった学生のわやたしが、人間になろうとする。
自分を突き飛ばすようにして、書く。言葉をさがす。言葉と生きることを手放さないように決めたひとは、書かねばならない。それは、書けないということを書くことなのかもしれない。だが、それでも書く。」
*「適切な保存とは、それが生きたまま手渡されることまで含むのかもしれない。秘密の鍵のかかった部屋で、ガラスケースの中にしまいこみ、上から布をかけてしまうことではない。
言葉とはつねに他者に向けて手渡されるものだ。その意味で、言葉を手放してはいけない。言葉を失ったとしても、言葉をあきらめないことをつづけなければならない。普通じゃない、普通じゃない、これは富裕じゃない。普通とは何か? という、問いではなく集中力を霧散させてしまうような誘惑と闘って、この感情を適切に保存しながら、手渡していくことをあきらめない。
そして同時に、わたしが人間であろうとするために、適切に保存されなければならないことがある。それは、わたしたちの忘却である。無邪気な残酷さである。
(・・・)
見ようとしてこなかった無邪気さや、「めんどういな」としか思わなかった貧しさ。その無機的で、かわいていて、つるつるした心のかたむきを、保存する。そのような心があり、これからもあり、まだあることもまた。保存する。これは言葉にされ、手渡される。情けなくうなだれ、居心地の悪さを感じながら、手渡される。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
