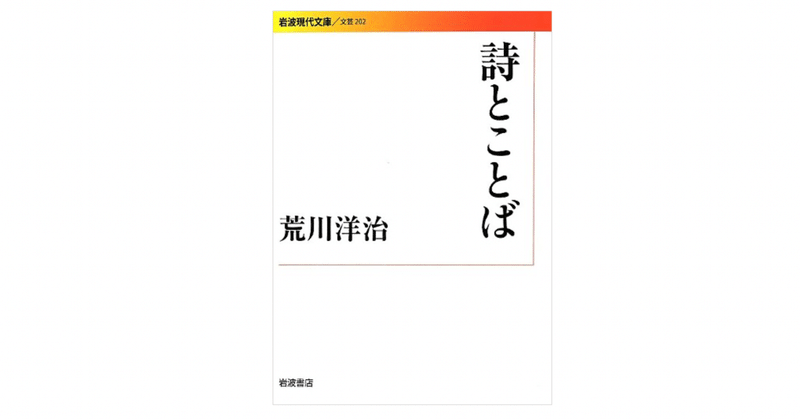
荒川 洋治『詩とことば』
☆mediopos2931 2022.11.26
いまは誰も真の意味で詩人になろうなどとは思わないだろう
誰もがユーチューバーのようになろうとする
あるいはSNSでの自己吐露のようなことばの使い手
詩人になろうとする者がいたとしてもそれは
「作者である「私」の趣味や感性をただ披露する」ような
「自分のために詩を書く」ような自称詩人ばかりだ
現代は詩の読まれない時代だ
だれもが求めるもののなかに詩は含まれない
詩は娯楽にはなりがたいからだ
わかりやすく楽しませてくれるような
娯楽になるものはいくらでもある
自己表現なるものもいくらでも簡単にできる
詩が沈滞するようになったのは
「人と、ことばとの関係が変わった」からだ
わかりやすいことばだけが求められ
「思考力や想像力を有する詩のことばは、
興味の対象からはずれる」ようになったのだ
さらにかつて戦争や闘争や政治といった
さまざまな外的な「壁」の明らかであったころには
詩はそれらの「時代という愛情」に包まれ
それらの力で詩となることができた
「詩を支えるものが自動的にはたらいたのである」
いまやそれらは何もなくなっている
詩はいったい何をうたえばいいのか
「そもそも詩は、何をするもの」なのか
「詩の根本が問われ」る時代となっている
ほんらい「詩」とは
「詩のことば」とは
括弧付きの自称「詩」
あるいは詩というおきまりのジャンルに
素直におさまっているようなものではない
ある意味でそれは
哲学の根源にある
「驚き」や「悲哀」などにも秘せられるような
いやそれよりもさらに根源的な
ことばの源から否応なく湧き出る
ポエジーの力に由来するもの
そんな「ことば」に出会いたいと切に思う
そしてそれが人間の「ほんとうの食べもの」となって
あらたな「詩」の歴史がはじまってゆきますように
■荒川 洋治『詩とことば』
(岩波現代文庫 岩波書店 2012/6)
(「IV これからのことば」〜「詩を知る」より)
「萩原朔太郎、室生犀星、高村光太郎、宮澤賢治など、よく知られた人の詩集(ひとり一冊)はいまも各社の文庫で読むことができる。でもそうした人たち以外の詩は、なかなか読むことができない。
かつては文庫でも、詩の全集があった。一九六〇年代に青春期を迎えた人には『現代詩人全集』(角川文庫・全一〇巻)が親しまれた。そのあと同じ角川文庫で『全集・戦後の詩』(全五巻。一九七三〜一九七四)が出た。田村隆一など「荒地」の詩人から一九六〇年代登場の新しい世代まで、その代表作を、俳句も含めるもので、いまも重版。この他にも大手の出版社から詩の全集類が出た。『日本詩人全集』(新潮社・全三四巻)、『日本の詩』(集英社・全二八巻)、『日本現代詩体系』(河出書房新社・全一三巻)など。
一九六八年、画期的なシリーズの刊行がはじまる。思潮社の〈現代詩文庫〉である。ひとり一巻で構成。第一巻田村隆一。第二巻谷川雁。現在。正・続篇を含め一七〇巻を超える。戦後詩人の代表的作品を収録。値段もてごろ。詩の読者でなくても、何冊かはもっているほどポピュラーなものになった。一九六九年に學藝書林から出たアンソロジー『言語芸術の探検』(全集・現代文学の発見13)もいい本だ。装幀は粟津潔。
でも詩集や、詩の本を出すところは、だんだん少なくなっている。こんな時代に『詩とことば』などという本を書くことじたいが、まちがっているといわれるかもしれないが、たとえば。こんなふうに考えたらいい。
いま、不思議というしかない、いろんな事件が起きる。この社会はどこかおかしいのではなかろうか。人間もおかしなものになったのではないかと感じている人は多い。もしそうだとしたら、いま好んで読まれているものがどういうものなのかを見る。すると、情報だけの本だったり、明日役に立つだけの本だったり、時流に合わせるものだったり、簡単なことばだけでつくられた散文だったりする。これ以上ストレスがほしくないので、簡単なものに吸い寄せられるのは人のさだめ。誰も非難できないが、このまま進むといっそう簡単な人間ができあがり、そのために、人はこわい思いをする。
いまもっとも、読まれていないものは、何か。文学書だ。そのなかでも読まれないのは、詩の本。詩とのかかわりがなくなってから、人の心が変わったのではないか。だからいまはむしろ詩が必要なのではないかと、考えることにしよう。詩を読まないのは、ことばがむずかしいからである。また社会で役に立たないと見られているからである。だが、その役に立たないことばを失うことによって、人間が変わることがあるのだ。実はぼくもこのところ、詩を読まないのだ。詩を読むと、途中でいらいらしてきて、すぐにわかるもの、簡単なものを読みたくなる。ぼくのなかにも詩を読みたくない気持ちが生まれているのだ。でもここでの詩は、ひとつの譬えである。「詩のようなことば」が遠ざけられたあたりから、何かが変わったのだ。これまで詩を読んでいた意図がおおぜいいて、このところ読まなくなったのではない。読むかどうかは別にして、詩のことばに象徴されることばがまわりから消えて、これまでなかったような、へんなことがあちこちで起きる。自分のなかでも起きる。詩は、人間に何かを教えていたのだろう。与えていたのだろう。それを失った人にはわからない、何かを。
いい詩がないから、読まないのだという人もいるだろうし、それはまったくその通りかもしれない。でもそれ以前に詩を含めた「詩のようなことば」全体が遠ざけられているのだと思う。」
(「IV これからのことば」〜「歴史」より)
「明治一五年、『新体詩抄』という書物がつくられた。訳詞一四編、創作詩五編。これが日本の近代詩の出発点といわれる。西欧の詩にならったもので。これまでに日本にあった漢詩、俳句、短歌とはまるきりちがう日本の詩をめざした。でもことばは古い。リズムも七五調。でも明治の詩人たちは、新体詩を次々につくって、詩の夜明けを謳歌した。(…)
訳詩集などで西欧の詩にも目が開かれたあと、北原白秋が現れ、近代感覚にふれた詩を書く。その白秋の影響もあって、萩原朔太郎、室生犀星の詩が生まれた。
彼らは古い韻律の残る抒情小曲からはじめたが、大正半ばには萩原朔太郎が、ちょっと気持ちのわるいほどの新しい詩を書いた。詩人ならではの感性を大胆なことばで表現したのだ。また、形式も自由詩(口語で書く。自分のリズムで書く)になった。昭和のはじめ、日本の詩人にはめずらしい世界観を持った宮澤賢治がいたが生前は知られることがなかった。また中野重治や金子光晴、「赤と黒」に拠った小野十三郎、萩原恭次郎などが現れ、詩のなかに思想や社会が示されるようになった。
第二次世界大戦。作家、歌人、俳人だけではなかった。高村光太郎、三好達治ら、戦前に活躍した国民的詩人たちの多くは、戦時中、すすんで時局に協力的な作品を書き、日本の詩の思想的な基盤のよわさが露呈した。
戦後の詩人たちは、その反省からも、詩のことばを確かな、強いものにするために、さまざまな工夫をこらした。詩誌「荒地」からは鮎川信夫、田村隆一、北村太郎、黒田三郎、吉本隆明らが出て、喚起力のある作品や批評によって新しい誌の理念を示した。これが現代の誌の出発点となる。後続の世代からは谷川俊太郎、寺山修司、大岡信、飯島耕一、吉岡実、堀川正美らが出て、現代詩の黄金期を築く。詩のことばは、この時期にその特色を固めたが一面複雑なものになる。ことばに、二重三重の鍵がかけられるようになった。
一九五〇年代後半から一九七〇年代はじめの、政治の季節のなかで、現代詩の動きはふたたび活発になる。「凶区」の天沢退二郎、鈴木志郞康らが実験的な詩を書いた。高橋睦郎、吉増剛造、清水昶らの詩も新世代の注目を浴びた。
一九七〇年代半ばになると、人々はことばの想像力や創造性より、物を楽しむことを優先する。そうした社会の空気もあり、現代詩はそれまでに存在した読者の関心からもはずれていく。行場を失った若い詩人たちは詩壇ジャーナリズムのなかでの限定的な名声を求めるようになり、ことばも思考も保守化した。論争もなく話題もない。一九七〇年代から一九八〇年代にかけて清水哲男、藤井貞和、伊藤弘呂美、井坂洋子、稲川方人らが登場したが、この二〇年間、時代を画する詩人は現れていない。新人不在の状態が続く。
(…)
どうして、詩が沈滞したのか。
人と、ことばとの関係が変わった。単純になったのだ。人間が弱くなり、忍耐がなくなったのか、努力しなくても近づける簡単なことばに引き寄せられ、思考力や想像力を有する詩のことばは、興味の対象からはずれることになる。でもこれだけが問題ではない。
詩人たちの作品そのものに原因がある。詩は、作者である「私」の趣味や感性をただ披露するものとなった。詩人たちは社会的な問題やできごとに正面から向き合う気持ちも力もなくした。どの作品も、たったひとりの作者が書いているのではないかと思われるほど、ことばも、かたちも、ちがいが感じられない。
詩人たちの知識にも「叫び」がない。詩の世界をゆるがす発言もない。詩の朗読だけはさかんだが、その詩のことばはいつものものと変わらない。それを声に出しても詩は変わらない。詩は一編の詩のなかにおいて実現されるものである。文字の詩のなかでのたたかいを回避する朗読に、逃避以外の意味があるのだろうか。詩人たちの間に流行の俳句づくりも同じだろう。
この状態を脱するためには、詩の主語となる「私」を大胆に拡張するしかない。詩がフィクションであるという詩の基本をあらためて確認し、詩が過剰に「私物化」される動きをくいとめなくてはならない。また、これからの詩は、詩とはこういうものであるという、詩の力、可能性、役割、宿命、難所、課題を、詩のなかで示していく。おおきな空気のなかで書く。そんな詩の書き方が必要だと思う。自分のために詩を書く時代は終わった。詩の全体を思う、思いながら書く。そんなやわらかみをもった詩を構想する必要がある。
これまでの現代詩は「時代という愛情」に包まれていた。戦争があり、闘争があった。政治の季節には政治があった。意見の合わない旧世代があった。まわりにいつも壁があった。ことばを出していれば、それが詩ではないものでも、あまりしっかりりとは書かないものでも、時代のあとおしで詩になった。詩を支えるものが自動的にはたらいたのである。詩をとりまく愛情は分厚いものだった。そのために詩とは何であるか。それを考えなくてもすんだのである。いまは時代も、たたかう相手も鮮明ではない。読者もいない。何もなくなったのだ。こんなとき、詩は何をするものなのだろうか。そもそも詩は、何をするものなのだろうか。詩の根本が問われているのだ。だとしたら、ここからほんとうの詩の歴史がはじまるのかもしれない。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
