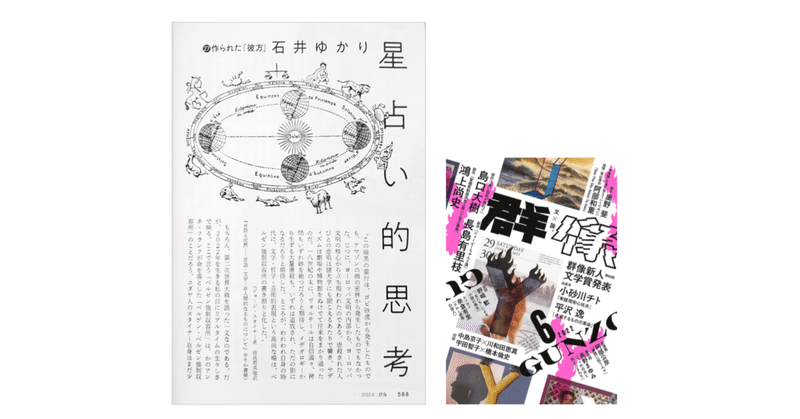
石井ゆかり「星占い的思考㉗作られた「彼方」 (群像 2022年 06 月号 講談社 2022/5)
☆mediopos2731 2022.5.10
争いや闘いが
なくなるときは
くるのだろうか
物心つくかつかないかという頃から
そんな素朴な思いを持って生きてきた
ひょっとしたらじぶんの魂の奥深くに
激しく争った記憶・闘った記憶が深く眠っていて
その悲しみをそして怒りを
繰り返したくなかったのかもしれず
そのためかどうかはわからないが
小さい頃からでき得るかぎり
闘いの場からは身をひいて
争わないように競わないように
闘うのだとしたら競うのだとしたら
自分自身との闘いであり競争でありたいと思い
そのためか怒りのような表現を苦手として
それを外に表さないように生きてきたところがある
さてこの5月11日
木星は闘いの星座・牡羊座に入り
5月25日闘いの星・火星も牡羊座入りするという
現在もさまざまな形で
見えているところ見えていないところで
繰り広げられている闘いがあり
それらの原因もまた表現され方もさまざまで
たくさんの要因が複雑に絡み合いながら
展開されているのだろうが
闘いは決してじぶんの外で起こっているのではない
じぶんのなかを見すえることを怠らなければ
そこにはさまざまな闘いが起こっていることがわかる
だからたとえどんなに闘いを止めようとしても
ひとのなかに激しい闘いがあるときには
それらは何らかの形で
外的な表現として現れざるを得なくなる
人類がずっと先に善き進化を遂げたとして
そのとき破壊的で人が血を流すような
そんな闘いを止めるときがくるとしたら
そのときには人類のすべてが
そうした内なる闘いを克服したときなのだろう
その意味でいえば内なる闘いがある以上
闘いは決してなくなることはないのではないか
そんなことを子どものように考えたりする
平和のための闘いと称しても
闘いであることに変わりはなく
またそれを援助したりするのもまた闘いでしかない
人類は大から小まであらゆることを原因にして
あらゆる形をした闘いを繰り広げてやまないでいる
だからせめてじぶんのなかだけであったとしても
じぶんのなかにある闘いを見すえることを怠らず
その力を別の力に変えようとすること
そんなことしかいまできることはなさそうだ
闘いが少しでも収まることを
星に願いながら・・・
■石井ゆかり「星占い的思考㉗作られた「彼方」
(群像 2022年 06 月号 講談社 2022/5 所収)
「5月11日、木星は闘いの星座・牡羊座に入る。闘いの星・火星も5月25日、牡羊座入りする。この燃え上がるような星の動きがいったいなにを示すのか、あまり考えたくない。星占いを全く知らない人でも、「闘いの星座」、「闘いの星」と繰り返されることの一分を読めば、陰鬱な気持ちにならざるを得ないだろうと思う。とはいえ、2022年年明けからの一連の出来事は、火星が冥王星から土星の上をなぞった間に起こった。この形が解除されつつある今、激しい衝突も「解除」されていくことを願いたい。それに「闘い」は1種類ではない。人間がもし、本当の「闘い」をできるとすれば、それは戦争をするのではなく、戦争という人類の宿痾をどうしたら断ち切れるのか、そこに向かって闘うことであるはずだ。それは即ち、自分自身と闘う、ということだ。しかしこれほど怖ろしいこともない。
10年以上前、ホーチミン・シティにほど近い戦争の遺構クチントンネルで、私はライフルを試射したことがある。気が進まなかったのだが、ガイドに半ば強引に勧められて、仕方なくAK−47を構えたのである。的は、茶色いイノシシのような絵が描かれた板だった。やり方を教わり、数発撃つうち、なんとか当ててみたいと感じた。あの的が板ではなく、本当の動物ならどうだろう、と思い始めた(!)。その気持ちを自覚したとき、私は心底怖くなった。35度の気温の中で、ぞっとした。トンネルの脇では観光客向けのドキュメンタル・ムービーが大画面に上映されていた。画面の中では可憐な少女達が私同様、銃を構えていた。自分の中に人を殺すほどの暴力性があるなど、知りたくもない。むしろ、真っ先に殺される「弱者」「被害者」としての恐怖や怒りに心を奪われる。」
「〝この暗黒の蛮行は、ゴビ砂漠から発生したものでも、アマゾンの雨の密林から発生したものでもなかった。じつに、ヨーロッパ文明の内部から、ヨーロッパ文明の核心から立ち現れたのである。虐殺された人びとの悲鳴は諸大学にも聞こえるあたりで響き、サディズムは劇場や博物館をぬけでて往来をまかり通ったのだ。十八世紀の末に、ヴォルテールは自信満々、拷問もいずれ跡を絶つだろうと期待し、イデオロギーから生ずる大量虐殺も、いずれは追放され、ただの影になるだろうと期待した。ところが、われわれ自身の時代に、文学・哲学・芸術的表現という高尚な場所は、ペルゼン強制収容所の書き割りと化した〟
(ジョージ・スタイナー著 由良君美他訳『言語と沈黙————言語・文学・非人間的なるものについて』せりか書房)」
「最初にあの分厚い文学評論『言語と沈黙』を読んだとき、私はスタイナーがユダヤ人だとわかっていながら、「この人は戦争を『やった』側なのかな」と何度か錯覚した。彼はユダヤ人として、世界のアウトサイダーとして、人類全体の過去を自分のアイデンティティに引き受けようとしているのか、それが不可能なら文学になんの意味があるものか、と、彼がやけくそに怒鳴り上げているようにも思えた。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
