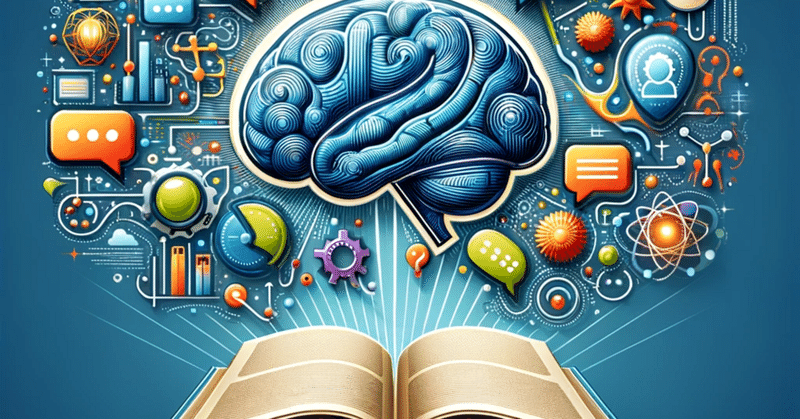
ChatGPTの真の実力を知る!~「ChatGPT がよくわかる本」より~
今回は生成AI関連の書籍を読む中で出会った、書籍「ChatGPT がよくわかる本」について紹介します。
端的にわかりやすくまとめられている本書を読んで、改めてChatGPTの仕組みを学びながら、実力の高さを今後の奥行きに可能性を感じました。特に、Microsoftの巨額の投資、膨大な学習データ、確率に基づく文章生成など、ChatGPTの背景にある仕組みを知ることで、その真の実力が見えてきます。
今回は本書から学んだ重要なポイントを紹介していきます。
ChatGPTはどのように生まれたのか?
実は、ChatGPTを開発したOpenAIは、2019年に法人を立ち上げてから、あの大手IT企業Microsoftから巨額の出資を受けているんです。その総額なんと1兆円以上!この資金がChatGPTの開発を大きく支えてきました。
Microsoftもこの出資によって恩恵を受けています。例えば、MicrosoftのサービスであるCopilotやBingにもChatGPTの仕組みが取り入れられているんですよ。
ChatGPTのすごさの秘密は?
ChatGPTがここまで優れている理由の一つが、なんと5兆もの言葉をテキストデータとして学習していること。この膨大なデータ量によって、ChatGPTの回答精度が飛躍的に上がっているんです。
ChatGPTの文章生成の仕組み
ChatGPTが文章を生成する際の仕組みは、実は確率に基づいているんです。例えば、英語の "Go" という単語の後に "to" が来る確率が10%、 "out" が来る確率が8%だとすると、ChatGPTは "Go to" や "Go out" といった文章を生成します。
これは日本語でも同じで、「昔々」と入力すると「あるところに」と続く可能性が高いですよね。ChatGPTはこの文脈に応じた確率の高い言葉を選んで、自然な文章を生成しているんです。
5兆もの単語を学習しているからこそ、ChatGPTのアウトプットの質が高いんですが、今後はさらに学習データの質が上がっていくと予想されます。
次世代のGPT-5では、もしかしたら人間のレベルを超える文章が生成できるようになるかもしれません。
2024年夏に公開されるとの報道があります。
ChatGPTの新たな可能性を拓くマルチモーダル機能
ChatGPTを使う上で、最近注目を集めているキーワードの一つが「マルチモーダル」です。これは、テキスト以外の情報、例えば画像なども入力できる仕組みのことを指します。
視覚障害者の生活を変えるマルチモーダル
マルチモーダルのおかげで、GPT-4には画像処理能力が備わっています。その一例が、視覚障害者向けのコミュニティ技術を開発する「Be My Eyes」という組織のサービスです。
視覚に障害のある方がスマホをかざすと、それが何であるかを言語で返してくれるのです。視力の弱い方でも、マルチモーダルの仕組みを活用することで、GPTを通じて情報を収集できるようになります。
こうした技術の進歩によって、今まで視覚障害者が抱えていた課題も解決されつつあります。ChatGPTは進化を続けることで、より多くの人々の問題解決に貢献できるでしょう。
ビジネスシーンでのChatGPT活用事例
ChatGPTは、様々なビジネスツールとの連携も進んでいます。その代表例が、顧客管理システムの「Salesforce」です。
セールスフォースとの連携で営業の効率化を
セールスフォースには、「CRM向け生成AI」という機能が組み込まれています。これは、ChatGPTがセールスフォースのサービスに統合されているということです。
例えば、営業担当者がEメールを作成する際、送り先の顧客にパーソナライズしたメールを自動で生成してくれます。これにより、メール作成の時間短縮と品質向上が同時に実現できるのです。
セールスフォースは、顧客情報を統合管理するシステムとして広く普及していますが、ChatGPTとの連携によって、マーケティング施策の立案やメルマガ配信のタイミング設定など、より戦略的な意思決定をサポートしてくれます。
Slackとの連携でコミュニケーションを円滑に
ChatGPTは、コミュニケーションツールのSlackにも組み込まれています。Slackでの会話履歴をもとに、予定の作成や文章の作成支援などを行ってくれるのです。これにより、これまでのコミュニケーションをより効率化し、生産性を高めることができます。
まとめ
ChatGPTは、マルチモーダル機能によって画像処理能力を獲得し、視覚障害者の生活を変える可能性を秘めています。また、セールスフォースやSlackなどのビジネスツールとの連携も進み、業務の効率化に貢献しています。
ChatGPTは日々進化を続けており、様々な分野での活用が期待されます。私たちもChatGPTの可能性を探りながら、うまく付き合っていく必要がありそうです。
これからもChatGPTは進化を続けていくでしょう。ChatGPTとうまく付き合いながら、その可能性を活用していきましょう。
ぜひ、改めて本書からChatGPTについて学びなおしてみてはいかがでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
