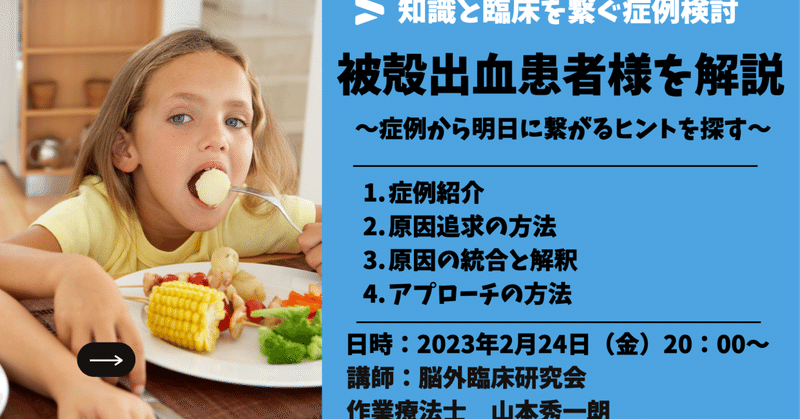
被殻出血の症例を作業療法士が徹底解説。目標設定からアプローチまでを考える
はじめまして、脳外臨床大学校の作業療法士の山本です。
このサイトでは、脳卒中のリハビリに関わる、
作業療法士・理学療法士・言語聴覚士に向けて
臨床で使えるのニューロリハビリと題して
脳の知識を臨床に使えるレベルに変換してお伝えしたいと思います。
*今回の有料内容は 脳外臨床大学校にて開催しました
60分間のZOOMセミナーの録画となっております。
YouTubeにて一部を公開していますので参考にしてください。
オンラインサロン 脳外臨床大学校では1980円〜毎月開催されるセミナーが
無料で視聴可能です。是非これを機にご入会ください。
今回は、作業療法士山本が被殻出血の患者様を検討した内容について説明したいと思います。
まずは、症例を紹介したいと思います。
被殻出血の患者様です。
心身機能は以下動画の通りです。
さて、皆さんは何をどんな視点でみましたか?
症例を把握する上で一番大切にしていることは
『木をみて森をみず』にならないことです。
一番初めからアプローチの方法や部位などを考えるために
評価するのではなく。
患者様の全体像を把握し、どのようなSTORYを作るのか?
これを考えるために症例を見る必要があると考えています。

そのための、一番必要なことは
症例の現象から、その現象が起こっている
『原因』をどれだけ明確に捉えることができるのか?
ここに予後が良くなるか?そうでないかの境目があると感じています。
*POINT:症状や診断名・動作分析をここで行うのではなく
現象と症状を結びつけることで原因(アプローチすべき部位)を見つけて行く必要があります。
現象を見ていきましょう!
現象を見るにもPOINTがあり、なんでも気になることを
列挙すればいいのか?というとそうではありません。
リハビリの目的は『再び適した状態への回復』です。
ではどのうなれば再び適した状態と言えるでしょうか?
その条件がFIMにもあるように
①基本動作 ②移乗・移動動作 ③セルフケア ④認知機能の
4段階からなります。
何を獲得するかによって変化するため現象評価をする際は絞って考える必要があります。

今回はADLの獲得→セルフケア→食事→上肢操作→随意運動の有無
を目的に評価を進めたいと思います。
食事における上肢操作は3種類です
①リーチ②物品操作③摂食です。
それぞれ必要な要素は

食事における上肢操作には
回内外・掌背屈・3指つまみが必要となります。
動作を見てみると回内はできるものの・・・・
その他ができないため、現状では右手による食事の獲得が不可能であると言えます。
利き手交換するという手段もありますが、これは私、セラピストが関わらなくでも可能であるため選択肢としたは十分ではないです。
この状態から上肢機能を再び適した状態へ導くためにいかに考えを進めていくがが重要になります。
損傷部位から考えてみたり

動きの特性から考えてみたり

といろんな視点から検討しているのが今回のセミナーとなっています。
結果はどうなったのか?
今回は、一症例を対象に症例検討を行いました。
これが正しいではなく、いろんな視点がありますが、
それをどれだけ明確に意識化しているかが重要であると考えています。
少しでも、皆さんの患者様の役に立てれば幸いです。
脳外臨床大学校では、
脳の機能解剖・ADL分析・症例検討・アプローチ・筋肉というテーマで毎月8回セミナーを行なっています。ともにフルリバリーを目指して、患者様のためにも
自分の将来のためにも頑張ってみませんか?
詳細はこちらから↓
症例検討動画 60分
ここから先は
¥ 6,000
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
