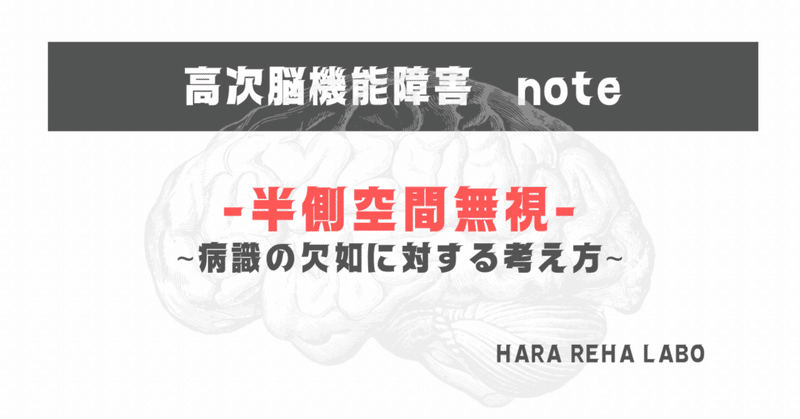
半側空間無視[気づきの階層モデルの活用]
お疲れ様です。はらリハです。
本日は…
「半側空間無視:自分に生じている障害を認識する能力(Self- awareness:自己の気づき)」について解説します。
※ 引用、参考書籍
はじめに
半側空間無視の回復を阻害する要因として一番多いのが「病識の欠如」です。
これは「自身が左側の世界を無視しながら生活している」ことに気付けていないため、他者から”それ(左の世界)”について注意されても、何のことか分からず、他者が”それ”を認識させることは困難極まりないです。
気づきの階層モデル
これに対してリハビリを行ううえで『Self ~awareness(自己の気づき)』に焦点をあてることは重要です。
Selfーawarenessを「自分に生じている障害を認識する能力」と定義
Crossonは、自己の気づきの程度を階層に分け、それぞれの程度に合わせた補填手段を選択できる『気づきの階層モデル』を作成しました。

それぞれの階層と半側空間無視の関係を解説します。
第1段階:知的気づき
第1段階は知的気づきです。
自己の障害に気付いていない患者さんに対して…
「あなたには半側空間無視があります」
と伝えても、そのことを気づく/理解することは難しいです。
ここでの段階に対しては、外的補填に加えて、状況的補填の解説が重要です。
例えば…
「〇〇さんは脳卒中という脳の細胞の一部に損傷を受けて、左手足の動かしにくさ、専門的には運動麻痺と呼ばれる症状が出現しています。(脳画像や手足を見せる)」
「この症状に加えて、半側空間無視と呼ばれる左側の注意が向きにくくなる症状も出現しています。」
「この症状があると、食事で左側の食べ物を無意識に残してしまったり、車椅子のブレーキをかけ忘れたり、左側の障害物にぶつかりやすくなったり、左側の空間に対して何かしらの不都合が生じます。」
というように、一般論として症状を理解してもらえるよう促します。
第2段階:体験的気づき
第2段階は、体験的気づきです。
自分が半側空間無視であることは頭で理解していても、日常生活の中では忘れてしまう患者さんは非常に多いです。
そういった患者さんには「実際の生活上で生じた問題をフィードバック」することが1つの対策です。
例えば…
左側のブレーキをかけ忘れた時に
「〇〇さん、いま左側のブレーキをかけ忘れましたね。これも半側空間無視の影響なので、次からはブレーキの時になるべく左側を意識しましょう」
と、見落としたタイミングで説明し、意識を高める方法をとりましょう。
ただ、説明の仕方を誤ると信頼関係を損ねる可能性があるため、その患者さんの性格、メンタル状態、タイミング、わかりやすい表現など、個性に合わせたフィードバックが重要です。
第3段階:予測的気づき
第3段階は、予測的気づきです。
ここから先は
¥ 200
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
