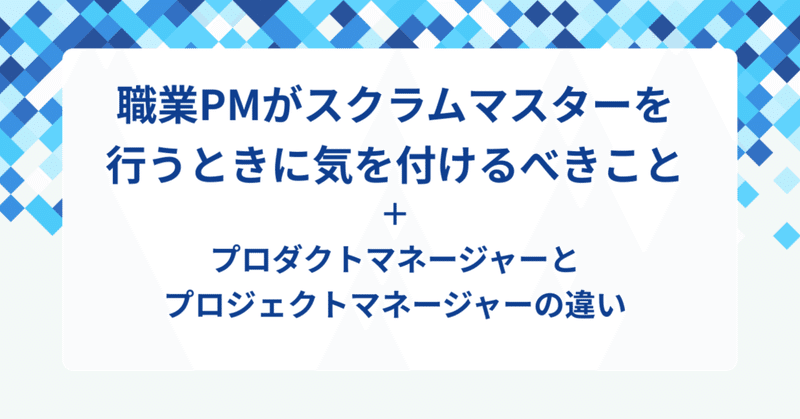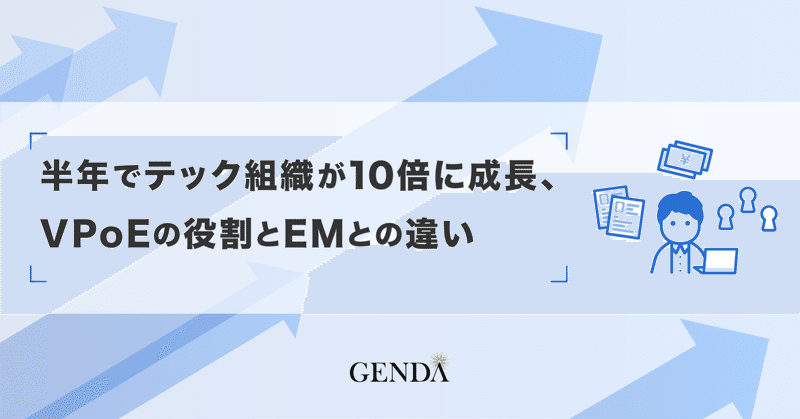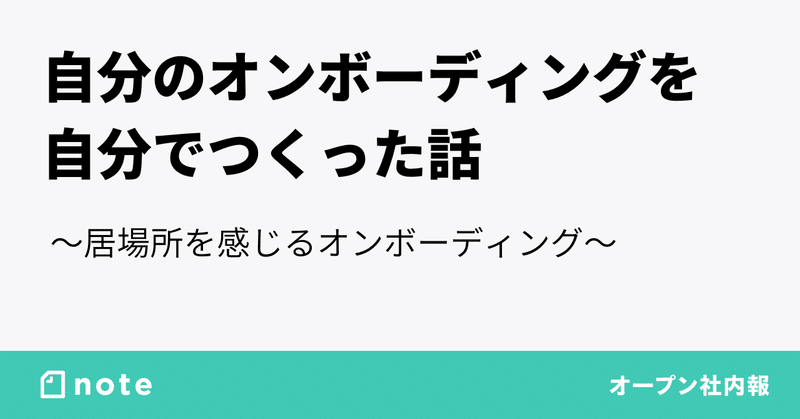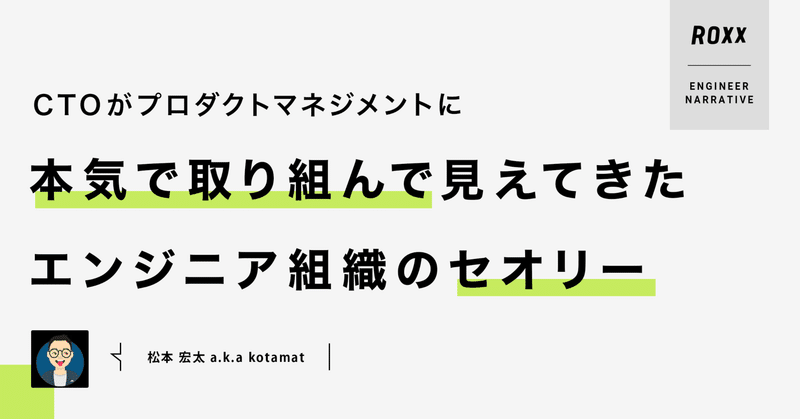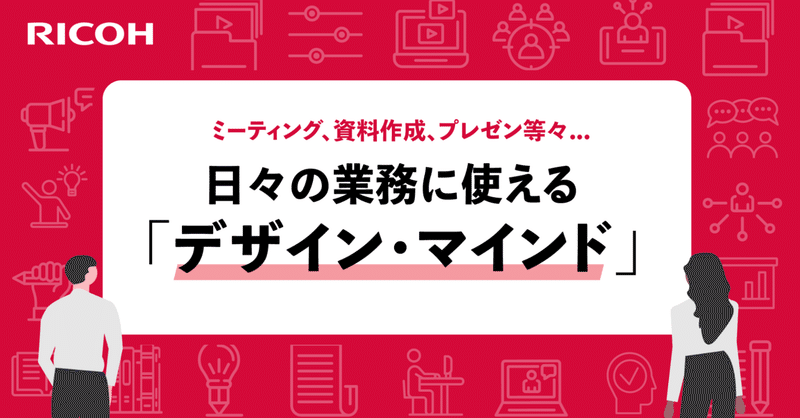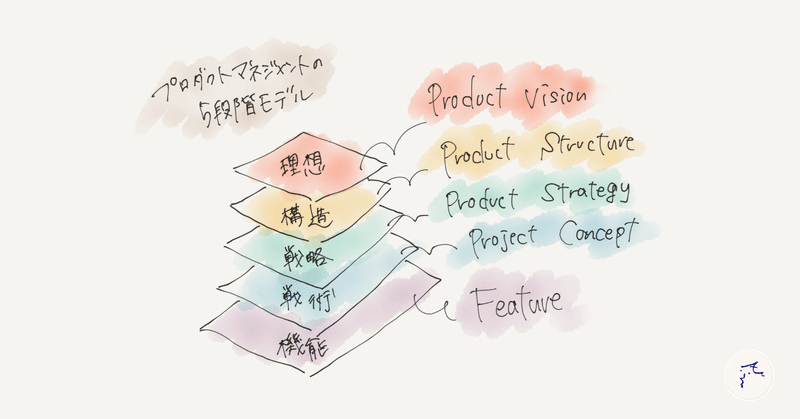PM(プロダクトマネジャー、プロジェクトマネジャー)の記事をピックアップする公式マガジンです。#PM、#PdM、#プロジェクトマネジャー、#プロダクトマネジャーのハッシュタグをつ…
もっと読む
- 運営しているクリエイター
2022年5月の記事一覧

[実録]なんとなくやりたいことやってたらtoB SaaSのPMをやってたので、PMに必要なことをどう得たのかまとめてみた
こんにちは。人事労務領域のSaaSのPMをやっているhiroki_mです。 どうしたらPMになれるのか、もしくはPMになるためにはどういうキャリアステップを踏む必要があるのか。というのを時折目にします。 しかし、どういうスキルセットが求められるかと言う情報は流通しているものの、PMになるまでのキャリアの実例が示されているものはあまりないようです。そこで、意識低く生きてきた自分の実例を振り返り、そこからどういうスキル・経験を得たのか抽出しまとめてみようと思います。 現在PMはや
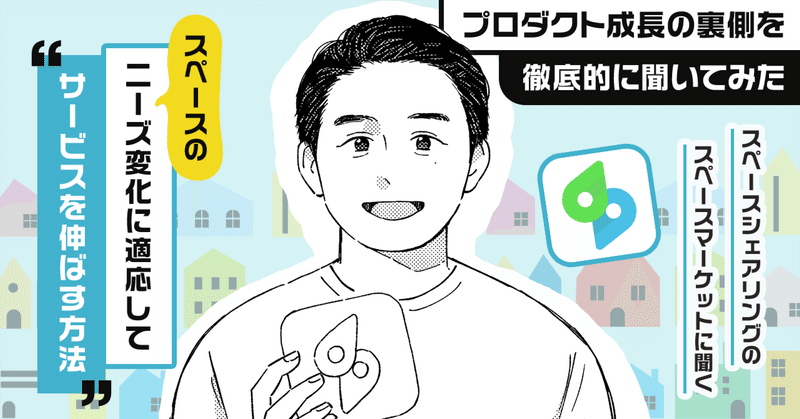
1,500円からはじまったスペースレンタルが8年で急成長。年間GMVは32億円に。「スペースマーケット」が語る成長の裏側、利用シーン写真が売上に効いたワケ
スペースマッチングプラットフォームの「スペースマーケット」を取材しました。 「スペースマーケット」について教えてください。重松: スペースマーケットは「スペースの貸し借り」のマッチングサイトです。プラットフォームとしてのGMV(流通金額)は年間32億円を超えています。 このビジネスに可能性を感じたのは、六本木の駐車場で月6万円の場所を、時間貸しにしたら月35万円稼げるようになった、という話を不動産会社の方から聞いたことがあって。 つまり、月極から時間貸しにしたら「場所の