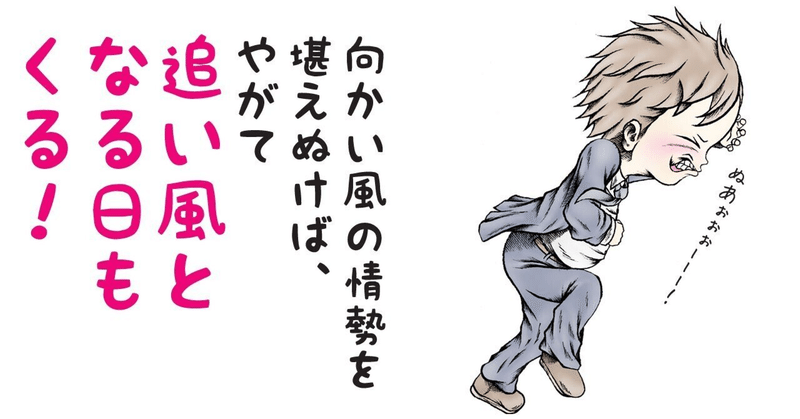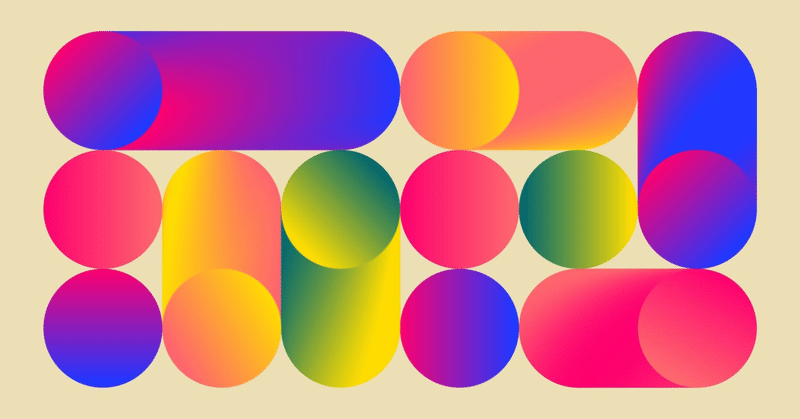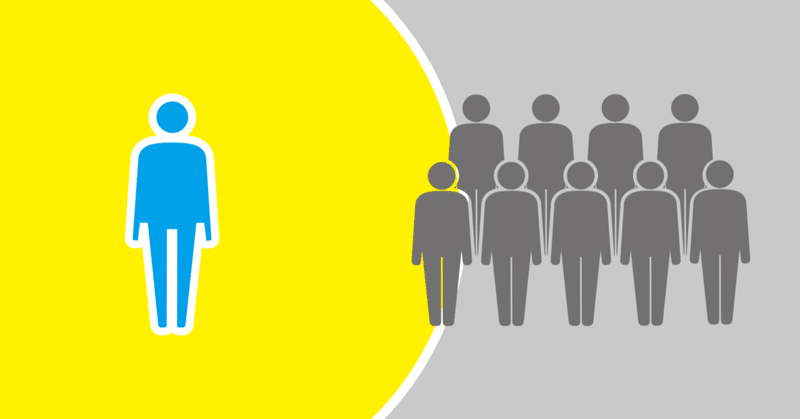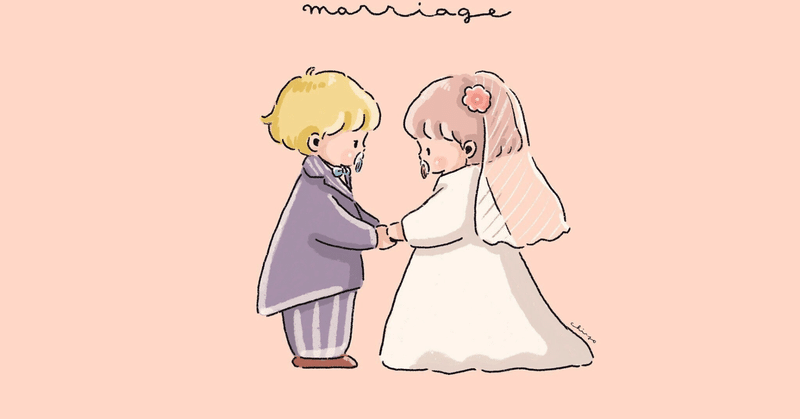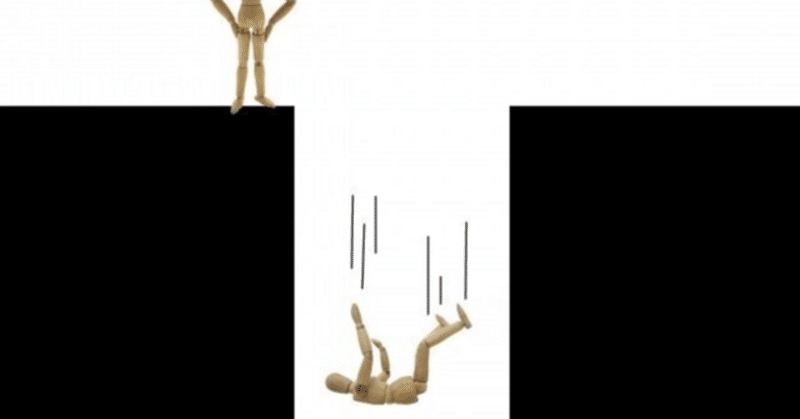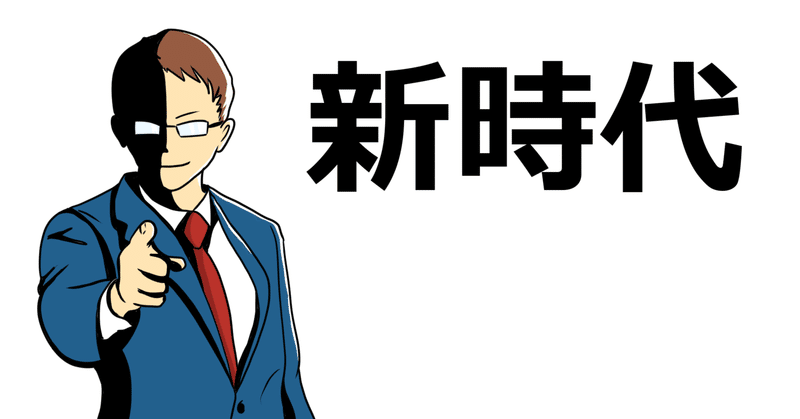#円安
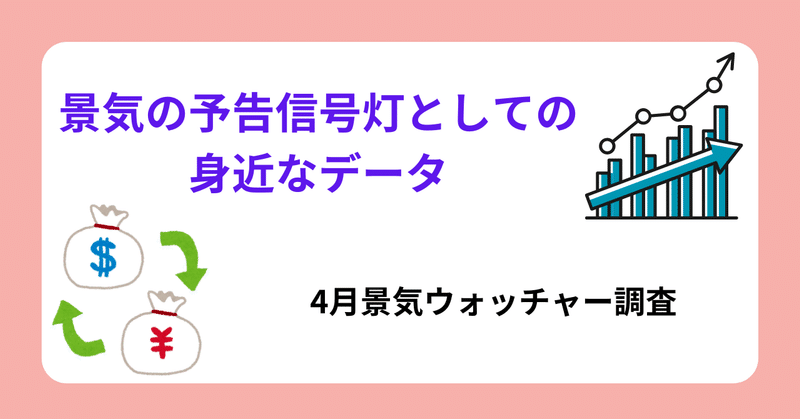
4月『景気ウォッチャー調査』では、円安の進展、物価高へに懸念などが、景況感を押し下げ、「価格or物価」や「為替」などが景況感にマイナス寄与。―景気の予告信号灯としての身近なデータ(2024年5月13日)―
調査期間中に34年ぶりの1ドル=160円台の円安になった4月『景気ウォッチャー調査』で、現状判断DIは47.4と前月差2.4ポイント低下。 4月の『景気ウォッチャー調査』の回答期間は4月25日~4月30日です。調査期間中の大きな話題はなかなか歯止めがかからない円安動向でした。4月26日の日銀・金融政策決定会合後、円安はペースを速め、29日に一時1ドル=160円台と90年4月以来およそ34年ぶりの円安・ドル高水準を付けました。その後、政府・日銀による為替介入とみられる円買