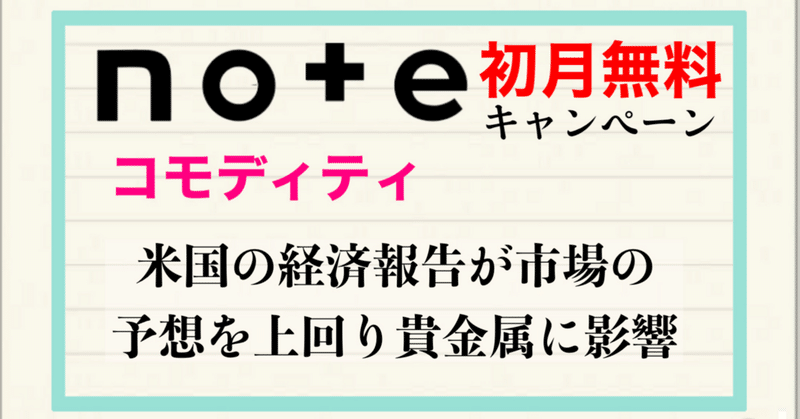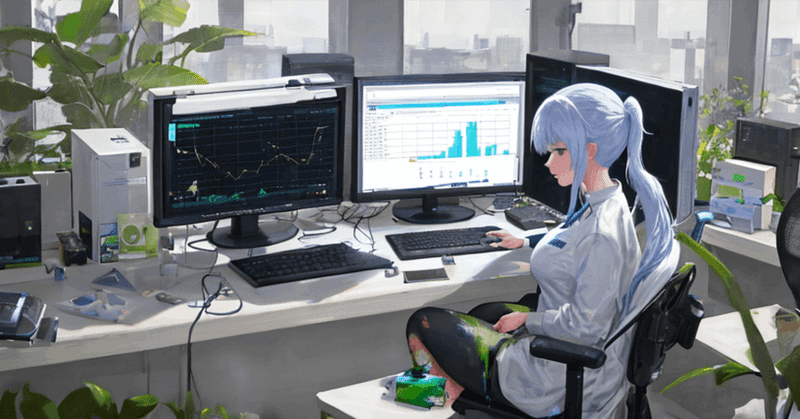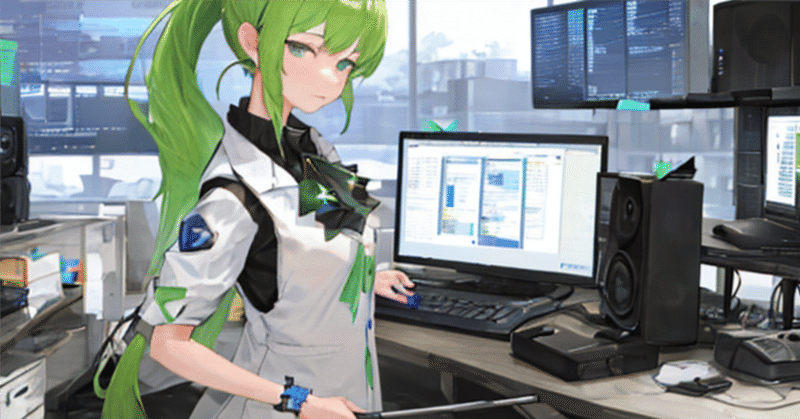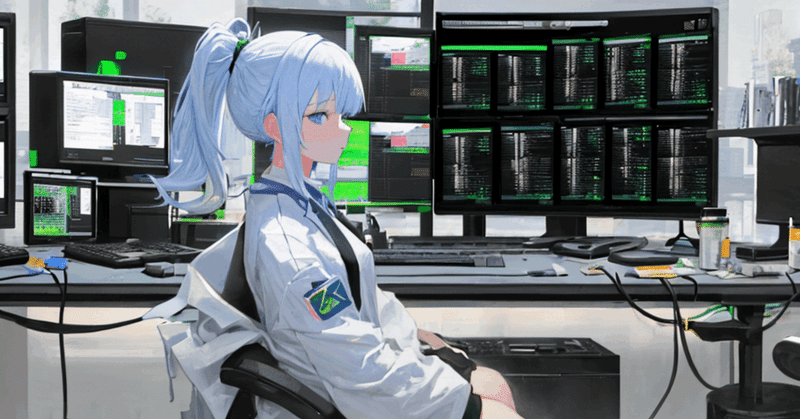#アメリカ
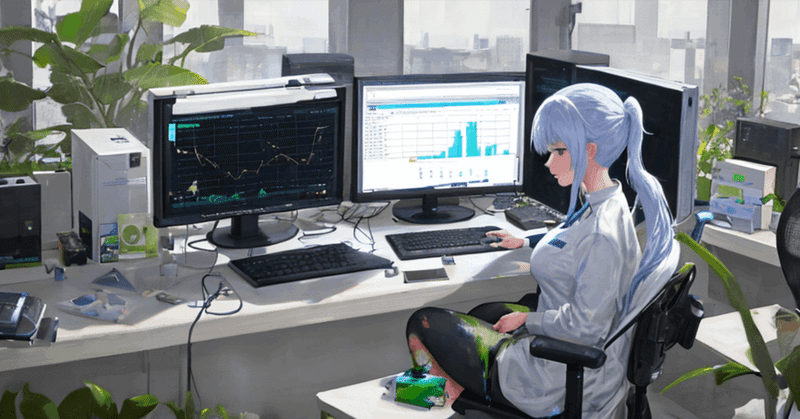
アメリカ企業の総資産、総負債、純資産、株式時価総額に対する負債比率の各データからアメリカ経済の現状と先行きを考えて行きます。アメリカ経済はリセッションに向かっているのか?それとも経済成長の加速に向かっているのか?を見て行きます。
経済学と金融理論、会計、マーケティング理論の知識をベースに記事を書いてます。 またニューヨークを拠点とした全米で上位1%に評価されているヘッジファンドの分析手法を参考にしてデータ分析し予想してます。 米国の経済学者やヘッジファンドの分析レポートも日々読んで参考にしてます。 私の記事はデータ分析と予想が中心で用語解説も交えながら進めてるので初めて株を取引する人でも直ぐに理解出来て予想は参考になると思います。 データの内容は個人投資家がほとんど見たことが無いか見ないデータ
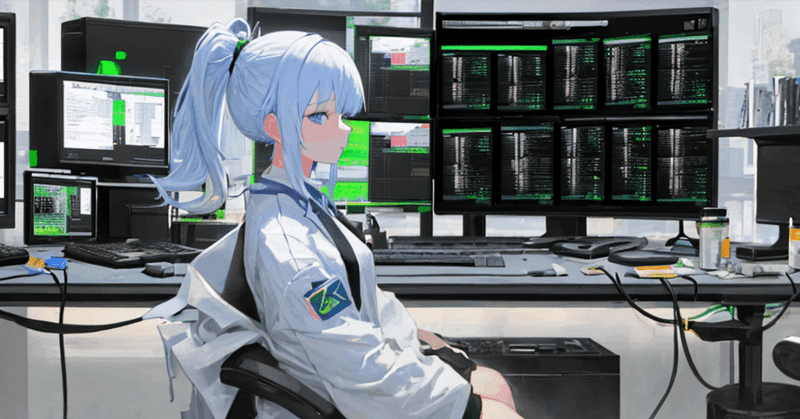
対GDP比の企業と家計の民間債務がGDP600兆円換算だとアメリカよりも180兆円も多い日本の過剰債務の実態を考えます。低金利で借金に借金を重ねて経済を回す借金依存体質の日本経済を考えます。
経済学と金融理論、会計、マーケティング理論の知識をベースに記事を書いてます。 またニューヨークを拠点とした全米で上位1%に評価されているヘッジファンドの分析手法を参考にしてデータ分析し予想してます。 米国の経済学者やヘッジファンドの分析レポートも日々読んで参考にしてます。 私の記事はデータ分析と予想が中心で用語解説も交えながら進めてるので初めて株を取引する人でも直ぐに理解出来て予想は参考になると思います。 データの内容は個人投資家がほとんど見たことが無いか見ないデータ

アメリカ経済はリセッションに向かっているのか?それとも経済成長の加速に向かっているのか?を経済と金融の両面から確認し分析して行きます。
私の記事はデータ分析と予想が中心で用語解説も交えながら進めてるので初めて株を取引する人でも直ぐに理解出来て予想は参考になると思います。 データの内容は個人投資家がほとんど見たことが無いか見ないデータが大量に出て来るので経済や株式市場、債券市場、ドル/円など誰でも詳しくなると思います。 経済学と金融理論、会計、マーケティング理論の知識をベースに記事を書いてます。 またニューヨークを拠点とした全米で上位1%に評価されているヘッジファンドの分析手法を参考にしてデータ分析し予想

アメリカ経済がリセッションに向かっているのか?それとも経済成長の加速に向かっているのか?をGDPの7割を占める個人消費に関連するマクロ経済のデータから考えて行きます。
S&P500やナスダック、日経平均の理論値は日々算出し経済指標やマクロ経済の基礎データを日々分析してます。 ドル/円の理論値を算出し予想しています。 国債や社債市場も分析し解説しています。 日米のマクロ経済も分析し予想しています。 等々、日々、原稿用紙で20枚前後は書いてます。 月に少なくとも原稿用紙500枚は書いていると思います。 経済学と金融理論、会計、マーケティング理論の知識をベースに記事を書いてます。 またニューヨークを拠点とした全米で上位1%に評価され
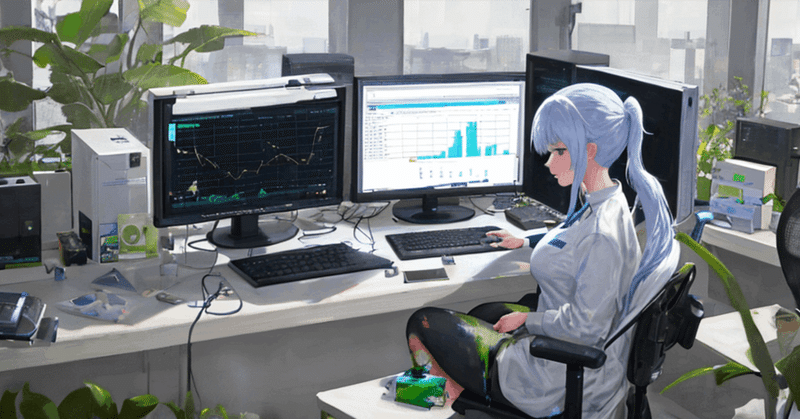
米国銀行のバランスシートを10のデータから確認し米国経済やマネーサプライ、景気、株式市場への影響などを分析し解説して行きます。
経済学と金融理論、会計、マーケティング理論の知識をベースに記事を書いてます。 またニューヨークを拠点とした全米で上位1%に評価されているヘッジファンドの分析手法を参考にしてデータ分析し予想してます。 米国の経済学者やヘッジファンドの分析レポートも日々読んで参考にしてます。 noteの月額500円のスタンダードプランの読者募集しています。 1記事だと100円となりますがスタンダードプランだと500円で過去の1300以上の記事も含め全てが読めるプランとなるので1記事購入よ

FRBのバランスシートから国債、住宅ローン担保証券、ドル紙幣流通量、準備預金、リバースレポ、アメリカ政府の預金を確認しジャンク債、投資適格債、予想インフレ率などから今のアメリカ市場のリスクオン、リスクオフの現状を見て行きます。株式市場の行方が見えて来ます。暴落か?それとも爆上げか?
FRBのFOMCでの結果を巡り株式市場や債券市場、為替市場が揺れています。 株価はナスダックを中心にグロース銘柄が売られ日本市場でもマザーズ指数は暴落しています。 債券市場でも債券は売られ金利は高騰し為替市場でも1ドル148円に乗るなど揺れています。 果たして、この先に待ち受けているのは リスクオフ相場として株価は暴落に向かうのか? それとも リスクオン相場として株価は爆上げに向かうのか? それを知る為にFRBのバランスシートの中から主たる資産と負債となる 1

米国経済がリセッションに向かっているのか?それとも経済成長の再加速に向かっているのかを7つのマクロ経済の基礎データから確認し分析して行きます。noteでは日々15~20程度の市場や経済のデータを確認し分析しています。読者募集中です。
アメリカ経済がリセッションに向かっているか、それとも経済成長の再加速に向かっているかを判断して行くには様々なマクロ経済の基礎データや市場のデータを確認して行く必要があります。 私は日々、マクロ経済の基礎データや市場のデータなど15~20程度のデータを確認し分析しているレポートをnoteに書いています。 先ほどは別の記事で15のデータを確認し分析しましたが今回は7つのデータを確認し分析して行きます。 ここからは有料読者向けの記事となります。