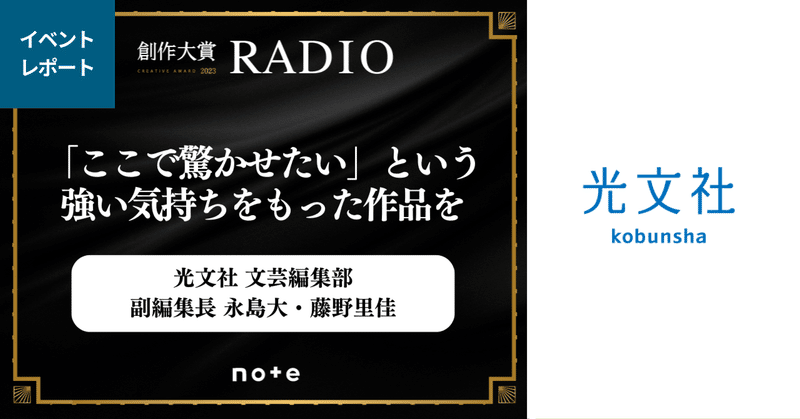
光文社 文芸編集部が語る「いま読みたい作品」──創作大賞RADIOレポート⑦ #創作大賞2023
4月25日にスタートした、日本最大級の投稿コンテスト「創作大賞」。第2回となる今回は15の編集部とテレビ局1社に協賛いただき、優秀作品は書籍化や連載、映像化など、クリエイターの活躍を後押ししていきます。
「参加しているのはどんな編集部?」「どんな作品を応募すればいいの?」というみなさんの疑問や悩みにお答えするため、協賛編集部をお招きしたTwitterスペースを毎週木曜日に配信中。6月12日は、協賛編集部として追加発表された光文社 文芸編集部から、永島大さんと藤野里佳さんにご出演いただきました。
創作大賞では、「ミステリー小説部門」の応募作の審査に参加いただきます。
▼ 配信のアーカイブは下記よりお聴きいただけます。
光文社 文芸編集部って、どんな編集部?
ミステリー中心の電子雑誌『ジャーロ』を発行
——光文社 文芸編集部について説明をお願いいたします。
永島さん(以下、永島) 光文社 文芸編集部は、紙の雑誌『小説宝石』と、電子雑誌『ジャーロ』を発行しており、12人のスタッフをだいたい半分ずつに分けて制作を行っております。
それぞれの雑誌編集を行いながら、単行本の編集も多数しており、私と藤野は『ジャーロ』班として主にミステリーを担当しています。今回の創作大賞も「ミステリー小説部門」に参加していますが、基本的には『ジャーロ』班のメンバーが審査を行う予定です。
——『ジャーロ』はどんな雑誌なのでしょうか?
永島『ジャーロ』は2000年創刊の雑誌で、昔は紙で出版していましたが、2016年から電子雑誌として発行しています。基本的にはミステリー小説やミステリーに関する評論を中心に掲載している雑誌です。
藤野さん(以下、藤野) 最近のヒット作だと、元々『ジャーロ』で行っている新人発掘プロジェクト「カッパ・ツー」で受賞された阿津川辰海さんによる『録音された誘拐』があります。昨年刊行された作品です。
永島 他のヒット作だと、『リボルバー・リリー』という作品が映画化される長浦京さんの『1947』という連載作品です。前回の号が連載の最終回だったため、これから単行本をつくるところです。
ミステリーの経験豊富な編集者が多い
——掲載される作品の傾向や、コンセプトはありますか?
藤野 電子雑誌なので、ミステリーマニアな人や、ミステリーを好きな人が積極的に読んでいる雑誌だとは思っています。だからといって、マニアの人しかわからないものを載せてるわけではなく、どんな人でも読みやすいものを意識して、「おもしろければいい」という方針で掲載していますね。
永島 『ジャーロ dash』という『ジャーロ』の無料試し読み版を出しています。小説は冒頭一部などしか読めないのですが、評論に関しては、だいたいのものが無料で読めるようになっているので、こんなことやってる雑誌なんだというのを知るために、試しに読んでいただけるといいなと思います。
——『ジャーロ』の強みや、他誌と比較した時の特徴を教えてください。
永島 ミステリー専門誌というところからはじまっているので、在籍する編集者はやはりミステリーに対しての知識は経験豊富な人間が多いと思います。そのため、今回の創作大賞でも「ミステリー小説部門」で受賞した作品を、よりクオリティの高いものに仕上げるためのアドバイスができる人間は結構いる、というのが強みかもしれないです。
——今回の創作大賞の副賞は「書籍化を目指す」ということですが、受賞作品に関しては、まずは『ジャーロ』に掲載するという流れでしょうか?
永島 今回の創作大賞は、文量の制限が2万字〜14万字と幅広いので、賞を取った作品が、短編なのか、長編なのか今の段階ではわからないですよね。短編だと、雑誌で掲載し、その後、また別の短編を書いてくださいと話が広がっていくかもしれません。もしくは、すごく長い長編だと、雑誌に載せるよりもいきなり単行本っていうこともあり得ると思います。そのあたりは、受賞作品と出会ってから判断したいです。
創作大賞で期待すること
小説の作法は気にせず、自由に書いてほしい
——今回、創作大賞に参加いただいた理由をうかがいたいです。御社でも新人賞のような枠組みはお持ちなんですよね?
永島 創作大賞は応募数がすごく多いので、普段出会えないような作品に出会えるチャンスがあるというのが参加理由としては一番大きいです。
藤野 普段は、光文文化財団主催で、日本ミステリー文学大賞新人賞を行っています。
永島 私たちがずっと行っている「カッパ・ツー」は、ミステリーに特化した新人発掘プロジェクトで、本当にミステリー好きで、がっつりとしたものを書かれる方が応募してくるものなんです。日本ミステリー文学大賞新人賞もミステリーですが、こちらも社会派でリアリティのある作品が多い傾向にあります。
いずれも小説講座に通われたり、小説の書き方をきちんと勉強した方が応募される賞なので、「小説を書くのは初めてだけれど、書いてみた」のような、わりとライトな動機で書かれた作品を読んでみたい、という理由で創作大賞には参加することにしました。
——ミステリーの作法などがわからなくても、光るところがあれば、デビューに向けて一緒に伴走いただけるということでしょうか?
藤野 はい。逆に、私たちのほうが「こうあらねばならない」ということに縛られているんじゃないかなと思ったりするので、本当に自由に考えて、作品内で人を殺していただきたいと思いますね。
殺人事件が起きて、魅力的な名探偵か犯人が登場する作品が読みたい
——今回、創作大賞の作品の条件として、「殺人事件が起こること」「魅力的な名探偵か犯人が登場すること」の2つを提示していますが、意図を教えてください。
藤野 ミステリー小説部門ということで、どうやったらわかりやすく応募者のみなさんに求めている作品を伝えられるのか、編集部で話し合いました。
ミステリーといえば「なぜこういうことが起きたんだろう」という謎があって、それが合理的に解決されるという、謎と解決の組み合わせが必須だと思ったんです。しかし、つまりどういうことかがわかりにくいと思ったので、それならいっそ「殺人事件」と、なるべくわかりやすいお題を設けることにしました。
殺人「事件」というからには、何でこの事件が起きたのか、どういうふうに殺されたのか、というのを作中の登場人物も、また読者も本気で考えたくなるはずなので、物語にもしていただきやすいと思ったんです。
そして、ミステリーならば、事件が起きて「目の前で〇〇さんが刺しました。終わり」ではなく、なんらかの謎もあるはずなので、それを解決に導くには名探偵がいてくれたほうがいいかなと。もしくは、謎は解かれないけれども、ものすごく頭のいい犯人や、読者が思い入れしちゃうような犯人がいるというのも、殺人事件モノの犯罪小説としては一つ魅力的な形だと思ったので、「名探偵もしくは犯人」とさせていただきました。
永島 名探偵と言ってますが、別に職業としての探偵じゃなくても全然いいんです。探偵役ということなので、警察の人でも、普通の会社員でも、学校の先生でもいいんです。学生でももちろん。人間じゃなくてもいいですね。
ミステリー小説のつくりかた
まずは「読者を驚かせる」ことを大切に
——さまざまなジャンルの小説があるなかで、ミステリー小説ならではの大前提はありますか?
永島 ミステリー小説の一番の魅力は、驚かせるということだと思うんですよね。それは、解決した最後のオチがびっくりするものかもしれないし、殺し方がすごくびっくりするものかもしれない。「こことここに、こんな繋がりがあったのか」といったような驚きかもしれないです。ミステリーというからには、こんなふうに、なにか驚くものが欲しいですよね。
その驚かせ方は何でもいいと思うんですけど、なにか一つでも、「読者を驚かせる」という気持ちが作家にはあったほうがいいかなと思います。最後にすごいどんでん返しが綺麗に決まるということじゃなくても大丈夫です。途中途中でも、ちょっとずつの小さな積み重ねに驚くということもあるので。
藤野 ミステリーは謎という不安定なものを追いかけて読んでいくことになるので、読者がそれを読み進める動機になるようなキャラクターの魅力も大事だと思います。この人がどうやって解決するのか知りたいとか、この人物がどうやって変わっていくのか見たいとか。読者が共感できるからキャラクターに惹かれることもありますし、全然わからないから惹かれることもあるので、いろいろな形の魅力があるとは思いますが……。
読者の視点になれる登場人物を出してみる
——魅力的なキャラクターについて、深掘りしたいです。お二人が思う、魅力的な名探偵や犯人はどなたでしょうか?
藤野 東野圭吾さんの「ガリレオ」シリーズの湯川学です。とても変人、かつ、普通の人にはわからないような発想ができる天才性があるという、両方を持っているのが、名探偵の魅力の一つの形だと思います。そんな彼が読者に好かれる理由の一つは、個人的には「言葉遣い」かなと思っています。すごくかっこいいなと思うところがありますね。
あと、普通の人には近づきがたいような湯川先生と読者を橋渡ししてくれるキャラクターが配置されているのもポイントです。そのキャラによって、読者が湯川先生に距離を感じたままでいずに済んでいると思います。そういう、読者側に立ってくれるサブキャラクターの配置は大事かもしれませんね。
永島 変人な雰囲気だと、普通の人には解けない難しい問題も解いてくれそうな気がしますよね。納得感もあります。けれども、そうしたときに、ちょっと読者に寄り添ってくれる、一般人ぽいワトソン役のような人がいると、読者目線で話が進められるのかなと。天才の目線でずっと書かれていると、読者はついていけなくなることもあると思うので。
そういう意味で読者に近いキャラクターは、わりと多くの小説に出てくるパターンですね。『名探偵コナン』でいう蘭姉ちゃん(毛利蘭)のような、ツッコミ役みたいな立ち位置です。
——特徴ある名探偵や犯人を魅力的に動かすコツはありますか?
藤野 お話ししたとおり、天才性のある人物を置くのなら、物語の視点は一般人寄りの感覚を持っている人を1人置いたほうが、動かしやすい気がします。天才が自分の行動を全部語っちゃうのも、興ざめしてしまうと思うので。探偵なり犯人を、どういうキャラクターにするのかによって、必要があれば、物語の視点となる人物を名探偵や犯人のそばにいる人に変える、というのは一つのやり方かもしれません。
永島 解決シーンやなにかを捜査をしてるシーンなどをイメージして、こんなセリフとかこんな雰囲気の行動をしていたらおもしろいよね、というところから、キャラクターを最初につくるというのもありかなと思います。
藤野 授業ではすごく不真面目だけど謎を解くときにだけIQが高くなるギャップがあるとか。メインとなる名探偵がこんな人だったらおもしろいから考えると、魅力に繋がる気がしますね。
「探偵がどうやって情報を得るか」のリアリティは大事
——天才ばかりだと、読者がリアリティを感じられないかもしれないと思ったのですが、そういうケースはありますか?
永島 リアリティの問題は難しいですね。同じような行動でも、作品によってはリアリティを感じるときもあれば、なんだか浮いちゃうこともあるので、こうすれば必ずリアリティが生まれるというのは言いづらいです。
やはり、それぞれのキャラクターがどんなふうに考えて動いているかを意識して書いてるほうがいいかなとは思います。たとえば、なにか事件が起こって、探偵が捜査をして、調べ物をするわけじゃないですか。捜査のためにいろいろなところに行って、行った先で当然情報が得られて話が進んでいくんですよ。この、情報の得かたというのが結構大事で、いきなり捜査で行った先の人から「こんな話がありますよ」と言われてしまうと、ミステリーとしてはご都合主義になってしまう。
「どういうふうに捜査をしていったら、どんな情報が上がってくるか」という、細かいところにリアリティが出るのかなと思います。失敗がいくつかあった上で成功にたどり着くというのが、王道なミステリーのあり方ではありますよね。
藤野 もし、これを逆手に取るなら、何も思いつかないんだけど、どんどん人が寄ってきちゃうような特殊な性質を持ってる人が探偵だったら、おもしろいかもしれないですね。
——犯人が魅力的なパターンもOKということですが、人間を殺す人を魅力的に描くのは難しそうです。魅力的な犯人像について、例があれば教えてください
永島 たとえば『刑事コロンボ』や『古畑任三郎』のような、いわゆる倒叙モノと言われる、最初に犯人がわかっているなかで物語が進んでいくタイプの作品は、犯人に魅力があったほうがいいと思います。
藤野 犯人側に知性の高さや、計算高さみたいなものがあって。ともすれば、ばれずにこのまま逃げ切ってほしいと思っちゃうような犯人だったら、それはそれで魅力的なのかもしれません。『シャーロック・ホームズ』のモリアーティ教授とかもそうですよね。
必要な情報を読者に先に提示することが、ミステリーの原則
——事件の設定やトリックなどを作家さんと一緒に考えることもあるのでしょうか?
藤野 あまりないです。場面作りやトリックというのは、基本的に作家さんが自分のオリジナリティで創作されるものなので、いただいたアイデアや原稿を拝見して、この辺がわかりにくいとか、リアリティが弱いといった意見をさせてもらうことはありますけど、トリックを提案することはないですね。
現実に再現できるのか誰にも検証できないような壮大なトリックを描きたい方もいると思いますが、その場合も「この舞台設定なら実現できそうな気がする」という説得力が、作品内で描かれているといいのかなと思います。
永島 犯人の詰めは甘くないほうがいいとは思いますね。犯人は絶対に逃げるつもりで事件を起こしているはずなので、探偵に謎が解かれてしまう前提で「この次の脱出方法を決めてないんじゃないかな?」というようなつくりは、やめたほうがいいと思います。
——実際に小説を書き出す前に、プロットや構成を組み立ててから書いたほうがいいのでしょうか?
永島 ミステリー小説においては、ある程度つくっておいたほうがいいと思いますね。犯人を決めないで書き出す人がいるという話は聞いたこともありますが、やっぱりベテランでないと難しいかと。決めていないと伏線もつくりづらいです。先がわかってれば、ここにちょっと伏線を忍ばせておこうということもできます。
藤野 「実は双子だった」など、解決の場面になって新たな情報が後から出てきてしまうのは、よくないですね。必要な情報が事前に提示できているかを確認するためにも、構成は事前に決めておいたほうが、詰めやすいとは思います。
永島 情報をしっかりと読者に提示しておいて、その提示した情報の中で解決できるというのが、ミステリーの原則のルールです。
新人賞の選考では長編作品を読むことが多いのですが、前半と後半で話がだいぶ変わってしまうような作品も多くあった印象があります。前半は新聞社を舞台にした社会派の事件を追うようなもので、緊迫して進んでいたにも関わらず、後半は思いっきりスパイアクションになってしまうとか。なんだか、テイストがだいぶ変わってしまうんですよね。
最初にプロットをきちんとつくってないからなのか、理由はわからないですけれど、意外とそういう作品は多いので、最初にある程度の構成は考えたほうがいいかなと思います。
——情報の提示や伏線の貼り方が見事だと思った作品を教えてほしいです。
永島 去年出版した、阿津川辰海さんの『録音された誘拐』は、最初に読んだときはめちゃくちゃ驚きました。自分が担当編集なので何度も読むんですが、2回目からは結果を知った状態で読むなかで、こんなに大胆に伏線が貼られていたことに驚く。こんなに堂々と書いてある!、って。
藤野 意外と伏線は大胆に書いても大丈夫ですよ。初めて読む人は結構わからないので。
永島 そのぐらい大胆に書いていないと、逆に伏線だと気づかれないことになってしまいます。後半に読んで驚いたときに、前半のあそこに書いてあったと思い出して、初めて伏線が成立するので。書いてあったことすら読者が忘れてしまっていると、なんにもなくなってしまいます。
——今回の創作大賞は2万字から応募できるので、短編も受け付けています。短編と長編で、構成のつくりかたは変わってきますか?
藤野 変わってくると思います。私の個人的な意見では、短編は登場人物に寄りかからなくても書くことができる事件を扱う印象です。その場合は、キャラクターにあまり引っ張られずに書ける分、謎やその解決の驚きだけで話を持っていく必要があると思いますね。
永島 ミステリーの場合、短編は切れ味が綺麗なほうがいいと思います。文章自体は短いけれども、しっかり驚くことができる部分が一箇所でもあればいいと思うんですよ。要素を入れすぎてしまうと、短編は逆にわかりにくくなってしまうので。なので、ここで驚かしたいんだよというところを、一番驚けるタイミングに入れて、あとはシンプルにつくったほうが切れ味がよくなると思います。長編だと、1個の要素だけで物語を組み立てるのは、難しいかもしれませんね。
藤野 長編は積み重ねとしてのおもしろさで、短編は会話の途中から始まるくらい唐突なほうが、逆におもしろい場合もあると思うので、そこは違いかもしれません。
「ここで驚かせたい」という強い思いを形に——
——応募者にまずはこれを意識してほしいというアドバイスはありますか?
永島 自分で、「ここはおもしろい」と思ってるところがあるといいなと思います。ミステリーはあんまり人生経験がなくても書けるジャンルだと思うので、若い人にも書きやすいと思うんですよね。自分の頭の中で想像した世界だけでつくれますし、年齢に応じていろいろな書き方があると思うので、自分の頭で考えて、ここでおもしろがらせたいとか、驚かせたいという思いが、1つあるといいです。あとはそれを膨らませて伝えるだけなので、最初にその思いが強くある作品のほうが、魅力的だと思います。
藤野 私も同じ意見です。完璧にしていないと成立しないと思わず、自分でおもしろいと思うところを、まず押して書いていただくのがいいかなと。それを拝読した上で、私たちはできる限り、おもしろくするためのお手伝いができると思います。
——今回、応募作は必ず冒頭にあらすじをつけるルールになっていますが、作品の魅力はあらすじでアピールしたほうがいいのでしょうか?
藤野 何でこういうことが起きたのか、この密室がなぜ解かれたのか、など一言で説明できるようなあらすじがあったほうがいいとは思います。あらすじが簡単につくれるということは、作品としてのまとまりがあるということだと思いますね。
永島 ミステリー小説の場合、あらすじは解決編まで書いてなくてもいいですけどね。
——審査ではスキ数など読者の人気度も参考にします。読者の目に留まりやすいタイトルのコツはありますか?
永島 あまり長すぎないほうがいいとは思います。長いタイトルも最近は多いですけどね。あと、今回は応募総数が多いんで、キャッチーな言葉があるほうがいいのかもしれないです。
藤野 タイトルがつけやすいということは、なにか一貫性のある物語になってるということだ思います。タイトルをつけるときに、これしかタイトルの候補はないなというものが出てくるような作品になると、いいと思います。
——今までの新人賞の選考の際に感じた、応募者が陥りがちな落とし穴などがあれば教えてください。
藤野 魅力的な殺人事件にするために、「なんでそんなことになっちゃうんだろう」という謎はつくったほうがいいのですが、そこに無意味な作為があると、結末を読んだときに読者はがっかりします。意味もなく残酷なことをするとか、意味もなくなにかを送りつけてくる犯人がいるとか。それが結末に結びつけばいいのですが、本当になにも意味はなかったとなってしまうのは、もったいないです。なにかを送ることで、事件のアリバイをつくることができていたとか、別の理由があったとか、そういうほうが驚きに繋がると思います。
——作品の推敲やブラッシュアップについてアドバイスをうかがいたいです
藤野 これは何人かの作家さんに聞いたのですが、たとえばパソコンで打つときは横書きで書いて、推敲するときは、縦書きに書式を直して読むという方がいらっしゃいました。縦横はどちらが先でもいいと思います。なるべく別の目で、新鮮な気持ちで読むためにということらしいですが、見え方を変えただけでも、誤字脱字は見つかると思いますし。一歩引いた目線で自分の作品を見ることができる方法ですね。
永島 もし身の回りに家族や友達などで読んでくれる人がいれば、自分じゃない人に読んでもらうというのは、一つの手だと思います。やっぱり書いている本人だと、どうしても気がつかないことはあるので。他人が読んだときにどう思うかというアドバイスを聞いた上で、必ずしも直す必要はありませんが、「こういうふうに読む人もいるんだな」ということを知ることは、大きいと思いますね。修正は、締切もあると思うので、自分でも直したほうがいいと納得できる箇所はできる限り直していくほうがいいと思います。
——それでは最後に、創作大賞に応募するみなさんにメッセージをお願いします。
永島 プロではない方の、新鮮な作品に出会いたいと思っております。今からでも短編ぐらいなら執筆も間に合うと思いますので、ぜひ、どしどし応募していただければと思います。
藤野 本当に難しく考えずに、自分がおもしろいと思うものをぜひ形にしてみてください。
登壇者プロフィール
永島大
光文社 文芸編集部 副編集長。1994年、光文社に入社。『週刊宝石』『FLASH』『女性自身』編集部を経て、2021年より文芸編集部に。電子雑誌『ジャーロ』では編集長業務を担当。また、阿津川辰海氏『録音された誘拐』『阿津川辰海 読書日記 ~かくしてミステリー作家は語る』、竹本健治『話を戻そう』などを手掛ける。
藤野里佳
光文社 文芸編集部 デスク。2013年、光文社に入社。『Gainer』『FLASH』編集部を経て、2020年より文芸編集部に。電子雑誌『ジャーロ』では誉田哲也氏、中山七里氏、浅倉秋成氏らの連載を担当。知念実希人氏『死神と天使の円舞曲』、平山夢明氏『俺が公園でペリカンにした話』などのほかミステリーを中心に担当する。
創作大賞のスケジュール
応募期間 :4月25日(火)〜7月17日(月) 23:59
読者応援期間:4月25日(火)〜7月24日(月)23:59
中間結果発表:9月中旬(予定)
最終結果発表:10月下旬(予定)

創作大賞関連イベントのお知らせ
開催済みイベントのレポート
創作大賞説明会レポート ── 寄せられた質問に全部答えました #創作大賞2023
「フォロワーが多い人が有利?」「AIを活用した作品は応募できる?」などの質問に回答しています。
富士見L文庫(KADOKAWA)が語る「いま読みたい作品」──創作大賞RADIOレポート① #創作大賞2023
『わたしの幸せな結婚』など人気の小説作品を抱える富士見L文庫にレーベルの特徴や、キャラクターの魅せ方などをお聞きしました。
JUMP j BOOKS(集英社)が語る「いま読みたい作品」──創作大賞RADIOレポート② #創作大賞2023
『ジャンプ』とともに歩んできた小説レーベルであるJUMP j BOOKSに、お題として提示されたイラストの意図、イラストから物語を膨らませるポイントなどを伺いました。
幻冬舎コミックス・文藝春秋コミック編集部が語る「いま読みたい作品」──創作大賞RADIOレポート③ #創作大賞2023
幻冬舎コミックスと、文藝春秋コミック編集部に、コミックエッセイや女性向けのストーリー漫画を面白く魅せるコツを伺いました。
Palcy(講談社)・マンガMee(集英社)が語る「いま読みたい作品」──創作大賞RADIOレポート④ #創作大賞2023
少女マンガや女性向けの作品を中心に掲載する、大人気マンガアプリ「Palcy」と「マンガMee」。「ヒキが強いとはどういうこと?」「エモで読者を引きつけるには?」など漫画原作に求めることをお聞きしました。
朝日新聞出版 書籍編集部・ポプラ社 文芸編集部が語る「いま読みたい作品」──創作大賞RADIOレポート⑤ #創作大賞2023
朝日新聞出版 書籍編集部と、ポプラ社 文芸編集部に、ジャンルや時代をこえ多くの人を惹きつけるための作品づくりのポイントをうかがいました。
くわしくは、創作大賞 特設サイトをご覧ください。
text by 戸田帆南
