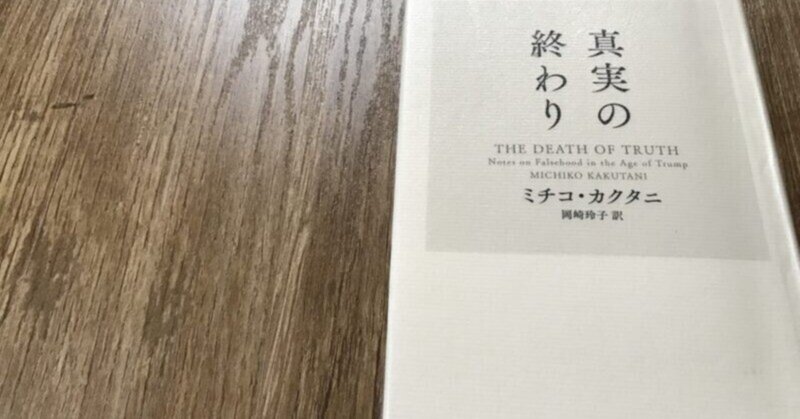
『真実の終わり』 ミチコ・カクタニ 「真実は人それぞれ」なのか
人類の歴史において、最も酷い政権のうちの二つが二〇世紀に権力を握った。その両方が、真実への冒涜と略奪に基づいていた。民衆は、シニシズム、疲弊感、不安によって、無制限の権力を求める指導者たちの嘘や偽りを受け入れるようになる、という考えに依拠していた。
最も酷い二つとは、いわずもがなナチスドイツ政権と米トランプ政権のことです。このキツイ書き出しではじまる本書『真実の終わり』を読み解いていきましょう。
『真実の終わり』の内容紹介
34年にわたってニューヨーク・タイムズ紙で書評を担当し、その鋭い批評眼から作家たちに畏れらたという著者ミチコ・カクタニ氏。この本はトランプ政権真っ只中の2018年に書かれたもので、トランプの嘘に侵食されていく社会が描かれています。
ハンナ・アーレント(1906-75 ドイツの哲学者『全体主義の起源』 『人間の条件』など)やジョージ・オーウェル(1903-50 イギリスの作家『一九八四年』『動物農場』など)のほか、膨大な資料や文献を紹介しながら「なぜ真実が軽視されるようになったのか」を紐解き、真実が失われていく不穏な世界をどう生きるか、を示す1冊です。(以下、引用部分は本書の引用を転用したものです)
原因は「ポストモダニズム」にあり!?
理性や科学、専門性よりも感情が意味を持つようになったとされる現代。その原因として著者が指摘するのは「ポストモダニズム」という思想です。
●ポストモダニズムとは
1960年代後半から80年代にかけて世界を席巻した思想。もとは建築分野から派生した言葉。実用主義的な近代建築物を嫌う「近代のあと(ポストモダン)」の建築家による建築様式を指す。これが思想にも派生した。革命など歴史を動かす大きな物語が意味を持った近代に対し、ポストモダンは「社会が団結して一つの夢を見る時代は終わった」という思想。
知識や道徳、言語、価値体系は構造主義が作り出したものとみなし、それを批判する自由な精神は芸術や文学にも反映されていきました。ポストモダニズムとして本書ではコーエン兄弟やクエンティン・タランティーノの名も挙がっています。
著者はポストモダンそのものではなく、ポストモダニズムが右派によって都合よく利用(気候変動否定、反ワクチン←新型コロナ以前から存在)されてきた経緯や手法を厳しく批判しています。
批判的思考を疲弊させ、真実を消滅させる
不完全で個人の視点で成立するポストモダニズムは、「なんでもアリ」「真実は人それぞれ」を作り出したと指摘します。トランプはそうした社会風潮を巧みに利用し、真実よりも感情に訴えることで人々を煽動してきた。オーウェルの小説『一九八四年』のビッグブラザーさながらに、言葉の意味をすげ替え、不都合な過去を修正していった、と。
一方、民衆は、Webメディアの個人データに基づくアルゴリズムによって自分の好む情報だけを目にするようになった。いわゆるフィルターバブルの状態で、トランプにとってはこれも好材料となったのです。
さらにトランプのSNSによる情報操作にはロシアも加わったという疑惑が。「現代のプロパガンダの核心は、誤った情報を与えてアジェンダを推進するだけでなく、批判的思考を疲弊させ、真実を消滅させることである」<引用> というロシアの民主化運動指導者ガルリ・カスパロフの言葉にもある「疲弊」というキーワードはコロナ禍の今に通じるものです。
さらにポスモダニズム的シニシズム(皮肉)は、既成の価値観を批判するのは有効だが「暴露した偽善にとって代わる何かを構築するのは」きわだって「使い物にならない」<引用>と。
評)「真実は人それぞれ」なのか
この本が書かれたのは新型コロナウィルス感染が起こる前の2018年です。コロナ禍の今、連日の報道は科学や専門基づいたものだけでなく、感染に対する恐怖感情を煽るだけのものも少なくありません。
何を信じればいいのかわからなくなりがちな中、2020年の大統領選に敗れた後もなおトロール(荒らし)として一部の人々の指示を集めているトランプ。その支持者の一部の「反ワクチン」やコロナ自体を否定する主張は驚きと呆ればかりか、まともな気力を奪っていきます。
SNSではコロナを否定する人と過剰に恐れる人、双方のおよそ議論にもならない主張が飛び交っています。オバマ元大統領は「我々の民主主義が直面している最も難しい課題の一つは、共通の基準としての事実を共有し合うことだ」<引用> と。
はたして「真実は人それぞれ」なのでしょうか。理解が及ばないこと、受け入れがたいことは「ウソ」であると排除し、自分の枠内で誰からも侵害されることのない考えを「真実」とするのは、私はあまりに心もとなく思うのです。
では、どうすればいいのか。著者は「簡単な解決策などない」としながらもこうあるべきという明確な意思を示しています。ぜひ本書で。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
