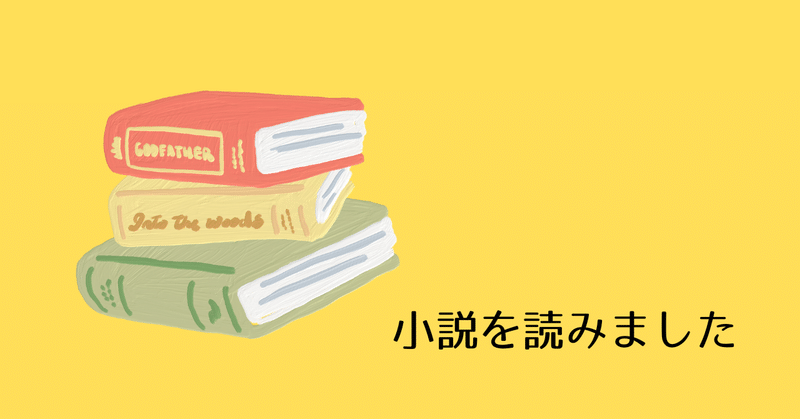
小説【本心】から米ドラマ【フレンズ】のロスとレイチェルの喧嘩について考える
平野啓一郎氏の「本心」
これは少しだけ未来に設定された話。2040年代、今からおよそ25年後。
物語は、29歳の青年、朔也(さくや)が亡くなった母親のVF(ヴァーチャル・フィギュア)の作製を依頼するところから始まる。
朔也の母親は「自由死」を願い続けていた。図らずとも事故死としてこの世を去った母親の「本心」を母親の情報を学習し続けるVFから語られることを朔也は期待していた。VFには「心」がないとわかってはいたが。
平野啓一郎氏の小説はこれが二冊目だ。
一冊目は映画化にもなった「ある男」。面白そうな映画があると聞き、
その映画が観たいな、と思っていたときに書店で原作を見かけた。
すぐに購入し読んだが、これが思いの外よかった。
私は「愛」がテーマの小説はあまり読まない。ミステリーやサスペンスはバッドエンドも好きな結末だが、「愛」がテーマのバッドエンドは読んでいてつらい。かといってハッピーエンドの恋愛小説も読んでいてどこかこそばゆくて苦手。自分が恋愛が苦手だったことも原因の一つかもしれないけど。
主人公の朔也は、高校を中退し、職を転々としながら今は「リアルアバター」の仕事をしている。「リアルアバター」とは、依頼した人の代わりに行動をする人のことで、仮想空間で自分の代わりに動かす「アバター」をその名のとおりリアルにすること。つまり依頼者の目を通して行動をする仕事だ。たとえば”羽田空港の展望デッキで飛行機を見る”という依頼があるとする。リアルアバターはゴーグルをつけて羽田空港の展望デッキへ行き飛行機を見る。すると依頼人は回線を通して、その景色を見ることができる。Face Timeのようなものではなく、おそらくはVRのようなシステムで、メタバースが日常となっている世界でのことだ。
母親はその仕事を好きではなかったが、あるとき朔也に河津七滝へ行ってほしいと仕事の依頼をしてきた、そのときは母親はその景色に感動し、朔也の仕事を認めてくれた。朔也は嬉しかったが、その後に母から告げられたことで激昂してしまう。それは「自由死をしたい」と母親が望んだことだった。
現在の日本では「死」は自由に選ぶことはできない。死期が迫っている時、痛みを和らげる緩和ケアを施し、延命治療はしない、という「尊厳死」は認められているが、人為的に寿命を短くする「安楽死」は法律で禁じられている。この物語は「自由死=安楽死」が認められている世の中が舞台となっている。しかし「安楽死」をテーマとしている話ではない。主人公の母親が「自由死」を望んだが、なぜそう望んだか、主人公はどうしても知りたかった。母の本心が知りたかった。だから母のVFを作ったのだった。決して裕福ではないのに、生活費の心配をしなくてはならないのに、母が遺してくれた財産を使ってまで。
しかし、どんなに精密であってもどんなに多くの情報を学習させて、母により近くなったとしても、<VF=母>には心がない。その<母>から本心を聞くことはできない。感情に任せて聞いても「お母さん、ちょっとわからないわ」という返事を繰り返されてしまう。それでもどこかで主人公は期待をしているのではないか。そしてそれを万が一聞けたとして、主人公は一体どうしたいのだろう。友達と呼べる友達もおらず、生活に追われ、リアルアバターとしての仕事を淡々とこなす毎日。毎日<母>と会話をすることで平衡を保とうとしているのか。そんな主人公が哀れにも思えてくる。
そして彼は、より<母>を本当の母親に近づけるために、母親が最後に勤めていた旅館で同僚でとても仲良くしていたという女性と会うようになる。<母>の存在を喜んだ女性は、毎日のように<母>と会話をしていた。そのおかげで<母>よりリアルに近づいていった。
母と息子の2人だけの生活から、母が死に、息子だけになった。そして遺産の大半を使って<母>を作り、また母と息子の生活が始まった。いや、そうなのだろうか。母ではなく<母>であり、結局息子は1人のままなのだ。
では<母>を作ったのは間違いだったのか、ただの無駄遣いだったのか。
いやそうではない。
訳あってその女性と同居を始めたり、自分の仕事中の出来事がきっかけで人間関係が変わってきたりと、主人公の周りで大きな変化が起き始める。
その辺りから<母>と会話をしなくなってきている。私はそれでいいんだよ、そう思い、自然と口元がほころびながら読み進めていた。
そして主人公は今まで知らなかった自己の出生の事実を知ることになる。
そしてそれはにわかには信じられないような話だった。
あれだけ愛した母には、全く知らない部分があった。
人は自分以外の人間には知らない部分などたくさんあって然りなはずなのに、なぜ打ちのめされるのだろう。なぜだ!
ここにこの小説のテーマがあるのだ。
「最愛の人の他者性」
愛している人は自分の見えているものが全てではない。
だから「本心」というものも一つではないのではないか。
***
アメリカのドラマ「フレンジ」は1994年から2004年まで放送された大人気ドラマでマンハッタンで暮らす男女6人の日常を描くシットコムだ。
DVDを買い、Blu-rayを買い、ネット配信でももう何回観ただろうか。ブルーレイなのに、観過ぎで画面がフリーズしてしまうほど。
そんな「フレンズ」だが、10年続いたこのドラマは、スタート時に25歳前後の主人公たちも最終回を迎える頃には35歳前後になっていて、彼らの成長も結果として描かれている。離婚歴のあるロス・ゲラーという古生物学者の男性とレイチェル・グリーンというアパレルメーカーに勤める独身の女性。この2人が恋の行方もこのドラマの見どころとなっている。
ロスとレイチェルは10年越しのロスの片思いから両思いへとなる。しかしすれ違いの生活が続くことにより破局。その後もくっついたり離れたり。お互い愛し合っていることは、周りから見ればわかりきっているのに、お互いはそれを認めない。ロスは結婚まですることになったのに、誓いの言葉の最中に誤ってレイチェルの名を読んでしまい、結局離婚。
しかしこれで2人がよりを戻すわけでもない。しかしどちらかが一歩進もうとすると、片方は面白くない。そんなことばかり繰り返していた。
あるとき、酔った勢いで(ベガスで)結婚をしてしまった2人。慌てて婚姻無効手続きをすることになるが、ロスはここでこの手続きをすると、結婚に3度失敗をしたことになってしまうことが耐えられないため、レイチェルに黙って手続きをしなかった。結局こんな”結婚”はうまくいくはずもなく、ほどなくレイチェルにバレてしまう。怒り心頭のレイチェルは婚姻無効手続きで判事に嘘を吐いてしまったせいで手続きそのものが無効になり、「離婚」をするしかなくなってしまった。今度はこのことでロスが激怒し、レイチェルを責めまくる。そしてレイチェルの過去の行動をも責めた。それは2度目の結婚をした彼に「愛している」と言ったこと。しかしレイチェルは猛反発。「私は真剣にあなたを愛しているから言った。今回のとはわけが違う!」と。その時ロスは呆然とし、「確かに違う」と力無く言った。
別の友人に「婚姻の無効手続きをしないのは、まだレイチェルを愛しているから」としつこく言われていた。しかしロスが頑としてそれを認めない。言われるたびに「レイチェルなんて愛していない。バツ3になるのが嫌なだけだ」そう言い続けていた。それなのに、ロスはレイチェルに言われて呆然となったのだ。
ロスは本当にレイチェルを愛していないのか。
本当にただバツ3になりたくなかっただけではないのか。
ロスは本当はレイチェルを愛しているのではないか。
だからレイチェルの言葉に呆然としてしまったのではないか。
いや、どちらかが本当のロスなんじゃない。
レイチェルを愛しているロスと愛していないロスがいる。
「本心」を読み終わってから、あらためて「フレンズ」を観てそう思った。
「本当の自分はこんなんじゃない」っていう言葉、よく聞くけれど、
こんな自分もあんな自分も、自分なんだよ、って。
それでいいと思う。
すぅっと気が落ち着く、一冊だった。
いただけるなら喜んでいただきます。
