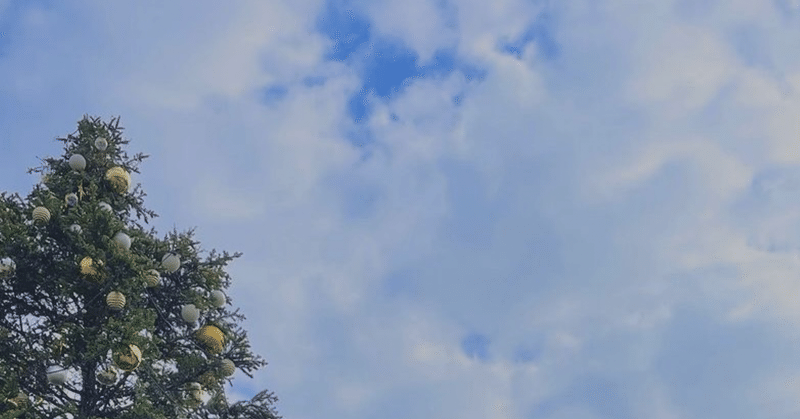
譚『空の泣きまね』の話/創作にまつわるあれこれ
皆様、今年も始まりましたね。
譚『空の泣きまね』
掛橋ちゃんがブログで楽譜を上げてくれたのを見て「書こう!」と思ったんだけど、後回しな性格がたたって(いつもより多めに回しております)、年も1月も明けてしまいました。
たぶん、この曲がどんな感じだったか覚えてる人はほとんどいないと思いますが、彼方の記憶と楽譜を頼りにメモがてら感想を書いていきます。

・相変わらず乃木スタ放送地域外在住かつHulu一気見即解約吝嗇人間なので、この曲は4期スタ誕ライブで初めて聴いた。
・優しいイントロに続いて〈ほら〉と語りかけるように歌いだす頭のパート(5〜12小節目)はスタ誕ライブ用に追加されたものらしいけど、「譚」の世界観の導入として自然に聞こえる(〈ほら〉〈例えば〉の味わい)
・13小節目からは安定と信頼のエモーショナル型カノン進行(D→C♯m7-5・F♯7→Bm7)。ここに宛てられている〈泣けてくる〉との詞がいい仕事してます(詞曲どっち先か分かりませんが)。
・サビに相当する〈空の色〜〉部分でメロディに動きができて一気に舞いあがる(AAA『恋音と雨空』にちょっと似てる、どっちも雨空だ)。
歌メロ自体は色味がけっこう淡めな感じで、本来こういうアコギで歌いあげるタイプの曲はもっとメロディがポップでわっしょい!なイメージ
>楽譜を見ると、この曲のサビ部分では、フレーズの始めやコードチェンジと重なるところのメロディにコードの構成音ではない音があてられていることが多くて、その淡い響きがすごい印象的(初めて聴いたときに音程合ってる?と思っちゃってベリベリごめん……)。
それこそ、サビ頭〈空の色〉の「そ」はA7にないシ(9th)の音だったり、他にも、次のGm7とミ(6th)、Dとシ(6th)などもそうで、お店の氷のような透明感がある。一目悠理ちゃんの声質とも合ってそう
>やっぱり『空の泣きまね』で泣いて笑ってるあたり曇り空を表象しているのかしら 個人的に、こういうメロディの動きが大きい+掴みどころのない響きで構成されている曲は歌唱の技術や慣れが“映え”に直結しそうだから色んな場所で歌っていってほしい
・〈悲しみに向き紛らわして〉で情感と音程の頂点を迎えて、「向き」のコードD→F♯m7/C♯の進行はちょっと重めで曇りがちなイメージにも聞こえる。
ここではコードチェンジの頻度が倍(2拍ごと)になって緩急のデザインを感じるところで、スタ誕ライブでは割と朗らかな感じの演奏/歌唱だった気がする
・その後の〈今日も〜〉で風呂敷を畳んでいく。この辺りからアンニュイなセブンスコードが激減して冒頭の響きに戻ってきている(BmとBm7に着目すると分かりやすく、基本的にBmの方では対応する歌メロの音がコードの構成音、Bm7ではそれ以外の音になっている)
こういう微妙な響きの違いで楽曲に揺らぎをちょい足ししているのは、どの程度意識的なものかは分からないけれど、割と渋めな設計思想(濃淡を楽しむ水墨画みたいな)。
>曖昧なBm7で「紛らわして」サッパリとしたBmで「手を振る」のはツーカーでしょ
・最後の部分は手筋のサブドミナントマイナー(Gm)で、浮かぶ夕景が寂しい。〈またね〉の延長線上の感情で、確かに明日を見てい「た」のが分かる。
こういう含みを持たせた歌詞はなんとなく悠理ちゃんっぽいと思った(モバメもとってないのに分かったような口利くんじゃない)。
・コードやメロディは味付けが薄めな自然派J-popで、素材本来の味を生かすタイプの楽曲。詞と曲の凹凸がパチっとはまってる感じが心地良い。
・悠理ちゃんはラップの方も気になる やみつきちゃんを一気見してた時に、ゲストに悠理ちゃん、新作のハーモニカ、KEN THE 390(弓木ちゃんめちゃ喜んでた)を迎えたラップ回がかなり良かったのもあって、いいトラックにバイリンガルなリリック乗せてほしいなぁと思う。
(アトノマツリのラップ部分とかメンバー作詞でもよくなあい?)
・悠理ちゃんのインスタ「アメリカ生まれの大学3年生」が繰り出すうきうきハッシュタグが良いかんじ 創作に意欲的なのも良い(バラエティでもかなり積極的だし個人的にファーストインプレッションとの差が大きかった)
・掛橋先生の新曲も聴きたい(そういえばやみつきちゃんスプレーアート回での困った掛橋ちゃんの「せんせい……」よかった)
創作にまつわるあれこれ
・畑違いの創作が好きな話
上に書いた『空の泣きまね』みたく、私はこういう畑違いの創作は好意的にチェックしたいと思っています(アイドルとソングライティングは距離感ちょっと微妙な気もするけど お隣の青い畑)。
例えば、沼ソング『君の心は6パックに割れてんだ』も、おそらく音楽理論をいなしきって感覚で作曲しているであろう大沼ちゃんの、インディーロックのサウンド感にエキセントリックな調性がクセになるトラックをタイトルの〈君の心は~〉というキュートでユニークな暗示でまとめ上げる剛腕が面白かったり。
(「沼ソング うごメモ」で調べても全然出てこないの何)
SHOWROOM配信をご覧いただきありがとうございました!🎬🌸
— 櫻坂46 (@sakurazaka46) January 25, 2023
SHOWROOM配信
観てくださったみなさん
ありがとうございました☺️
新作沼ソング
『君の心は6パックに割れてんだ』
ぜひ聴いてください〜💖
by #大沼晶保#沼ソング#SHOWROOM#櫻坂46 pic.twitter.com/jENApaq888
また、作詞作曲までは行かなくとも、嶋佐OASISみたく人気芸人が楽曲をコピーしたりするやつとかもキャッキャと楽しんでしまいます(同時に音楽が表現のひとつであることを再確認)。
他のジャンルでは、カップスターYouTubeの角ちゃんさくちゃん漫才なんかも面白かった。あと、私がナポリの男たちをよく観ているのにも心根のこういう姿勢が関係してそう。
(ヒットソングメドレーは2021が一番好き)
このように、私は畑違いの創作をわりかし細胞レベルで好んでいるのですが、その原動力は「好きな人がなんか珍しいことを真心こめてやってるのがほどよい刺激になって楽しい」とかその程度のもので、そういう活動に対してよくある「無垢な感性や別分野での経験を活かした創作でうっかりそのジャンルにイノベーションの種をもたらしちゃうんじゃ…?」みたいな期待を寄せて奨励しているわけではないんですね。
まぁ、こういうのはジャンルの組み合わせやその成熟度にもよるんでしょうが(例えば芸人と非芸人のお笑いとかは結構鉱脈残ってそう)、そんな虫のいい話は基本的になくて、しいて言えば元の分野での活動にちょっとは経験値を還元できるかもね、新たなアプローチを選択肢として持てるかもね、ぐらいに考えています。実現できたらおいしい系の。
私たちが物珍しく感じるような創作活動は、たいてい単純な好奇心のもと、趣味と地続きの領域で行われてるものが多数でしょうし、そのジャンルの才能の芽を摘むことにもあんまりならないんじゃないかなぁと思っているので、嘲笑・揶揄を恐れずどんどんやってほしいな~と考えています(「真心」の定義付けも難しいけれど)。
・「クリエイティブであれ」にインセンティブ働きすぎ問題
坂道メンバーの創作を手放しで賞賛しがちな私も、その一方で公式の作品(表題曲とか)を手拍子で批判チックに語ってしまうことがあります。私がネガティブ寄りに言及してきたどんな楽曲であっても、人(評価基準)によってはその曲を好きだと感じるのが以上、その人の音楽体験に泥をかけてしまうようなことはできるだけ避けたいので、自分のnoteを読み返してちょっとワイルドだなぁと思ったところは少しマイルドな表現(地球の裏側)に直したりしながらも、「運営はんがもっとクリエイティブな攻めたことやったはるとこ見たいわぁ」みたいな願望だけはうっすらと書き続けています。
ですが、最近インターネットを眺めていて、こういう「クリエイティブであれ」という主張に一考の余地があることを忘れて、むやみに連射するのもどうなのかしらと考えることがあるんですね。
特にTwitterとかだと、それ自体は基本的に「もっとちゃんとしなさいよ」の言い換えだったり、あるいは「新しい価値観を受容できるカルチャー人間ですよ」のポーズをとる意味もこめた微笑ましい行為だったりもすると思うんですが、実際にウンエイサンが社運をかけたクリエイティブな作品(ふわっとした表現)が世間にいまいちウケなかった場合でも、革新性に拒否反応を示す閉塞的なファンダムをワイワイ批判するサブカルつぶやきの肥やしにすれば不満なし(分断を強調する行為もプラスに働く)というライフハックが割とよくある形で存在して見える以上、「クリエイティブであれ」方向の抽象的な主張はそこまで信頼できるわけでもないものになっているのかなぁと思います(ある程度具体性を帯びていないと熟慮や覚悟が伝わりづらかったりもする)。
本来、創作に革新性や独創性を求めるのは正しすぎる姿勢だと思っているのですが、そこにさもしさが埋め込まれているのを感じてしまうと、それが危機感やワガママをきっかけとした誠実な思考に基づいたものなのかどうか揺らぎはじめて、サッカー観戦中の「シュート打て!」ぐらいの精度に思えてしまうことがあるんですね。
私は坂のある街では善良な一市民でありたいし、坂道人気に乗じてSNS上で自分の想いを拡散させながらコミュニケーションを楽しむ中で、自分があんまり良く思えない楽曲に微々たる罪悪感を蒸着させてしまわないよう、制作側が見てるわけない提言とかはなるだけオブラート(京言葉)に包んだもの(八ツ橋)にしているんですが、でも、あからさまに課題として映る部分を共有するのはモヤモヤを解消していくためにも重要な営みだし、でも、それが本当に課題かの議論は割とすっ飛ばされがちで、でも、そもそも個人のつぶやきなんて大して力ないんだから気にしなくてもいいだろ、リスクを背負う覚悟なんていらないだろ、すっこんでろタコ、とも、でも、割と影響力ってあったりするんじゃない?とも、ソニーグループのブランドミッションよろしくただクリエイティブで感動させてほしいだけなのに……とも思います(千日手)。
何が正しいかわからないモードに入ってしまい、いつもどおり結局「センシティブな感想を言うときは誠実に、内容をできるだけ吟味したいよね」ぐらいの丸くてマイルドな結論に着地する読み甲斐のない文章にはなってしまうんですが、こういう身にならない内省も時にはあっていいのかな、と思います。
最後まで読んでくださったあなたには、
のお裾分けシステムすごい良いと思います
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
