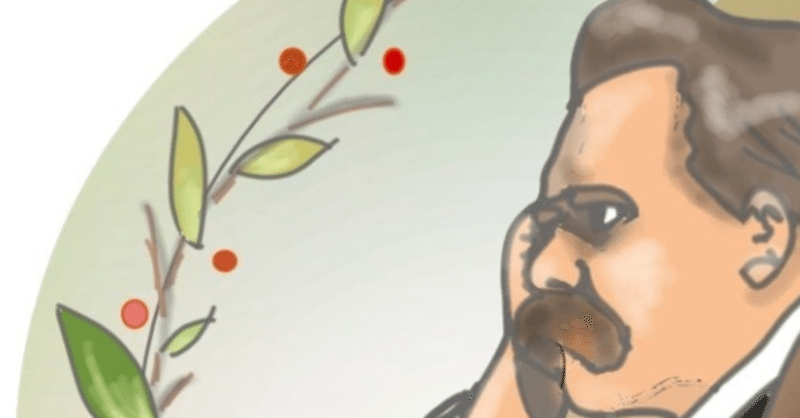
竹田青嗣「ニーチェ入門」(ちくま新書)読書会レジュメ(“ニーチェ”のスタートアップ的解釈)
1.はじめのニーチェ
当時の思想家たちには、「この世(人生)は矛盾・苦しみにあふれている」という考え方が大前提にある。これは現代においても、おそらく同じ。
ショーペンハウアーによると、人間は理性によってこの世界の矛盾(生の苦悩)を解決することはできない。人間はただ、この苦悩をある仕方で慰めることができるだけだ。その方策とは、「哲学」、「芸術」そして「宗教」である。
それを前提としたうえで、ショーペンハウアーのようにペシミスティックに考えるのではなく、人間の欲望や自我を肯定する「ディオニュソス的」な考え方をするのがニーチェ先生。
まずアポロン神は光明と芸術を司る。理知にあふれた予言の神でもあり、情念を芸術へと形象化する力を象徴する。これに対して、ディオニュソス神は酒精の神で、祝祭における我を忘れた狂騒や陶酔を象徴する。現代的な言い方をすれば、アポロン神は混沌に形を与える力を、ディオニュソス神は、秩序化され形式化された世界にもう一度根源的なカオスを賦活するような力を司ると考えればいい。
ショーペンハウアーでは、この世の矛盾は解決しようがなく、宗教とか芸術によってしか脱却できないというペシミズムに力点がある。しかしニーチェの力点は、人間はその欲望の本性(生への意志)によってさまざまな苦しみを作り出す存在だが、それにもかかわらずこの欲望(生への意志)以外には人間の生の理由はありえない、という点にある。これがニーチェの「ディオニュソス的」という概念の核心部なのである。
ニーチェは、仏教的なアプローチで「この世の矛盾」から生まれる苦しみを克服することにネガティブ。なぜなら、欲望を否定することで人間が”弱体化”してしまうから。
たしかに、人間から欲望を取り除いてしまったら、その人自身も弱体化するし、なにより、社会や技術も前進してこなかったはず。欲望は社会進化の原動力であるはず。一方で、社会が前進しすぎた結果として「地球資源の有限性」に人類は直面しているのも事実。
「煩悩」こそが一切の苦しみや矛盾の源泉であり、したがって「色即是空」と観じて「煩悩」を消し去れば人間は救われるという考え方である。しかし、ニーチェは『悲劇の誕生』においてこの考え方にはっきりと反対しているのである。「欲望する存在としての人間は矛盾に満ちている、しかしそれにもかかわらず、この欲望の本性は否定されるべきではない」。
また、ニーチェは、知識と理性に信頼をおき、正しく思考し推論することによって「真理」に達するという考え方を否定。
あくまで知識と理性に信頼をおき、正しく思考し推論すること。そのことによって「真理」に達すること。このことこそ人間の生にとってもっとも重要な営みであるという考え方。これがニーチェのいう「理論的楽天主義」だが、こういう考え方をソクラテスがはじめてギリシャ世界にもたらした。そのことによって、あのディオニュソス的な本質を持ったギリシャ悲劇の精神は決定的に滅んでしまった。ニーチェはそう主張するのである。
「より高い人間」の創出ということ。これがニーチェが設定した人間の文化の目標である。このことの意味は大きくいって二つある。第一は、ルサンチマン思想によって人間を平均化、凡庸化することへの対抗。第二は、「歴史」の目標を「人間」以外のものに設定することへの対抗ということである。
当時のキリスト教、民主主義思想、近代哲学などは、ニーチェにとって人間精神を「凡庸化」する元凶と見なされていた
2.批判する獅子
そもそも、「哲学」の本質は、既存の通説的な観念や考え方に対する疑いや批判にある。
哲学者の仕事は、しばしば、それまで自明となっているある観念への徹底的な疑いや批判というかたちで行われる。たとえば、ソクラテスはギリシャ哲学に流通していた「原理」や「起源」(アルケー)の観念を批判したし、デカルトは中世以来の神学的な世界観を疑った。また、イギリス経験論は「実体」とか「実在」という観念を徹底的に疑い、カントは哲学の伝統的な形而上学の問い(神は存在するか・自由原因はあるか・魂は不滅か、というような問い)それ自体を批判した。しかし、それまで自明とされていた観念(世界像)を徹底的に疑い批判するという点では、ニーチェほど鮮やかにそれを行った哲学者はいない。というのは、ニーチェの批判の対象とは、要するに、「これまでヨーロッパにおいて考えられてきた人間的な価値の一切」だったからである。
哲学者ニーチェの批判の対象は、当時において「これまでヨーロッパにおいて考えられてきた人間的な価値の一切」。具体的には、①キリスト教、②道徳、③真理という観念の3点。これらは、現在においても人間的な価値として重宝されている概念ともいえる。
ヨーロッパで考えられてきた、「これこそが人間のあるべき理想である」という考え方の一切を徹底的に疑ってみること。これがニーチェの根底的「批判」の眼目にほかならない。さて、では「これまでヨーロッパにおいて考えられてきた人間的な価値」とは何か。それは大きく言って三つある。まず「キリスト教」、つぎに「道徳」、そして「真理」という観念(「真理への意志」)である。ニーチェによればこれらがヨーロッパにおける「これまでの最高価値」であり、まさしくこれらを徹底的に批判しなくてはならない。
①キリスト教について
ニーチェは、欲望を含めた自分自身を肯定する利己的な人間(貴族的な人間)が「よい」人間であると定義する。一方でニーチェはキリスト教を批判している。すなわち、キリスト教は、強い者は悪いという否定的評価をはじめに置き、つぎにその”反動”として「だからわれわれ弱い者はよい」というロジック(弱者のルサンチマン=恨み・嫉妬・反感)を基礎にしている僧侶的なものである、とのこと。
ニーチェの言い分はこうである。キリスト教の信仰が崩壊したためにニヒリズムが現われた、そうひとびとは考えるかもしれない。しかしじつはそうではなくて、キリスト教それ自身の本質が「ニヒリズム」なのであり、現在それが顕在化しているのにほかならない。
「よい」の本質は「利他性」(人が喜ぶことを行う)にはなく、むしろ「利己性」にある、あるいは自己の「力の感情」にある。これがここでニーチェが示している根本仮説である。
「貴族的評価様式」は、「高い者」、「強力な者」から生じた本来的な「よい」の本質を持つ。つまりそれは、「力強い肉体、今を盛りの豊かな、溢れたぎるばかりの健康、加うるにそれを保持するうえに必要なものごと、すなわち戦争、冒険、狩猟、闘技、さらにはおよそ強い、自由な快活な行動を含む一切のものごと」が前提となるような価値評価である。それは、これら諸力についての肯定的、かつ能動的な自己感情を根拠としている。これに対して、「僧侶的評価様式」は正反対の性格をもつ。こちらは「高位」で「強力なもの」からではなく、「卑俗で」「弱い」人間たちから出てくる。……この僧侶的価値評価の本性は「反動的」である。なぜならこの評価は、まず「敵(強い者)は悪い」という否定的評価をはじめに置き、つぎにその”反動”として「だからわれわれ(弱い者)は善い」という肯定の評価を作るからだ。このことからこの「僧侶的評価様式」の起源を見てとることができる。つまりそれは、弱者の「ルサンチマン」(恨み、嫉妬、反感)から出てくるのである、と。
「僧侶的評価様式」を、民衆支配の手段として利用したとして、ニーチェはキリスト教を厳しく批判する。
ルサンチマンから発した「善悪」という「僧侶的評価様式」をはじめに作り出したのは初期キリスト教である。ただそれは、まだ現実的な弱者としての自分たちを心理的に補償するための思考法にすぎなかった。ところが、パウロによって打ち立てられた世界宗教としてのキリスト教(協会)は、この「善悪」の評価をさらに屈折させて独自の価値の体系を築きあげることになった。すなわちそれは、個々人が「唯一の神」を贖い切れない負債(罪責)を負っているという考え方を打ち立てたのである。人々はこれによって、自分の存在それ自体を”疚しいもの”と考えるにいたる。ヨーロッパにおけるキリスト教の支配とは、じつは万人に対するこの罪責観念の普遍化ということを意味する。
「私は苦しい――これは誰かのせいにちがいない」。こう考えることは、現実を動かす力がないときにはまさに生を堪えがたいものにする。そこで禁欲主義的僧侶はこう教える。「お前が苦しいのは確かに誰かのせいだが、その誰かとは、ほかならぬお前自身にほかならない」、と。この「ルサンチマンの方向転換」は、ある意味で、弱者たち、苦悩するものの生を宥め、守るという役割を果たす。そしてこの「ルサンチマンの方向転換」に成功することで、禁欲主義的僧侶たちは「苦悩者らにたいする支配」を打ち立て、その王国を築くことに成功した。ヨーロッパにおけるキリスト教会の支配とは、つまりそういう事態だったのだ、と。
当時のヨーロッパのニヒリズムは、キリスト教に原因があるということも主張。
ヨーロッパ独自の人間の価値観、それは「何のために生きるか(苦しむか)」という問いに対して「一つの意味」を与えつづけてきた。「神のために」、あるいは「あの世の生のために」という意味を。これが「禁欲主義的理想」だが、「あえてこれをはっきりと規定するなら」それは「虚無への意志であり、(略)生のもっとも基本的な諸前提にたいする反逆」だと言える。つまり、現代のニヒリズムとは、キリスト教的理想の反対物では決してない。それはじつはこの「虚無への意志」というヨーロッパの理想の本性が、宗教的な覆いを剝がされて露わになったものにほかならない……。
貴族的な人間は、自己の欲望を肯定する。そして、現実を直視し、矛盾が存在することは受け入れたうえで、コントロール可能なものに集中して、現実を動かそうという存在とのこと。
「貴族的」とは、スタートアップファウンダー的なマインドセットなのかもしれない。
ルサンチマンを持たない人間は、現実の矛盾をいったん認めた上で、自分の力において可能な目標を立て、あくまで現実を動かすことを意欲する。しかしルサンチマンを抱いた人間は、現実の矛盾を直視したくないために、願望と不満の中で現実を呪詛しこれを心の内で否認することに情熱を燃やす。こうして彼は、動かしがたい現実を前にして「敵は悪い」という価値評価を作り、さらにまた「汝の敵を愛せよ」という反転した道徳を生み出す。そしてそれはやがて、どこかに「本当に世界」があるはずだという「信仰」に至りつくことになる。
②道徳について
「利他性」を絶対的な価値基準とするような「道徳」観念も、貴族的な人間の牙を抜きかねないもの。
人類の進歩やイノベーションを生み出してきたのも、起業家個人の強烈な「欲」や「情熱」であることからして、ニーチェのいう、自己の欲望を肯定して現実を変えていこうとする貴族的な人間こそいまの日本に求められている可能性が高い(「知的バーバリアン」)。
一番声高に「利己性」の悪を叫び、「利他性」を絶対的な「善」として強調する人間が現れる。ニーチェによれば、まさしくそれをなすのが「僧職者」だちである。彼らは「善」と「義」の絶対性をいっそう強く叫ぶことによって、なにより虐げられた人間たちのルサンチマンを巧みに組織するのだ。「道徳」の”うさんくささ”の本質はこういう場面から生じてくる。「利他性」はもともと人間どうしの共同生活の中で自然な存在理由をもっている。困ったものを助けること、弱いものを保護すること、協力しあうこと、相互扶助等々は、人間の共同生活にとって必要不可欠なものである。ところが、「僧職者」たちは「利他性」を絶対化し、これを人間の絶対的な「善悪」の(つまり価値の)基準として流通させようとするだろう。
③真理について
「解釈」とは、世界が何であるかについていわば任意の「物語」を立てることである。「世界を解釈するもの、それは私たちの要求である」(『権力への意志』)。つまり人々の要求が多様であるのに応じて、「世界が何であるか」についての無数の解釈が存在する。それだけが根本の“事実”なのである。そしてその中で、いわばもっとも力をもった(説得性をもった、または権力をもった)「解釈」がこれまで「真理」と呼ばれていたにすぎない。これがニーチェの考え方である。
伝統的に「真理」と呼ばれていたものは、じつは最も強力な「解釈」のことだったにすぎない。では「解釈」の本質は何か。それは「価値評価」にほかならない。「価値評価」は何を根拠としているか。生命体の、それと意識されることも明示されることもない「保存・生長の諸条件」を根拠とする。「すべての生あるもの」はこの「保存・生長」を不断の要請として自らに課している。これをニーチェは「力」と呼ぶ。
ヨーロッパのニヒリズムの原因
19世紀ヨーロッパには、「相対主義」、「懐疑論」、「無神論」、「ペシミズム」、「デカダン」などの思想(総称して、「ニヒリズム」。人間の理想や価値における「超越的根拠」の喪失。)が登場していた。
ニーチェはその背景について、「この世界は仮象にすぎず、<真の世界>が存在するはずだ」という解釈が普及したものの、誰も<真の世界>などに到達できないことが原因だと指摘。
高度成長期を終えて、失われた何十年の“延長”を繰り返している日本にも、ある種のニヒリズムが蔓延しつつあるようにも思える。高度成長のような国民全員に共有されるわかりやすい「成長物語」が社会から失われてしまっているのが一次的な原因にも思えるが、より根本的には、ニーチェが指摘するとおり、真理=共通解釈=共通物語を求める姿勢に問題があるのかもしれない。
人間は、なぜ自分たちはこれほど苦しみつつ生きるのかとつねに問いつづけるような存在である。いったいわれわれは「何のために」生きているのかと。宗教や哲学はこの問いに対してさまざまな仕方で答えてきたのだが、ニーチェによればその答えは基本的に三つの「カテゴリー」を持っていた。まず第一に「目的」、つまり「世界には確固とした目的があるはずだ」。第二に「統一」、「世界には摂理とその全体がある、つまりそれは何者かによって統一されているにちがいない」。そして最後に「真理」、すなわち「この世界は仮象にすぎない。したがって、<真の世界>が存在するはずだ」。人間はこのように、「苦悩」から世界に「意味」を探しもとめる。そして彼らは「目的」・「統一」・「真理」という三つの大きな意味を見出したのだが、これらの理念の確実性をどこまでも“誠実に”確かめようとしてきた。そしてこのいわば「真理へのあくなき誠実」が、ついには、世界はその彼岸に何ものも持っていないという事実の発見にまでいきつくことになるのである。
「苦悩」→「ルサンチマン」→「三つの推論(目的・統一・真理)」→「ニヒリズム」という道すじを経て現れたヨーロッパのニヒリズムは、ニーチェの中で、当然ひとつの新しい思想的課題を要請する。つまりそれは、ニヒリズムの克服、そして新しい「理想」を創出するという未曾有の課題である。これが「超人」そして「永遠回帰」の思想として結実するのである。
3.価値の顚倒
「真理が見つからない…(´・ω・`)」と萎えてしまっている人類に対する2大処方箋としてニーチェが提示するのが、①「超人」思想と②「永遠回帰」思想。前者は、社会的・歴史的なアングルから構築した思想であり、後者は、個人の実存というアングルから構築した思想として整理できる。
①「超人」の思想
「真理が見つからない…(´・ω・`)」と萎えてしまっている人類に対する一つ目の処方箋が、「超人」の思想。
「超人」思想の基本コンセプトそれ自体は……要するに、これまでの「道徳」と「理想」を廃棄し、新しい「道徳」と「理想」を打ち立てることがその眼目である。では、どんな「道徳」と「理想」が可能なのか。最も簡潔な答えはこうである。それが存在することによって人間ををいっそう“強く”、“高貴に”するような「道徳」と「理想」を打ち立てること。言い換えれば、人間に、より深いルサンチマンやニヒリズムではなく、より大きな「エロス」と「力」を生み出させるような「道徳」と「理想」を創出すること。そのために、さらに「高い」人間のモデル(超人)を生み出すこと。そして、いま生きている人間は、このより高い人間の創出ということをおのれの「目標」として生きること。
「超人」の解釈は非常に難しいが、いわゆる「貴族的」な思考をもった、欲望に忠実な強い人間像として整理することが可能であり、ケインズが提唱した以下の「アニマル・スピリット」に通じる概念なのではないかと思われる。
投機による不安定性のほかにも、人間性の特質にもとづく不安定性、すなわち、われわれの積極的活動の大部分は、道徳的なものであれ、快楽的なものであれ、あるいは経済的なものであれ、とにかく数学的期待値のごときに依存するよりは、むしろおのずと湧きあがる楽観に左右されるという事実に起因する不安定性がある。何日も経たなければ結果が出ないことでも積極的になそうとする、その決意のおそらく大部分は、ひとえに血気(アニマル・スピリッツ)と呼ばれる、不活動よりは活動に駆り立てる人間本来の衝動の結果として行われるのであって、数量化された利得に数量化された確率を掛けた加重平均の結果として行われるのではない。
「超人」思想には、ある種の不平等性である「階序」を認める点など、扱いづらい側面もある(「超人」思想はナチスに援用されたとの見方もある)。しかし、強者と弱者が存在するのは事実であり、それを認めることと、「強者の論理」とは明確に区別するべきである。
ニーチェが主張しているのは、あくまでも強者と弱者が存在するという”ファクト”の是認。これはイデオロギーや社会革命思想ではなく、社会のあり方に対する洞察にすぎない。この事実を否定していると、人間が凡庸化して虚弱化してしまう、というのがニーチェの主張である。
なお、「平等」の概念も単一ではなく、例えば、結果についての平等と機会についての平等がある。おそらく、「自由」を拘束しあうルサンチマン思想を批判している点からすれば、ニーチェは「機会の平等」については肯定的であり、否定しているのはあくまでも「結果の平等」の話なのではないかと思われる。
「横並び」主義を否定して、優勝劣敗が生まれることを前提としてイノベーションに専念する。まさにスタートアップに通じる思想だというのは考えすぎだろうか。
ヨーロッパにおけるキリスト教の勝利は、支配されていた弱者たちのイデオロギー上の勝利を意味する。「人間は神のもとに平等である」というイデオロギー、そして、「人間は生まれつき平等である」というイデオロギー、これらは、「優れた者と劣った者が存在する」という事実の否認から生じるルサンチマン思想のイデオロギーにほかならない。この人間の「平均化」は何を意味するか。互いにその「自由」を拘束しあうこと。そのことによっていっそう凡庸化し、虚弱化した人間を制度的に作り出すことである。ニーチェはそう考える。
要するに平等主義のイデオロギーは、自分たちは貧しい、ゆえに苦しい、だから貧富の差は存在すべきでないと主張する。それはもとをただせば、強者と弱者の秩序自体が不当なものであって存在すべきでない、したがって人間はすべて平等であるべきだというキリスト教的、ルサンチマン的推論をその源泉としている。またそれは、強い人間と弱い人間が存在するという動かしがたい現実を否認することによって、個々人が人間として持っているはずの真の課題を取り逃がすのである。つまり、「弱者」にとってほんとうに重要なのは、自分より「よい境遇」にある人間に対して羨みや妬みを抱くことではなく、より「高い」人間の生き方をモデルとして、それに憧れつつ生きるという課題である。また「強者」にとって重要なのは、他人の上にあるということで奢ったり誇ったりする代わりに、自分より弱い人間を励ましつつ、つねに「もっと高い、もっと人間的なもの」に近づくように生きるという課題なのである、と。
②「永遠回帰」の思想
「真理が見つからない…(´・ω・`)」と萎えてしまっている人類に対する二つ目の処方箋が、「永遠回帰」の思想。
ニーチェ自身が、「永遠回帰」の思想がもっとも伝えることが難しいものだと認めており、解釈も非常に難しい。竹田青嗣「ニーチェ入門」(ちくま新書)の整理は以下のとおり。
「永遠回帰」の解釈
(1)機械的思考の極限形式としての「永遠回帰」
(2)ニヒリズムの極限化としての「永遠回帰」
(3)育成の、理想形成としての「永遠回帰」
(4)ルサンチマン克服の、生の肯定としての「永遠回帰」(1)機械的思考の極限形式としての「永遠回帰」
「永遠回帰」の一つの解釈・側面は、世界は神によって創造されたわけではなく、したがって目的もなく、次第に発展していくというベクトルがあるわけでもなく、ただただ”輪廻”のような循環を空虚に繰り返すものでしかなく、それ自体に何の意味もないという考え方。
たとえばまったく抵抗のないビリヤード台の上でたくさんの球が、摩擦によって力を失うことなく永遠にぶつかり合って動き回っている、という状態をイメージしてみるとよい。時間は無限にあるから、一定の空間の中で一定のエネルギーがその力を減じることなく運動していると、いつかある時点で、以前のどこかの時点で存在したとまったく同じ物質の配置、配列が戻ってくる可能性があるはずだ。すると、その次の時点から、一切が「何から何までことごとく同じ順序と脈絡」で反復することになる、というわけである。
重要なのは、もしこの新しい世界観(像)を受け取るなら、つぎのような従来の三つの伝統的世界観が否定されることになるということである。第一。世界は神によって創造された、したがって世界はその進み行きのうちにある「目的」を持っているという世界観(キリスト教的)。第二。世界は神によって作られたかどうかは言えないが、たとえばそれが生命の「進化」を促すように、次第に「進歩」し「発展」するものであるにちがいないという世界観(ヘーゲル的)。第三。世界ははじめの起点から何らかのかたちで持つが、その後はそれ自身の法則つまりただ機械的因果によってのみ動いているという世界観(唯物論的)。
(2)ニヒリズムの極限化としての「永遠回帰」
機械的思考の極限形式としての「永遠回帰」を前提とすると、世界はただ存在しているだけ、ということになる。これがニヒリズムの極限化としての「永遠回帰」である。
世界は、始まりも終わりもなく、したがって動機も意味もなく、いわば永遠運動する自動機械のようにただ単に存在しているにすぎない。これが「永遠回帰」にイデーがもたらす第二の論理的帰結である。
「一切が永遠に反復する」というイデーは、人間の存在を、宇宙の壮大な自動運動の一部分にすぎないものへとおとしめるのである。
「人生死ぬまでの暇つぶし」という言葉があるように、現代においてはそこまで過激な思想ではないが、キリスト教的思想が支配的であった当時においてはかなり過激なものとして受け取られた模様。
(3)育成の、理想形成としての「永遠回帰」
「永遠回帰」の思想は、一方で、ニヒリズムを極限まで押し進めることを意味する。しかしそれは単に「否に、否への意志に停滞する」のではない。「むしろ逆のことにまで」、つまり「ディオニュソス的な」大いなる「肯定」にまで「徹底しようと欲する」試みである、とニーチェは言う。
「永遠回帰」に耐ええない思想、つまりそれが示す徹底的なニヒリズムに耐ええない思想はやがて思想として「没落」する。そういう意味で、「永遠回帰」は人間がニヒリズムに耐えて新しい思想を打ち立てうるか否かの決定的な“試金石“である。
上記についてはかなり理解が難しい。いったん「ニヒリズムを徹底する、つまり、極限的な虚無性まで含めてすべてを受け入れる。そして、腹をくくる。」という意味に理解しているが、適切なのかは不明。
(4)ルサンチマン克服の、生の肯定としての「永遠回帰」
ニヒリズムを徹底するということの発展形として、「世界に目的とか意味とか、あるわけねえだろ。ガタガタいうな、甘えるんじゃねえ。それでも生きるんだ。」というメッセージも「永遠回帰」には含まれているという趣旨であると理解できる(ように思えるがどうなのだろうか)。
苦しい生のただ中を生きる人間にとっては、自分たちが「なんのために生きているのか」、「なんのために苦しんでいるのか」という問いの答えが、どうしても必要なものになる。それがうまく答えられるなら人は大きな生の苦しみに耐えうるからだ。逆に、この問いがまったく答えられないなら生は耐え難いものとなる。人間が、長い間「神」や「道徳」や「真理」を信仰し、求めつづけてきたことの根本の理由はここにある。「ニヒリズムを徹底すること」。それはつまり人々からこの「なんのために」の答えを永遠に剥奪することを意味するといってよい。この世のどこかに「真なるもの」が存在するわけでもなければ、何ものかが世界の「目的」や「統一」を司っているわけではない。世界はただ無限の時の中を、意味もなく、ぐるぐると回帰しているだけである……。
ニーチェの立論は「ニヒリズムを徹底して人生あきらめろ」というものではなく、あくまでも、新しい「価値創造」をもたらすためにニヒリズムを徹底せよ、というもの。しかし、ニヒリズムの徹底がどのようなロジックで価値創造の原理につながるのかは、明快な解釈がない模様。
「永遠回帰」は単なる物理学的宇宙論なのではない。ニーチェのつもりではそれは、このようなニヒリズムの徹底の果てに現われる「聖なる虚言」、すなわちこれまでとはまったく異なった新しい「価値創造」の原理でなければならない。しかし、いったいどのように考えれば「永遠回帰」の説がそのような「価値創造」原理へと転化するのか。ここに「永遠回帰」の思想の最も深い”謎“がある。
下記のように、「生を是認し、さらにそれに「然り」ということ」こそが「永遠回帰」のコンセプトであるとの説明もある。「然り」とは、今風にいえば「オッス」といったところだろうか。
人は生の苦悩に対してふたつの根本的な態度をとりうる。一つはそこに「キリスト教的意味」を見出すこと。つまりルサンチマンから自分の生の時間に復讐するという態度。もう一つは「悲劇的意味」を見出すこと。すなわち、巨大な苦悩にもかかわらず生を是認し、さらにそれに「然り」ということ。後者の態度をニーチェは「ディオニュソス的」態度と呼ぶ。この二つの態度の決定的な違いは何か。前者は人間の「生への意志」(=欲望)を卑小化し、頽落させ、弱体化させる。その理由は、ここで人間の生への欲望は本質的にルサンチマンの欲望として生きるからである。これに対して後者は、人間の生への欲望を高貴にし、尊厳あるものとし、そして豊かにする……。
「なんのためにわたしたちが生きているのか、なんのために苦しんでいるのか(略)……それがわかったら、それがわかったらね!」とオーリガは叫ぶ。ニーチェは答える。この問いに答えるものはもはや誰もいない、この問いの答えは存在しない。世界と歴史の時間にはどんな「意味」も存在しないと。そして、それにもかかわらず君は生きねばならず、したがって「なんのために」ではなく「いかに」生きるかを自分自身で選ばなくてはならない、と。
要するに、「永遠回帰」という思想は、「この世界?人生?真実もないし、意味もないっす。押忍押忍。意味なんてないからこそ自分の欲望に忠実に生き抜きます。魂燃やします。」というある種のアニマル的ドM性を推奨するものなのかもしれない。
4.「力」の思想
竹田青嗣「ニーチェ入門」いわく、「力への意志」という概念があるからこそ、ニーチェの思想はエッジが立っているとのこと。
本書は、「力への意志」への理解を以下のように整理する。
(1)徹底的認識論としての(認識論の破壊としての)「力への意思」
(2)生理学としての「力への意思」
(3)「価値」の根本理論としての「力への意思」
(4)実存の規範としての「力への意思」(1)徹底的認識論としての(認識論の破壊としての)「力への意思」
「この世に存在するのは解釈だけである」という考え方は、構造主義(言語学など)も有名になったこともあり、現代においてはかなり一般化しているように思える。
「事実というものは存在しない、ただ解釈だけがある」という命題は大きく言ってふたつの“解釈可能性”を持っているということだ。第一は、これを懐疑論的、相対主義的に受け取る観点。……第二は、これを解釈や評価についての徹底的な懐疑として受け取らず、およそ世界像の生成についての「根本原理」として受け取る観点である。
面白いのは、ニーチェが、生命体が自分の保存・生長の条件を参照して解釈を行っていると主張しており、リチャード・ドーキンス「利己的な遺伝子」に通じる考え方になっているところ。
振り返ってみると、「利己的な遺伝子」のメッセージである、①生命体は遺伝子を運ぶ機械に過ぎない、②遺伝子に求められるのは非情なまでの利己主義といったものも、ニーチェのその他の考え方に通じるように思える。すなわち、①については、「人生に意味なんてない。世界も遺伝子残存のための永遠回帰に過ぎない。」というニーチェ的考え方につながり、また、②も、「世界に意味なんてないが、欲に従って「超人」として生きるべし」という考え方につながり得る。
生命体が世界のありようを、自分の「保存・生長の条件」に応じて、また「支配欲」に応じて「価値評価」すること。したがって無数の“解釈された世界”が存在すること、これが根源現象である、と。……つまり、ある対象(事物)が「何であるか」という「認識」は、その対象(事物)に向き合う生命体の「肉体」(欲望=身体)によって決定される。
「価値評価する」という原理は「世界それ自体」のうちにはない。「価値評価する力」はただ生命体だけがもっている。その理由は明らかだ。生命体は、事物のように単に存在しているのではなく、たえず自分自身の「保存・生長」をめがけて存在しているからである。だから生命体だけが「解釈」し、生命体だけが世界に「遠近法」を持ち込むのである。
脱線するが、「「価値評価する力」はただ生命体だけがもっている」という考え方は、AI(人工知能)と人間(生き物)の境界線の参考にもなるかもしれない。
「世界」の秩序それ自体が生命体の「欲望=身体」との相関性として生成する。まさしくこの考え方によって、これまでヨーロッパ形而上学を支えていた「世界の摂理」、「客観存在」、「真理」、「客観認識」といった中心概念は、すべて徹底的に“没落”させられることになるのだ。つまりこれらの形而上学的概念は、懐疑論や相対主義によってではなく、「力」の思想という存在論上の根本的な視線変更によってはじめて徹底的に没落するのである。
ソシュールの言語学もまた、人間はその「欲望=身体」に応じて「世界を言葉によって分節する」ということをはっきりと示唆する。つまり「世界の秩序」とは、「欲望=身体」が紡ぎ出した言葉の産物なのである。
ニーチェの「力」の思想は、この考え方をいわば「価値論的」に基礎づけているのだ。いったい何が「言葉」による世界解釈を可能にしているのか。根源的には、生命体の「価値評価」(「欲望=身体」のそれ)がそれを可能にしている。生命体における“つねに自己自身の「保存と生長」をめがける”「力」こそが、およそ「価値評価なるもの」の根源なのである。
「人類よ、所詮君たちは生命体に過ぎない。認識とか真理とかいう気障な言葉つかって気取ってないで、欲望・エロスドリブンなことを認めろよ」というメッセージを受け取りました。
つまり、「知覚」・「認知」・「認識」・「客観」・「真理」といった「認識論的」あるいは「機械論的」概念の系列を、「肉体」・「欲望」・「快苦」・「力の感情」・「自我感情」といった欲望論的、エロス的概念へと“還元”すること。このように言うなら、それが単に懐疑論的、相対主義的な仕方でヨーロッパ形而上学を”解体“するものでなかったことが最もよく明らかになるだろう。
ちなみに、この「力の意志」が何に由来するかという議論は、「環世界」の議論とも通底するものがあり、ニーチェの先見性?に脱帽する。
環世界(かんせかい、Umwelt)はヤーコプ・フォン・ユクスキュルが提唱した生物学の概念。環境世界とも訳される。
すべての動物はそれぞれに種特有の知覚世界をもって生きており、それを主体として行動しているという考え。ユクスキュルによれば、普遍的な時間や空間(Umgebung、「環境」)も、動物主体にとってはそれぞれ独自の時間・空間として知覚されている。動物の行動は各動物で異なる知覚と作用の結果であり、それぞれに動物に特有の意味をもってなされる。ユクスキュルは、動物主体と客体との意味を持った相互関係を自然の「生命計画」と名づけて、これらの研究の深化を呼びかけた。
(2)生理学としての「力への意思」
本書によれば、ニーチェは、「力への意志」の議論を通じて、まず、「ダーウィン進化論」に対抗している。つまり、生命体は単なる自己保存や種族維持ではなく、より強力な個体=肉体の解放と創出こそが第一義的という考え方を提示している。また、「ヘーゲル歴史主義」にも対抗している。つまり、倫理や道徳によって人間を弱体化・平均化するのではなく、強力な個人の創出こそが目標であるという考え方を提示している。
「権力への意志」(=力への意志)と呼ばれているものは、見てきたように、さしあたり生命体(特に身体をもつ生き物)が必ずもっている「自己拡大の本性」と考えればいい。
一切は生命体の「力への意志」に発し、ここから身体や器官それ自体が形成され、またそれが発する「世界解釈」からさまざまな「世界秩序」が生成されると考えられる。
人間が自分の「意識」で作り出すさまざまな「目的」や「目標」や「意味」は、じつは「力への意志」の「より強くなろうと欲すること」、「生長しようと欲すること」という根源現象からの派生形態にすぎない。そして「意識」はそのことに気づかない。……あくまで「より強くなろうと欲すること」が本質で、人間が頭で作り出す「目的」や「意味」などはその仮象にすぎないということだ。
(3)「価値」の根本理論としての「力への意思」
人間は欲望ドリブンであるからこそ、いわゆる世の中の価値基準というものも、欲望相関性のあるものである(そしてそれが正しい)という指摘。確かに、現代における「よい」「わるい」「いけてる」「いけてない」「優秀」「劣っている」という基準は、突き詰めると、金銭欲、権力欲、名誉欲、性欲などの諸欲望に収れんされるような気もする。
これまでの「世界」という概念はニーチェにおいて「真理」や「客観」という概念から切り離され、それぞれの生命体の”欲望相関性”として成立する諸「世界」へと変更された。……人間の「価値」の秩序、「よし悪し」、「美醜」、「真偽」といった価値の秩序もまた、根本的には「力への意志」による解釈を源泉とする、ということだ。こうして、およそ「価値」なるものの根拠は、なんら超越的なものを想定することなく、生命体がもっている根本衝動としての「力への意志」に定位される。
改めて、ニーチェは「”意識”高い系」の当時のヨーロッパを断罪する。
ヨーロッパ人が大きな誤りを犯したのは、「意識」の価値を基準とすることによってである。人間の「意識」は生の苦悩からルサンチマンを抱く。このルサンチマンから、人間は、「本当の世界」、「彼岸」、「絶対者」、「客観」、「真理」などの諸概念を”捏造“する。そしてこの諸観念を聖化し、絶対化することで、自分たちの生を断罪し、否認するという巨大な顚倒を完成させた。近代ヨーロッパのニヒリズムは、人々がこの巨大な顚倒を自覚できなかったことの結果である。
ルサンチマンをもつ人間、したがってまたそこから現れる”つねに他人のことのみを考える“ような諸道徳ではなくて、ルサンチマンを持たない「強者」、高貴な人間における「生への欲望」のありようを、人間一般の「価値」のモデルとすること。「超人」というプランはこういう思考のプロセスから導かれたのである。
「君子色を好む」というのも、歴史的真実であるし、また、ニーチェ的にいえば、否定するべきものでもないのかもしれない。
(4)実存の規範としての「力への意思」
生命体としての人間は、自分の保存・生長を起点にして世界を解釈するし、価値基準を持つ、したがってディオニュソス的な生き方こそ正しい、というのがニーチェの主張。
上記のような次第なので、「力への意志」は、キリスト教的な「隣人愛」に対抗する概念でもある。ニーチェは、人間は自己への愛を通じてはじめて他者を愛することができると主張している。
芸術のうちには、つまり人間が美的なものエロス的なものを追求する努力のうちには、まさしく生を「肯定する力」を象徴するものがある。なぜならこの領域では、いわば「生命感情」(力の感情)と「肉体的なもの」が調和し、溶け合うからである。それは、宗教や道徳や哲学において両者がしばしば対立的なかたちで現れるのと、ちょうど逆なのである。生の本質が、「精神的なもの」にではなく「肉体的なもの」にあること、言い換えれば、「アポロン的なもの」にではなく、「ディオニュソス的なもの」にあること、ここにニーチェの根本的直観がある。「力への意志」とはつまり、この直観を仕上げるための壮麗な理論だと言えなくない。
ニーチェによれば、美の本質はあくまで「生を肯定する力」にある。したがって芸術の本性はあくまで「ディオニュソス的」という概念のうちに見出されるものなのだ。芸術とは「苦悩にもかかわらず」生を意欲するものであって、「苦悩」への反動から生を何らかの「幻影」で覆い隠そうとするようなものではありえない、と。
一切の価値の源泉は「力への意志」だが、人間においてそれはとくに、「性欲、陶酔、残酷」という三つの言葉に象徴される。生はつねにこの言葉に象徴されるような「生命感情」をもとめる。それらは人間の生の起源であり、源泉であり、根拠なのであると。おそらくここに、「人間は何のために生きるのか」という問いに対するニーチェの最も深い答えが隠されている。たとえば、芸術や恋愛や性欲などにおける「陶酔や恍惚」は、それらがひとつの本質として繋がっていることを象徴的に教えるものだ。つまりニーチェは、「肉体」、「性の力」、「陶酔」、「恋愛」、「恍惚」、「支配欲」といった諸感情の中心に貫いているのは、「力への意志」という強靭な本質にほかならないと言っているのである。人間はたしかに、これらの諸感情の中で最も強い「生命感情」、生の充実感と生の肯定感を抱くような存在だといえるだろう。そしてニーチェは、生の「価値」の根本的な根拠はまさしくここにあって他のどんな場所にも存在しないと言うのだ。なぜなら、もともと「価値」とは「力への意志」が世界に投げ与えたものであって、世界の隠された場所から人間に与えられたものではないからである。
5.まとめ
さまざまな不条理やアクシデント、カオスな状況を乗り越えていかなければならないスタートアップ関係者は、「永遠回帰」の思想、ひいてはディオニュソス的なマインドセットを持っているほうが生き残る確率が高いように思える。そもそも、新しい事業を興すのは、多かれ少なかれ「力への意志」が背景にある「超人」でなければやらないし、できないこと。
スタートアップ関係者は、ニーチェ・マインドを体得するとよいのではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
