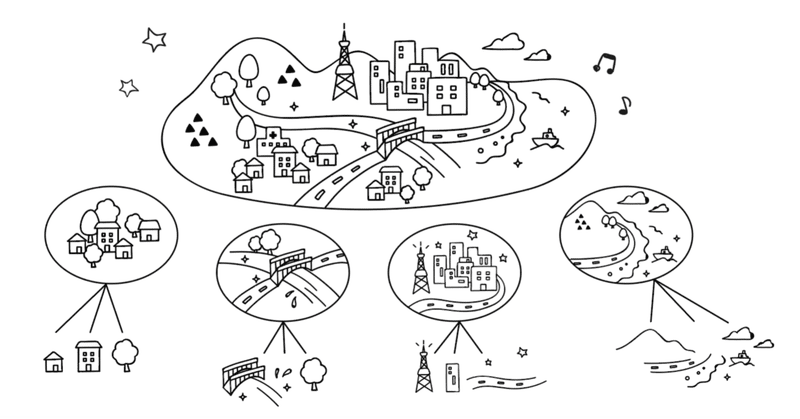
牧瀬先生に聞く!地方創生・まちづくり・政策づくりのヒント【第1回】
教えてくれた人:関東学院大学大法学部教授 牧瀬稔先生
聴いた人:自治体総合ニュース 担当:柴田
このnoteは関東学院大学法学部教授 牧瀬稔先生に、地方創生やまちづくり、政策づくりに関するヒントを教えていただきます。
全5回シリーズで、今回はその記念すべき1回目!
牧瀬先生には、自治体総合フェア2024でもセミナーのコーディネートもいただきます!牧瀬先生、改めて御礼申し上げます!
※牧瀬先生のセミナーは、【5月16日(木)14:00-15:30】 「議会共創」を目指して~望ましい議会コミュニケーションのあり方を考える~です!
はじめに 〜まちづくりに関わる最新キーワードを知ろう〜(その1/2)
【質問】まちづくりのトレンドについて教えてください?!
地方創生・まちづくり・政策づくりについてこれからお聞きしますが、
【まちづくり】のトレンドはどういったものがありますでしょうか。
牧瀬先生:
まちづくりは、日々、進化(深化)しています。そのため新しい言葉(概念)が登場しています。例えば、シビックプライドやSDGs、公民連携、リスキリングなどがあります。これらの言葉(概念)を簡単に紹介します。
シビックプライド(Civic Pride)の意味は、「都市に対する市民の誇り」という概念で使われます。シビックプライドの成果として、自治会・町会活動の活発化や住民の転出抑制に影響を与えることを指摘する学識者がいます。Uターンの増加を示唆する研究もあります。そのほか良い効果が指摘されており、シビックプライドには多くの可能性があります。
相模原市は「さがみはらみんなのシビックプライド条例」があります。条例名に「シビックプライド」という言葉の入った全国初の条例です。
図表1は同条例の前文です。縦読みすると、「シビックプライド」と「相模原ファン」と読めるユニークな条例です(縦読みできる条例としても、きっと全国初です)。同市は同条例を根拠としてシビックプライド政策を着実に進めています。

毎年、総務省は「転入超過数多い上位20市町村」を公表しています。相模原市は圏外でしたが、シビックプライド政策を開始した直後から圏内に入り、現在も上位に位置しています。これはシビックプライド政策が一つの理由と言われています。
次にSDGsを紹介します。SDGsとは「Sustainable Development Goals」の頭文字をとった略称です。Sustainable Development Goalsは「持続可能な開発目標」と訳されます。
SDGsは目標1の「貧困をなくそう」から目標17の「パートナーシップで目標を達成しよう」まであります。17目標に関連して169のターゲットがあります。SDGsは持続可能な世界を実現し、地球上の誰一人として取り残さないことを目指しています。日本だけで実施しているのではなく、世界全体で進められている活動です。市民にとって、「SDGs」や「持続可能な開発目標」と言われても理解できないかもしれません。私が市民に話すときは「す(S)ごい で(D)かい ゴ(Gs)ール」と紹介しています。
SDGsの目標1は「貧困をなくそう」です。2030年までに、全世界から貧困をなくすことが目標です。現在、絶対的貧困層は約8億人います。約8億人の貧困層を0人にすることがSDGsの掲げる一つの目標です。不可能とは言えませんが、実現するには大きなハードルがあります。だから「『す』ごい『で』かい『ゴ』ールを掲げて取り組んでいる」と市民に伝えると、SDGsの意味を何となく理解してくれるようです。
SDGsの実践者は市民が中心です。市民が理解しなくては行動変容が起きません。行動変容が起きないと、SDGsの目標は達成されません。
SDGsに限ったことではありませんが、地方自治体が政策を進める際、関係者に伝わるように(理解できるよう)に伝えることは基本です。すなわち「伝える」ではなく「伝わるように伝える」ことがポイントと考えます。
すごいでっかいゴール!確かにわかりやすいですね!
「伝わるように伝えること」、とても大切ですね!
次回は公民連携とリスキリンついてお聞きします!
すぐ詳しく知りたい人は、体系的に学びたい方には、
下記の書籍で詳しくノウハウがご紹介させています!
