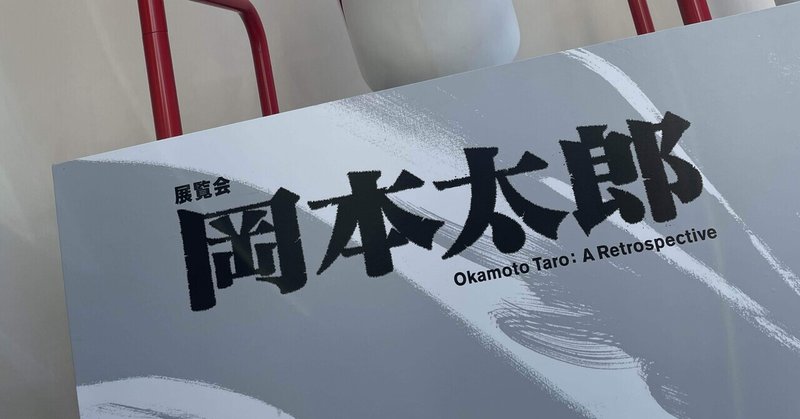
昨年、話題になった岡本太郎のことをもっと知りたい #ほぼ日の學校
「ほぼ日の學校」アドベントカレンダー3日目です。
昨年、東京都美術館に岡本太郎さんの展示を見に行きました。
色、モチーフのおもしろさ、大きさな作品にぶつけたエネルギーを感じました。もっと知りたいと思ったのですが、結局、他の展示を見ないまま、今に至ります。
たくさんの美術に触れた経験があるわけではないので、自分の感じ方に頼らず、情報で補完して、頭でも理解したいと思っていました。
で「岡本太郎は、なんでも呑み込んじゃう! 前編」を視聴しました。
岡本太郎記念館館長の平野さんの話す内容を伺うと、もっと感覚的に受け取った感情に身をゆだねてもいい人であり、作品なんだろうと思いました。
授業紹介
岡本太郎は、なんでも呑み込んじゃう! 前編
平野暁臣 ( 岡本太郎記念館館長、 空間メディアプロデューサー)
藤井亮 (映像作家、 クリエイティブディレクター)
NHKの深夜番組から大人気になった岡本太郎オマージュの怪獣ドラマ「タローマン」。このハチャメチャな新しいタイプのヒーローを、岡本太郎記念館の平野暁臣さんはどう受け取ったのか。タローマンの生みの親・藤井亮さんもお呼びして、岡本太郎のこと、タローマンのこと、敏子さんや太陽の塔のことまで、岡本太郎の教えのように自由に話してもらいました。進行役は糸井重里です。芸術家「岡本太郎」の入門編としてもおすすめです。
岡本太郎は、なんでも呑み込んじゃう! 前編 | 平野暁臣、藤井亮 | ほぼ日の學校 (1101.com)
冒頭、平野さんの言葉に頷きます。
これは、一度作品を見て、そう感じました。かっこいいこといいますね、宮沢りえさん。
平野
宮沢りえさんが言ってたけど
「太郎を知らないで生きるより
知って生きるほうが
ちょっと幸せだ たのしい」って
ぼくもそう思いますね
NHK『TAROMAN』を企画・制作した藤井亮さんのTAROMAN制作に関する話から。
そして、『TAROMAN』の題材にした岡本太郎の言葉、口述筆記された岡本太郎の言葉の話が続きます。それらを踏まえての岡本太郎の作品の話です。
岡本太郎の作品の作り方
平野
今からこういうテーマで
こういう作品を描くぞつって
「こうかな?あっ 違う違う
もうちょっとこうかな?」
というように
階段登っていくような作り方は
全くしなかったんですよね
平野
「あ!こういう絵が描きたい!」
と思った時にはすでに頭の中に
完成形があって
頭の中にあるものをキャンバスに
プロジェクションして
それをそのままこう描いている
ような感じらしいんですよ
平野
出そうと思って
出してるんじゃなくて
出ちゃうんですよ
ことばもそうだし
絵もそうだし
みんなそうだと思います きっと
テーマとかタイトルとかそういう
概念が先にあって それをロジカルに
構築していってるんじゃなくて
最初からもうドーンと
出ちゃうっていう感じみたいな
ただ作品にぶつけたものが、最初から、ただ自分の中にあるものを放出したわけじゃないんです。
岡本太郎の芸術へのアプローチ
糸井
普通の絵描き以上に本当は
ものを知ってるし勉強もしてあるし
絵画の理論も全部わかってるけど
捨てるという大仕事を
自分に課したというか
そういうふうに見えるんですよね
平野
たぶんパリ時代に民俗学を
学んだことがすごく大きくて
そもそも太郎がパリ行って
最初にやったのは抽象絵画なんです
抽象でしょ
抽象からスタートしたんだけど
すぐにその枠組みから外れちゃって
それも入らずに
民俗学に行くわけですよね
平野
彼が感動したことのひとつは
それこそ祭りの祭具にしろ
どんなものであれ
プリミティブな人たち
民衆が作るものっていうのは
どんなに見た目芸術的であっても
それは芸術品として
作ったわけじゃなくて
生活の一部として
生活者が作ったわけで
職業芸術家が商品として
作ったものではないわけですよね
そこがすばらしいと思うわけです
私も展示で見た岡本太郎が日本全国を回って撮った写真は、まさにそこに対する観察に溢れてました。
人間とは何かというところから
芸術を始めたいと考えて
民俗学をやるわけです
実際始めてみると確かに
職業芸術家なんか全く存在しない
世界であれだけのものが
神と人間が一体になったような
そういうようなものが作られていて
でもそれ作っているのは
普通の人たちなわけですね
そういうのに感動するわけで
それで自分の芸術の方向を
決めるわけですよね
そう、普通の人が持っている、それを生活で形にしたものの感動を求めていたのなら、私なんかが付け焼き刃に頭で理解しなくても、見て感じたことを、そのまま自分の中で反芻して、熟成させてもいいのかもしれないと思いました。
感想
岡本太郎美術館(川崎)、岡本太郎記念館(表参道)、絶対、2024年のどっかで行かなきゃ。今度は、予習は無しで行ってみたいと思います。
この授業は後編もあるので、アドベントカレンダー期間中、後編も視聴したいところ。
いい歌を詠むため、歌の肥やしにいたします。 「スキ」「フォロー」「サポート」時のお礼メッセージでも一部、歌を詠んでいます。
