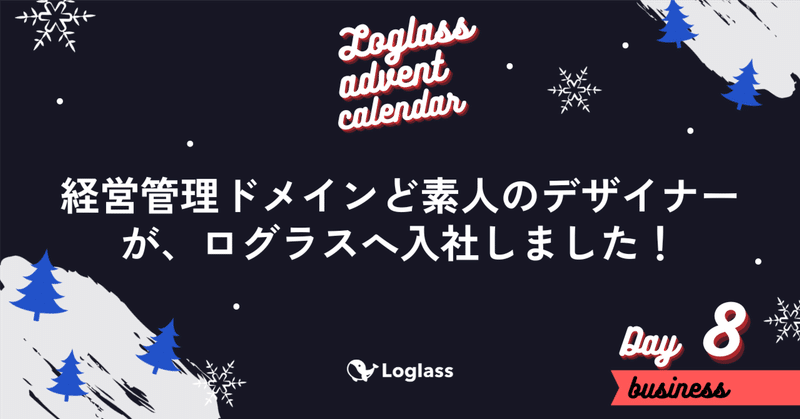
経営管理ドメインど素人のデザイナーが、ログラスへ入社しました!
🐳この記事は「ログラスアドベントカレンダー2023」の8日目の記事です。明日はHRの越智さんです!
こんにちは! 9月に入社したデザイナーの大澤信哉です。
前職の株式会社ビズリーチには6年ほど在籍し、企業向けのスカウトサービスのプロダクトデザインを担当していました。
この記事では、ログラスにおけるドメイン知識の獲得機会や、未経験領域で早期にバリューを発揮するための考え方についてご紹介します。
未経験の事業領域で活躍できるのか?
経営管理クラウド「Loglass 経営管理」(以下Loglass)は、経営管理・経営企画領域における、予算策定・予実管理・経営会議資料の作成等の業務プロセスを改善するソフトウェアです。
前職のHR業界とは異なる領域であり、もともと数字も苦手で会計なんて言葉とは無縁の人生を送ってきた私ですが、結論、なんとかやっております!
実際に、入社して最初に携わった配賦に関する機能拡充プロジェクトでは、周囲の助けを借りながら1ヶ月ほどで一連の導線設計やUIデザインを主導できました。
「配賦」という言葉自体、入社して初めて知りましたが、ログラスにはドメイン知識獲得の機会や環境がたくさんあり、それらに助けられて成果を出せています。 この場をお借りして、丁寧に引き継ぎやオンボーディングを進めてくださったデザインチーム・開発チームのみなさんに感謝申し上げます。
入社2ヶ月めで、展示会スタッフとしてプロダクトの説明が可能になるまで
普段から、お客様の業務支援や、サービス運用のサポートを担うカスタマーサクセス(以下CS)のメンバーとの接点が多く、顧客理解のチャンスに溢れています。
ログラスではドメイン駆動設計(DDD)やスクラム開発のフレームワークを取り入れており、ドメインモデル図の作成やスプリントレビューの場に、CSのメンバーが参画する体制が敷かれています。
日々お客様と対峙しているCSのメンバーから課題をヒアリングしたり、開発した機能のレビューをいただく機会が多く、それらの背景情報としてドメイン知識を獲得しやすい環境です。

また、日頃から特定のユースケースに関する勉強会が盛んに行われ、その内容を録画・共有する文化が浸透しています。
各部署でテーマに沿った勉強会が頻繁に開催されており、セールスチームではお客様へのサービス導入に関するアドバイスや、プロダクト活用の事例共有などが活発に行われています。

私が所属する開発チームでは、週に一度、昼休みに勉強会の録画の鑑賞会を行なっており、お客様の課題やプロダクトでの解消方法についてキャッチアップしています。
加えて、プロダクトの情報設計がオブジェクト指向ユーザーインターフェース(OOUI)に基づいており、初心者でも直感的に機能理解しやすいことも特徴です。
導入事例:株式会社タナベコンサルティンググループ様
やはり作り手としては、機能や振る舞いというソリューションそのものには興味関心を抱きやすいため、それらを起点に要件・仕様の背景情報として、会計の知識や業務フローの実態を紐解くことも有用だと感じます。
特に私が所属する開発チームはマスタ系の機能を管轄しているため、業務でもデータ構造の話が持ち上がることが多く、業務フローを俯瞰して捉える機会に恵まれています。
結果、入社2ヶ月めで展示会スタッフとしてプロダクトの説明ができるだけのドメイン知識は獲得できました。
ログラスでは、職種を問わず展示会にスタッフとして参加することができ、市場の生の声を聞くことも非常に勉強になります。
配賦に関する機能について質問された時は、思わずテンションが上がって意気揚々と答えてしまいました笑
職能の専門性を発揮することで、いち早くバリューを発揮
未経験の領域であっても、プロダクトデザインの専門性を発揮することで、早期に組織へ貢献することができました。
現在は既存プロダクトのグロースチームに所属する傍ら、デザインレギュレーションの制定を推進しています。
管理会計という個社ごとに事情が異なる領域で活用されるプロダクトには、高い汎用性が求められます。
100社あれば100通りの組織構造、予算、科目、レポートが存在し、SaaSとして価値提供するには、オブジェクティブな導線設計を突き詰める必要があります。
複雑なユースケースに対応するため、個別最適な画面設計やUIコンポーネントを作りたい気持ちになる場面は多々ありますが、最大限プロダクトをシンプルな状態に保つためのデザインパターンの定義を進めています。
個人的なwillとしても、可能な限りデザイン負債を作らないよう、デザインレギュレーションの制定と浸透には注力したいと思っています。
事業会社で一定期間プロダクトのグロースに携わった方であれば誰しもデザイン負債に直面したことがあるかと思いますが、レギュレーションなきデザインは体験の不統一を招き、ユーザーの認知コストを増大させてしまいます。
レビュー時や開発時の確認・判断のコストの増加にも繋がるため、ログラスのバリューであるLTV First(※長期的思考で物事を捉え、お客様に提供する生涯価値を最大化すること)の観点からも、組織として重要な取り組みと位置付けられています。
現状のログラスはほとんど中途入社の社員で構成されており、職能を問わず誰しも前職の失敗や経験を活かして同じ轍を踏まないための活動に取り組んでいる方が多い印象です。
デザインの領域に関しても、無闇に色数を増やさないよう初期フェーズからカラーパレットを定義したり、既にAtomレベルの基本コンポーネントの実装は完了している状況で、アンチパターンを避ける取り組みがなされています。
これらの土壌の延長として、現在は私の方でコンポーネント同士を組み合わせたデザインパターンの定義や、ライティングガイドラインの制定など、レギュレーションの拡充を推進しています。
このように、未経験の領域でもこれまで培ってきた自身の専門性や経験を活かし、組織のパフォーマンス向上に寄与する活動によって、早期に貢献することは十分可能です。とくに「あのとき◯◯しておけばよかった…!!」という苦い経験をお待ちの方は、その雪辱を晴らす事もできて一石二鳥です!
ログラスに入って感じる自己成長
ビジネスパーソンとしてはやや恥ずかしい話ですが、事業の状況やコストに対して関心が持てるようになりました!笑
開発組織に属している方であっても、期初や月次の事業報告、別の部署の同僚との会話の中などで、「PL」や「売上」といったワードを耳にする機会はあるかと思いますが、正直なところ人に説明できるほど深く理解できている方は少ないのではないでしょうか。
かくいう私もよく聞く単語をさらっと調べるに留まっており、事業報告やKPIの達成状況などについて聞く時、どこか他人事のように感じることが多くありました。
ログラスに入って実感したことですが、いつも何気なく目にしていた事業報告のスライドを作るためには、膨大な量のExcelシートを集計・加工する必要があります。
事業の健康状態を把握するためには大きな労力が生じており、経営企画が本来割くべき戦略策定に時間を避けていないことを、サービス提供者として知ることができました。
前述の配賦の機能拡充に関しては、まさにコストに対する解像度が上がるきっかけになりました。
共通費を組織や事業に按分する工程の存在を知ることで、コーポレート部門の人件費や、身の回りのオフィス環境などのコストのあり方について理解が深まりました。
そしてなにより自身の給料を生み出すにはどれほどの売上が必要か試算すると、かなりピリつきました…!!
いわば事業報告を聞く側から事業報告を作る立場の視点に回ることで、これまで関心を持ってこなかった財務三表や、管理会計という領域に向き合う環境に身を置けることは、ビジネスパーソンとしての貴重な成長機会だと感じます。
特に現場でゴリゴリもの作りにあたっているデザイナーとしては、経営視点の観点や感覚を身につける機会を得難いため、業務として管理会計ドメインに触れられることは一石二鳥だなと思っています(そしてまだまだ知らないことが多いなと実感する毎日です)。
最後に
経営管理という非常にニッチな領域に対して、自身が働くイメージを想起しづらいと感じられる方は少なくないと思います。
しかし、どんな事業ドメインであれ、根本にあるのはお客様の課題解決に他なりません。
顧客を知り、常にソリューションをアップデートし続けるという点では、過去に得た経験や知識が必ず活かせます。
ログラスのミッションである「良い景気を作ろう。」を推し進めるに当たり、企業の行く末を占う経営管理のドメインにメスをいれるアプローチは、企業の成長を促すうえでまさに根本への対処といえます。
そして、経営企画という一握りプロフェッショナルが泥臭く向き合ってきた領域に、サービス提供者として寄り添える環境はビジネスパーソンとしての視座を上げる絶好の機会です。
このnoteを読んで、ログラスでの働き方や自己成長の機会について興味を持っていただけた方は、ぜひご連絡ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
