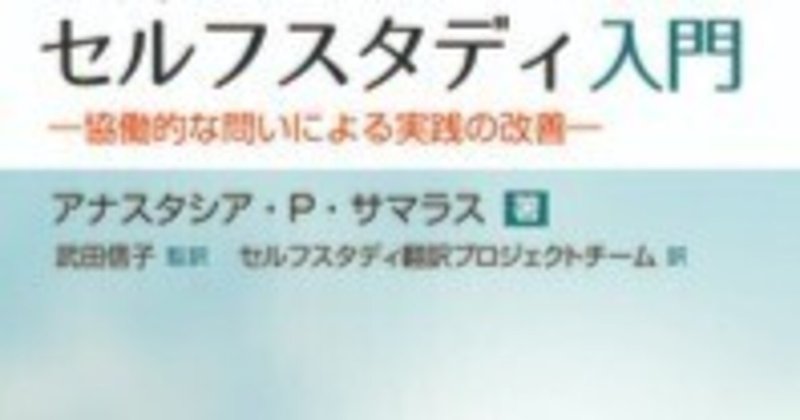
対人援助専門職による実践研究論文の書き方について(セルフスタディ)
ソーシャルワーク分野のFacebookグループページに書いたことを転載させていただきます。
***********
自分の実践を研究として実践研究論文を執筆してみたいと思われる方、
そういうSWや対人援助職の指導をなさる方への情報提供です。
実践と研究をつなぐセルフスタディという研究方法論があります。
教師教育の分野で国際的に広がっています。
私は、臨床心理士で、教師教育者ですが、トロント大学大学院のソーシャルワーク研究科故マリオン・ボーゴ氏のところでサバティカルを1年(2000年)と半年(2015年)過ごさせていただき、ソーシャルワーカー教育を学んできました。『ダイレクト・ソーシャルワークハンドブック』(明石書店)の監訳者でもあります。
今回、セルフスタディが、対人援助職の実践を研究にしていくために役立つ方法論だと思って、翻訳プロジェクトを立ち上げ、完成しました。
元の本が教師向けに書かれている本ですし、訳者も教育関係者が揃っていますので、読むときには、SW実践に応用するにはどうしたらいいだろうかと考えながら読んでいただく必要があるのですが、他に類書がありませんので、まずはこの本からと思います。
方法論のマニュアルとして書かれていますので、とても実際的で、論文が書ける本です。
SWの専門性を高めていくためには、優れた実践に基づくSW教育が必要になると思います。でもなかなか実践を基にした研究が、かゆいところに手が届く形で論文になることはありません。そこで対人援助の世界にこういった方法論が導入されることが必要だと考えた次第です。
なお、2024年6月8日(土)の夜、zoomで出版記念セミナーを無料開催しますので、スケジュールを空けておいて、どうぞいらしてください。詳細はあらためて。お待ちしています。
*********
セルフスタディはまだ歴史が浅い研究方法論です。セルフスタディという方法論が出てくる前は、実践を自分で客観的に記述することは難しいとされ、また、そうして記述された論文は、時に科学的でないとされ、学術誌に掲載されることは少なかったのではないかと思います。
実践は、他の研究者による事例研究として記述されたり、著名な実践家による「エッセー」であったりしたわけです。
ところが、現場には非常に優れた知の蓄積があり、それを実践家が個人で記して他者の役に立てるということは、その専門分野の発展にとって大変重要なことです。
そのために、なんとか、現場実践を研究として論文化することができないかと工夫を始めた人たちがいるのです。現場から大学教授になって後進の役に立ちたいと思った中堅の優秀な実践家たちが中心だったのだと思います。
この四半世紀の間に、そのような方法論を用いて記述した実践が、次第に学術研究論文として学会(アメリカ教育学会という教育界において一番権威のある学会)で認められるようになりました。
ソーシャルワークにおいても、実践記録は、優れた個人の実践家の記録として残ってきたと思いますが、それを研究論文であると言い切ることはできるでしょうか。ソーシャルワークの学会誌に、実践研究論文がどの程度採用されているでしょうか。
セルフスタディと称するためには、一定の手続きを踏むことが求められます。単に自分による自分のための研究では認められません。そのような方法論は、日本にほとんど紹介されてきませんでしたので、日本にはまだセルフスタディによる研究論文は10本も書かれていない状況です。
この方法論が日本に馴染むか馴染まないかということに関して言えば、馴染むことは可能であるけれど、それを必要と考える人がいてセルフスタディを志すコミュニティが作られるかどうか、によると思います。
対人援助職の分野においてもこの方法論が使えることについて、国際的に示唆されてはいますが、まだそこに到達していません。しかしながら、私は20代の頃から、実践に役立つ研究、実践と研究が支え合う専門分野の構築が必要であると考えてきましたので、この方法論が日本に導入されるようにと翻訳に取り組んだ次第です。
優れたソーシャルワーク実践の論文を読みたいと思いませんか。
(ただ、セルフスタディは、現時点では、自分の実践の論文化に焦点があって、かならずしも優れた実践の論文化を目指しているわけではないように思いますので、今後の課題であると思っています)
#ソーシャルワーク #セルフスタディ #実践と研究 #実践研究論文 #方法論 #専門性開発 #教師教育 #一般社団法人ジェイス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
