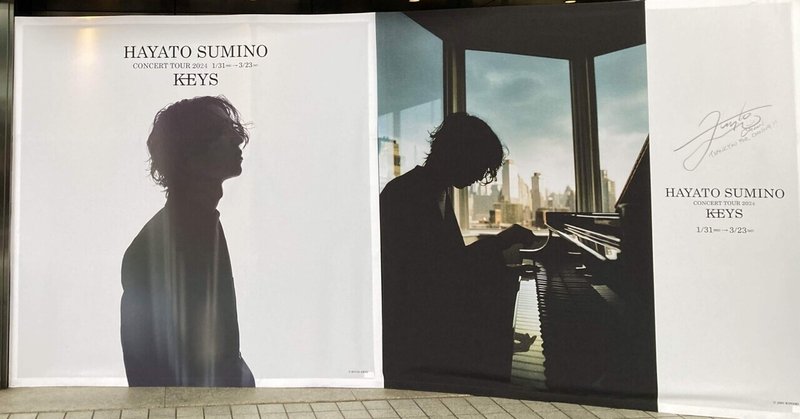
24の調によるトルコ行進曲変奏曲について考える①
タイトルが誰の何の曲か分からない方に説明する。ピアニストで作編曲もする多岐に渡って活躍されている音楽家の角野隼斗さんが、2024年全国ツアーで弾いていた彼の作ったピアノ曲でありモーツァルトのトルコ行進曲を元に変奏曲として今ツアーのために書いたものだ。
ハ長調とかイ短調とかいう「調性」という言葉がある。長調、短調合わせて24あり、この24調を全て登場させて1曲の変奏曲のスタイルにしてしまおうという挑戦的な楽曲である。ざっくりといっても長調と短調ではまるで性格が異なり、そして12色ある長短調もまたそれぞれ与える印象が変わってくるもの。24のアイデアを角野さんがどう組み立てていったのか、ビール時々ハイボール片手に思い耽ることにするシリーズ第一弾。今回は主に調性について。
まず、使われている調性については以下の通り。

異名同音であるC♯-D♭、D♯-E♭、F♯-G♭、G♯-A♭、A♯-B♭について、長調または短調で1回ずつ網羅されているのかと思っていたがそれは違った。
例えば、変ト(G♭)や嬰イ(A♯)を主音とする調は使われておらず、嬰へ(F♯)を2回、変ロ(B♭)を2回使っている。このあたりは角野さんのことなのでパズルを埋める上での紆余曲折があったのではないかと想像する。でもG♭ならまだしもA♯なんてほとんどお目にかからないのであえて節理を無視して使ったら面白かったかもしれない。うん、無理は言わないです。
フラット調が5回、シャープ調が5回ずつ使われている。何もついていない幹音は7音なので長調、短調で出番が2回あり、14+5+5 で24調。
次に少し時間がかかったが各変奏から各変奏に変わる際の相関だったり、音の間隔をくまなく洗い出してみた。というのは「すべてのパターンの転調を使うように」という制約をご自分に与えて作ったから、と角野さん自身が仰っていたからだ。(2024.1/28かてぃんラボより。)すべてのパターンというのは、どのぐらい離れた音程の転調をしているか、を間隔でパターン分けして、半音・全音・短3度・長3度・完全4度・増4度の6つのグループ分けをしているというものである。もうそれを聞いたらすべて暴きたくなってしまうのがヲタクの性でしょう。今回は前述の6パターンだけではなく近親転調も含め、9のグループに分けることにした。最初に断っておきたいのが、少し難しいかもしれない。
まず9パターンの説明から仮にグループを作ってみる。
A 半音転調 B 全音転調 C 短3度転調
D 長3度転調 E 完全4度転調 F 増4度転調
G 同主調転調 H 下属調(属調)転調
I 平行調転調
A〜Fは音程(音の間隔)で分けたもの
G〜Iは音程のグループにも当てはまるものもあるけどきれいだから(近親調だから)あえて分けた
EとH、CとIはほぼ同義
だけどきれいだから分けた(2回目)
1.イ短調
↩️I平行調転調
2.ハ長調
↩️D長3度(短6度)転調
3.変イ長調
↩️A半音転調
4.イ長調
↩️I平行調転調
5.嬰ヘ短調
↩️G同主調転調
6.嬰ヘ長調
↩️I平行調転調
7.嬰二短調
↩️D長3度(短6度)転調
8.ロ長調
↩️C短3度(長6度)転調
9.ニ長調
↩️H下属調(属調)転調
10.ト長調
↩️G同主調転調
11. ト短調
↩️I平行調転調
12.変ロ長調
↩️B全音転調
13.ハ短調
↩️A半音転調
14.嬰ハ短調
↩️(G同主調転調)
15. 変ニ長調
↩️D長3度(短6度)転調
16.ヘ長調
↩️A半音転調
17. ホ長調
↩️G同主調転調
18.ホ短調
↩️H下属調(属調)転調
19.ロ短調
↩️C短3度(長6度)転調
20.嬰ト短調
↩️F増4度転調
21.二短調
↩️C短3度(長6度)転調
22.へ短調
↩️H下属調(属調)転調
23.変ロ短調
↩️E完全4度転調
24.変ホ長調
それぞれ何回ずつあるのか見ていきたい。
A 半音転調 3回
3→4、13→14、16→17
B 全音転調 1回
12→13
C 短3度転調 3回
8→9、19→20、21→22
D 長3度転調 3回
2→3、7→8、15→16
E 完全4度転調 1回
23→24
F 増4度転調 1回
20→21
G 同主調転調 4回
5→6、10→11、(※14→15)、17→18
H 下属調(属調)転調 3回
9→10、18→19、22→23
I 平行調転調 4回
1→2、4→5、6→7、11→12
※14 嬰ハ短調→15 変ニ長調は主音を同音としてみなす。
大体3〜4回に分かれている。
3度転調は「一番ロマンチックでエモーショナルな転調」とご本人が語っており、同主調転調は起承転結が切り替わるような、掌を返すような印象。
半音転調は流れが動き、気持ちが高揚するような印象。個人的に幹音調(♯♭がついていない調)から派生音調(♯♭がついている調)に上がった時が好きなのですが、この24調の中で角野さんは3回異なる半音転調をしている。下がっても素敵なんですよ、と紹介されたようだった。
あとたった1回、増4度転調をしている。言わずもがな増4度は悪魔の音程として忌み嫌われるものである。第20変奏から第21変奏に渡る増4度のアルペジオを経て鳴り響く絶望的で悲鳴のようなA音。桃色の姫が甲羅を背負った獰猛なあいつに連れ去られる絵がどうしてもそこで浮かんでしまう。
今一番知りたいことは、ラストがなぜ変ホ長調なのか。
とりあえず今日はここまで。
次回はトルコ音楽との関係について。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
