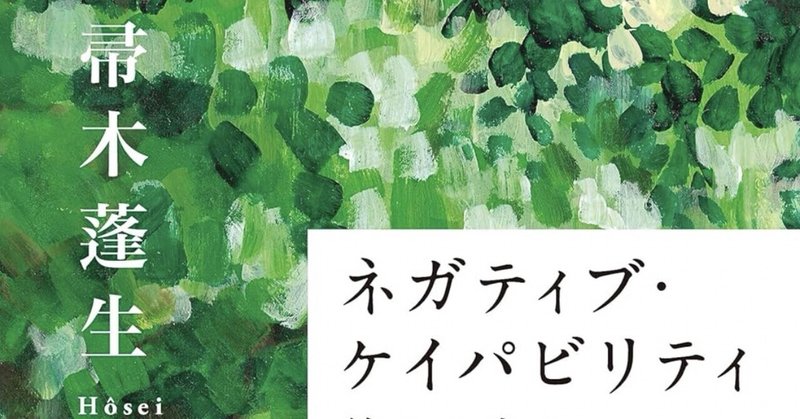
【読書メモ】「ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力」帚木蓬生(Hahakigi Hosei)著
表題にあるネガティブケイパビリティとは、答えが出ない状況や不確実性に耐え、そこから学び続ける能力を指します。
この概念は、19世紀の詩人ジョン・キーツが最初に言及し、現代では心理学や経営学など様々な分野で注目されています。
ポジティブケイパビリティとは、解決策を見出し、成果を出すために必要なスキルや知識を活用する能力です。
これら二つの能力は互いに補完関係にあり、現代の複雑で予測不可能な状況を乗り越えるために重要です。
自分のことを思い起こせば、会社に勤めていたとき営業専門になったことがなく、明示的な結果を出す人間ではありませんでした。
転職はしたものの、それは次の会社での挑戦に魅力があったからです。
また中学高校では、中高一貫の男子校でしたが、とくに目立った成績を出す人間ではなく、成績という成果を出す能力(ポジティブケーパビリティ)が低かったと理解できます。
目立った成績でなくても、学校生活を自分なりに耐えました。高校の途中で転校したいと親に相談しましたが、最終的に卒業しました。
転校したかった理由は、男子校(女子がいない。卒業後に男女共学になりました。)であり、リーダー育成を目指す方針のある学校の重苦しい雰囲気でした。
自分はとくにリーダーになりたいわけではないのに、なぜこんなに重苦しい日々を過ごさせられるのか?なんのために授業料の高い学校で学ぶのか?経済的な負担からも公立校へ転校すべき?と思春期の心の中に渦巻きました。
当時、スッキリすることがない学校生活の心のうちを尊敬する親戚のおじさんに話したことがあります。
おじさんからは、青春とは曇り空が基本であり、晴れた日は、数日あるかどうかであると言われました。あとから振り返ると青春は輝いている、とのことでした。とくに輝いているとは思えないです。ボンヤリしてます。
英国のパブリックスクールについて描かれた書物には、若い生徒一人一人を麦に例え、10代は麦踏みの時代である。それは、人生後半に大きく伸びるために必要な踏みつけられる時期であり、過程だとのことでした。(オレらは麦か?とつっこみたくなりました。)
ネガティブケイパビリティとポジティブケイパビリティの比較
1. 定義と焦点
・ネガティブケイパビリティ: 不確実性、複雑性、曖昧さに耐える能力。答えがすぐには得られない状況で忍耐強く探求を続けること。
・ポジティブケイパビリティ: 知識やスキルを活用して具体的な問題を解決し、成果を達成する能力。
2. 重要性
・現代社会では予測不能な事態が頻繁に発生し、すぐに解決策が見つからないことが多い。このため、ネガティブケイパビリティが重要となる。
・一方で、確実な知識や技術を使って問題を解決するポジティブケイパビリティも同様に重要。効率的な対策と成果を導くために必要。
ネガティブケイパビリティの身につけ方
これらは必ずしも私が実践しているものばかりでなく、本に記述されているものです。
1. 反省的思考の実践
・自己の考えや感情、反応を観察し、自問自答する時間を持つこと。この習慣は、不確実な状況における自己の立ち位置を理解するのに役立つ。
2. 忍耐力と柔軟性の育成
・答えがすぐには出ない状況に直面した際、焦りやストレスを感じずに冷静に対処する訓練をする。異なる視点から問題を考察する柔軟性も養う。
3. 深い学びへのコミットメント
・表面的な理解に留まらず、深く広い知識を追求する。多様な情報源から学び、多角的な理解を目指す。
4. 瞑想やマインドフルネスの実践
・自己の内面にフォーカスし、現在に集中する訓練を行う。これにより、精神的なクリアさと集中力が向上し、不確実な状況に対する耐性が育つ。
長く生きてきた1人の人間として感じたことを含めた読書メモです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
