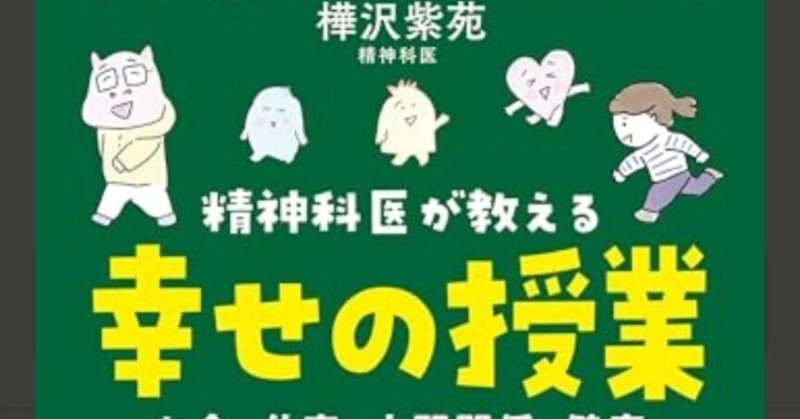
『幸せの授業』を読んで…
『幸せの授業』を読んで…
私は樺沢紫苑先生に幸せを感じさせて頂くことが出来た読者です。
幸せの在り方って、今まで誰も教えてくれなかった。
そして幸せについて考えた事もなかった。
また自分以外の人が皆幸せだと思ってた。
そしてある時期から、自分は不幸だとも、
何故って?
それは、常に人と比較している自分がいること。
あの人は良いお仕事についてるから、成功してる…
あの娘は、いい大学に入ったから、成功してる…
あの人はいい資格を持っているので 将来有望に違いない
あのお宅は…
あの人は…
いつも 人と比較する人生でした。
比較をすることで、周りの環境のせいにする。そんな不幸感の持ち主でした。
私自身も、小学5年生の夏休みも終わろうとする、暑い日に父が不慮の事故で亡くなりました。
元気に、仕事に出かけた父が、まさか病室で、しかも意識不明の状態で対面するとは誰が想像したでしょうか?
事故から1度も目を覚ますことなく、たった1週間で、還らぬ人となりました。
その事を人に話すことに抵抗があり、思春期〜結婚後も父が亡くなってることを、あえて話す事はしませんでした。
軽はずみに、言いたくなかったのでしょう。
父が、いないという事は、不幸と言うのを周りに伝えているようなもの。
それを避けたかった。
「私は幸せなのよ 」って言うのをアピールしたかった。
しかし、
大事な家族をなくしたにもかかわらず、生活していかないといけない残酷さ。
それでも、母親 祖母は一生懸命 私を育ててくれ 学校にも行かせてくれましたが、私の心の虚無感は ずっとあったと思います。
母は、「うちの家は、よそのお家とは違うのよ…」と 言って幸せというのを感じてはいけない雰囲気でした。
その父も去年50年の最後の法要を、姉が主催し無事済ませました。
そんな生い立ちを持つ人生感の中での、本との出会い。
樺沢先生のこの本の『幸せの授業』お陰で、
その幸せの実態がとても簡単にわかりやすく書いてありました。
しかも対話形式になっていて、ゆかりさんが勘違いしている所を樺沢先生が強調して的確に教えている会話。
ゆかりさんが思っている所は、皆が思っている所
ちょっとした言葉のニューアンスが、すごく勘違いを引き起こす。
例えば、幸せになるのではなくて、幸せを感じる事
私はずっと幸せなると思ってました。
これをやれば幸せになれると思い、又これをやらなかったから、幸せになれなかったと思うこともありました。
私には、幸せというのは完成形でした。
しかし、樺沢先生は、『幸せを感じる』というプロセスであると。
結果でなくて過程、これは私にとっては大感動でした 幸せって感じる事だったとは…
この本を読んで、いろんな方に聞いて見ました。
あなたは、幸せですか?
そんな質問や、話しなんて普段は、なかなかしないもの。
親しい 身内としか、なかなか話すことができません。
その幸せとは、幸せになるのですか?それとも
幸せを感じるの事だと思いますか?
幸せは、意識しないといけないと樺沢先生はおっしゃってますが、意識するには日ごろから五感を鍛えて、ポジティブ日記、親切日記、感謝日記をつける事
記憶にとどめて、意識して親切にすること。
でないとすぐに忘れてしまうから。
こんな具合に幸せと遭遇することが出来た私は、お正月には、おせちと一緒に幸せの小さな三段重を作りたいと思います。
一番下には、定番のお煮しめ 2番目には、家族の好きな、つながりの卵焼きなど、一番上に少し豪華な、もっともっとの海老や蟹やイクラ等。
それを家族で頂きたいと思います。
幸せの三段重おせち。
レシピも公開しないと、いけませんね~。
最後になりますが、樺沢先生との出会いに感謝申し上げます。
ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
