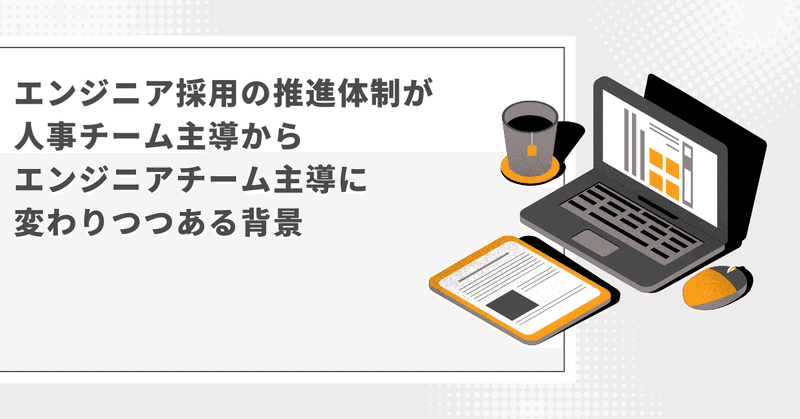
エンジニア採用の推進体制が人事チーム主導からエンジニアチーム主導に変わりつつある背景
かつての日本企業は人事部門が全部門の採用を担当するのが一般的でした。しかし最近はこの常識が崩れ、採用部門の在り方が多様化しています。人事から採用チームが独立し ” 採用部 " が立ち上がるケースもあれば、採用を現業部門のミッションのひとつに位置付け、部門内に人事担当者(=HRBP)を設置し、その担当者が採用活動を推進するケースもあります。
この変化の背景には、採用獲得難易度が以前よりも格段に高まり、もはや人事部主導では採用活動で成功できなくなったことが挙げられます。特に難易度の高いエンジニアの採用については、人事部のみで採用活動を行うケースはどんどん少なくなってきています。その背景について解説をします。
中途採用業務の推進体制はかつては人事主導、今は事業部門主導に移行しつつある。この背景は採用市場が大きく変化し、より事業に即した採用活動を行わないと競争力が維持できないからである。これを人事部の努力不足と捉える企業があるが、時代の変化に対応できる企業が競争優位に立てるのである。
— のびー @ IT企業CHRO (@nobby_nyyr) November 23, 2023
採用チャネルの多様化が起きた
以前のエンジニアの採用(中途採用)は主に”転職エージェント” ”求人媒体” "直接応募” の3つのチャネルが主流でした。現在はどんな状況でしょうか?レバテック社のプレスリリース(2022/5/11)によると、社会人エンジニアに聞く最も利用頻度が高い転職チャネルは「求人媒体(27.4%)」となりました。ついで、「転職エージェント(23.2%)」「スカウト(16.9%)」と続きます。新たなSaaSサービスも登場し、採用チャネルは多種多様になりました。そしてかつて転職エージェントに頼っていた企業が、多様化する採用チャネルに対応しなければならなくなりました。

採用チャネルが多様化した背景とは
ターニングポイントは、2015年前後と思われますが、この頃採用市場はどのようなことが起きていたのかを振り返ります。
①エージェントフィーの高騰化
かつての母集団形成において、量・質ともに高い効果を発揮していたのは転職エージェント経由の採用です。大企業や成長企業など採用予算が多い企業は、最も効率よく候補者紹介を受けられる転職エージェントをフル活用していました。当時は他の採用チャネルがまだ少なく、転職エージェントが圧倒的に効率の良い採用チャネルでもありました。したがって転職エージェントからの紹介数(量・質)を増やすことが採用成功の鍵を握っていました。
自社に優先的に良い人材を紹介してもらうために・・・。企業側もエージェントとの繋がりを強化していきました。それが紹介手数料のインフレにつながっていきました。特にエンジニア職は求人倍率も高く各社の競争が激しく、一般的には年収の35%前後の手数料率が50%,70%さらには100% という契約を結ぶ会社もありました。エンジニア採用にはお金が必要となり、資金繰りに余裕のある会社に良いエンジニアが流れていきましたが、いくらなんでもコストがかかりすぎる、というのが課題のひとつでもありました
②ダイレクトリクルーティングサービスの成長
一方、エンジニアの経験・専門スキルはエンジニアでなければわからないことがあり、転職エージェントに登録してもキャリアコンサルタントが十分に理解し、本当に適した企業を紹介できたかというとそこは疑問が残ります。求職者側もある程度そのことを理解してお付き合いをしていました。
そのような中、ビズリーチをはじめとしたダイレクトリクルーティングサービスが登場した結果、求職者と企業側とのダイレクトなやり取りが容易になり、自らのスキルを直接企業担当者にアピールできるようになりました。企業側もスカウトでエンジニアのどこのスキルに魅力を感じたかを直接意思表示できるようになりました。スキルもレジュメ上だけでなく、SNS上で共有しているスキルや特定のサイトのコーディングテストの点数などでもアピールできるサービスも登場しました。
③エンジニアのネットワークがよりオープンに変化
もうひとつ大きな要素として、エンジニアが多くの技術やサービスに触れることで、エンジニアのオープンマインドが芽生えていき、同時に働き方もオープンなものを求めていくようになりました。特にクラウド技術の浸透やオープンソースが一般化したことは、これまで閉じていた蓋を開けるようなきっかけとなりました。USを中心にエンジニアが使用するツールやSNSが共通化されていき、情報公開の在り方もグローバルの潮流の影響を受けるようになりました。
この延長上で、エンジニアどうしの企業を超えたネットワーク活動が盛んになっていきました。それが採用活動にも変化をもたらし、交流を通じて企業に勧誘をしたり、勉強会をきっかけに企業に興味を持ちそのまま入社するといったリファラル採用がだんだんと主流になりました。そのため、エンジニアどうしの自由な活動を奨励する企業やスキル習得に熱心な企業に人気が集まるようになり、そのことをPRすることが採用活動を成功させる要因にもなっていきました。
④つまりまとめると・・・
以上のような変化が発生する中で、エンジニア採用はかつては転職エージェントのリレーション作りが重要だったが、今ではエンジニアリング知識を用いて候補者と積極的にコミュニケーションすることが重要となりました。知識だけでなく、自社の情報を積極的に開示したり、自社のエンジニアと触れ合う機会を作ることで、他社との差別化をアトラクトする企業が増えていきました。その結果、エンジニア採用の主流が、人事チーム主導からエンジニアチーム主導に変化をしていきました。
以前は転職エージェントとの関係作りが重要だったエンジニアの中途採用は、今ではエンジニアリングの知識を用いて候補者と積極的に交流することが重要となりました。また、知識を用いるだけでなく自社の情報開示やメンバーと触れ合う機会を作ることで、他社との差別化を図ることが主流となっています。
— のびー @ IT企業CHRO (@nobby_nyyr) November 26, 2023
新たなマーケットニーズに合わせて採用チームを再編成しよう
世の中の動きはどんどん変わっていきます。そして、社会での競争に勝っていくためには、新たな時代のニーズに即した体制に素早く移していくことが肝要です。採用チームもかつての組織体制から変化をしていってます。新たな時代のニーズに合わせて、採用チームの在り方も見直しをして行ってはいかがでしょうか。
【参考】エンジニア採用が難しくなっている背景は次の記事でも取り上げています
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
