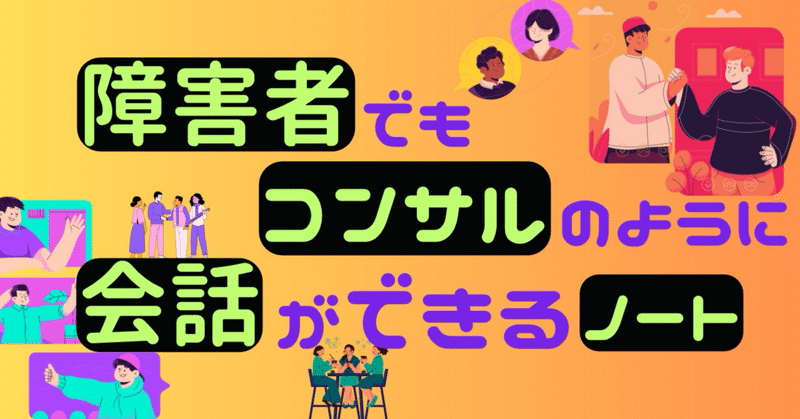
障害者でもコンサルのように会話ができるノート
はじめに
この記事はまだ未完成です。随時、更新していきます。
私は以前、経営コンサルタントとして経営者、幹部、社員の皆さんと会話をし、
情報提供を行い、その悩みを聞いてきました。
どのようにして、
双極性障害、ASD、高IQと向き合いながら、
他人とのコミュニケーションが取れているのか?
そして、どのように自分自身のコントロールをしているのか?
今回は、障害者だけでなく、健常者の方にも参考になる内容かと思います。
相手と向き合うために
自分のマインド①
まず、前提として会話ができる状態にないと始まりません。障害のある方は精神的に不安になり、大丈夫かな、と思うでしょうが、今はそのような不安は取り除きましょう。
もし、不安な気持ちのまま会話に臨めば、相手はそれを無意識に感じとります。
そして、あなたの印象を悪い方向へ位置付けてしまうかも。
大事なのは、会話を怖がらないこと、です。
話したい、会話をしてみよう、その気持ちが大事です。
自分のマインド②
会話に挑戦したあなたは、相手の言葉を聞いて受け答えをしなければいけません。
この時にありがちなのは言葉に詰まってしまうこと。言葉の詰まりは自分自身への自信のなさが原因になることもあります。
よく、言葉のキャッチボールをしましょう、と言う言葉がありますよね。
これはキャッチボールのように、スムーズな会話を心がけましょう、と言う意味もあります。
分からなければ、素直に分からない、と、
間違えたら、間違えました、と、
自分に自信を持って、言葉はホントは凶器ではないんです。
だから、間違ったことでも、違うことでも言って大丈夫。
まずは、自信を持つこと。
その自信が弾む会話につながります。
自分のマインド③
会話を怖がらずに、相手と言葉を交わすことができました。
相手との会話はいろんな話題にもなり、疲れますよね。
でも、会話はいずれ終わるもの。
会話が終わると、気持ちも落ち着き、冷静になります。
その時に、先ほどの会話を思い出してしまう方もいらっしゃいます。
なんであんなことを言ったのだろう。
余計なことまで話してしまったのでは。
自分が変に思われてしまったのではないか。
私も同じ経験がありました。なぜ、あの時こう言ってしまったんだろう。
こう考えるのは、人間の防衛本能なのではと感じています。
今の自分を守るため。
これは人間の正常な考えなので心配はないです。
ただ、振り返ると、それはもう通り過ぎた過去の会話。
それを、どうしよう、と悩んでしまうと答えは見つかりません。
自分の発言を信じ、あれはあれで良かったんだ、という気持ちの整理をつけましょう。
自分が咄嗟に出した言葉、瞬時に出た言葉は、あなたが今までの人生で培った記憶と知識から出た無意識の言葉です。
自分のことを信じ、後悔せず、次の会話に繋げましょう。
会話でコミュニケーション
難しくないさりげないコツ①
健常者でも会話をするとどこかしっくりこないことがあります。
しっくりこない、と言うのは、
なんだかそっけないな、とか、違うこと考えているのかな、とか、
会話のテンポが合わないな、とか、、、です。
このような場合は、本当に違うことを考えている、と言う場合もありますが、多くの場合は会話に余裕がないことです。
会話に余裕がない、とは、相手と自分の言葉の間に適切な余白がなく、会話をしている状態です。
…少し、難しいですね。
ここは、先ほど例に挙げたキャッチボールで例えてみましょう。
キャッチボールは、
ボールを構え、相手に投げて、相手がボールをキャッチし、相手がボールを構え、自分に投げてきます。
ここでもし、ボールを構えず、相手に投げたらどうなるでしょうか?
いろんな方向へボールが飛んで行ったり、とてつもなく速い球が返ってきたり、大変ですね。
逆に、ボールを長く構えても、
相手がいつボールを返してくるのか分からず、お互いのタイミングが掴みづらくなります。
このボールを構える、と言うのが会話での余白だと考えてください。
では、その余白はどうしたらつくれるのか、どうしたら適切な間隔になるのか。
それは、相槌、です。
ああ、へぇ、ふーん、、、など会話の節目に入れてみましょう。
さりげないことですが、相槌があることで、相手からは話を聞いてもらえている、という気持ちになってもらいやすいです。
もし、難しければ、へぇ、など簡単に使えるものから使い、
慣れてくると、抑揚やイントネーションで同じ単語でも違う意味で相手に伝えることができます。
難しくないさりげないコツ②
相槌、と言うスキルで相手とのコミュニケーションに弾みが出ました。
相手がもし、あなたの嫌いな人で、もしくは1度しか会わない人なら、それだけで十分です。
しかし、相手ともっと仲良くなりたい。
相手ともっと深く話ができる関係になりたい。
そんな時は、もう一つスキルを身につけましょう。
それは、うなづき、です。
もっと言うならば、顔の表情です。
いくら相手の話をしっかり聞いて、会話して、相槌を打ったところで、
顔が真顔だったり、怒ってそうな顔をしていたら元も子もありません。
この顔の表情をうまく身につけることで、相手からは話していて楽しい人、面白い人だと思わせることができるでしょう。
相手の話にうなづき、
驚く場面では驚いた表情。
面白い話では笑った表情。
悲しい話では悲しむ表情。
おそらく、健常者ならば話を聞いただけで感情が湧き表情をつくってくれると思いますが、障害のある方などは感情が分からない、と言う方もいます。
実は、私も、感情が分かりません。
よく子供の頃、国語のテストで、文章を読んで○○さんの気持ちを書いてください。
という、テストがありましたが、
〇〇さんに聞かないと分からない。が毎回私の思う答えでした。
なので、簡単そうに見えて意外に表情を変えるのは難しいんですよね。
でも、簡単にできるコツはあります。
まず、私がどうしていたかをお教えしますね。
私は、相手の言葉を聞き、その単語の感情をイメージしました。
悲しいと思われる話なら「悲しさ」を。
びっくりしたような話なら「驚き」を。
そして、そこで連想される表情を再現しました。
「悲しさ」なら、眉を下げて、下唇を少しわずかに上げて、、、
「驚き」なら、目を少し見開いて、口をわずかに開けて、、、
このようなことを無意識にできるようになるまで、やりました。
何度か間違得たこともありました。
その結果、私は相手の表情も読んで、仕草や、間、何かをするタイミングのわずかなズレで相手の体調を感じたり、そんな日々を送っています。
それが生きる術になったんだと思っています。
でも、ここまでやらなくとも生活はできます。
まず、最初は表情を作るところから、少しづつで大丈夫です。
できるところから、無理はしないで、自分のペースで、を心がけましょう。
難しくないさりげないコツ③
難しくない、、、いや、ちょっと難しいかもしれないです。
ごめんなさい。
相手の会話に、相槌をして、うなづいて、表情をつけて。
ここまでできれば、正直会話していけますよ。
でも、もーっと仲良くなりたくて、自分の印象つけたい、
そんな相手がいる人はここもみてチャレンジしてください。
それは、身体の動きです。
人間は無意識に相手の動作が目に入り、自分の話に興味があるかと探ってきます。
私は障害者なので(誰にも言ってはなかったですが)、他の人よりも頑張らないと、と思ってしまっていました。
誰よりも顔を覚えてもらい、誰よりも印象に残るようにと。
よく知られていて、分かりやすいのは腕組みです。
腕組みは自分を守る意味があり、話し合いの途中で相手が腕を組んだ場合は、
商談が難しい局面になっているでしょう。
前のめりな前傾姿勢であれば話はいい方向に、腕を机に乗せているようであれば直好でしょう。
ちょっと、心理学っぽくなってしまいましたね。
でも、こういう人間のクセを覚えておくと、ほんの少し、生きやすくなります。
私がそう断言します。
会話に疲れないために
気分を変えるコツ①
ここまでで、会話に成功しましたね。会話をするとどんな気分になりますか?
達成感、幸福感、など会話に対していいイメージを持っている方はおそらく会話を終えたあと気分を害することはないと思います。
しかし、私を含め障害者の方は会話そのものがストレスに感じる方もいらっしゃいます。
会話をした後に疲労がどっと出てきて身体が重くなったり、頭が痛くなったり。
もちろん、健常者の方も会話をして、イラッとした場合なども同様かと思います。
そんな時、少しでも気分を落ち着ける、また、気分をあまり下がらないようにするコツをお伝えします。
私がまずしていたのは、
深呼吸です。
もちろん、ため息、でも構いません。
1人になった時に深呼吸や、ため息をすることでリラックスでき、気分を落ち着けられました。
オススメですよ。
気分を変えるコツ②
私はよく上司からアレをやってコレをやって、などいろいろお願いされることがありました。
どれも難しいものばかりで、今日までにそれを全部どうしたら終えられるのか。他の仕事もあるのに。
人との会話でもいろいろなことを言われ、お願いされ、謝り、無駄に笑ったり、なんで今話したんだろうと思うこともあったり。
そんな時は一度、
忘れてみてください。
もちろん、会話の内容を全て忘れる、という意味ではなく、その出来事が今あった事を忘れる、です。
分かりやすくいうと、
違うことを考えてみてください。
切羽詰まった状況だからこそ、考えました。
自分の身体が大事なので。
今週末何しようかな、でもいいです。
一瞬でも気分を違うところへ持っていく、ということが大事だと思います。
気分を変えるコツ③
私はいろいろ動く中で、自分のことを忘れ、仕事に没頭する時がありました。それは仕事量が多かった、という意味です。
食事も取らず、休憩も取らず、朝から晩まで仕事をし、家に帰る頃には気力も体力も何もかも残っていませんでした。
何が言いたいかというと、会話をしてても、会話が終わっても、深呼吸や一瞬でも他の楽しみを考えることが、できない人がいるということでした。
あるとき、私はおそらく無意識にため息をしました。
その場所は会社のスタッフがいる社内で。
どうしたの?何かあったの?あんな大きなため息。
と、みんなから心配をされてしまいました。
身体はもう限界までいていたんです。
それから、意識をする、ということを心がけました。
会話だけでなく、会話をするというのは、
人前に立つということなんだと。
私は、
サインを決める、ことにしました。
手をぎゅっと握ったり、少し長めの呼吸だったり。
それを気分を変える合図にしました。
自分なりにサインを決めてみてください。
よく、
ハンカチにアロマを垂らし深呼吸する、というのを聞きます。
これも自分らしいサインになりそうですよね。
おわりに
この記事はまだ未完成です。
これからもっと、人との会話で困ること、困ったことが出てくると思います。
そんな時に、こうしたらよかった、こういう方法があるのかとここを覗きに来てください。
私は障害者ながら今までに多くの人と会話をし、働き、雇い、雇われ、接客し、先輩にも後輩にもなり、上司にも部下にもなりました。
一時期では50人ほどのスタッフをまとめ仕事をしたこともあります。
障害者でもここまでできる。
障害を持っていても、普通の人と同じように会話ができる。
障害者の人も自信を持ってもいいのではないでしょうか?
ノアのプロフィールはこちら⬇️
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

