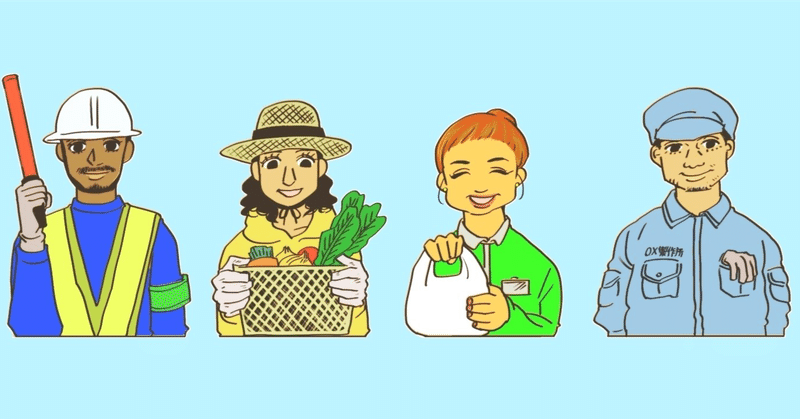
予測されることと、価値観を混同しないこと
47都道府県はもはや維持できない。20年後の日本人はどこに暮らすのか? 累計76万部超の『未来の年表』シリーズ著者最新作!
今回は、これまで誰も本格的に試みることのなかった2つのアプローチに挑んだ。1つは、現在を生きる人々が国土をどう動いているのかを追うこと。もう1つは、「未来の日本人」が日本列島のどこに暮らしているのかを明らかにすることである。
鳥取県の全人口は44.9万人に減る一方、横浜市の高齢者は120万人に激増する。奈良県上北山村では出産期の女性がたった1人まで減る一方、守谷・浦安・長久手・三田などでは80歳超の人々が2.5倍以上増加する――これが、あと25年後に私たちを待ち受ける未来だ。人口推計に基づく予測は、ほぼ外れない。
2045年まで各自治体の人口がどう変動するかをまとめた、最新版「日本の地域別将来推計人口」が公表されて以降、その詳細を深堀りした一般書はなかった。本書はその先陣を切るものである。
日本の人口に関する議論がいつも噛み合わないのは、予測事項と価値観が混同するからだ。本書で提起される通り、日本の人口は確実に減る。戦後直後のベビーブームが異常なだけで、医療水準が違うにせよ、戦前は1億人を下回っていた人口数へ回帰していくのは当然。
では、人口が減っていいのか、という議論が次に来るが、これは価値観が入る。個人的には一人当たりGDPが世界二位に戻れば良しなので人口数には興味がないのだが、人口が減ると相対的に存在感がなくなるというのも事実だし、何より、戦争を前提とすれば兵隊が減る。
というように、話がいつも逸れていくのが人口議論で本書もその通りで著者は少子化対策は失敗したというが、そもそも少子化対策は三十年くらいのスパンをかけてみないと効果が分からず、中国、韓国、台湾と比較すると、日本の方が合計出生率は高いという事実はどう評価すればいいのか分からない。そう、議論は逸れるのに、国際間比較をしないというのも人口議論によくあることである。
事実として提示される部分で特に新鮮なのは、関西圏は首都圏へ人口供給地域になってしまい、不足分は外国人で補っているという事実。元々朝鮮系の人は多かったので、土壌が整っているのかどうかは知らんが、人口統計を見ると確かにそうなっている。
目新しいのはそんなところで、人口減少対策はしつつ、減少幅を考えて社会インフラを整えましょうというのも当たり前のこと。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
