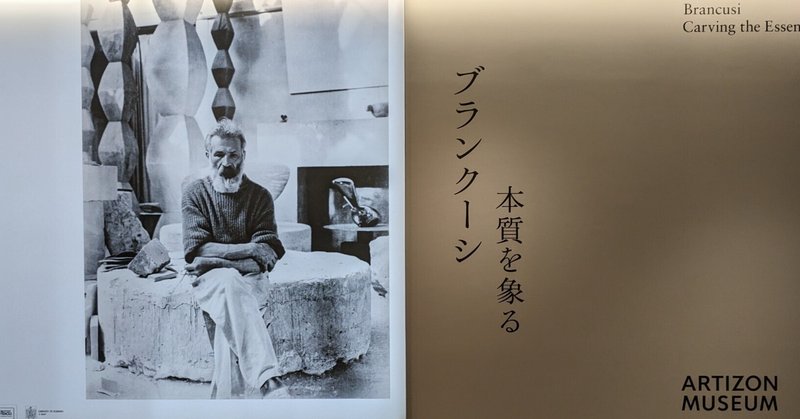
「ブランクーシ 本質を象る」@アーティゾン美術館
東京で用事があったので、前入りしてアーティゾン美術館のブランクーシ展へ行ってきました。
久しぶりに会う友人と東京駅で落ち合い、アーティゾンに行くまでにいくつかのお店を立ち寄りながら、ぶらりと美術館へ。
いや〜東京は誘惑物が多くて大変ですね。何も買わなかった自分、えらい。
それはさておき、本題です。
全体的な感想
ブランクーシは一、二点ほどしか見たことないなということで興味本位で行ったのですが、日本初のブランクーシ展ということでした。
ブランクーシだけではなく、少しだけその工房にいたロダン、親交のあったモディリアーニやデュシャンなどの作品もありました。
面白いのは作品の横には作品番号だけあって、作家名やタイトルなどのキャプションがないこと。
タイトルがないと何を象ったのかさっぱり分からないのがしばしばで、想像力を働かせるのが面白かったです。
そして手元の作品リストと照合すると、まったく合っていないという。
ただちょっと戸惑ったのが、ブランクーシの作品か他の人の作品なのかが分からなかったところ。
例えばある時代の彫刻についての展覧会であれば問題ないかもしれません。でもブランクーシ展で他の人の作品が展示されているのが、ブランクーシに影響与えたというものという意味合いであれば、ブランクーシの作品ではないと明示することがある程度必要なのではないかなと思いました。
因みに、ブランクーシの《眠れるミューズII》の近くにモディリアーニの《若い農夫》が展示されており、なるほど、2人が交流あったのも分かるなと、フォルムの親和性を感じられました。
ブランクーシは自分の作品を自らの手で撮影していたそうで、その写真も多く展示されていました。
ただの記録としてだけではないその写真は、自分の作品を使っての二次創作のようでもあり興味深かったです。
本日のBest
コンスタンティン・ブランクーシ《空間の鳥》1926年 (1982年鋳造)、ブロンズ、大理石(円筒形台座)、石灰岩(十字形台座)、横浜美術館
《空間の鳥》は以前にも見たことがあるのですが、その衝撃は何度見ても同じだな、と今回つくづく思いました。
タイトルを見なければ鳥とは分からないフォルムなのに、でもやっぱり鳥だよなと思わせるのがすごい。
金色のせいか崇高な雰囲気、足元の微妙な段々と、そこからすぅっと伸び上がるフォルムから、鳥が少しはばいてから、自由に高みに向かって飛ぶのが見えてくる気がします。
今回の展覧会の解説により、それがただの鳥ではなくて、ブランクーシの出身地、ルーマニア伝承の民話がベースとなっているのを初めて知りました。
崇高さや自由な雰囲気はこれを表現したかったのかなと感じました。
石橋財団コレクション選
ブランクーシ展は6階であり、5階と4階はコレクション展でした。
ブランクーシ展に合わせてか、彫刻も多かったです。
そして清水多嘉示という画家兼彫刻家の特集も組まれていました。
清水多嘉示は初めて知ったのですが、マティスやセザンヌなどに影響を受けたのかなという作品がありつつも、《憩いの読書》は独自のスタイルが見受けられ、洋服の質感の表現などが素敵でした。
それ以外も、さすが石橋財団と思うくらい、見応えのある作品ばかりでした。
中でも新所蔵作品とあった、ロベール・ドローネーの《街の窓》は色合いが私好みでした。基本的に抽象画を好きと思うことが少ないのですが、淡いけれども少しくすんだ色、それでいて爽やかさを感じるのが、ちょうど夏に向かう今頃の季節の、緑も落ち着いてきて日陰もある感じにも見えて惹かれました。見たタイミングもよかったのか、窓の景色を感じられたのでした。
アーティゾンは興味深い展覧会も多く、コレクションも素晴らしいので、お気に入りの美術館の1つです。
久しぶりの訪問でしたが、やっぱりいいな…と堪能しました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
