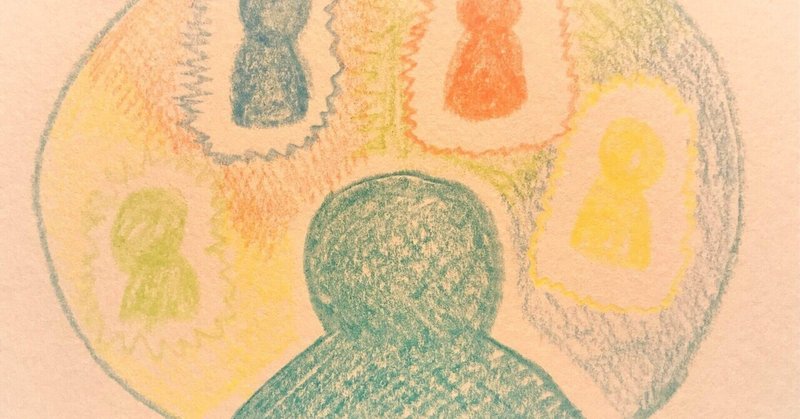
聞きたいことがズレているとき
目的をもった面談で話がズレているとき、ついつい論点が逸れていることを伝えて戻す。
ただ、果たしてよかったのだろうか?とかんかていた時期があったことを竹端さんのVoicyを聴いて思い出した。
質問に対して、意図せぬ身の上話しになっていくときに、「あれ、伝わっていないのかも」とついつい別の切り口で問う。
竹端さんは、オープンダイアログを学んだあとにこのような場面での考えが変わったそうだ。
関係なさそうでも、その人にとってはその問いに答えるためには必要な話しかもしれないと思って聴くようになったという。
問われた側は、途中で論点を戻されてしまうことで聴いてもらえなかったと心を閉ざすこともあるかもしれない。
それは、あり得ることだと思った。
聞くときこそ効率は考えたくない
たしかに、時間の制約があって、通常1時間を予定している面談で3時間も話すことは現実的ではない。
ただ、生産性ばかりにとらわれて関係のない話はしないことが評価されあり、認められないのは息苦しさを感じる。
ぼくもいろんな方と面談をするなかで、ふだん誰からも聴いてもらう機会ぎないのかもしれないと感じたことがあった。
どうしても、自分の意見を伝えたくなってしまうが、相手は求めていないのであれば、そんな意見は必要ないかもしれない。
以前、ほんじゃーにーでも紹介した東畑さんの『聞く技術 聞いてもらう技術』を読み返しながら、再度そのあたりを考えてみたいと思った。
聞きすぎは自助を妨げるかもしれない
とはいえ、聞き過ぎが良くない事態を招くこともある。
向谷地生良さん著『技法以前』で知ったのは、以下のようなお話し。
統合失調症のAさんは、リストカットと大量服薬をしてしまう。よくよく聴くと医者や精神科のスタッフは忙しいなかできる限り話を聞くようにしていた。
結論をいうならば、この悪循環のポイントは「彼の思いを懸命に受け止めようとして、忙しいなかでできる限りの時間をとって話を聞いてきる」ところにある。
つまり、自助を阻害する「聞き過ぎ」と「苦労の丸投げ」が起きているのである。Aさんには、無意識のうちに自分に真剣に向き合ってくれるスタッフとの「充実したひととき」という切符、わ手に入れるために、リストカットと大量服薬というカードを切りつづける必要が生じているとといえる。
援助者の基本スタンスは、「当事者自身が自分を助けることを助ける」ことだ。
当事者不在は、「助ける主役は当事者自身であること」を忘れること。
そのスタンスを保ちつつ、どう関わっていくか。
まだまだ問いに対する思考は続く。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
