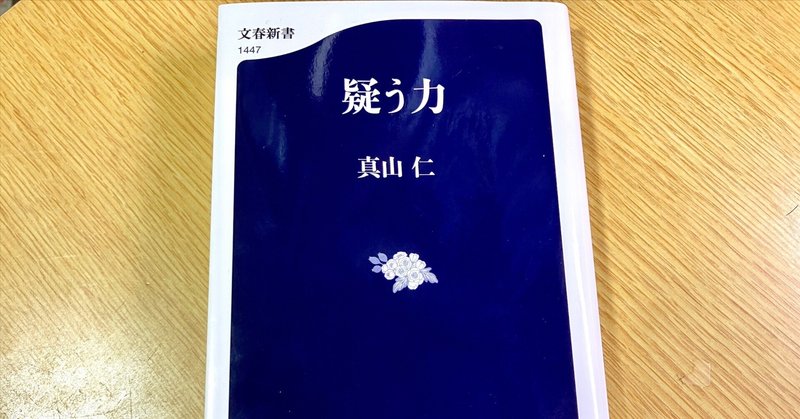
自分の頭で考える。「疑う力」
「ハゲタカ」などの作品で知られる作家・真山仁さんの書かれた新書「疑う力」を読みました。
与えられた常識、前提を「本当に正しいのか」と疑ってみること。
その中で浮かび上がった正しいこと、そうでないことをさらに深掘りすること。
そうして、自分の頭で考え続けていくこと。
本書では、これらのことが具体的な事例を通して詳細に書かれています。
私自身どちらかというと人が言ったこと、メディアで報じられている事を鵜呑みにしやすい性格なので、本書は多面的な思考を養うという点で有意義でした。
玉石混交の情報が膨大に行き交う現代で、何が本当に正しいのか見極めることはすごく難しいことです。本書で書かれているように、ある意味人の数だけ真実は存在するのかもしれません。人の数だけ物の見方、考え方が存在するように。
それでも正しさを追求するならば、その中で出来得ること、それは月並みではありますが、なるべく時間をかけてじっくり考えていくことではないでしょうか。
時間をかけることでしか見えてこないものって、あります。
例えばNHKのドキュメンタリー番組は予算も時間も膨大にかけられていますが、そういう番組にしか描けない真実の側面というものは確実にあるような気がします。
もちろん、何でもかんでも時間をかければいいというものでもありませんが。
むしろ、現代はスピード重視、結果重視になっていて、じっくり考える暇がある人の方が少ないかもしれません。
それでも、今、そして未来をより良いものにしようと思うなら。
じっくりゆっくりと考えてみることも時には大事だと思います。
もう1つ例を出すならば、私は門外漢ですが、政治にもそれが言えると思います。
本当に今、そして未来を明るいものにしていくならば、まず未来ある若者のための政治を考えるのが一番重要だと思います。
もちろん、今の有権者、特に多くを占める高齢者層の意向に沿う政策にならざるを得ないのも分かります。だって一番人口が多いから。民主主義って多数決だから。
でも、それだけで本当にいいのかなって思います。
私自身、明確な解決策を持っているわけではありません。
ただ、このまま日本がジリ貧になっていくのをただ黙って見過ごすのだけは絶対に嫌です。
本書では筆者の主張として、若者と大人が腹を割って話す場を作るのが大事だと述べられていました。そういう場として昔は職場でいわゆる飲み会があった、と。
私は会社員ではないので分かりませんが、今は昔のようには頻繁に飲みュニケーションというような機会は減っているそうです。
別に飲み会でなくてもいいとは思いますが、世代間の断絶は確かにあると思います。ネットが出てきて特に、みんなそれぞれの専門の中のタコツボに閉じこもって、気の合う人とだけ付き合うようになっているように見えます。
それはそれで居心地が良くていいのでは、と思ったりもしますが、社会全体、国全体にとってみるとマイナスな側面も否めません。
ただ、社会全体にとってプラスになることを本気で考えている人がどれくらいいるかというと、それも疑問です。自分自身にも言えることです。
じっくり考えるということに加えて、色んな世代の人達と交流して意見交換するということが、まずは大事だと思います。
筆者は、18歳から選挙権があるなら、被選挙権も18歳からあってもいいのではないかと言いますが、私も一理ある意見だと思います。
そうなってこそ、若い世代が政治に本気に向き合い、本当の意味で世代間交流が生まれると思うからです。
まず最初にやるべきこと。
それは、正しいを疑うこと。
前提が間違っていることもある。
自らの偏見が邪魔していることも。
自分の頭で考え続けてみよう。
今、そして、未来のために。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
