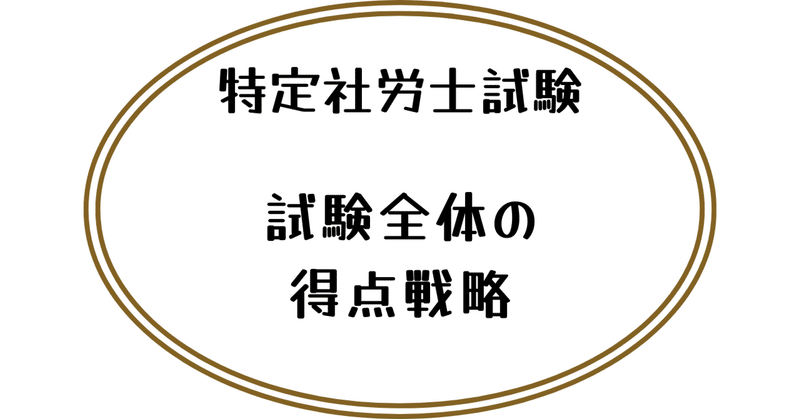
[特定社労士試験]試験全体の得点戦略
こんにちは。ににです。(自己紹介はこちら)
今回は個別の問題の解き方からちょっと離れて、合格するために、試験全体としてどのように戦略を立てていくかをお話しします。

合格ライン
特定社労士試験の合格ラインは、2つ設定されています。
令和5年度でいうと、
100点満点中、55点以上
、かつ、
第2問10点以上
です。
「55点以上」のところは、年度によって若干変わることがあります。第2問の「10点以上」は、第1回から令和5年度の19回まで、今のところ不変です。
試験の最終目標は、このラインを超える点数を取ることです。
合格するためには、どの問題でどれくらいの得点を取ることを見込めば良いのでしょうか?

配点
配点について、もう少し細かく見てみます。
年度によって変わる可能性はもちろんありますが、ここ10年ほどは同じ配点です。
$$
\begin{array}{ccc} \hline
第1問(事例) & 小問(1) & 10点 \\
& 小問(2) & 20点 \\
& 小問(3) & 20点 \\
& 小問(4) & 10点 \\
& 小問(5) & 10点 \\ \hline
第2問(倫理) & 小問(1) & 15点 \\
& 小問(2) & 15点 \\ \hline
\end{array}
$$

小問ごとの対策の優先順位
この配点に対し、それぞれの小問の難易度や性質も踏まえて、対策の優先順位をつけてみました。
ここでいう優先順位とは、かけるべき労力の相対的な大小、という意味だと思ってください。

優先順位① 第2問(倫理)
何よりも優先すべきは、第2問(倫理)の小問2つです。
それはもちろん、「第2問10点以上」という足切りが設定されているからです。
設問自体の難易度は中程度ですが、最悪でも10点、3分の1の得点を取れなければ、その時点で脱落が決まります。
最優先で対策すべきです。

優先順位② 第1問(事例)小問(2)(3)
優先順位の2つ目は、第1問(事例)の小問(2)と小問(3)です。
ここの優先順位が高い理由は、
配点が大きい
小問(4)・小問(5)にもつながる
からです。
配点は、2つの小問合わせて40点もあります。ここを取れなければ、他の設問だけで合格点までたどり着くのは難しいです。
そして、ここでの解答は、小問(4)や小問(5)にもつながってきます。
そう考えると、ただの40点以上の重みがあるといえます。
基本的には書いてあることから抜き出す形式なので、問題としての難易度はそれほど高くはありません。
また、互いに独立した5項目を書く形というのも点を取りやすい要因です。
1つミスしたら芋づる式に全滅・・・、といったことにはなりませんからね。
その意味でも得点しやすい設問といえるので、確実にある程度の得点を取れるように、優先順位を高くするべきです。

優先順位③ 第1問(事例)小問(1)
優先順位の3つ目は、第1問(事例)の小問(1)です。
この理由はただ一つ、
簡単だから
です。
ほぼ決まった「型」に、事例の内容を当てはめるだけです。確実に満点近くを取れるよう、準備しておきましょう。

得点戦略
次に、それぞれの小問でどれくらいの点数を目標とすべきかを考えてみます。
あらかじめひとつ断っておきますが、これから挙げる点数は、「これだけ取れればいい」というものではなく、「どれだけ難しい問題だとしても最低限これくらい取れる」くらいまで勉強をする、その目安となるものです。
試験本番は、当たり前ですが初見の問題が出題されます。
事前の試験勉強で過去問を解くときより、かなり点数は下がると思っておいた方が良いです。
余談ですが、私はこういった試験のときは、常に100点を狙うことにしています。
100点を狙って勉強を積み重ね、本番でいろいろな想定外があったとしても合格点は確保できるだろう、そんな感じでイメージしていました。
もちろん合格点は55点前後なので、100点なんて狙う必要も取る必要もないのですが、気持ちの問題です。
ここまで極端である必要はないと思いますが、ある程度合格ラインより余裕のある点数を取ることを想定して勉強していってくださいね。
さて本題に戻って、小問ごとにどれくらいの点数を目標とすべきかの一例を示します。
$$
\begin{array}{lccccc}
&配点&難易度&重要度&\textbf{目標点数}&得点率 \\ \hline\hline
第1問&&&&& \\
小問(1)&10&★☆☆☆☆&★★★☆☆&\textbf{8}&80% \\
小問(2)(3)&40(20×2)&★★☆☆☆&★★★★☆&\textbf{24}&60% \\
小問(4)&10&★★★☆☆&★★★☆☆&\textbf{5}&50% \\
小問(5)&10&★★★★☆&★★☆☆☆&\textbf{5}&50% \\ \hline\hline
第2問&&&&& \\
小問(1)(2)&30(15×2)&★★☆☆☆&★★★★★&\textbf{20}&67% \\ \hline\hline
総得点&&&&\textbf{62}&62% \\
\end{array}
$$
いかがでしょうか。これで合計が62点、まず間違いなく合格ラインを上回ることができます。
「得点率、思ったより低いな」と思われたんじゃないかと思います。
足切りがある第2問(倫理)は、かなり余裕をもって20点は取れるくらいまで仕上げ、簡単な第1問(事例)の小問(1)で8割取るとすると、残りの問題はおよそ半分の得点で良いんです。
もちろん、この得点戦略は一例です。人によって小問ごとの得手不得手があるでしょうから、若干の微調整は必要かもしれません。
しかし、おおむねこんな感じで考えておけば、気持ちにも余裕が持てるのではないでしょうか。

まとめ
得点戦略ということで、どの小問に力を入れて対策を進めるべきかをお話ししました。
これをベースに、ご自身がどこで何点を狙っていくのか計画を立て、それに沿うように勉強を進めていってください。
#受験
#社労士
#社会保険労務士
#特定社労士
#特定社会保険労務士
#特定社労士試験
#紛争解決手続代理業務試験
#まなび
#資格
#しごと
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
