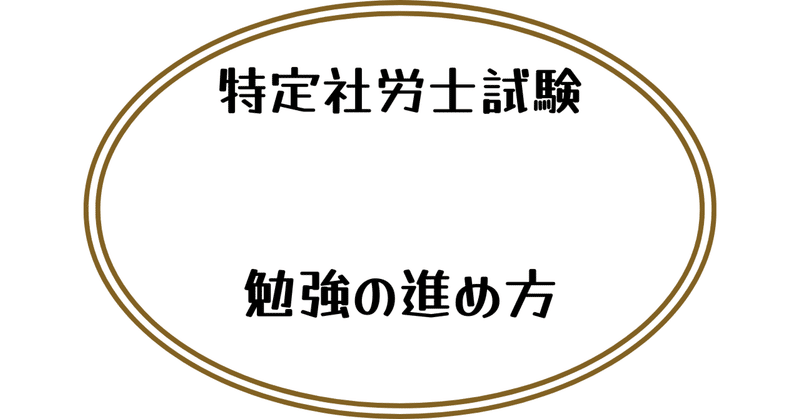
[特定社労士試験]勉強の進め方
こんにちは。ににです。(自己紹介はこちら)
今回は、本番で問題を解けるようになるために、事前の試験勉強はどのように進めればよいのかを解説します。
小問ごとの解き方については、それぞれ別記事にて詳しく解説しています。今日の記事は、本番でその解き方をするための、事前の勉強のお話です。
(小問ごとの解き方の記事はこちら)
第1問(事例) 小問(1)
小問(2)(3) 前編 後編
小問(4)
小問(5)
第2問(倫理) 前編 後編

インプット中心かアウトプット中心か
特定社労士試験に限らず、試験勉強においては、「インプット中心」の勉強と、「アウトプット中心」の勉強の2通りのやり方があります。
「インプット中心」とは、知識を習得することを試験勉強のメインに考えることです。その結果、試験で問われていることが理解でき、解答できるようになる、という考え方です。
一方、「アウトプット中心」では、試験問題(過去問や模擬試験)を解くことが試験勉強のメインとなります。問題を解いてみて、不足しているとわかった知識を補っていくというやり方です。
特定社労士試験においては、「アウトプット中心」の方が合っています。
特定社労士試験は筆記式であるため、書き方を身につけるところの比重がとても大きいからです。
知識がいくらあっても、それを解答用紙に「どう書くか」を身につけなければ、点数をもらう、ひいては試験に合格することはできませんからね。
このあたりの考え方は、別記事にて詳しくお話ししていますので、そちらもぜひご覧ください。
というわけで、特定社労士の試験においては、アウトプット中心で勉強することをオススメします。

勉強の進め方
①過去問を解く
アウトプット中心の勉強でまず使うものは、過去問です。
全国社労士会の会員専用ページ→業務関連情報→紛争解決手続代理業務→紛争解決手続代理業務試験について
に置いてありますし、参考書なんかにもついていることがあります。
勉強の初期段階では、第2問(倫理)だけ、または第1問(事例)だけといった形で、どちらかだけを集中して勉強していく方が良いでしょう。
それぞれの問題の「お作法」のようなものを身につけるためです。
ある程度学習が進んだら、まとまった時間が取れるときはぜひ通しで解くことをオススメします。
試験対策としては、問題を解くことそのものだけではなく、2時間の制限時間をどう使っていくかの練習も重ねる必要があるからです。

②出題の趣旨で論点を確認する
過去問を解いたら、次に使うのは「出題の趣旨」です。
出題の趣旨とは、各年度の試験の合格発表のときに公表されるもので、どういった論点に着目すべきかが書いてあるものです。
全国社労士会のページの、過去問と同じ場所に置いてあります。
具体的にどんな内容かというと、たとえば第1問(事例)小問(2)なら、
解答にあたっては、本問は雇用期間を1年とする有期雇用契約であるから、更新の継続による次期更新の期待についての合理的理由の存在、雇止め理由に客観的合理性と相当性のないこと、雇用終了の特約は真意に基づくものではなく無効であること等の主張すべき要件事実を簡潔に摘示して、記載を求めるものである。
といったことが書いてあります。解答そのものではないものの、論点としてどういった点を取り上げるべきかがわかります。
出題者側から公にされている唯一の、解答に関するヒントです。
これと、自分が解いた過去問の解答を見比べて、解答要素とした論点が正しかったのかどうか確認してください。

③参考書などで、論点を導く考え方を学ぶ
問題のテーマに対して、出題の趣旨を見れば解答すべき論点はわかります。
ですが試験本番では、出題の趣旨が分からない状態で論点を導き出さなければなりません。
それをやれるようにするためには、テーマ→論点というつながりを自分の中に持っておく必要があります。
これが、このnote群でいうところの「フレームワーク」です。
ここを身につけるときに有用なのが、参考書です。
たいていの参考書には、事例のテーマごとに、考えるべき判例や法解釈が掲載されています。
それを学び、「このテーマならこの論点」というフレームワークを使えるようにストックしていくことが重要です。
また、参考書にはもう一つの役割があります。
それは、「どう書くか」の型の参考にすることです。
それらに載っている解答例は、実際に試験に合格できる書き方になっているはずです。
いいなと思った表現や論理展開があったら、それを「型」としてストックしていって、使いこなせるようになってください。
ただし、「型」は人によって書きやすい・書きにくいがどうしても出てくるので、「なんか書きづらいな」と思ったら、無理にそれに固執することなく、他の書き方を試すことも大事です。
私が使っていた参考書を紹介した記事もありますので、参考までにご覧くださいませ。

④時間配分・解答手順などを試す/体感する
ある程度学習が進み、第1問(事例)・第2問(倫理)それぞれがある程度解けるようになってきたら、過去問を1年度分、通しで解くようにしてください。
時間配分や解答手順など、試験全体としてどうするか決めておかなくてはならないことがあるからです。
試験全体でだいたい1,600字を手書きすることになりますが、それにどのくらいの時間がかかるか、自信をもって即答できる人はいないでしょう。
そういったことを確認したり、その他考える工程も含めてどう2時間に収めるかの工夫も必要になってくるかもしれません。
ちなみに、そういった点にフォーカスしているのが、今読んでいただいている私の記事群です。
使う教材として、拙記事群もラインナップに加えておいていただければ幸いです。

まとめ
今回は、勉強の進め方についてお伝えしました。
使う教材は、以下の4つです。
・過去問
・出題の趣旨
・参考書
・このnote記事群
そして、今回お伝えした勉強のサイクルを図にしました。
「過去問を解く」というアウトプットを起点に、出題の趣旨や参考書を使って必要知識をインプットするとともに、フレームワークや型をストックしていくことの繰り返しです。
そして、時間配分などもいろいろ試して自分なりのやり方を見つけていってください。

#受験
#社労士
#社会保険労務士
#特定社労士
#特定社会保険労務士
#特定社労士試験
#紛争解決手続代理業務試験
#まなび
#資格
#しごと
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
