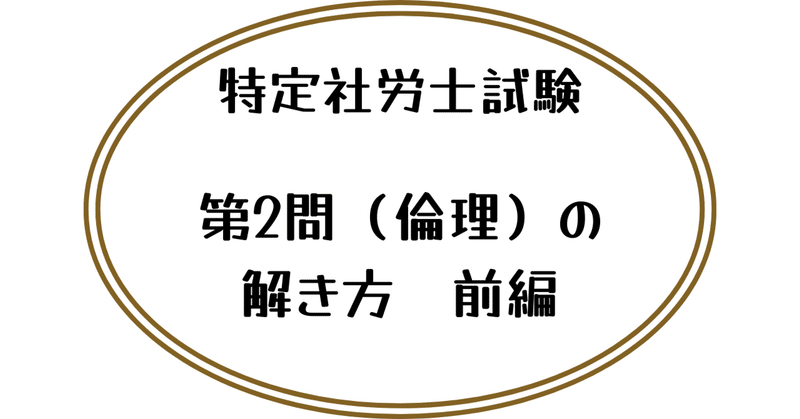
[特定社労士試験]第2問(倫理)の解き方 前編
こんにちは。ににです。(自己紹介はこちら)
今回は、第2問(倫理)の解き方全2回の前編として、フレームワークについてお話しします。
※第15回(令和元年度)~第19回(令和5年度)がすべて同じ問題構成・形式のため、その形式に沿っての解説です。今後の試験において、形式が変わる可能性があることをご承知おきください。
なお、試験全体の問題の構成は、以下の記事でご確認くださいませ。

第2問(倫理)の内容
第2問は、倫理の問題です。
形式としては、250文字程度の字数制限の中で、与えられた状況において、特定社労士として依頼を受託できるかどうか、その判断を問われるというものです。
これが2問あり、配点は各15点の計30点です。
第2問(倫理)でもっとも気をつけなければならないのは、合格基準に「第2問は10点以上とする」という、いわゆる「足切り」が設定されていることです。
これにより、試験対策上、まずは第2問(倫理)で最低10点を確保することが最優先となります。
そのあたりの得点戦略の考え方については、後日別記事でご紹介します。
では本題を。
第2問(倫理)は、小問2つで構成されていますが、ここ8年くらいは、それぞれ独立した設定の問題が出題されています。
とはいえ、平成27年度の第11回や平成26年度の第10回では、小問同士がたがいに関連している形式で出題されています。念のため、関連している可能性も考え、設問文は小問(1)と(2)を通して最初に読むのが良いです。
問題としては、あるシチュエーションにおいて依頼を受けた特定社労士が、その依頼を受託することができるかどうか、その判断と理由を問う形式です。
ちょっと長いですが、令和5年度第19回の小問(1)を例示します。
開業の特定社会保険労務士甲は、地元の商工団体が主催する立食パーティーに参加した。パーティーには多数の商工事業者が出席しており、甲は、人脈を広げようと、知らない人にも次々と挨拶して名刺を交換していた。その中で、初対面のA社代表取締役Bとも名刺を交換し、ごく短時間、立ち話をした。Bとの会話の内容は、次のようなものであった。
B:「半年ほど前、当社は従業員を1人解雇したのですが、先日、その元従業員から、解雇は違法だから損害を賠償しろという文書が内容証明郵便で送られてきたのです。甲さんは、そのような事件を取り扱っていますか。」
甲:「法律上、裁判の代理人などはできないのですが、元従業員の方が労働局にあっせんを申し立てた場合には、会社側の代理人として対応することができます。」
B:「そうですか。もしそのようなことになったら、ご連絡させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。」甲:「わかりました。こちらこそよろしくお願いします。」
その後しばらくして、甲は、知人の紹介で、Cから相談を受けた。Cの相談内容は、A社から不当に解雇されたので、労働局にあっせんを申し立てたいが、自分ひとりでは不安なので、代理人になってほしい、というものであった。
法律に照らし、甲は、Cの依頼に応じ、Cの代理人としてA社に対しあっせんを申し立てることができるか。(ア)「申し立てることができる」又は(イ)「申し立てることはできない」の結論を解答用紙第6欄の結論欄にカタカナの記号で記入し、その理由を250字以内で記載しなさい。
要約すると、社労士がB(会社の社長)と立ち話程度の話をした解雇案件について、C(Bの会社を解雇された元従業員)からあっせんの代理の依頼があった、という状況です。
シチュエーションは回によりさまざまですが、こんな感じで微妙な場面設定がされることがほとんどです。

解法
では、解法を解説していきます。
第2問(倫理)においてもやはり、「フレームワーク」と「型」の考え方が有効です。

フレームワーク
まずは、第2問(倫理)におけるフレームワークを見ていきましょう。
第2問(倫理)は、シチュエーションこそさまざまですが、本質としては毎回同じです。つまり、フレームワークは1つ用意しておけば大丈夫です。
まず、私が試験本番で問題用紙に書いたメモを見ていただきたいと思います。

いちばん上の「×」は、「受託できない」という結論として、最後に書いたものです。
フレームワークとして機能している箇所は、その下の「22」から「信」までです。
「22」「守」「利」「信」、これらは、論点の頭文字を省略して書いたものです。
第1問(事例)でのフレームワークでは書く順番はあまり重要ではないですが、第2問(倫理)においては、順番も重要です。
なので、フローチャートのようなイメージで捉えておくのが良いです。
この記事の最後で、フローチャートも紹介します。
では、順に解説していきます。

①22:社会保険労務士法第22条
ひとつ目の「22」は、社会保険労務士法第22条(以下、社会保険労務士法を「法」と記述します)のことです。
この条文の見出しは「業務を行い得ない事件」です。
そもそも法律で受託できないと定められているケースに該当しないか、それを最初に確認しなければなりません。
法22条で「業務を行い得ない事件」として定められているのは、以下の4つです。
第1項 国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱った事件
第2項第1号 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
第2項第2号 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
第2項第3号 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件(ただし、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない)
※第2項には第4号・第5号もありますが、第1号・第2号と本質としては同じです。
主人公の開業社労士が独立前に働いていた事務所で関与した事件に関する場合は、第4号・第5号となります。
第1項の「国又は地方公共団体の公務員」は、あまり出てきません。しかし、公共機関の相談員として過去に相談を受けて・・・みたいなパターンがたまに出題されるので、押さえておく必要があります。
メインとなるのは、第2項の3つです。
この中に、「協議」「賛助」という言葉が出てきますが、考える過程においては「相談」「助言」と読み換えて考えるのがわかりやすいです。(解答文を書くときはちゃんと「協議」「賛助」と書いてください)
3つがそれぞれ、どういう事件のことをいっているのかを図にしてみました。
社労士が、先にSから、Tとの間の紛争について相談を受けている、または依頼を受託しているという状況で、Tから新たな依頼(設問の主題となる依頼)を受けたという状況です。
このTからの依頼について、法22条第2項に当てはまるかどうか、を判断していきます。
(設問によっては、Sから受けているのが相談なのかどうなのか、という段階が論点となることもあります)

第1号は、「相手方の相談を受けて助言し、又はその依頼を承諾した事件」です。
これはまぁわかりやすいですね。Tからの依頼について該当するかどうかを考えるときの「相手方」とは、この問題で問われているTからの依頼の事件の対象となる相手、上の図でいうとSです。
Tからの依頼の前にSからの相談や依頼を受けていた場合は、Tの依頼は受けられないよ、ということです。
第2号は「相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」です。
構造としては上記第1号のときと同じですが、「協議の程度及び方法が信頼関係に基づく」が曲者で、判断に迷いがちなところです。
信頼関係に基づくかどうかの具体的な判断基準というものはないので、状況によって判断しなければなりません。
が、試験対策的なことをいうと、ここの判断に迷うような微妙な設定の問題だとしたら、どちらと判断しても大きな失点にはならないと思います。
そういった問題の場合、結論がどちらかよりも、そこに至るまでの論理の組み立ての方が重視されます。
傍証として、令和5年度第19回の「出題の趣旨」の記述を引用します。
どのような結論をとるにせよ、法律の定めと具体的な事実関係とを論理的に組み合わせた明快な理由付けが期待される。
「どのような結論を取るにせよ」という記述があり、明快に理由付けされていれば結論はどちらでもありうることが示されています。
第3号は「受任している事件の相手方からの依頼による他の事件」です。第1号・第2号と違い、3人目の人物、Uが登場します。
Sからの依頼を受任している場合は、たとえSとは無関係であっても、TとUの間の紛争について、Tからの依頼は受けられないということです。
なお、第3号の「相手方」は、第1号・第2号のときと違い、もともと受任している事件(上記の例ではSからの依頼)の相手方であるTのことを指しています。
第1号・第2号は、今回の依頼(Tからの依頼)の相手方、Sのことです。
同じ「相手方」という言葉を使っていますが、指す内容が違っているので、こんがらがらないようにしてください。
この「22」の段階では、Tからの依頼が法22条の各項に該当するのかどうか、あるいは、先だって存在している社労士とSとのかかわりが法22条の「協議」や「賛助」に該当しているのか、そういったことを判断してください。
法22条の制限により受託できない場合の解答文の書き方としては、「社会保険労務士法22条第2項第1号の制限により、依頼は受けられない」といった形となります。

②守:守秘義務
「守」以降は、直接的に法で「受任できない」と制限されているわけではないものの、社労士が遵守すべき義務を守ろうとすると受任できなくなるというパターンです。
「守」は「守秘義務」の頭文字です。法第21条に「秘密を守る義務」が定められています。
守秘義務を果たした結果として依頼人の利益を100%実現できなくなる場合は、はじめから依頼を受けてはいけないと判断しなければなりません。
具体的には、以下のような場面が典型的です。
会社Sと顧問契約を結んでいる
Sから、従業員Tを解雇することについて相談を受けた(まだ紛争は生じていない)
SがTを解雇した後、Tからその解雇についてあっせんを申請したいと依頼を受けた
SからはTによるあっせんの話は聞いていない
Sとは顧問契約を結んでいるだけで、紛争について相談(協議)を受けているわけでも、依頼を受けているわけでもありません。よって、法22条の制限にはかかりません。
でも、SからTの解雇について相談を受けていることから、この社労士はSの意思決定に関する秘密を知っていることになります。
その状態で仮にTからの依頼を受けたとしても、Sの秘密を守らなくてはならないので、Tのためになる行動を100%取ることができません。よって、はじめからTの依頼は受けるべきではない、となります。
ここの論理構成で注意しなければならないのは、「守秘義務を守れなくなるから依頼を受けられない」ではなく、「守秘義務を守ると依頼人の利益を実現できないから依頼を受けられない」としなければならないことです。
前者のように、「守秘義務を守れない」とすることは、「法21条の秘密を守る義務に違反しますよ」と宣言するようなものです。特定社労士の倫理以前の問題で、社労士法に反する行為です。
試験の解答でこう書いてしまうと、おそらく大幅な減点をされるものと思います。
法21条の守秘義務を守ることは大前提として、その義務を果たしたら倫理的に問題があるよ、という構成にしてください。
また、守秘義務の判断をするにあたり、実際に秘密を知っていたかどうかはあまり関係がありません。
「秘密を知りうる立場にある」というだけで、「依頼人(上記の例のT)の利益を十分に実現できない可能性がある」→「依頼は受けられない」となります。
ここは、後ろの方で出てきますが、社労士としての信用失墜行為あるいは品位保持義務違反にかかわってきます。
社労士として、少しでも疑われる可能性がある状況は避けなければならない、ということです。
守秘義務の関係で依頼を受けられないとするときは、「(Tなどの)権利を十分に実現しえない可能性がある」という理由となります。

③利:利益相反
「利」は、「利益相反」です。「りえきそうはん」と読みます。
利益相反とは、一方の利益となるある行為が、他方の不利益になることをいいます。
この試験においては、社労士の利益と、依頼主の不利益の間の利益相反が問題になります。
上記守秘義務の項で挙げた例と同じ状況の場合、仮に社労士がTの依頼を受け、Tのために業務を遂行したとすると、Tから報酬を得ることになり、社労士の利益となります。
しかし、社労士がTのために業務を遂行することは、Sにとっては相手方にプラスの方向に紛争が進むということですから、Sの不利益になってしまいます。
本来、社労士とSは、顧問契約を結んでいるという同じ側にいる立場です。にもかかわらず一方の利益と他方の不利益が同時にもたらされる、この状態が社労士とSの間で利益相反が発生している状態です。
利益相反もやはり、守秘義務のときと同じように、最終的には社労士としての信用失墜行為あるいは品位保持義務違反に行きつきます。
可能性があるという段階で避けなければならない、というのも同じです。
利益相反により依頼を受けられないとするときは、「公正に業務を遂行したとしてもその業務の公正さを疑われかねない」あるいは「品位保持義務違反となるおそれが否定できない」といった理由となります。

④信:信用失墜行為
「信」は、「信用失墜行為」です。
法第16条に、以下の規定があります。
(信用失墜行為の禁止)
第十六条 社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
「22」から「利」までの各項目をクリアしているとしても、社労士として信用を失墜させるようなことをしてはいけないよ、という制限です。
あるいは、法16条には「信用又は品位」とあるので、「品位保持義務」として考えても良いと思います。
(第1条の2の「社会保険労務士の職責」に、「常に品位を保持し、(中略)業務を行わなければならない。」という記載もあります)
厳密には違うのでしょうが、私は試験対策上、ほぼ一緒くたにして考えていました。
ここに当てはまるかどうかは、状況に応じて判断する必要があります。
Tからの依頼を受けることが社労士としてふさわしい行動かどうか、主にSとの関係において考えることとなります。
この「信」については、上の守秘義務と利益相反の項でも出てきているとおり、それぞれの項目を受けての結論となることもあれば、これ単体で理由として使うこともあります。

フローチャート
以上、フレームワークとして考えるべき論点を紹介しました。
実際に試験問題を解くときには、フローチャートとしてイメージしておくと良いです。
というわけで、フローチャートを作成しました。
上記4つの論点と、それぞれの論点にひっかかって「受託できない」となったときの、解答文の書き方の例を記載しています。
このフローチャートは私が最終的にたどり着いた形ですが、もちろんこれを元にご自身でカスタマイズしていって、自分がいちばん使いやすい形にブラッシュアップしていってください。


まとめ
第2問(倫理)の解き方のうち、「何を書くか」の部分を解説しました。
シチュエーションは回によりさまざまですが、ベースとなる考え方はどの買いも変わりません。
オリジナルのフローチャートを作って活用しつつ、しっかり身につけていってください。
#受験
#社労士
#社会保険労務士
#特定社労士
#特定社会保険労務士
#特定社労士試験
#紛争解決手続代理業務試験
#まなび
#資格
#しごと
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
