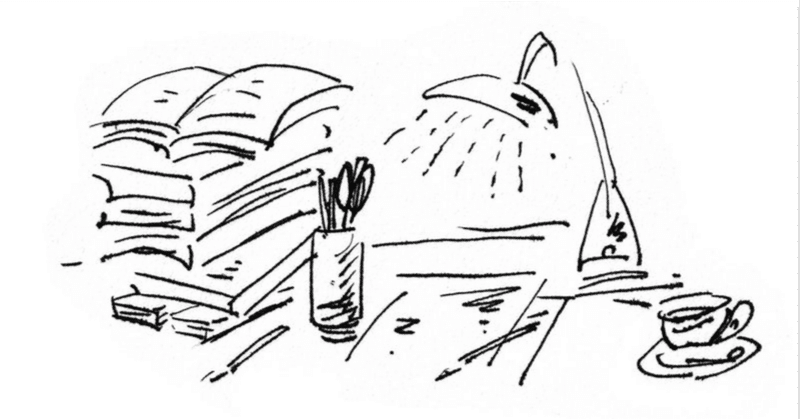
柄谷行人さんに触れる
柄谷行人コーナーに出会う
書店で柄谷行人コーナーを見つけた。知らぬ人だった。「トランスクリティーク」以降の本を買いそろえて斜め読みを始めた。
近著「力と交換様式」で哲学のノーベル賞 バーグルエン賞を受賞と帯のついた解説書も出ている。
インタビュー形式の本人の解説を読んでいるとマルクスの資本論を中心に西欧哲学を評論する中で、人間の社会基盤を支配する「交換様式」という着想を得たようだ。
昭和の学生運動経験者の発言は当時を肯定しようとする気が有り、どうしても色眼鏡で見てしまう。また、氏のアイディアには新たな交換様式(社会)が立ち現れるというアイディアが含まれており、ワールド・ニューオーダーを画策する勢力に利用されている感もある。
しかし、本人はそのようなこととは無縁なのかもしれない。
このあたりは留保する。
その手法
まだ読み始めだが柄谷行人の仕事は評論がベースとなっていることは感じる。氏の文章を読んでいると、頻繁に西欧・日本の哲学者・社会学者が登場し、彼らの思考の過程と足りていないところの分析が語られる。
「巨人の肩の上に乗る」
過去の思想界の巨人達の思考を分析比較し、そこから新たな知見を得る。これが氏の手法だろうか?(もかしたらこれから読む著書の中に現場の知見を生かしたものも登場するのかもしれないが)
この手法なら遠くへ行けるのかもしれない。
この思想が何か役に立つのか?
優れた意志決定には真実に近い世界認識が必要という。(印南一路「優れた意思決定」中公文庫,2002)。
もし交換様式が国家も含めた人間の社会システムの根幹に横たわっているのであれば、これを知ることは未来を予測するために重要だろう。
理系の脳には重荷だが、もう少し読み進めてみたい。
日本の危機を広く知ってもらうため日々noteで投稿しています。あわせて日本復活に必要と考えている新しい技術・産業についても書いています。
