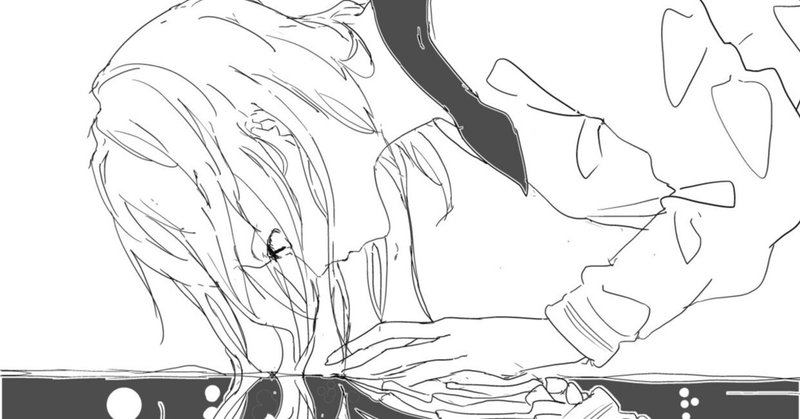
体の中に耀る月 第一話「腕」
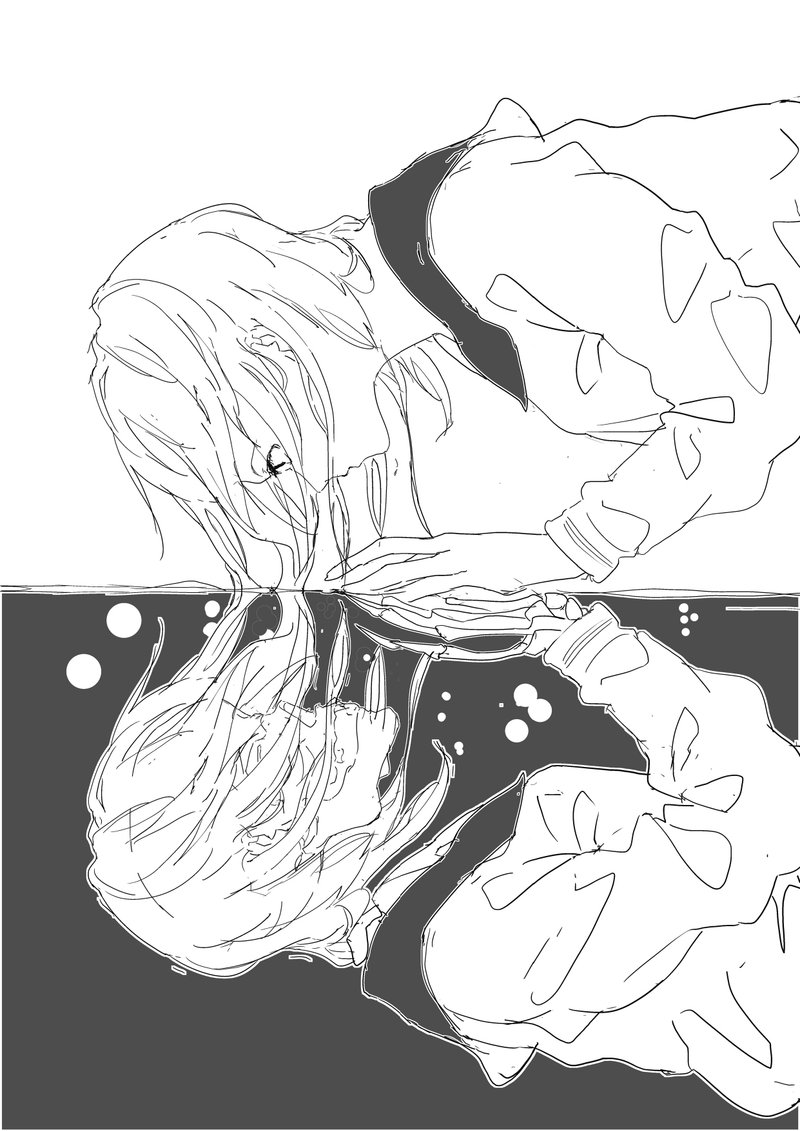
※約一週間に渡り、拙作全部を公開してみる試みです。(前回はぶつ切りの上にnote用のコラムめいたものの間に挟んで公開していたので、わけが分からなくなりました。ごめんなさい)
※素人につき、賞応募や管理優先のため、予告なく削除することがあります。
第1話「腕」
誰より、僕が傷だらけであることを、誰に知ってもらえば良いだろう。
睦(あつし)は、教師に指定されたページを正しく開いて、テキストを読んでいるふりをしていた。
「ので、あるからして‥‥、だから‥‥なるわけです。」
心に触れる教師と、心に触れない教師。
「今の話をよく覚えておいてください。次は、‥‥。」
子どもの気持ちを探る親と、気持ちに無関心な親。
彼は、頭の中でことばにして、自分の気持ちを考えているわけではない。
「良いですね。それでは滔、滔、滔、滔々。」
退屈だ、とか、やってらんねー、とか、そういうことを考えていた。
「滔々滔々滔々滔々」
他の皆と同じように。
それは昔の事だ。昔といっても、睦(アツシ)は中学二年生なので、たった数年前の事だ。数年前の出来事に「まだ」とか「もう」とか、修飾してみるには、睦は幼すぎた。
しかし、大人らしい事には、人一倍興味のある年齢ではある。
超能力がある、という気味の悪い噂が立った事に、彼は少なからず傷付いていた。彼自身には傷付いた自覚はなく、ただ「嫌な思い出」として忘れようとしていた。
自分に常ならざる力があることには、物心付く前から気付いていた。しかし、それを自慢にできたのは、ほんの小さな頃だけだった。結局それが、誇れるほど、便利でも強力でもなかったからだ。透視とか催眠のような力だが、とても限定的。
「とう、とう、とう、とう、とう、とう」
教師は喋り続けている。
目の前に並ぶ無数の文字は、それだけで、睦のやる気を削いだ。
彼は、別の教師の事を考えていた。なぜか、彼の嫌な思い出の事を知っていた、担任の生物教師の事だ。記憶の反芻の中、睦の目の前には、華奢で小柄な女教師がいる。
「君に頼みたいことがあるんだけど」
睦の頭に疑問符が浮かんだが、それを表情には出さないよう、努めた。
教師に、「知らない」ことを、知られないよう振る舞うことが、睦のこの頃の流行りだった。
「と、言うと?」
担任教師は、このところ暇を見付けては、順番に生徒を呼び出している。
その理由を、彼は当然知っていた。いや、学校中の人間が知っている。一年学期末試験に、睦のクラス内で集団カンニングの噂があった。
後になって、気の弱い生徒が、「SNSを介して試験問題が売られていた」と告白した。けっこうな騒ぎになったが、首謀者は分からないままだった。
結局、睦のクラスでの学期末試験は無効になった。再試験が行われる事になり、試験問題を買っていなかった生徒からは、ブーイングが起こった。しかし、生徒の言質や、わずかな証拠だけで、生徒30人全員の白黒をハッキリ付けるのは、無理がある。
万一の冤罪で、生徒とその保護者の恨みをどれだけ買うか知れない。全員の不満を、少しずつ買って、場を納めよう収めようというのが、教師陣の判断だった。
だから、生玉典子は警戒している。今度の中間考査でも、同じような事が起こらないよう、面談という名の「尋問」で、犯人探しと牽制を兼ねている。
だが、睦を前にして、生玉典子は「頼みたいことがある」と言った。
続けて、「君、不思議な事ができるらしいね」
睦は思わず目を伏せた。
しまった。びびってるように見えたかな。
生玉先生は、睦にとって、怖い女教諭だった。能面に似ていて、顔に凹凸は少なく扁平である。しかし、バランスの取れた端正な顔立ちで、切れ長の瞳の奥に、琥珀がある。
生玉典子は、怒鳴りはしないが、生徒への視線は、鋭くて冷たい。
訥々と生徒を諭しながら、
「別にどうでもいいんだけどね」
という本音が、胸中に淀んでいるようだ。
血生臭い、女の深淵を見るようで、睦にとって、生玉典子は近寄りがたい存在だ。
ただ、彼女を美人だと持て囃す同級生も多く、恐れを知られるのは、恥ずかしい。
「なんスか、それ」
斜に構えて、聞き返す。
「君には、見なくてもどこに何があるのかわかる。そういう力があるって、お友だちから聞いたんだけど」
睦の心臓が高鳴った。即座に、早口で否定する。
「そんな事できるわけないじゃないスか。先生、ドラマの見すぎっスよ」
その様を、冷めた目で眺めて、生玉典子は言った。恬淡として。
「あら、そう。睦君は、嘘を吐くのが下手ね。下手というか、ど下手くそね。いえ、もう、一片の才能も無いと言っても、過言ではないかもしれないわ。まさかと思っていたけど、心当たりがあるのね?」
突然の痛罵に、睦は唖然とした。
生玉典子は続ける。
「もしできるなら、その力で、カンニングな犯人探しを手伝ってほしいと思ったのよ。テスト中に、スマホとかタブレットとか、隠し持って怪しい動きをしてるコを」
「‥‥‥‥」
「良いのよ、気にしなくて。幸本(コウモト)君本人がカンニング犯じゃないことは分かっているわ。いつも通りだったし」
そう、いつも通りの中の下である。
しかし、睦の心に、むくむくと悔しさが沸き起こる。
睦は年相応に、素直よりも、有能な嘘つきに憧れていた。先生の物言いに、信用よりも、侮辱を感じた。歯噛みをしたあと、
「でも、俺は‥‥」といきり立った。
「でも、何?」
琥珀の瞳が光る。
しまった。睦は再び目を伏せる。
「いえ、なんでもないです‥‥」
「隠し事してるの?」
隠し事をしていた。先生の言うとおり、睦自身は、昨年末のカンニング騒動に関わっていない。しかし、首謀者を知っていた。
犯人は、睦の小学校からの悪友だった。下校途中、「睦にだけ」と、犯行を自白していた。
「教師ってチョロいよな」と嗤っていたクラスメートの俊之(としゆき)は、実はカンニングなんかしなくても、成績が良かった。
その、大人の世界を下に見る態度は、睦にとっての憧れだった。友人を売るなど、卑怯の極みだった。睦は憮然として、口をつぐんだ。
「そう、じゃあもう、行って良いわよ」
「あの、先生」
「なあに」
「‥‥誰から聞いたんスか」
「何を?」
「俺の噂」
生玉典子は、なぜか不敵に笑った。そして、彼女は脚を組み換えた。タイトスカートから伸びる、白く肉付きの良い足が動き、思わず目で追ってしまう。しかし、睦は、これにも慌てて目を逸らした。視線は宙を掻く。
ああ、だから嫌なんだ。睦は、顔が火照るのを感じた。生玉典子は、思春期の性的な好奇心を、冷ややかに見下している。
「先生もねぇ、実は、ちょっとした不思議な力があるの。」
「どういう意味スか」
「人の心が読めるのよ」
また、心臓がドクンと脈打つ。睦は顔を上げた。
「は」
そんな、まさか。と言うことは、今まで俺が考えていた事‥‥アレも、アレも、アレも、全部この人にはもろバレだったと言うのか‥‥?
滝のような汗が、睦の顔を覆った。
いや、落ち着け‥‥
「そ、それなら、そのテレパシーで…犯人が分かるはずじゃないですか。嫌だな、先生、からかわないでよ」
生玉典子は、リズムを取るように、膝を動かした。衣擦れの音が睦の耳をくすぐる。
「ふふ。そんなに楽な話でもないの。先生もね、心が分かる子と、分からない子が、いるのよ」
「お、俺のは、分かるんですか?!」
「そうねえ‥‥」
生玉典子は、睦の心の奥底まで覗きこもうという風に、ぐっと顔を近付けていた。
「本当に?」
「大体ね」
生玉典子の水晶体に、青白い睦自身の顔がある。
「じゃあカンニングも」
睦は、今度は椅子から飛び上がった。
「やっぱり、何か知ってるのねえ」
「だ、騙したのか。テレパシーが使えるなんて言って」
「誰もテレパシーが使えるなんて言ってないわ。睦君。今のは自白よ」
「え」
「言いなさいよ」
「‥‥いや」
生玉典子が、睦を睨み付けている。
睦は、黙る。不安や恐れを隠して‥‥そうだ、絶対に言わない。余計な事を言わないよう、今から俺は、デポン期に絶滅した節足動物の化石のように、黙る。
先生が、「もういいから、帰りなさい」と言うまで。
睦が頑なに黙すのを見て、生玉典子は、アッサリと「良いわ、帰りなさいよ」と言った。本当に、睦の心を読んでいるようだ。
「え、良いんスか」
呆けたように、つい生玉典子と目を合わせると、生玉典子は、蛇のような俊敏さで、睦の視線を捕らえて
「その代わり、もう一回聞くからね。必ず。」
その言い方に、何か鬼気迫る物を感じ、恐怖がぶり返した睦は、すぐ部屋を飛び出した。
「とう、とうとうとうとうとう」
古典教師の話は、意識しなくとも、耳をすり抜けていくのに。
冷静に考えれば、怯える必要はない。生玉典子の何が怖いのか、睦には分からなかった。
その容姿や、ことばの一つ一つを思い返して、恐怖を克服しようとする。しかし、逆にその神経過敏が、恐怖の根源という気もした。
「もう一回聞くからね」
生玉典子の言葉を思い返して、睦は、疑問符を付ける。どういう意味なんだろう‥‥
睦は俊之の後ろ姿を、盗み見た。
その日は、俊之の方から「一緒に帰ろうぜ」と誘ってきた。
下校途中、「今日、生玉先生に呼び出されてたけど、言ってねえよな?」と、訊いてくる。
単刀直入。きっと、睦の密告が気になっていて、下校に誘った。
「言うわけねーじゃん!俺を信用してないのかよ」
睦は否定する。
「良かった。いや、睦は、嘘吐けない奴だからさ」
なんの弁明か分からないその言葉。底意があるのか分からない。しかし、睦はムッとした。生玉典子にバカにされた記憶が新しい。
「でも、どうやって試験問題盗んだんだよ?誰にも言わないから教えろよ」
「えー、内緒だよ。内緒」
俊之は、肝要なところを言おうとしない。睦は、ますます見下されているように感じて、不満を抱いた。睦が俊之を慕い、憧れるのは、特別な能力なんてなくても、自分にできないことを要領よくこなせるからだ。周りの羨望も欲しいまま。
睦には透視能力がある。しかし、限定的。 透視と言っても、分かるのは立体のみ。複数のコップから、ボールが入っているものが分かっても、裏返されたトランプの文字を、読み取る事はできない。それが分かると気付いたのは、睦が物心付いたとき。それを小学校の時は、無垢な心でただ自慢にしていた。周りに、透視能力を披露しまくった。
初めはすごい・すごいと持て囃していた同級生の気持ちは、次第に厭き、さらに、妬みを生んだ孕んだ。
ある日、担任教師に「超能力がある人はテストで良い点が取れるから、ズルい」と、見当違いの告げ口をしたものが現れた。
睦は、「話し合い」という名の裁判に、被告人として吊し上げられた。
教師はまず、超能力の存在自体を疑っていた。そんなものがあるわけない。その上で、カンニングの噂が立ったということは、睦が、何か、疑われるような行為をしたのかも知れない、と考えていた。 いたたまれなくなった彼は、カンニングなどしたことがないのに、「もうしません」と、嘘の自白をせざるを得なくなった。
思い返すと、頭が熱くなった。理不尽な扱いに対して、怒りか恥ずかしさか、判じ得ないような気持ち。
クラスメートは睦を俾猊し、距離を置いた。睦がカンニングなどしていないと、知っている人間でさえ、睦の側にいようとしなくなった。俊之を除いて。
俊之は昔、大事なことを教えてくれた。孤立した睦を励ましてくれた、友人だ。
俊之は、落ち込む睦に、クラスメートに睦を卑しむ権利はない、と言った。
そもそもカンニングの何が悪いというのか?
「何点か稼いで、それで相対的に成績を落とすのは、それほど賢くない連中ばっかりだ。カンニングを許さないのは、バカにされたと感じた、一部の生徒と教師だけ。けど、騙されたり出し抜かれた奴が怒るのには、「『自分が騙される筈がない」』、という慢心があったからだ」
「いわば、責任転嫁なんだ。
あとは、クラスメートは、良いことにも悪いことにも、ただ流されているだけの、主体性のない連中ばっかりだ‥‥」
そんな事を睦に言った。元気を出せ。落ち込むのはバカだ。そんな風に、睦を励まし続けた。俊之の口振りは、小学生と思えないほど、老長けていた。カンニングを悪い事だとも思っていないようだ。
俊之の言っていることはよく分からなかったが、周囲の目を気にせずに、一緒にいてくれた俊之に、睦は気を許した。そして、同い年ながら一回りも年上のようで、大人を食った態度に憧れを抱いている。
しかし、だからこそ、カンニング事件の主犯であるとカミングアウトし、そのくせ肝心なところは隠す俊之は、「俺はお前よりも上手くやっている」という誇示をしているようにも見えた。そして、睦を友人としてではなく、体のいい子分として扱っている。そういう疑念。
睦にとって、俊之は付き合いの長い友だちなのに。
試験日が近付いている。
生玉典子の牽制のおかげか、俊之の気紛れか、今度の中間では、試験問題が盗み出される事はなかった。前回は、SNSに架空のアカウントが作られ、そいつがメッセンジャーを通じて、生徒に試験問題を横流ししていた。ただし、有料。しかし、高額ではない。
生徒の誰もが、お小遣いで買える程度の額だった。SNSを頻繁にチェックする生徒は、詐欺を疑いながら、ものの試しに、その「参考問題」を購入した。それが、試験問題そのものだとは思わなかった。試験後、くだんの架空のアカウントは削除されていて、誰がアカウント保持者かは、分からなかった。
友人申請は、謎のアカウントから、全クラスメイトに一斉送信されていた。プロフィール画像は、可愛い女子がトイプードルと映っている写真。経歴は、汐ノ宮中学在学。睦たちの通う学校だ。
生徒の中に、写真を保存していた者がいて、教師は、それを「押収」し、学内生徒と照らし合わせた。しかし、それは、校内の誰でもなかった。
頭の固い教師は、見ず知らずの人間からの友人申請を受けたのか、と、生徒の何人かに怒鳴り散らした。素直で気の弱い生徒は、涙ぐんだ。
「友人のナニガシとは既に友達だったし、他にも同世代の友人がたくさんいた。フォロワーも100人以上いた。学校にいるなら、SNSを通じて友達にもなれるし、アカウントが偽者なんて思わなかった」と。
教師は閉口した。
睦は、生徒の言い分に気持ちを寄せた。
生玉典子は、そのとき、ただ成り行きを見守っていた。
俊之は陰で、教師を嘲笑った。
「自分の無能を棚にあげて、生徒に当たるなんて、最低だよな」
教師は、今回の中間試験にあたり、生徒が不審なアカウントと友人関係を築いていないか、聞き込みをしているらしい。睦から見てもそれは中途半端な対応だった。しかし、網目状に広がるオンラインネットワークをつぶさに調べるのは、簡単じゃない。
保護者に警戒を促しても、協力の程度はまちまちだった。だから、教師陣は、犯人特定を置いて、テスト問題が流出しないよう、セキュリティを強化することに努めている。
取り分け、生玉典子は慎重で、今回は手書きで試験問題を作成し、試験日前日に印刷することにしたようだ。それを、睦は後で本人から聞いた。アナログ。しかしそれだけ不正は難しい。
中間試験の前日、それに挑戦するかのように、俊之は「今度は俺だけ満点取ってやろうかな」と睦に言った。睦は驚いた。
「またカンニングするつもりなのか?」
「だって、慌てたりキレてる大人って、面白えじゃん。おちょくってやりたくなる。」
俊之は言った。面白い?面白いかも知れないが
「今度こそバレたら、ヤバイぜ。停学になるかも」
「バレなきゃ良いんだろ、平気だよ」
傲然と言い放たれて、睦はもう二の句が告げない。
「睦よ。バレること心配してたら、バレるんだぜ?」
「そういうもの?」
「そう。堂々としてる方が良いんだよ」
睦の胸中に、いろんなものが渦巻いていた。自分本意を、全て肯定できてしまう俊之への憧れ。しかし、それだけではない、薄暗い感情が漂う。口にすれば、それはただの嫉妬の発露。また、親や教師の言葉を借りた、陳腐な説教になると感じた。
だから何も言えなかった。
嘘を上手に吐けるのが、そんなに偉いかよ。
悔しい睦は、ひとつ、俊之の秘密していることを探ることにした。もちろん、生玉典子に漏らすつもりはない。それは卑怯というものだ。
そうだ、俊之の「犯行トリック」を暴いてやる。それを俊之に言って鼻をあかす。
睦は、素直なだけの愚鈍な人間じゃないということを、俊之に知らしめる。
睦は、しばらく「それ」を使っていなかったものの、それは、歩くとか走るとかと同じく、感覚で分かることだった。睦は、本来「何か」に覆われている中身にまで、視界を広げることができるのである。
「それ」はただ、少し口を開けて、神経を集中させる。簡単な事だ。
睦に分かる事は、限られている。「それ」で分かるのは、ぼんやりとした物のシルエットだけで、ほとんど形が一緒なものを区別することはできない。たとえば掌に隠されたものが、ビー玉か飴かとか、そんな事まで分からないし、箱に隠されたものが、ノートか教科書か分からない。柔らかいか硬いか、大体の感触ぐらいなら、人が見ただけで想像付くように、少しは判別できたが、ぐちゃぐちゃに折り畳まれたシャツは、ぐちゃぐちゃに折り畳まれた何かであって、ズボンかシャツか、大きな風呂敷か、分からない。とても限定的な能力。
テスト一日目。
睦は、斜め前の席の、俊之を見た。前屈みで頬杖をついている俊之は、気だるげに、前の席の女子と話をしている。俊之はモテた。
「はい、教科書を鞄の中にしまって。机には、筆記具以外のものを置かないこと」
教師の一声で、クラスメートが、ごそごそと動いた。俊之も居ずまいを正したが、それでも少し前屈みだった。
一科目目は、数学だ。
「時間です。はじめてください。」
教師の一声に、また、クラスメートがごそごそ蠢く。単なる定期テストたが、睦は感じる。異様な緊張感。教師は、テストの時、生徒に呪いをかけている。数字で測る者と測られる者。もちろん測る者が上位者だ。測られる者の中に優劣の層ができても、生徒と教師という立場は別格だ。少なくとも、学校を卒業するまでは。この立場の呪いを自らの意思で破ろうとする俊之は、やっぱり凄い奴だと思う。
睦もまた、少し緊張しながら、不自然でない程度に、口を開けた。口を開けなければ、何故か「それ」は使えない。
浅く吐く。神経を集中させる。上半身で、俊之の方から返ってきた、感覚を拾う。空っぽの机。鞄に、ノートや教科書、おそらくスマホもある。睦は首を傾げた。
睦は、俊之がカンニング犯なら、すぐに何か不正に値するようなものが見つかると楽観視していた。たとえば、机にスマホやタブレットを入れているとか。もう一度、試す。
空っぽの机。服の中にも、制服以外の、別の何かは感じられない。
睦は、直に、俊之を見た。俊之は、淀みなく手を動かしている。
睦は、文字通り、肩透かしを食った。
「そこ、ごそごそしない」
「あ、はい」
睦は、自分の解答用紙に、目を向けた。
二科目めの、現代国語。
一科目めで、出遅れた。睦は、俊之の事を気にせず、テストに集中した。国語は苦手だ。
「あなたは呼ぶ声で わたしは答える声
あなたは願望で わたしは夢の実現
あなたは夜で わたしは昼」
何が言いたいか分からない詩の後、問いに、「作者の意図を答えよ」とある。
はー・・・。睦は頭を抱えた。
結局、俊之とテストの、双方に気を配ろうとして、どちらも注意力散漫だった上に、釣果もない。睦は落ち込んだ。
俊之の方を見る。俊之は勉強ができる。カンニングなんてしなくても、高得点を取れる。ひょっとして、ただ、自分をからかうつもりで、「カンニング犯だ」と騙っただけかもしれない。睦は考えた。
聞いてみようか。「嘘だろ?」と。それで、図星なら動揺するだろうか。それとも、笑い飛ばすか。どうしてそう思ったんだ、と。確証があればいいのに。けど、どの返答も「嘘」が混じっているとしたら、結局俊之がなんと答えようと、その真偽を見極めることができないだろう。
睦がまごついているうちに、俊之が席を立った矢先だった。歩いていた南戸(みなみど)とぶつかって、俊之は、椅子の上に尻餅を付いた。南戸もよろけて、俊之の隣の席にぶつかり、そしてこちらは床に尻餅を付いた。俊之が舌打ちした。
睦は、俊之のキレやすいところが、好きじゃない。
「おい、横幅広いくせに、ちんたら歩いてんなよ」
南戸は、何も言わなかった。俯いたまま。俊之と仲が良い前の席の女子が、横槍を入れた。
「南戸。ぶつかったんだから俊之君に謝りなよ」
南戸が悪いんだろうか。睦は、不穏な空気が漂うのを肌で感じ、俊之に声をかけるタイミングを失った。睦は黙って、ただ事の成り行きを見つめていた。
「‥‥なさい」
地面に向かって、南戸が何か呟くのが、かすかに聞こえた気がした。南戸。情けない奴。自分は悪くないと思うなら、そう言えば良いのに。
俊之は、もう一度舌打ちして、教室を出ていった。その後ろ姿を、床に膝を付けたまま見守った南戸は、のろのろと立ち上がろうとした。
それを、くだんの女子が、再び突き飛ばした。
ガシャッ。ズリッという音がして、南戸は、顔から床に伏した。今度は、すぐに後ろを振り返り、女子を睨んだ。しかし何も言わない。
女子は悪びれず、
「ごめん。ぶつかっちゃった」と言った。
わざとだ。白々しい。南戸が何も言わないことに、業を煮やした睦は、
「おい、今のわざとだろ。南戸に謝れ」と女子に言った。
女子は、
「は?アンタ、関係ないし」
と言った。
「なんでも良いから謝れ」
「謝ったじゃん!」
「ちゃんと謝れ」
「正義漢ぶるなよ、吐き気がする」
女はすぐ口答えする。二言めに「気持ち悪い」と言えば、勝った気になる。
「じゃあ吐けよ」
女子は、睦の剣幕に怯んだ。睦を睨み付けたが、それ以上何も言わずに、教室を出ていった。
睦は、南戸に手を差しのべようか、迷った。南戸に同情したというより、俊之や女子生徒にやられっぱなしの南戸を見ていると、むかっ腹が立っただけだ。南戸は、上背がないのに、小肥りでダサい。友達になりたいとは思っていなかった。
睦が俊巡している間に、南戸は、睦の助け船にお礼の一言もなく、足早に去っていった。
なんだよ、どいつもこいつも。舌打ちしたくなったが、堪えた。
翌日、テスト二日め。
一日目に、出鼻を挫かれたために、なんとなくやる気が出なかった。一時間めは、生物の試験だ。生玉典子が教室に入ってくるのを見て、睦は余計にげんなりした。生玉典子は、均整の取れた体の線がよく分かる、タイトなワンピースを着ていた。生徒に一瞥もくれず、テスト用紙を教卓に放り、言う。
「手を膝に置いて、座りなさい」
凄烈な一言。
往生際悪く、教科書を開き続ける生徒を、ひとりひとり睨んでいく。やがて訪れる、衣擦れさえない静寂。異様。まるで黙祷。
睦は思わず笑いそうになった。けど、笑うと絶対に生玉典子から、罵声が飛んでくる気がして必死に堪えた。
テストの際の緒注意を、滔々と陳べ始めた。生徒に、カンニング事件を強く想起させるような注意はない。
「では、始めてください。」
睦は、生玉典子を見て、そして、俊之を見た。
口を開いて、「感じて」みる。
俊之におかしなところはない。 生玉典子が、今後どれだけ睦を尋問するつもりでも、睦は、「分からない」と答える他ない。それはホッとする反面、癪に障る。試験に集中できない。睦は、ソワソワとペンを回しながら、もう一度、俊之を「感じて」みた。
それが、違和感の原因だった。俊之の耳に、何か。金属?プラスチック?イヤホンのようなもの。補聴器のような小さい何かで、ワイヤレス。睦は思わず、俊之を見た。もちろん肉眼では、目を凝らしても俊之の後ろ姿、わずかに耳朶が見えるだけだ。
睦はもう一度神経を集中して、「感じて」見た。次の違和感は、教卓だった。教室の中にはたくさん物がある。教科書、ノート、筆記具、腕時計、それが生徒の数。そして、生徒自身も。
睦は、今度は神経の焦点を、教卓にあてて、「感じて」みた。固い長方形の何か。たぶん、タブレット。睦は、それがカンニングの相方であることを直感した。生玉典子の所持品ではない。なぜなら睦は、教卓の側面を「感じて」見ているのにも関わらず、その怪しいタブレットは、睦に液晶面を向けている。生玉典子が無造作に自分のタブレットを入れたのなら、それは、タブレットを上方から見たときの、薄い側面が見えるだけのはずだった。誰かが意図的に、教卓の奥に貼り付けている。おそらく、見付かりにくいように、誰かが仕込んだもの。
それから先の出来事は、矢継ぎ早に起こった。おもむろに生玉典子が立ち上がり、肉付きの良い脚を小幅に開いて、体を傾げる。睦が気にしていた教卓の中に、腕を差し込み、まさぐり始めた。ぺりっと渇いた音がした。その時、俊之は何食わぬ顔でイヤホンを外し、鞄の中に滑り込ませた。主犯のタブレットが見付かっても、その持ち主が誰か分からなければ、にわかに俊之へ疑いがかかることはない。
しかし、少なくとも数人は、俊之の怪しい行動を見ているのだ。生玉典子の上半身は、教卓の陰に隠れていても、生徒の視点は皆「俊之と同じ側」にあるのだから。俊之は、生徒の誰かが密告するとは、考えないのだろうか。…いや、俊之は、教師にさえ見られず確たる証拠が無ければ、堂々と否定するのじゃないか。
「カンニングの何が悪い」
「怒っているのは、バカにされた教師だけだ」
俊之の言葉を思い出した。
生玉典子は、しなやかに上半身を起こした。無造作に、教卓の上へ、鈍色のタブレットを放る。沈黙。今までテストに集中していた生徒は、手を止めて、生玉典子とタブレットに、視線を向けている。机と机の間を縫い生玉典子は真っ直ぐに歩いた。俊之の方へ。
「立ちなさい」
俊之は、生玉典子を見上げ、困惑しながら、教室を見渡した。いかにも、「なぜ?」という風な無垢の表情。どうしてこんな顔ができるのか、睦は不思議に思った。
「立ちなさい、トシユキ君」
二度めの圧力。
「なぜですか?」
反駁しながらも、俊之は立ち上がった。
「君は職員室へ。先生と一緒に来なさい。テストは中止よ。けど、他の生徒は勝手に退出しないように。木村先生を呼んでくるから、それまで静かに待っていること」
「なぜですか?僕は何も」
俊之が言い終わらないうちに、生玉典子は、机の脇に提がっている、俊之の鞄をまさぐった。
「これは?」
それは、ベージュで小さな雪だるまのような形をした何かだった。さっきまで、俊之の耳の中に入っていたもの。
「イヤホンです。他にも持ってきてる奴は、いますよ」
「まるで、今まで付けていたみたいに温かい」
「先生が持っているからです」
俊之は、傲然と言い放った。典子は溜め息を吐いて、イヤホンを俊之の机に転がした。タブレットと同じように。
典子に俊之を追い込む決定打は無いように思えた。しかし、それを悔しがる様子はない。自身の確信だけで十分で、俊之の態度などどうでも良い。ただ、嘘を吐き続ける俊之と、それを黙殺する生徒を、睥睨している。お前らバカじゃないの?
俊之は、なぜ気圧されず、立っていられるんだろう。いや、そもそも生玉典子への恐怖は、睦しか感じていないものなのかもしれない。睦が特殊能力によって感じ取ったものを、そのまま盗み見たようなタイミングで、生玉典子は俊之を吊し上げた。この勘の良さを、恐ろしいと思えるのも、睦だけなのだ。
睦は努めて視線を下に下げていた。そっと視線を上げると、なぜか生玉典子と目が合った。冷利で、琥珀色の瞳を、睦に向けていた。次の生玉典子のことばは、睦が予想だにしていないことだった。
「実はね、つい先日、カンニング犯は君だって言ってきた子がいたのよ」
生玉典子は言った。睦は、心臓が皮膚の裏を叩くのを聞いた。何を言うつもりだろう。俺はチクってないぞ。・・・チクってないよな?
「誰ですか、それは」
俊之は、聞き返した。
睦は、再び顔を上げた。今度も、生玉典子と目が合った。なんで俺を見るんだよ。
「言ったら可哀想よ」
「可哀想なのは俺です。証拠もないのに、いい加減な情報でカンニング犯にされかけてるんだから」
間。しばらく、生玉典子は口をつぐんでいた。何かを考えているように見えた。口元に、薄く笑みを浮かべているように感じる。
「そうね、一理あるわね」
何だって。睦は混乱した。
もう一度、生玉典子が口を開きかけたとき、睦は勢いよく立ち上がった。
「おい!」
反動で、椅子が転けた。空気が凍りついた。今度は、生玉典子だけではない。教室中の視線が、睦に注がれていた。無論、俊之も。
ただし、彼だけには、「驚き」の表情はない。怒り。
目尻を吊り上げて、睦を睨み付けていた。
生物のテストは無効になったが、他の科目は予定通り行われた。俊之は、程なくして教室に戻ってきた。結局、俊之にかかった嫌疑はどうなったか、聞いている生徒がいた。俊之は答えなかった。睦は聞けなかった。
頭の中は、大混乱だ。反省や、自問自答や、典子への怒りと、俊之への爽快なような罪悪感のような複雑な気持ち。俊之に謝るべきか、生玉典子に怒るべきか、それとも…開き直るべきか。混乱のままに、テストは終わった。
俊之は、睦に目もくれず帰ってしまった。睦のやり場のない気持ちは、結局生玉典子に向かうことになった。
職員室で、典子は生物室にいると教えてもらった。走る。
「先生!どうしてくれるんですか」
教室のドアを開けて、叫んだ。生玉典子は、なぜか着替えの最中だった。テストの時のタイトなワンピースではなく、ベージュのボウタイブラウス。マーメイドラインの膝丈スカートを履こうとしているところ。生玉典子が脱いだものは、人体模型の腕に提げられていた。睦は硬直した。しかし、生玉典子は、取り乱す素振りを見せなかった。
「何?」
不機嫌な様子で、チャックを上げる。模型からワンピースを取り、肩のところにハンガーを通し、傍らの紙袋に入れた。流れるような所作だった。しかし、片方の耳にはピアスがない。菫色の小さな玉が付いたピアス。生玉典子は、何気なく耳に手をやり、それに気付いた。紙袋にまさぐり足元を見渡す。
人形の従者は物を言えない。ただ、困ったようにその場に立ち尽くすのみ。
呆然自失の状態から回復した睦は、叫んだ。
「酷いじゃないですか!」
「何が?」
生玉典子は素っ気ない。
「何がって、まるで、俺が、その」
言いたいことがまとまらない。しどろもどろになっていると、典子は睦を睨み付けた。そして舌打ち。
「な、な」
教師の悪態に呆然とする睦。
「イラつくわねえ」
踵が低いわりに、よく響くパンプスが床を打つ。生玉典子の手が、睦の顔に向かって来た。思わず目を瞑る。バシっと音がしたが、痛みはない。おそるおそる目を開けると、典子は、睦の後方の扉を閉めただけだった。睦は、開け放した戸を閉めていなかった。しかし、琥珀の眼光は、今白炎を湛えて、睦を見下ろしていた。
「どうにかならないのかしら。アンタのその鈍感さは」
しかし、典子が続けるのは、粗野な行動で思いがけず着替えを覗いてしまった事への、苦情ではない。見付からないピアスへの苛立ちでもない。
「言ったはずよ。アンタのは自白だって」
彼女から目を逸らそうと、睦の瞳は虚空を掻く。今日一日で、何度典子の視線から逃れようとしただろうか。片方の耳にだけ通ったピアスが、わずかに揺れている。
「でも、俺は‥‥」
再び舌打ち。睦は、黙る。
「私が試験を中止してからは、確かに、みんなトシユキを見てたわ。けど、アンタは違うわね。試験が始まったというのに、一人トシユキを見たり、教卓を見たり。目立ってたわよ」
「お、俺の視線で分かったって事ですか」
「そういう事をやりそうな生徒に、当たりも付けてたけど。まあそういう事ね」
「せ、先生。ちゃんと、俊之に、言ってよ!俺がチクったんじゃないって」
抵抗した。
「何故?」
「なぜって、それは、だって」
睦は、俊之を売ったりしていない。それは、自分で俊之に言っても説得力がないからだ。
「アンタのは自滅よ。自白に自滅。なぜ私が二人の仲を執りなさなきゃならないの?自分で解決しなさい」
けんもほろろな典子の態度に、睦の中で反抗心が大きくなった。恐怖を抑えて、言い返す。
「自滅って、元はと言えば、先生が煽るような事言うから・・・・」
「いい加減にしなさい」
生玉典子は激怒していた。身をすくめる。しかし、同時に疑問が芽生えた。なぜ、典子は睦に怒るんだろうか。カンニング犯の俊之ではなく。
睦は、生玉典子の視線を真正面から捉えた。睦にとって、それはなかなか、勇気のいることだった。そして、睦は思わず「感じて」しまった。使うつもりではなかった。
生玉典子の呼吸。静かに波打つ鼓動。この人はいつも、何かに怒りを湛えているが、静かだ。睦の自分でも気づかない性格や特性。それが、典子が感じる怒りを増長するようだ。それが怖い。ボウタイのブラウス。普段の生玉典子には見られない、愛らしい服。その下にあるワイヤー。ワイヤー?ああ、そうか。下着だ。下着に引っ掛かる、小さな硬い玉。
睦は、顔に血が上って意識が遠退くのを感じた。遠くで、何かを言っている自分を感じた。
「引っ掛かってます‥‥その、下着に。」
典子は一瞬、睦が何を言っているか分からず、眉を顰めた。そして、少しだけ目を見開き、細くて長い指を、ボウタイの真ん中に差し込み、菫色の玉をつまみ出した。
「さっきので確信したわ。アンタには、普通人間は持っていない、特殊な感覚器官がある」
睦は返事ができない。
「きっとそれは汎用性があって悪用もできる。人の好奇心をいたずらにくすぐる。なのになんなの?アンタのその鈍さは。ボーッとしてると思えば、トシユキごときや私に鎌をかけられた程度で狼狽える」
「‥‥」
「カンニングがなに。つまんない友情にヒビがいったからって、喚くんじゃないわよ。アンタ、いつか、もっと大きなトラブルに巻き込まれるわよ。解剖されてから嘆いても遅いってことを自覚しなさい」
言いたいことを言うと、典子は、生物室から出て行った。取り残された睦は、たった半日の事だが、精神が疲弊し、呆然としていた。アルコールの匂い。瓶詰めにされた節足動物、そして、爬虫類。生き物は睦だけとなった空間で、そこはなぜか脈動が満ちている。
にわかに意識をハッキリさせた睦は、典子の跡を追った。言いたいことも、聞きたいことも、相変わらずまとまっていなかった。しかし、その場に取り残され、所在無げに佇むよりは、典子に罵倒されようが「何か」を叫んで憂さを晴らす。睦が、咄嗟に選んだのは後者だった。
「先生、待ってよ」
典子の足は速かった。部屋を出たのは、数秒の差だと言うのに、典子はもう廊下の端にいて睦の視界から消えようとしていた。
「ちょっと待って」
聞こえないのか、聞こえないフリをしているのか、典子が再び振り向いたのは、校門を出てすぐのところだった。
上半身だけを捻り、睦に顔を向けた。露骨に嫌な顔をしながら。
「まだ何か?」
「あの」
呼び止めておいて尚、睦は俊巡した。いちばん気掛かりなのは、本当に、典子が睦の言動だけで気付いたのかということだ。睦が、典子のことばを借りると「特殊な感覚器官」を持っていることに。しかし、この期に及んで、睦は典子にそれを認めることを躊躇っていた。睦は、質問の主旨を少しずらす事にした。
「その、先生。聞きたいことが」
「何?」
「俺は先生から見たら、そんなに分かり易いの?隠し事もできないほど。どうやったら、うまく秘密にできる?」
典子は、素っ気ない。
「さあ。恋愛でもしたら」
さて、これを至言とみるか迷言とみるか、意見が分かれる事だろう。睦については、典子のことばが理解できず、ただ呆けていた。それを気にせず典子は再び歩を進めようとする。
「ちょ、ちょっと先生」
「何?」
今にも舌打ちしそうな表情である。
「そのさ。先生が俊之には怒らなくて、俺にイライラするのって、つまりそういうことなんでしょ?あんまり嘘が上手じゃないから。だから、もっと丁寧に教えてよ」
そうそう、俊之に馬鹿にされるのも、睦が嘘を吐けないからだ。どうにか見返してやりたい。
しかし、典子は目を丸くした。それは、睦への軽蔑ではなく、純然とした驚きに見えた。
「呆れた。そんな事考えてたの」
「なんだよ、そんな事って」
典子が睦を軽蔑するのも、同じ理由のはずだ。
生玉典子は、考えていた。睦には、典子はいつでも生徒との会話を忌避しているようにみえた。生徒とのコミュニケーションが感染性のウイルスであるかのように。自分が汚染されないよう、遠目から睨み付けているだけ。そんな雰囲気が、睦は苦手だった。しかし、典子は、睦に噛んで含めるようにことばを紡いだ。それに睦は驚いた。それは侮蔑ではない。説教らしい説教だった。
「嘘と秘密は全然違うわよ」
「え、どういうこと?」
「嘘は序列そのものよ。秘密を守るのに、確かに嘘は便利よ。でも、嘘を吐く人間は、騙される人間を対等とは思わないし、騙されない人間は、嘘を吐く人間を対等とは思わないわ。なんの生産性もないライアーゲームに、私は真剣になれないの。トシユキが嘘吐きだから、私がアンタよりトシユキを評価しているなんてのは、誤解も甚だしい事よ」
「え、よく分かんないんだけど」
辛うじて睦に理解できるのは、
「俊之をスゴいとは思わないってこと?」ということだ。
「トシユキは、アンタとはまた別の自滅型でしょうね。私は、自分を守る事に頭を使わない人間が嫌いなの。身を粉にしてトシユキを更生させなきゃいけない義理もないわ」
「‥‥」
やっぱりよく分からない。しかし、義理くらいあっても良いじゃないか。生徒と先生なんだから。と口答えしたら、またキレられそうなので、止めておく。
「聞きたいことは、それで全部?」
「いや。じゃあ、秘密の上手な隠し方教えてよ」
「ああ?」
睨まれる。怖い。まるでチンピラだ。
「知らないわよ。なんで私が?」
「せ、先生だって、一応教師だろ?!俺だって困ってるんだ。空が飛べるわけでも、ビームが出せるわけでもない。触れば傷が治る便利な手を持ってる訳じゃない。せいぜい、隠れたものの形がわかる程度で、特殊能力とか言われて尊敬されたかと思えば、冷たい目で見られたり疑われたりするんだぜ!」
そして、顔を蒼白にして、睦は黙った。言いたいことをやっとことばにした。睦を典子が冷たくあしらうことはなかった。相変わらず冷たい物言いではあったが。
「まずひとつ言っておくけど」
「は、はい」
「物を頼むなら、それなりの態度が伴っていないとダメ。私にはちゃんとしたことばを使って。良い?」
「りょ、了解ス」
「ふざけてんの?次『で』を省いたら、卒業まで、いびり続けるわよ」
「は、はい」
「じゃあ、行くわよ」
「え、はい‥‥。とりあえず、先生さようなら」
「さよなら、じゃないわよ。アンタも行くのよ」
「え、どこ行くんすか」
「今から行くところへ行くのよ。上手に秘密にするなんて一朝一夕でできることじゃないの」
どういうわけか、睦は行く先も分からぬまま、生玉典子に同行することになった。フェミニンな格好が、典子に似合っていないわけではない。しかし常はタイトな服が多い彼女である。家へ帰るのに、わざわざ着替えたりはしないだろう。
(どこに行くんだろう。)
学校から二駅。昼下がりの電車は空いていた。セミクロスシートで向かい合って座りながら、典子は、まるで睦などいないもののように振る舞っている。窓の外を見つめているが、瞳の中には険があった。
(そもそも「今から行くところに行く」ってなんだよ。世の中の外出する人間の大半が、今から行くところへ向かってるよ )
しかし、睦には、それを面と向かっていう勇気はない。それでなくても、生玉典子と話すとき、睦はいつも緊張している。典子との短いやり取りの間で、既に睦は疲弊していて、勇気も使い果たしていた。
(こういうの、何て言うんだっけ。口八丁で煙に巻く、みたいな‥‥ク‥‥ベン‥‥ベン‥‥ケイ‥弁慶?違うな)
「降りるわよ」
典子の一言で、睦の思考は中断された。慌てて、彼女に付いていく。
ブロック塀から、モチノキの梢が覗いている。閑静な住宅街を歩いて行く。
右手に現れたある一軒家で典子は足を止めた。インターホンを鳴らす。
やはりそれは、典子の家ではない。俺は付いてきて良かったのか?不安が過る。
そして、ある婦人が玄関の戸を開けたとき、睦は驚愕した。それは、恐怖に近かった。婦人の容姿に驚いたのではない。婦人と相対した、典子の表情に驚いたのだ。典子は、顔中に笑みを浮かべていた。
「ごめんください。敦子さんの具合はいかがですか?」
声も心なしか高い。典子の笑顔に、違和感を持つ様子もなく婦人は応えた。
「あらあ、いつもありがとう」
美人だが、顔色が悪く幸薄そうな女だった。厚塗のファンデーションの下に、小皺のひび割れが無数に隠れていた。若作り、ということばが、睦の頭に浮かんだ。顔は中年だのに、首から下は女子高生の普段着のように思えたビビッドカラーで体のラインが分かる派手目のトップス。ジーパン。
「この子は?」
中年の女は、睦に目をやり、聞いた。
「敦子さんのクラスメートの、幸元睦君と言います。とても正義感の強い子で、敦子さんの話をしたら、ぜひお見舞いに行きたいと‥‥」
ここで、典子は笑みを消し目を伏せた。
「突然では、ご迷惑になるからと、説き伏せようとしたんですが、本当に申し訳ありません‥‥」
女は、ハッとして目を見開き頭を振った。
「とんでもないわよ。わざわざ来てくださったのだから。ボク、お茶でも飲んでいきなさいよ」
ボク?自分の事だろうか。睦は、首を傾げた。なぜだろう。中年女の態度には、なにか、わざとらしいものがある。戸にかけた手を、何気なく見ると、ジェルネイル。小さなビーズが付いている。静脈の浮いた真っ白な手だけが、本当に女子高生のように張りがあって美しい。それが睦には不気味に思えた。
「いいえ、遅くなってしまいましたが、試験までの授業ノートを渡しに来ただけです。それから、補習については、また、敦子さんが登校されたときに」
奥ゆかしく振る舞う、今の典子は、もちろん睦から見れば違和感の塊だ。それは、けばけばしい初対面の中年女が与える不信感以上だった。睦は、趣味の悪いコントを見ている気分になった。そのただ一人の観客として、事の成り行きを呆然と眺めるだけ。
「お邪魔します‥‥」
典子に続いて、家に上がる。すると、この中年女は、典子ではなく、睦を見る。刺すような視線で。初対面であるはずの睦に何か含むところがあるのは、明らかな視線。気にしないよう努めながら、睦たちがリビングのソファに落ち着くと、中年女はキッチンに立った。
お湯を沸かしながら、彼女は言った。「男の子って苦手なのよね」
睦は、ギクリとした。睦の返事も、典子の返事を待たずに、彼女は続けた。
「不潔だし乱暴でしょ?そりゃ、そうじゃない男の子もいるだろうけど、女の子に比べて、やっぱり不躾な子が多いと思うのよ」
睦は、一気に居心地が悪くなった。ソファに奥深く座るのも、彼女の機嫌を損ねるような気がして、体重の半分を足にかけ、肩をすぼめていた。
彼女はよく喋った。盆に紅茶を乗せて、自身も典子の向かいに座りながら、喋り続けた。
「敦子はね、今二階にいるのよ。やっぱり具合が良くないってね。繊細なの。今の共学って、図太い方が良い・どんな子とも気楽に喋れるのが良い子って教育法でしょ。でも、それって、ただ分別がないのと同じじゃない。誰でも仲良くすれば良いってもんじゃないわよ。他人なんて、何考えてるか分からないんだから。私、今でも、あの子を女子校にやった方が良かったんじゃないかと思うの。上品だし、人あしらいは「人あしらい」として、やり方を教えてもらった方が良かったと思うの。でも、主人が、共学でないと嫌だって。お金を出すのは俺だからって。男の人は、自分の意見を通すのに、二言めにはそういう事言うのよね。でも可哀想よね。合理も信念も、娘への情もない。でも、私、納得したフリして、主人の顔を立てたのよ。ね、先生も分かるでしょう?男の人って単純だから、『そうです、アナタの言うとおり』って言えば、機嫌よく働いて、お金を出してくれるでしょ。扱いやすいわ。でも、共学については、後悔してるの。
‥‥中年女は、典子を上から下まで眺めた。
そういえば、先生、私のオススメ聞いてくれたのね。やっぱり年頃の女性は、そういう服装が似合うと思うの。○○○は、安いけど、海外製がだから、縫製がいい加減で。かと言って、△△△は、ちょっと高いわよね。私のオススメのメーカーは、販促モノだけど、値段もお手頃だし、国内製で良いわよ。もちろん、高級ブランドも一二着はあっても良いけど、家計を管理するのも、女の仕事でしょ? ね?ボクも今は分からないだろうけど、男の子が頼りないと、女の子がうんと苦労することになるのよ。頑張りなさいね」
典子の来訪の理由は、きっと、敦子の学校生活について、話をするためだったのだろう。しかし、中年女の話は、どんどん娘の「敦子」の事から弓なりに逸れていった。
典子は、話の先を戻すことなく、相槌を打っていた。
そうですね。はい。ご心配、ありがとうございます。流石です。至言ですね。すごい。センスが良いですね。
耐えず笑みを浮かべて、相槌を打っていた。女は、頬を紅潮させ、どんどん饒舌になった。
「私なんて、何ほどでもないのよ。先生みたいに良い大学も出ていないし。でもやっぱり、人あしらいはうまい方かしら。いろいろ苦労してきたし、それくらいわね。先生も早く結婚しなくちゃ。結婚無しで、人生は語れないわよ」
喋る、喋る。睦は、典子が怒らない事には持たなかった。それより先に、女の話に厭きた。中年女はずっと、いかに美貌の維持と教育に心を砕いているか語っていた。
それは、家庭円満と未来を担う子どもの為に、尊敬されるべき行動の数々である。うんぬん。典子が、女の話を聞くのは必ず将来の為になる、正しい選択である。典子は正しい。典子の態度は素晴らしい。典子を説教できる私はもっと素晴らしい。かんぬん。そんな感じだった。
俺は何しにここへ来た。
それより紀子は何しにここへ来た?
「ちょっと、お手洗いに行ってくるわね」
中年女が、席を外した。
飲むのを躊躇っていたが、洒脱なカップに注がれた紅茶を、啜る。渋い。それが美味しいのか美味しくないのか、判断が付かない。女が席を外している間、ふと、隣に座る典子の顔を見て、睦はギョッとした。なんの感情もない。苔むした阿羅漢の像のようだった。
「せ、先生」
小声で問いかける。
「俺、帰った方が良いかな」
「あ?」
やっぱり怒っている。
腸に怒りを湛えている。
「だって、何もすることないし、あの人、俺の事嫌ってるみたいだし」
「アンタ、ここに茶飲みに来たの?」
怒りの矛先が、自分に向いていることを悟りすくむ。どうして俺が怒られるんだ。
「じゃあ、どうすれば良いんだよ」
「そうね。あの人に気に入られるよう振る舞いなさい。とりあえず褒めて」
なぜ。そう思ったが、憮然とした表情の典子に逆らえない。とりあえず従う。
「わ、わかったよ‥‥。ともかく褒めれば良いんだね。」
「待ちなさい。頓珍漢な事言わないか不安だわ。まず、この間来たときと、カーテンと絨毯が違うわ。グスタビアンスタイルの雑誌でも見たんじゃないかしら。そこを褒めて」
「ぐ、ぐす?なんて?」
「ことばは覚えなくて良いわ、別に。むしろ、『雑誌で見ました。何というんですか?』ぐらいの方が、あの人は喜んで話すわ。」
典子は、あの中年女を見下しているのではないか。睦は、ふと思った。
では、彼女はどちらなんだろう。嘘吐きか「自分を守れない」人間か。
典子は続けた。
「あとは、ひたすら相槌をうちなさい。相槌の語彙はどれくらいあるの?」
「ゴイってなに?」
典子は、こめかみを押さえた。
「じゃあ、相手の鼻あたりを見て、頷いていなさい。相手の話を全部聞かなくても良いわ。いくつか耳慣れない単語だけを拾って、『それは何ですか?』って聞くの。そうしたら話は途切れないわ」
「分かったけど、そんな事して、何になるの?」
「アレに好かれるためよ」
アレって。中年女のことか。
睦は、典子の意図するところ分からないまま、ただ、言うとおりにした。確かに、典子の言うとおりになった。睦が、真剣に話を聞いている(フリをしている)と、中年女の態度は、次第に柔らかくなっていった。
「今時の子とは違う」とか、「感心だ」と言って、しきりに、茶と茶菓子を勧めた。
睦はいい気分になれない。気味が悪かった。典子の言うとおり、彼女の口にする単語をいくつか覚えるだけで、話そのものは聞き流していた。睦は、ファッションにも、インテリアにも、家庭円満の秘訣にも、興味がない。彼女の娘の、「敦子」の事ですら、それらしい名前の生徒が、クラスメートにいたような気がするが、記憶がおぼろである。
中年女は、青いライラックの模様が描かれたティーポットとともに、キッチンへ立った。睦は、冗漫な話を聞く(フリをする)のに、うんざりしていた。小声で典子に話しかけた。
「先生、俺もトイレ行きたいんだけど」
「そう」
典子は、おざなりに返事をしただけだった。たまらず、今度は中年女に尿意を告げようとした。その前に典子は、睦の聞いたことのない 柔らかな声で、言った。
「あの、睦君がお手洗いを貸して欲しいそうです。ずいぶん緊張したみたい」
「あらあら、ちゃんと返してね」
中年女の返事。返してね?冗談か。全然面白くない。睦は、憮然として立ち上がった。
「待ちなさい」
アルトな声。どうやら典子には二つ喉があるらしい。睦は思った。
「廊下へ出るついでに、二階に、敦子がいるか確かめて」
「人んち勝手にウロウロするのなんか、嫌だよ」
「アンタはウロウロしなくても、できるでしょう」
そうか。典子は、睦に、彼特有の「感覚器官」を使えと言っているのだ。
はあ、もう嫌だ。意味も分からず、典子に顎で使われるのなんか。中年女のご託なんか、くそ喰らえだ。睦はリビングを出て、そのまま帰ってやろうと思った。
‥‥帰る前に、もう一度だけ、従ってやるか?
ひょっとして、典子は睦を、便利な子分、ないし道具を見つけたとでも思っているんじゃないか?だとしたら、典子なんて怖がるのもばからしい。ただの嫌な奴じゃないか。
廊下に出て上を見上げる。ゆっくり息を吐く。返ってくる波動を感じるため、神経を集中させる。
廊下の北側に、八畳ほどの部屋。そこに、人らしいシルエットを感じた。典子にその事を伝えるべきか、そのまま帰るという、自分の反抗心に従うべきか悩む。反抗心はもちろん、明日も、明後日も、試験だ。睦は、勉強熱心ではないが、日が傾いてきて、ようやく自分が全く勉強していない事に、不安になった。
そのうち、二階のシルエットがスッと動き、廊下の端にある階段へ向かっていることを感じとり、睦は、焦った。
ヤバイ、見付かる。いや、すぐに考えを改める。ヤバくない。ちゃんと、女主人が睦の訪問を了承しているのだから、敦子、他のどんな家人に見付かろうと、ヤバくない。睦は、廊下に立ち尽くした。
敦子ってどんな奴だっけ。見たら思い出すだろうか。
コの字型の階段を降りてくる誰か。まず、細い足先から睦の視界に入ってきて、上へ上へと全身像が露になっていった。睦は息を呑んだ。
これは並々ならぬ美少女。目尻から真っ直ぐに通り上品につんととがった鼻。その下に珊瑚色の小振りな唇。ドングリのように愛らしく円らな瞳。こんな子、クラスにいただろうか。睦がことばを発せずにいると、敦子から「いらっしゃい」と話しかけてきた。
「あ、どうも」
敦子は、リビングとトイレの間、廊下の真ん中に佇む睦の脇をすり抜けて、外に出ようとした。5月の穏やかな空気が、開けた戸の隙間から入り込んだ。
「具合悪いんじゃないの?」
典子と中年女の話を思い出し、聞いた。
「普通」
敦子が出て行くのを眺めていた。パタンと音がして、静寂。女が夢中で喋り続ける声が、廊下に漏れていた。間もなく再びドアが開き敦子の顔が半分だけ現れた。
「一緒に行く?」
「あ、うん」
咄嗟に返事をしてから、なぜ、「あ、うん」なんだ、と思い返した。そして次に、どこへ行くんだ、という疑問が浮かんだ。しかし、それを口には出さない。可愛い女の子。睦はドキドキしながら付いて行った。
睦は、敦子の豊かな黒髪を眺めながら、歩いた。まだ日は高かった。静かな住宅街、睦と敦子以外、人通りは疎らだった。
一緒に行く事にしたものの、睦は敦子をよく知らない。学校を休みがちの女子が教室にいた気がする。それが敦子か?敦子が、なんのために睦に声をかけたか、わからない。人懐こい性格ではないようだ。むしろ、無口で表情に乏しい。典子のように刺々しいわけではないが整った容姿が睦に深窓の令嬢といった印象を与えた。尻込みしてしまう。
敦子の向かった先は、なんの事はない、公園だった。広いグラウンドの中央には、砂場。公園ぐるりには杉や松、銀杏の木が植えられている。木々を囲うように巡らされた煉瓦の内側には、ジャングルジムや、ホッピング、滑り台といった遊具がある。この歳で公園か。敦子の美しさに魅せられていた睦は、にわかに冷静になった。
「俺、戻った方が良いかな。今日は先生と一緒に、お見舞いに来ただけなんだ」と言った。
「さあ、ママは、たぶん睦君がいなくても気にしないと思う」
「そ、そう」
敦子は、母親とは逆に、ことばが少ない。しかし、相手の返事を気にせず、待ちもしないという点では同じだった。敦子は、鉄棒を逆手に持ち、グラウンドを蹴る。逆上がりをしようとしているらしい。睦は、ワンピースで逆上がりをすると、下着が丸見えになるのでは、と一人赤面した。しかし、すぐにそれが杞憂であることに気づく。
袖から続く、細い腕。腕と変わらない太さの華奢な足。どこにも筋肉が無さそう。どれだけ繰り返しても、地を蹴る両足は弱々しく、せいぜい鉄棒の丈程度で勢いを止めた。肘も伸び切っている。
成功する見込みがないから、重力が反転してスカートがめくれる事もない。大丈夫だ。睦は少しがっかりもしている。
敦子は、読んで字のごとく無駄な足掻きを止め、睦に
「どうすればできる?」と聞いた。
「ずっと練習してるのに、できない」
ずっとって、いつからだろう。
「勢い付ければ良いんだけど。口で教えるのは難しいよ」
「じゃあ、やってみて」
敦子に促されて、鉄棒に向かう。睦自身、小学生以来だが昔とった杵柄。肘に力を入れて、グッと地を蹴ると、体は地と平行の鉄棒を軸に、すんなりと回転した。
「わーすごい!」
敦子の顔が、一気に紅潮した。その顔の可愛らしいこと。睦の本能は、再び一瞬で彼女に惹き付けられ、気が付くと呟いていた。独り言のように。
「あの、俺と付き合ってくれる?」
「え?」
敦子は目を丸くした。睦は恥ずかしくなって、しどろもどろになった。まごついているうちに敦子は
「嫌」
恬淡と拒否した。告白を退けられたことは当然だった。睦は、敦子と入学以来今初めてことばを交わしているのである。何てことを言ったんだ、俺は。恥ずかしい。ショックだ。
しかし、続く敦子の
「痛いのが嫌いだから」
という返事に、違和感を持ち、
「俺、痛い事なんかしないけど‥‥」と、小声で反駁した。
痛いのが嫌、とはどういうことだろう?体が?心が?どちらにせよ、それは、付き合った果てに二人がうまくいかなくなった時の事じゃないだろうか。
敦子は続けた。
「男の子は汚いし」
敦子のことばに、さらに傷付いた睦だったが、聞き覚えがある。
「それ、君のお母さんが言ってたこと?」
「うん」
敦子は頷いた。
「お、俺はちゃんと、風呂に入ってるけど‥‥」
度々入浴をサボる事は、伏せておく。
「ふうん…じゃあ睦君は普通の『男の子』じゃないんだね」
睦は驚いた。寸暇の考えの後気付いた。「男の子は汚い」という母親のことばは絶対で、例外がない。睦は違う、というのなら、それは、母親のことばに誤謬があるわけではない。睦の方が、母親のことばの「定義外」のものとなるのか。反抗期である睦は、親に限らず、教師にも無闇に反抗してみせる。敦子の並外れた素直さに、睦は混乱した。ふざけているのか。真剣なのか。そんな睦の胸中を更に引っ掻き回すように敦子は続けた。
「じゃあね、私のお願い聞いてくれたら、彼女になってあげるね」
どういうことだ。睦は、敦子独特の思考回路に、付いていけない。しかし、敦子は自分の返答が優れたものだと思ったらしく、満腔の笑みを浮かべていた。
「お願いってなに?」
「それはまだ秘密。睦君と仲良くなれたら、教えてあげる」
敦子は、嬉しそうにスキップをして、再び鉄棒を握った。逆上がりは、全くできそうになかったが、敦子は地に足が付く度に、はしゃいだ。マイペースな敦子に、睦は戸惑っていたが、敦子が喜んでいるだけで至福を感じる。初めての感覚だった。
公園へ来て数十分ほど経った。敦子が、帰ると言うので、睦もその後を付いていった。黙って抜け出したことが、典子の逆鱗に触れるのではないかと、怖くなった。敦子の遊び相手になっていたと、誤魔化そう。そうしよう。
敦子の家に戻ると、敦子の母と、典子は、玄関先に立っていた。
「ああ、睦君。どこへ行ったのかと思ったわ」
柔らかい声。笑顔。しかし、目が笑っていない。
「ええと」
にわかに、敦子の母の罵声が飛んできた。睦と敦子が一緒にいるのを見て、敦子の母は、血相を変えた。
「ちょっと、アンタ!敦子に何したの?!」
「アンタ」というのが、自分の事と気付かず、睦は呆けた。突然の怒りに、付いていけなかった。
「なんで敦子を連れ出したの?まさか、いやらしいことをしたんじゃないでしょうね?」
いやらしい?俺がこの短時間で敦子に何をするって言うんだ。しかし、敦子の母親は激して、反論する間もない。
敦子の母はどんどん赤黒くなって叫んでいた。睦に掴みかからんばかりに詰め寄ってくる。
「これだから、男の子は嫌なのよ!アンタ、どうなるか、分かってるでしょうね?!」
「落ち着いてください」
典子は、腰を低くしながらも、しかし睦と敦子の母の間に入った。敦子の母の手が、睦に届かないように、睦を後ろに下がらせた。
「どいてよ!典子さん。アンタの責任でもあるのよ?!こんな○○を家に連れてきた」
敦子の母は、典子の肘を掴んだ。爪を立てた。典子の皮膚が破れ、血が滲んだ。睦は、それに気付き動揺した。
敦子の母の爪先が、典子の血で染まっていった。しかし当の典子は顔色を変えなかった。
「落ち着いてください。」
ほどなくして、敦子が言った。
「睦君は友だちだよ。何もされてないよ」と言った。
敦子は豹変した母に全く動じていなかった。これは、普通だろうか。激しやすい性格というのだろうが、常軌を逸している。睦は、背筋に冷たいものを感じた。
敦子の一言で、少し落ち着いたらしかった。しかし、睦への怒りと警戒の、全てが解かれたわけではない。
「そんな事、分からないわよ。敦子も、簡単に、男の子を信用したらダメよ」
「はい」
敦子の首肯には、なんの情感もない。敦子は母のことばに、絶対服従以外ないようだ。
敦子の母は、典子の腕を話した。ぶつぶつと文句を言いながら、敦子の連れて、家へ戻った。戸の閉まる、荒々しい音が響く。
典子は、鞄からハンカチを出して、二の腕を押さえた。睦は、身構えた。睦の無遠慮な素行に対して、今度は、典子から罵声が飛んでくるもの、と思っていた。
「せ、先生。ごめんなさい」
「謝る必要はないわよ」
典子が、歩き始めたので、睦もそれに付いていった。
「アンタ、よくやったわ」
典子は、そう言った。皮肉かと思い、典子を見上げた。そこには、いつものような、仏頂面が張り付いている。
「いいの?敦子の母親は、相当怒ってたけど」
「謝れば済むことよ」
事も無げに応える。そうだろうか。睦とて、それほど悪いことをしたと思ってはいないが、敦子の母の激し方は、尋常じゃなかった。収まるのも早い、ということだろうか。
「腕は大丈夫?」
「平気よ」
典子は、左腕を、格子柄のハンカチで押さえていた。
「ごめんなさい」
「謝らなくていいの。正直、見直したわ。敦子が、アンタの事を友だちだと言うから、驚いた」
たしかに敦子は、睦の事を友だちと言ったが、方便だ。
「‥‥あのさ、俺、あの子に告白したんだ」
「は?アナタ、敦子と親しかったの?」
「いや‥‥全然知らなかった」
「じゃあ、なんで告白なんてできるのよ?」
「顔が可愛かったから」
典子は睦を見た。軽蔑の表情。
「顔?それだけ?」
「だって、まともに話したことないのに、顔以外のどこを好きになるっていうんだよ。つい、だよ。ほんのはずみ」
睦は、どんどん顔が熱くなっていくのを感じた。自分が、恥ずかしい真似をしたことくらい分かっている。黙っておけば良かった。まるで懺悔のように、何もかも喋る自分が嫌いだ。
「ああ、そう。それで」
「断られた」
「そうでしょうね」
「たぶん敦子は、母親に友だちって言って誤魔化してくれたんだ」
典子は言った。
「違うでしょうね。そういう方便は効かない子なのよ。アンタを本当に友だちと思うようになったの」
「たかだか十分で?幼児じゃあるまいし。それになんで、先生がそんな事分かるのさ」
「分かるわよ。周りに合わせることができなくて、学校にも、あまり来ないし、友だちもいないわ。このままだと、進学が難しくなるのよ」
「ふうん」
「私、本当はアナタと敦子が友だちになれば、敦子は、学校に来やすくなると思ったのよ」
典子は、生徒の気持ちに疎いと思っていた。睦は、彼女の思惑を意外に感じた。
「どうして俺なのさ。女友だちの方が良いだろ。とりわけ母親があんな奴なら」
「アンタと敦子なら、合うと思ったのよ」
「え?」
「似ているし」
「どこが」
「どことなくよ」
「なんだよ、それ」
「敦子と仲良くしてね」
「無理だよ。母親に嫌われただろ」
「大丈夫よ。逆鱗に触れなければ、彼女はとても扱いやすいのよ」
「敦子は可愛いし嫌な感じはしないけど、俺は、あの母親嫌いだよ。興味のない話を聞くの、疲れるし」
「へえ、嫌いなの」
「あんなおばさん好きな奴、いる?先生だって本当は嫌いでしょ。ずっと愛想笑いしてた」
「どうかしら」
睦は気を悪くする。なぜ、返事を曖昧にするのだろう。
「嘘は、ダメなんだろ」
「そうよ。アナタ、半日嘘で無駄にしたのよ。そしてアナタは、敦子と仲良くしようとすればするほど、あの母親を怒らせないようずっと嘘を続けなくちゃいけないの。」
「なんの話だよ」
どうして返すことばで、すぐ俺を責める。
「アナタは、トシユキに憧れてるでしょ。彼のようになっても何にもならないのに。自分を実態よりも大きく見せるために、『絶対バレない』とか『俺はすごい』とか、自分を騙しながら嘘を重ねるの。嘘の量は増え、そのうち矛盾が生じ、バレる不安はどんどん大きくなっていくわ。そして、緊張がふつ切れたある日が、自滅の日よ」
「な、なんだよ‥‥先生だって、結局、あの母親に、嘘の態度を貫いてるじゃないか?いずれ自滅する日が来るんじゃないの」
言ってやったぜ。しかし、すぐに後悔する。典子を見ると、彼女の腕の傷まで、視界に入る。典子はなぜ睦を庇ったのだろうか。教師とはそういうものなんだろうか。
「そうね、自滅するかもしれないわ」
一瞬、典子の眉が苦しそうに歪んだ気がした。左腕の爪痕は、血こそとっくに乾いていたが生々しい。
「じゃあなんで、わざわざ敦子の家に行くんだよ。学校の報告なんて、郵便とかメールとか、いろいろあるだろ」
睦の声は弱々しい。こんな会話はもう止めたい。典子の話は、少しずつ睦の体を蝕み、心を重くするようだ。
「敦子の顔が見たいのよ」
「嘘だろ」
「本当よ」
本当だろうか。学校で、典子は常に生徒に対して、常に見下したような態度を取る、典子。それがとりわけ不器用そうな敦子を気にかける。どういうことだろうか。
「今日はこれでおしまい。家に帰りなさい」
「なにが?」
「隠し事をする方法。余計な事を言わずに、ただ相手をしゃべらせる。それで大抵の事は隠せる。そういうやり方」
「‥‥」
「じゃあね。明日がんばりなさいね。テスト」
納得がいかない。それこそ、わざわざ睦を敦子の家に連れていかなくとも、いまの一言で済むのではなかっただろうか。典子にもっと反抗したいが、そんな時間はない。典子の背後に、今まさに西へと沈もうとしている太陽。橙色と紫色が、交じり合って燃えていた。現実に引き戻される。
睦は悔しくて泣き出しそうになった。逆光でよく見えなかったが、典子が、笑ったように感じた。優しい笑みではない、皮肉的な微笑み。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
