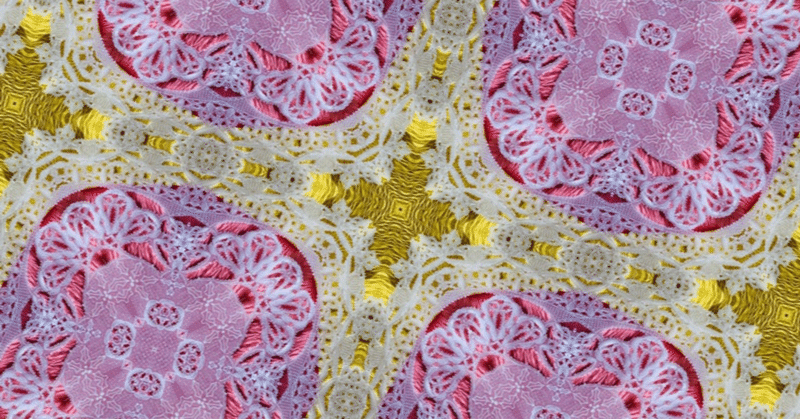
隣のネズミ-1
(全7回短編小説、隣人に悩まされる女性の話 背景として現在の社会状況が一部反映されています)
私の物語を、何もこんな冴えないところから始めなくても良いのではないか、とも思う。私と夫、それから発達障害の息子と三人の慎ましやかな生活。
夫や小学生の息子の関心は、必ずしも家庭には向いていない。夫はそこそこ優しいが、やはり仕事が第一で、息子も不器用ながら学校生活を楽しんでいる。
つまるところ、私・水島翠(みずしま みどり)の今の生活を一言で表せば、サポートなのだ。仕事においても家事育児においても、華々しいところのない地味な作業の連続。今一番の楽しみといえば、通勤時間に、インスタグラムでお気に入り登録をしているインフルエンサーのコーディネートを真似したり、Twitterで回ってくる犬猫や赤ちゃんの面白い投稿を見ることくらいだ。
「文筆家じゃない人間が書くストーリーには、テーマがいるのよ」
私は夫に言った。青春時代に煌やいた経験といえば、中学の時、競技かるたの校内大会で一位を取ったぐらいのものだ。高校では生徒会の書記を務めていたが、文化祭や運動会の段取り・準備は、細々とした雑用で、はっきりいってサポートに徹する今とそう変わらない。大学生活は、卒業するための単位と就職するための資格を取り、若気の至りとも言えるような恋をしているようでしていないような、泡沫にたゆたううちに、いつの間にか終わっていた。
夫に言ってから気付いた。そもそも私の人生に、そう「冴えた」ところは無かった、と。
特に悲しくはならなかった。安定した生活は自分が望んだことだったし、普通の生活だって、手に入れ維持管理するにはそれなりの努力がいるのだ。私は、自分を凡庸だと理解していたけれど、卑下はしていなかった。
「でも、素人が書く人生とか苦悩とか、そんな漠然としたテーマの、純文学まがいのものを、あなたは読みたいと思う?」
あなた、こと太郎(たろう)さんは言った。この人の、この凡庸の代名詞みたいな名前から織りなされる人生の方が、角河文庫なぞの名のしれた出版社から発刊されていたら、まだ触肢が伸びようかというものだ。「太郎の人生」うん、そうでもないか。
「難しく考えなくても、今の君のもやもやを外に出して気持ちで、物語にすれば良いんだよ。どれだけ自分を悩ませることでも、ストーリーに仕立ててしまうと、まるで本当に他人の事のように感じられてくることがよくあるから」
「そんなこと言って、愚痴を聞くのが面倒になっただけじゃないの」と、言い返したいのをぐっとこらえた。旦那に八つ当たりしても、仕方がない。
それに、と、私は考えた。旦那の言う事にも一理あるかも知れない。他人にどれだけ文句を言っても、自分が思うようには変わらないから、結局、自分のモノの見方を改めるしかない。他ならぬ旦那がそれを教えたというのは、皮肉なことだけど。
そして思いは堂々巡りしている。旦那は銀行勤めで、私たち家族は配置替えのたびに引越をしている。と言っても、息子が生まれてからは、これが初めての引越だけど、問題なのは、このマンションは、旦那の勤め先が社宅として買い上げている部屋の他、リタイアした後は他人に文句を言う事を生きがいしている高齢者が何人か住んでいる、ということ。さらに問題なのは、老人というほどの年齢ではないけれど、そういうタイプの中年が隣人であるということ。
彼女は名前を坂田那智子(さかたなちこ)と言って、一年ほど前に引っ越して来た部屋の、いわゆるお隣さんだった。最近では隣人とすら没交流のマンション住人は増えていると聞くけれど、昨今の天災激甚化により、共助の果たす役割も大きい・・・と、管理会社から簡単な防災の講習を受けた私は、その気になって隣近所へ挨拶に回った。
それは春から初夏に移るころ、息子の進級準備への忙しさも相まって、性に合わず私はハイになっていた。
初めから、坂田さんは感じの悪い人だった・・・と苦々しく振り返ろうとして、気付いた。最初から?いや、第一印象はどうだったかな。むしろ良かったんじゃないかしら。
両の隣人のうち、引っ越して早々に挨拶に行ったとき、坂田さんは留守だった。それから真上と真下。計四件の部屋を回ったのだが、引っ越して一週間もしなうちに「挨拶に来られなかったので」という嫌味な手紙をわざわざ書いてよこしたはす向かいに住む老人がいたので、早くも私の気分は萎えていた。
坂田さんとは、デイサービスへ息子を迎えに行った、帰りのエレベーターの中で初めて出会った。上の階へ昇る間、私は彼女の後姿をぼんやりと眺めていた。視界の端に残っていた彼女の横顔と、後ろ姿から察するに、私より一回り年上のようだ。黒地に明るい緑のラインの入ったパーカーにロングスカート。帯の太い腕時計と、デニム生地をリメイクしたようなバッグに、たくさん缶バッジを付けているのが印象的だった。
同じ階で降り、隣同士の部屋に入ろうとする折、私はようやく、彼女がお隣の坂田さんだということに気付き、彼女は私がお隣に越してきた水島だという事に気付いた。
お互い、あら、とか、まあ、とか言いつつ近づきながら、挨拶をした。挨拶用の菓子折りがひとつ残っているのを思い出し、「すぐ持ってきますから」と言うと、「気にしないで」と笑った坂田さんは、闊達な性格に見えた。初めは。
けれど、自閉傾向の強い息子の頭の中には、帰宅して手を洗い、オヤツを食べるという計画が、私の予期せぬ「隣人とのおしゃべり」に阻害されたことへの不満が既に生じていて、グイグイと腕を引っ張った。
「あーら、かわいい。ぼく、いくつ?」
息子は、自分のことを「ぼく」と言われるのも好きではなかった。彼は坂田さんを無視して、私のカバンから鍵をひったくり家に入ってしまった。
ごめんなさい、と言うことには慣れていた。卑屈になっているわけではない。母親になってから、息子くらいの年頃の子が無礼を働くのは、全部親の責任だと本気で信じているような人たちにたくさん会って来たから。けれど、周りのサポートや理解が無ければ、到底息子を育てては来れなかったという経験もある。相反する感情を処理するために、息子が自分の特性を理解してなんにでも対処できるよう成長するまでは、親である自分がこじれて面倒になる前に謝ってしまうのがいちばん楽だという姿勢になってしまっている。
坂田さんの顔が、一瞬険しくなったような気がした。そういう反応にも慣れていた。
「では、失礼します」
笑顔のまま、家に戻ろうとすると、坂田さんは
「え、あの。叱らないの・・・?」と言った。
「あーそうですね。注意しておきます。すみません」
「そう、良かった」
ニッコリと笑う坂田さんに、底意を感じた私は
「あの、坂田さんは、お子さんは?」と尋ねた。
今度は、ハッキリと眉間に皺を寄せた。
「・・・いないけど、どうして?」
「え。あ、そうなんですか」
初対面ながら他人の子どもへ注意することを促すくらい教育熱心なのだから、私は「自分の子どもには疎まれているのだろう」という意地悪心が生じた。だから、彼女は、それを悟られぬよう大げさにでも「今何歳の、可愛い子どもがいるのよ」と返事をし、それきりお互いの子どもについて深堀りすることなく、挨拶は終わるだろう、と・・・それが私の打算だった。
挨拶は微妙な空気で終わってしまったが、その時はまだ、坂田さんへの印象は、到底悪いというものではなかった。むしろ、悪いことを聞いてしまったのだろうか、と、軽挙への自責が勝っていた。
お詫び、というわけではないが、すぐに用意していた菓子折りを持ってインターホンを押すと、坂田さんは笑顔で応えてくれた。サッパリした人なのだと思った。
当初は、なぜ自分の回顧録を書くのに、わざわざ嫌な奴のモヤモヤする事を思い出さねばならないのか、と、腹が立っていた。しかし不思議な事に、書いていくうちに、そのイライラやモヤモヤは、いくばくかすうっと薄れた。腹が立っていては、文章がまとまらないからだ。もちろん、消えたわけではないが、今では「うざい」としか思わない坂田さんが、自分の中で、初めはそうではなかった、という気付きは新鮮だった。もちろん「嫌いになる予兆」みたいなものは、当初からあったわけだが。
もう少し、「坂田さん回顧」を続けてみることにした。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
