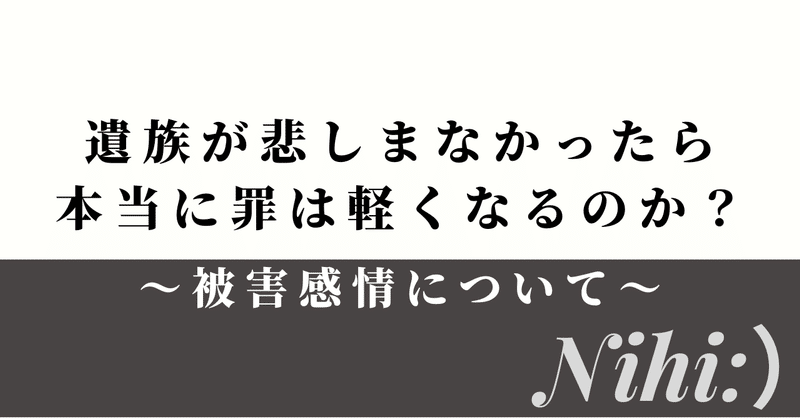
遺族が悲しまなかったら本当に罪は軽くなる?~遺族の被害感情について~
きっかけ(永山事件)
ふと永山事件について調べていた。
永山事件(永山則夫連続射殺事件)
…当時19歳の少年であった永山則夫が米軍基地で窃盗した拳銃を用い、警備官やタクシー運転手など計4名を射殺した事件。(犯行から逮捕まで1968~1969年)
犯人の永山則夫の生い立ちから犯行に至るまでの経緯が、思っていたより悲惨で非常に壮絶な事件であったと知った。
この事件の詳細だけでもテーマとして取り上げるに値するに充分なものなのだが、今回は永山事件ではなく、死刑制度に関連するテーマである。
というのも、この永山事件というのはその後の死刑制度について大きな影響を与え、また議論されつづけ、そのきっかけとなる事件なのだ。
その理由の一つとして、永山事件はこの事件の判決が決定するにあたり、死刑になるかどうかの基準が初めて明示された判例だったという。
この基準を「永山基準」と呼ぶ。
現在ではその基準の是非については議論されており、そもそもの死刑制度の是非にまでも繋がっていくため決着のついていない話だという。
実際に永山事件でも時間経過とともに様々な要素が絡み、第一審から「 死刑 → 無期懲役 → 死刑 」と2度も判決が覆されている。
ともかく私は永山基準で死刑がどのような項目で決定されているのかが気になった。
「永山基準」
1.犯罪の性質
2.犯行の動機
3.犯行態様(特に殺害方法の執拗性、残虐性、(計画性))
4.結果の重大性(特に殺害された被害者の数)
5.遺族の被害感情
6.社会的影響
7.犯人の年齢
8.前科
9.犯行後の情状
以上の基準を見て、一つの項目に違和感を感じた。
「遺族の被害感情」
・・・?
年齢や同期、犯行の残虐性など、死刑を決定づける要因として納得できるが、この中に遺族の感情が影響して良いのだろうか…?
例えば「息子の未来が奪われてとても悲しい。」とか「母親が亡くなってからなにもかもが手に付かなくなりました。」などと言ったら罪は重くなるのか?
逆に遺族が何も言わなかったら、罪は軽くなるのか?
被害感情とは(被害感情・処罰感情)
この件を明らかにするために被害感情という言葉の定義をするべきだろう。被害者の感情は2種類に大別されるようだ。
「被害感情」
…被害者が失ったモノ・ヒトに対して物理的回復(物の欠損や身体的損傷など)、精神的回復(精神的苦痛、喪失感など)を望む感情。
「処罰感情」
…被告人に対して処罰を望む感情。被告人を宥恕して(許して)いる場合、処罰感情は小さいといえる。
本題「被害感情で罪の重さは変わるか?」
※参照した文献が被害感情ではなく処罰感情に注目していたため留意。
一般人・裁判官に対して実際にとられたアンケートの結果では、遺族が宥恕している場合より厳罰を希望している場合の方が処罰は重くなった。ある事案を用いて実際に量刑を問うと、遺族が宥恕している場合より厳罰を求めたときの方が量刑が平均0.95年多くなった。(意見陳述制度、被害者参加制度における場合)
結果:被害感情によって罪の重さは変わるといえる。
これでいうと一旦量刑を求めてから被害感情を考慮してもらうようにして、遺族が「宥恕」か「厳罰」かで量刑がどう変わるかを比較してほしかったが、、、。
ただ、被害感情を検討材料とし認めた場合、その大きさによって裁判官はその事件の重大性として結び付ける傾向があるようだ。
とはいえ、被害者の求刑が実際に影響している判例は少ないらしい(平成21~23年)。

様々な判例を見ていると、以下の傾向がありそうだ。
残虐性、計画性などの犯行様態が判明しており、極めて残虐である場合では被害者の被害感情・処罰感情は処罰に影響しない。
反して、犯人の同期や犯行様態が不鮮明でその事件の違反性を判断するに十分でない場合は、被害感情・処罰感情は処罰に影響してくる。
議論:被害感情を考慮するべきか?
これまでも当然様々な議論がされてきたが、被害感情を事件の重大性を決定づける要因、つまり事実として考慮すべきという主張、あくまで客観的事実として捉えるに留めるべきという主張があるらしい。
前者は刑事司法は公益のためだけでなく、被害者の利益でもあるべきと主張されている。
たとえば家族が一人殺されたとして、その一人の命が奪われたという事実は遺族との関係や思い入れによって増減するのはおかしいと思ったのだが、物に例えると分かりやすかった。
あなたの普段使っているボールペンが盗まれ粉々にされた場合と、祖父の形見であるボールペンが盗まれ粉々にされた場合。
さて、あなたにとってこの罪の重さは同じだろうか。
犯人からすると全く同じ価値でしかないボールペンであるが、一方被害者からするとその辺の私物と形見とでは、その意味が大きく変わってくる。
個人差に関わらず、モノ・ヒトに対して普遍的な評価がある以上、それを認め考慮せざるを得ないだろう。
ただ、反対派の主張としては、被害感情・処罰感情は操作性があると同時に二極化されがちでありその大小は基準としてふさわしくないとの考え。
また、被害感情はともかく処罰感情は考慮すべきでないという考えもあり、重視されるべきは失われた金銭的補償や身体精神的な立ち直り、つまり被害感情の回復であり、応報感情である処罰感情を考慮することは被害者の真意に沿うことにはなり得ないという。
被害感情は重視されすぎるとその事件の違反性を誤って判断しかねないが、かといって無視されてしまうとかえって本質を欠いてしまう。
主観的事実としてではなく客観的事実として、あくまで検討材料として用いられるとが適当と思う。
まとめ
不十分な調査ではあるが、以上の結果となった。
筆者は相変わらず「被害感情・処罰感情」について疑問は感じているが、場合によって少なくとも考慮されるべき要因であるということも理解できたし、これが議論され続けているのも納得だ。
調べていくと、現在の死刑制度は殺した人数でほとんど決まっているらしく、こういったおかしな側面などについて議論を波及させていく必要もありそうだ。
この議論が帰結する日は来るのだろうか。
いずれにしても、これまで考えてこなかった死刑制度の是非に関して少しでも関心を持てたことはよかったと思う。
また、この記事を書くきっかけとなった永山事件がとにかく見応えのある事件だった。本記事では詳細の記述は控えたが、犯人の永山則夫の生い立ちがとにかく不憫で、犯行前も日本中を逃げ回るような生活をしており、逮捕されたあとに獄中結婚をし、書籍をいくつも書いて日本文学賞を受賞するなど、非常に壮大で凄惨な人生を送った。永山は時間の経過や周囲の人間との関わりによって改心しはじめていた。そんな中、死刑→無期懲役→死刑という判決に翻弄されたのだ。
永山は「生きる希望の無かった人に生きる希望を与えて殺す。こういうやり方をするんですね。」という言葉を残している。
永山基準は永山のためにも、今後議論していく必要があると思う。
引用
昆 雄一(2014)「なぜ被害者・遺族が処罰感情を表明すると,量刑が重くなりうるのか」中央ロー・ジャーナル第 11 巻第 2 号(2014)
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/record/6780/files/1349_6239_11~2~53.pdf
横田 信之(2013)「犯罪被害者と量刑」p419.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcl/52/3/52_409/_pdf
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
