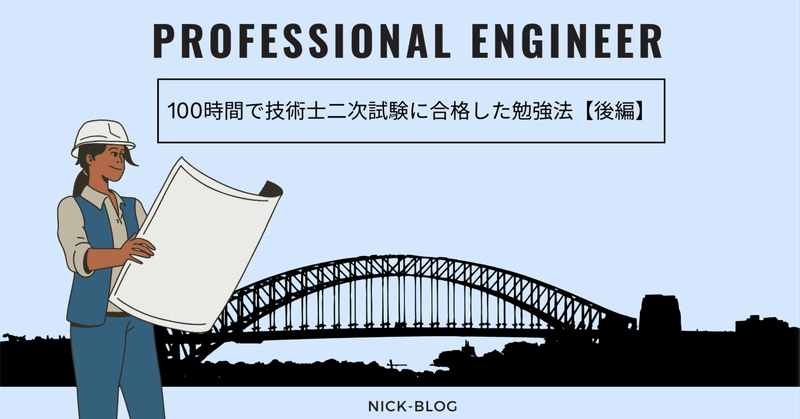
100時間で技術士二次試験に合格した勉強法 【後半】
『効率的に勉強し、出来るだけ短い期間で技術士二次試験に合格したい』
本記事は、そんな技術士試験の受験者に向けた記事です。
(更新記録)
R6.2.11 SNS利用に関する記述について補足しました。
R6.2.16 骨子作成における問題・課題・対策の関係について追記しました。
別記事(100時間で技術士二次試験に合格した勉強法【前半】)では技術士試験の勉強を始める前に知っておくべき事項として、試験の特徴、想定問題、情報の調べ方、などについて説明しました。
後半となる本記事では、より具体的な『答案の書き方のコツ』(論文作成のコツ)と『留意点』を紹介します。
(過去に、個人ブログで作成した複数の記事を統合、見直しをしました。)
本記事と前半の記事は、技術士二次試験を初めて受験するのであれば、勉強をスタートする前に最初に読んで頂きたい記事です。
センスの良い人なら、この記事を読んでいれば、独学でも1~2回の受験で合格すると思います。大学受験しかり、ペーパー試験は攻略法の様なものはあります。(私の部下たちは、これらの内容を含む2~3回の勉強会と個人演習で合格しています。)
さて、前半の記事でも記載しましたが、技術士二次試験(建設部門)の合格率は10%程度の狭き門となっています。
私の周りにも、優秀な技術者であるにも関わらず、受験にあたってのノウハウを知らないせいで何年も資格取得にチャレンジされる人も多いです。
そして、結果的に数百時間という膨大な時間を試験準備に投じなければならないケースもあります。

優秀な技術者でも、合格するのが難しい理由のひとつに、論文試験という特殊な試験であることが挙げられます。
過去の試験で不合格だった人も、論文試験に慣れていないために、本来の技術力を発揮できなかったという人も多いと思います。
そもそも、『どの様に学習を進めたらよいのか分からない』という人も多いのではないでしょうか。

本記事では、勉強会での指導や私の経験を踏まえた、技術士二次試験における『答案の書き方のコツ』や『留意点』を紹介します。
紹介する内容で指導してきた部下や同僚の多くは私と同じくらいの時間(100時間程度;4月からの準備)で合格しているので、そこそこの再現性はあるのではないか思います。
元々の技術的なベースがある人なら、ちょっとしたコツやNG事項を知るだけで論文のレベルを大幅に高めることも可能です。
【記事の対象】
本記事は、以下のような人を対象に想定しています。
技術士試験(建設部門)を初めての受験する人
(特に「河川砂防」「道路」「都市計画」「鉄道」「港湾航空」「建設環境」)の受験を考えている人)これまで独学中心で勉強をしてきた人
合格水準の論文を書くための基本事項を知らない人
効率的な勉強方法を再確認したい人
1.骨子作成とその構成

1.1 骨子の必要性
様々な指導サイト等でも書かれていることですが、いきなり答案を書き始めるのではなく、演習でも本番でも最初に骨子を作成しましょう
これは試験本番では手書きで論文を作成するため、一度書いた論文を書き直すことは、時間的に難しいためです。
そこで、骨子を作成→推敲→修正を繰り返し、大きな書き直しが不要な熟度の高い骨子を作成してから答案を書くのです。
骨子が作成できれば、答案作成はただの作業になるので、骨子の作成時間は1題につき、15分~20分を費やしても構いません。
答案を書く速さにもよりますが、私は本番でも試験時間が30分以上時間が余ったので、骨子作成にはこの位の時間をかけても全く問題ありません。
1.2 骨子の作り方

骨子とは『論文の目次・構成』のことです。
骨子の作成では、以下の基本型のとおり整理します。
(骨子の基本型)
①背景・現状・問題 :回答用紙×0.5枚程度
②課題(課題の深堀) :回答用紙×0.5~1.0枚程度
③対策(具体策、留意点):回答用紙×1.5~2.0枚程度
※ ①の問題は課題に置き換えても良いです。
問題・課題・対策(解決策)の関係は以下のとおりです。
問題:現状と目標とのギャップ
課題:問題を解決するための取組
対策:課題解決(取組を実施する)のための具体的な方法
※ 対策=解決策、対応策と記載されている場合がある
骨子は一度で完璧に仕上げることは難しいです。
骨子を作成したら、2~3度見直して、以下のような添削をして骨子を完成させます。
・順番の入れ替え
・不要箇所や重複箇所の削除
・設問に答えているかの確認
・追記等
1.3 骨子作成例

私が受験した2010年頃は設問が
「●●における××の施工についての課題と対策を述べよ」
のようなシンプルなものが多かったため、1.2に記した型を使っていました。
しかし、近年の技術士試験では必須科目、選択科目ともに設問を(1)~(3)のように細かく分けて論文の構成を誘導していることも多いです。
この様な場合は、設問にしたがって骨子を組むことで問題ありません。
誘導型の設問に対するの骨子の例として、私の合格時の再現答案を参考に解説していきます。

この設問に対する骨子と論文は以下のとおりです。
※ 受験時に手書きで作成した骨子を電子ファイルに書き起こしたものです。
ここから先は
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
