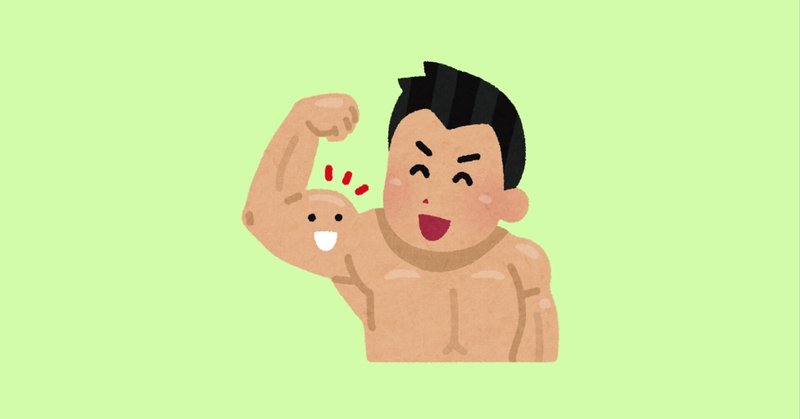
タンパク質の驚くべきパワー: 健康を支える不思議な栄養素 #食事編5
さあ、今回は「タンパク質」について話していきたいと思います。
タンパク質は単なる栄養素ではありません。これは私たちの体を構成し、エネルギーを生み出す不可欠な要素です。多くの人が肉や魚を思い浮かべるかもしれませんが、現代の食生活では炭水化物や脂質に偏りがちです。バランスの取れた食事の中で、タンパク質の適度な摂取がなぜ重要なのか、その理由と方法を詳しく見ていきましょう。
タンパク質の基本と重要性
タンパク質は炭水化物・脂質と共に体の土台となるエネルギーを作る3大要素の1つで、単に筋肉を構築するだけでなく、骨、皮膚、髪の成長や修復にも不可欠です。日々の活動に必要なエネルギーや持久力の源であり、私たちの代謝や免疫機能も調整します。タンパク質不足は成長障害、感染症のリスク増加、心機能低下など、多くの健康問題を引き起こす可能性があります。
1日のタンパク質の目標摂取量
ではいったいどの程度のタンパク質を摂取するのが良いのかというと、
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準2020年版」では、18歳以上の1日当たりのたんぱく質摂取の推奨量は、女性が50g、男性が65gとされています。

上のグラフを見る限り、たんぱく質の平均摂取量は推奨量を満たしていますが、この推奨量は、あくまでタンパク質の欠乏によって病気にならない最低限の目安と言えます。
日本人の食事摂取基準でも、良好な栄養状態を維持するのに十分な量を示す「目標量」は、例えば50〜64歳、デスクワークで身体活動量が普通の男性なら91〜130gとされていますから、上記の平均摂取量程度では足りないわけです。
ほとんどの年代ではタンパク質が不足している
目標量は性別、年齢、身体活動レベルによって異なり、デスクワークなどで身体活動レベルが普通(II)の1日のたんぱく質摂取目標量では
・男性
18〜29歳:86〜133g
30〜49歳:88〜135g
50〜64歳:91〜130g
・女性
18〜29歳:65〜100g
30〜49歳:67〜103g
50〜64歳:68〜98g
上記の平均摂取量と目標摂取量を比べてわかる通り、ほとんどの年代でタンパク質が不足していると言えそうです。
そのため人によっては体重や日々の運動量にもよりますが、少なくとも下記のタンパク質量を日々確保したいところです。
ケース1:身体をあまり動かさない方
・体重✖️0.9g
運動をしたり身体を動かす仕事の方
・体重✖️1.6g
高齢者(70歳以上)の方
・体重✖️1.1g
高齢者の方は筋肉量の維持と健康状態の向上のために、やや多めのタンパク質を摂ることが大事になってきます。
*腎臓病の人はたんぱく質の摂取量に制限があり、腎臓の数値が悪くなってきている人も注意が必要です。
加工肉と赤肉は体に良くない?
タンパク質といえば、肉や魚を想像する方も多いと思います。
豊富なタンパク質源であることから、元気がでる食材として肉を思いつかれる方も。
ところが、健康の面では肉は様々な問題点も指摘されています。
注意が必要なものとして、加工肉と赤肉、特に加工肉は要注意です。
まず、そもそも加工肉と赤肉がそれぞれ何を指しているかというと
加工肉
加工肉は肉を保存するために塩漬け、燻製、発酵、乾燥などの方法で加工したものです。例えば、ハム、ソーセージ、ベーコン、サラミ、肉の缶詰など
赤肉
赤肉は、牛、豚、羊、馬などの哺乳動物の肉を指します。これらの肉は生の状態で赤い色をしているため赤肉と呼ばれます。一般的に「脂身が少ない」ことを意味する赤身の肉とは異なります。対して鶏肉は「白い肉」とされ、赤肉とは区別されます。
これら加工肉と赤肉はWHO(世界保健機関)にあるIARCという機関が、加工肉は発がん性があり、赤肉はおそらく発がん性があると発表しています。
これを聞いて驚かれる方もいらっしゃるかと思いますが、ちなみにタバコやアルコール飲料、紫外線なども加工肉と同様の発がん性があるグループに分類されています。
加工肉に関しては、1日あたり50g摂取するごとに、大腸がんのリスクが18%増加すると推定されています。
赤肉に関しては、加工肉ほどの強いエビデンスは見出されなかったものの、1日あたり100g摂取するごとに大腸がんのリスクが17%増加すると推定されています。
大腸がん以外にも、赤肉と加工肉の摂取が多い人ほど、脳卒中や心筋梗塞、糖尿病などのリスクが高くなることが報告されてもいます。
同様の推定をした、もう一つのがんの国際的な研究機関WCRFは、
赤肉は多くても、料理後の重さで1週間に350〜500g以上は食べないこと、また加工肉は食べるとしたらほんの少しだけにとどめることを勧めています。
ではなぜ加工肉と赤肉が体に良くないのかというと、成分的要素と肉を多く食べる食生活の2つが考えられています。
成分的要素では、肉の加熱で発生する化合物や飽和脂肪酸、腸内環境の悪化など様々な仮説が考えられています。
一方で肉を多く食べる食生活では、甘いものや精製された穀物などをよく食べる傾向にあり、それらが悪影響を及ぼしているなどの仮説なども挙げられています。
ただし日本人は肉を多く含む食事をしているからといって、死亡率や病気のリスクが高いというわけでもなく、なかなか一筋縄ではいかない研究結果になっていたりもします。
とはいえ、日本でも近年肉の摂取がますます増えてきていることなどからも、日本人の食生活でも肉類を極端に多く食べるような食生活は大腸がんのリスクが高くなる可能性があると考えられます。
ちなみに日本では大腸がんは2018年時点で死亡数第1位、2019年時点で死亡数第2位のがんです。
これらのことを踏まえると、加工肉や赤肉をたくさん食べるのを控えることと(特に加工肉は)、食生活全体を改善していくことが大事なのだと思います。
どんなタンパク質を食べたら良いのか?
では加工肉や赤肉を減らしつつ、一体どんなものを食べてタンパク質を確保したら良いのでしょうか。
動物性と植物性タンパク質がそれぞれありますので、それらを意識して摂取するのが良いでしょう。
動物性タンパク質:鶏肉、魚、卵など
植物性タンパク質:大豆食品(豆腐、納豆、味噌など)、穀物(米、小麦、そばなど)、種子・ナッツ類(ゴマ、くるみ、アーモンドなど)
肉類であれば鶏肉が良し
加工肉や赤肉でない場合のお肉は鶏肉がおすすめです。
鶏肉を多く食べても疾患のリスクとの関係について強いエビデンスは出ていないので、お肉を食べたいけど健康のことを考える方は鶏肉がおすすめです。
魚は多くの病気に対してメリット多し
魚は多くの健康上のメリットがあると考えられています。
豊富な動物性タンパク質だけでなく、オメガ3脂肪酸のような良質な脂質なども含んでいます。
実際に魚の摂取量が多い人ほど、死亡率、心臓病や脳卒中のリスクが低いことが報告されています。
また魚を1日1品食べている人ほど、死亡率が10%ほど低くなるという報告もされるなど、健康上のメリットは高いと考えられます。
とはいえ、塩鮭やイクラの塩漬けなどの加工品は塩分の観点から健康への疑問視や、魚を食べている人の食生活自体がそもそも良い可能性もあると示唆されたりと、一概に魚を食べているだけで健康に良いかと言われると難しいところですが、総合的に死亡率や他の病気のリスクを考えると、やはり魚類を含めた食生活をオススメします。
魚を普段から食べるには
でも、なかなか魚って頻繁に食べるのって難しいですよね。
そんなときはスーパーの刺身でも良いですし、鯖の缶詰なんかも手軽かつ豊富な栄養素を含んでいるので、オススメです。
最近では調理家電も進化していて、低温調理器や電気自動調理鍋など手軽に料理をすることができるようになり、これらを上手に活用することで、魚類を手軽に食べたりすることができるようになりました。
魚の水銀問題
健康への多くのメリットが報告されている魚ですが、デメリットとして水銀の問題が懸念されています。
海水汚染だったり、自然界にもともと存在する水銀を魚が取り込み、それら魚を人間が食べることで水銀が体内に蓄積されていきます。
当然水銀が体に多く溜まっていくと、数々の悪影響を体に及ぼします。
食物連鎖の関係で、小さい魚を食べる大きくて比較的長く生きる魚に水銀が多く含まれていることから、マグロやメカジキなど大型魚を多く扱うアメリカでは特定の魚を含む寿司などの食品には「この魚には水銀が含まれています」と注意書きがされているほどです。
日本人は他の国よりも魚の摂取量が多いですが、大型魚だけでなく小型魚などまんべんなく食べますし、一般の人にとっては、魚の平均的な水銀摂取量から考えて、健康に影響を与えるレベルとは今のところ考えられていません。
とはいえ、健康リスクが皆無とは言えませんので、妊娠中はもちろんのこと、特に大型魚の摂取量はほどほどにして、色々な魚を幅広く楽しむ食生活を送ることが健康にとっても望ましいと思います。
さあ次回は「脂質」についてです、お楽しみに!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
