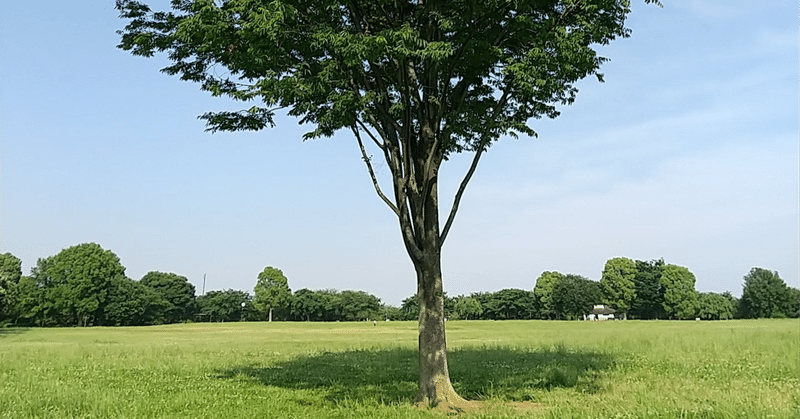
働きづらさとは
私は首都圏で働きづらさをかかえる人への就労支援を行うNPO法人に所属している。
働きながらキャリアコンサルタントの資格を取得したものの、大抵のキャリコン職は「実務経験3年以上」が必要で、それまで事務職の経験しかなかった私はどこも門前払い。「実務経験無し可」の求人を出していたのが今の法人だったのだが、あいにく希望の職種はその年度は募集しておらず、1年待っての応募、そして採用だった。
今年で5年目。
1年目は端的に言えば「私の知らない世界」だった。目の前に現れる人は、超超箱入り娘だった私の人生では出会った事のない人ばかり。その人が生きてる世界の過酷さに、超超箱入り娘の私は一週間でメンタルをやられて眠れなくなった。早すぎだろ。
今では笑って話せるけど、あの頃は仕事が終わると毎日足元がフワフワして自分が物語の世界にいるような、現実を生きていないような、クライアントの世界に身も心もどっぷり浸かってしまってそこから抜け出せず、仕事とプライベートを切り替えるために毎日仕事帰りにミスドでドーナツを一個食べて帰る、という切り替え行動をしないと自分を取り戻せなかった。それを一年間続けてやっと半人前になった。
2年目3年目が一番楽しかった。自分のやりたい事とできる事が段々近づく感覚。手応えを得られるケースもあれば、「まだまだだな…。」と項垂れるケースもあった。母の介護施設入居など家庭状況は大変だったが充実していた。
4年目に異動と共に昇格になり、マネジメントも担当することになった。マネジメント業務は思いの外難しかったが組織全体を俯瞰できておもしろかった。だが家庭状況がさらに悪化したこと、ケースが前職のケースよりも過酷というより異形なケースが多く、日に日にメンタルが削られ7ヶ月でバーンアウトした。
3ヶ月休職して、今はモデル事業を担当している。支援の地理的範囲は広いがクライアントとの関係性は浅く短い。
5年この仕事をしてきて今、疑問が二つある。一つは「働きづらさをかかえてない人などいるのか?」ということ、二つ目は「この働きづらさは個人的な課題ではなく社会の課題では?」ということだ。
私が毎日会う人だけが「働きづらさ」をかかえている人なのか?でも彼・彼女らが口にする「働きづらさ」は私も同様に感じるものばかりだ。
9時から17時、週4日。これが今の私のギリギリの働き方。だから私は契約職員で給与体系は時給。法人の正規職員は「週5日、1日8時間」が基本の働き方。いやムリムリ、マジでムリ。メンタルやられてバーンアウトして休職して復職して半年、そんな体力も精神力も今はねぇわ。
私はこの働き方ができる恵まれた職場にいる。そして、この働き方が選べるだけの恵まれた家計状況にいることも重々承知している。だからクライアントの話を聞くたびに思う、私は恵まれてる。他の企業や公的機関じゃ、こんな働き方しかできない私は正社員としては採用されないんだろうな。
でも、と思う。
そんな働き方、本当にみんなが望んでることなの?体力的にも精神的にもボロボロになるまで働くことが?
今までの社会の設定自体がもう無理ゲーなんじゃないの?1日8時間もしくはそれ以上、週5日いや週6日週7日、体力も精神力も集中力も常にトップギアで働き、そこに病気や出産育児、家事や介護で「休む」という設定は無く、むしろ「休む=悪」の設定。
いやいや、おかしいでしょ。ロボットじゃないんだから。機械でも経年劣化という見積りはされるのに、なぜ人間はないの?あ、機械と同じく替えがきくという設定か。ふざけんな。
2025年問題が叫ばれているけど、そもそものの無理ゲー設定をどうにかしてくれ。頭の良い人達は色々考えてるみたいだけど。
私は2025年まではなんとしても生き延びなければならない。だから無理ゲーにはエントリーしない。今の自分のできる事を、できる範囲で、できる時にやる。
そのために今の自分がどこまでできるのか、どこからが余白なのか、トップギアがどこまででそれをどれだけ続けられるのか、常に自分を探知している。できないことはできないと言い、異動の話にも「復職して半年で異動はムリです。」と断った。
断っていいのだ、未経験だった私を雇ってくれた恩ある職場であっても、自分の生命よりも大切なものなんて無い。一回傷付いた脳は、体は、簡単には元に戻らない。
さらに私は中年で、こっからは下降線をたどる一方だ。できないことが増える自分への恐怖と、まだできる事があるのではという微かな希望。その狭間を行ったり来たりしながら働いている。
働きづらさをかかえてない人なんていない、と現場にいる私は思う。あなただけが特別じゃないし、あなただけが感じてることでもない。頑張って無理ゲーに合わせろなんて言わない。今のあなたにできる事をできる範囲でできる時にやればいい。私はあなたに健康でいて欲しいし、何より生きててほしいよ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
