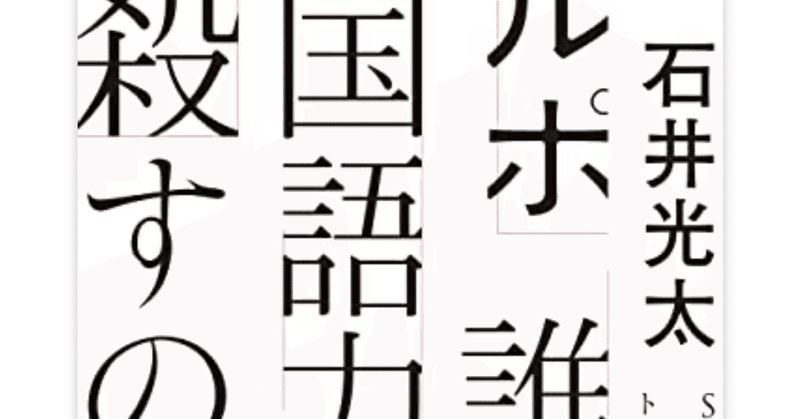
ルポ 誰が国語力を殺すのか:石井光太
今回貪った本→https://amzn.asia/d/5NrKqBI
『ごんぎつね』の読めない小学生、反省文の書けない高校生……
子供たちの言葉を奪う社会の病理と国語力再生の最前線を描く渾身のルポ!
「文科省も、学校も、親も、みんな結局は成果主義なんですよ。すぐに形として表れる結果ばかりを追い求めつづけている。だから、もっともっとという具合に新しいことをやろうとする。国語力を育てることって成果主義とは真逆で、目に見えないものなんです。一つの詩を丹念に読み込んで感動の涙を流しても、テストの点数に結びつかないし、資格を取得できるわけでもない。でも、そうやって内面で育ててきたものがあるからこそ、何十年か先に誰も想像しなかったような素晴らしい人間性を持てるようになるんです。
Xのような言論空間では、「国語力の問題」が何かと議論される。具体的にはクソリプに対して「文字は読めても文章が読めない」だとか「書いてないことを読んでしまう」といった具合だ。それらに触れる中で、「自分自身はどうなのか」と危機感を抱いたことがある人も多いのではないか。僕もその一人で、読解力、ひいては「国語力」に人並み以上の力があると自信をもって言えないでいた。
そんな中出会ったのがこの1冊。
著者の石井光太といえば過去に『物乞う仏陀』https://amzn.asia/d/ccgUWwC を自身で購入したこともあり、迷わず読み始めた。
読み終えて、子どもを育てる親として読んでおいてよかったと率直に思った。
人は言葉とともに成長していく。これは現在、育児をしている身からして、日々強く感じていることだ。
言葉は人と人とをつなぎ、人は言葉によって自己を知る。
この本で取り扱う「国語力」とは単に文章的な能力に留まらず、もっと広く深いもの。人としての基本能力=生きていくための力、そのものと言ってもいい。
本書の前半は、国語力そのものの説明、そして、国語力低下の現状とその原因を現場目線で紐解いていき、後半は国語力の向上を目指す現場の取り組みを紹介している。
途中、幼少期の複雑な生い立ちから、言葉を失った子どもの事例が複数紹介されるが、それは本当に衝撃的だった。
言葉を失った子どもたちは「オノマトペ」でしか会話ができず、自分の行動の理由もうまく言語化できない。現実に対しての解像度が著しく低いため、どうしてそうなったのか、これからどうしたいのか、どうするべきなのか、それらを思考することができず立ちすくんでしまう。
改めて、言葉の世界の広がりがそのまま現実世界の広がりとなることを認識した。
冒頭引用した通り、国語力という目に見えない、結果が可視化しずらいものを育てるには、相当の忍耐力を必要とする。それは、地味で険しい道のりだ。
しかし、国語力の向上こそが人生をより豊にするための必須条件であり、国語力から紡がれる言葉こそ、なにか困難な状況に陥ったときの一筋の希望であり、立ち上がる力である。そのことを信じ、現場で日々身を粉にしている人には本当に頭が下がる。
言葉は一生使う道具である。
国語力は一生鍛錬が必要な力である。
僧侶として、一人の人間としても言葉により向き合うきっかけとなった1冊。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
