
オーディションは手話 当事者約20人出演のドラマ「デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士」ができるまで
皆さん、はじめまして。
本ドラマの制作統括をした伊藤学です。
『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』は、企画から3年以上の歳月をかけ完成しました。ろう者・難聴者・コーダ(CODA)の当事者にも参加いただいたこのドラマ。企画の経緯やスタッフ・キャストのドラマへの関わりを知っていただくことで、ドラマをもっと楽しんでもらいたいと思っております。
伊藤 学
1986年生まれ。長野県松本市出身。
上智大学心理学科を卒業後、フリーランスの助監督・メイキングとして映画ドラマ作品に携わる。その後、角川大映スタジオに入社し、映画『そして、バトンは渡された』、ドラマ『消えた初恋』などの作品にプロデューサー職として参加。現在は、KADOKAWA映像企画制作部企画課に所属。
ドラマ化のきっかけは自身の経験から
皆さんの身近にろう、または難聴の方はいらっしゃるでしょうか。
わたしの周りにはそのような知り合いがおらず、この作品と出会うまでろう者や難聴者について思いを馳せるということはありませんでした。
何か知ろうとするきっかけがない限りは、同じ日本に住んでいたとしても、近くて遠い存在なのではないかと思います。
ただ、漠然と「手話」には興味を持っており、いつか手話を題材にした作品を企画できないか、とは考えていました。
そんな時に、本屋で出会ったのが『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』(丸山正樹 著/文春文庫)でした。
「手話通訳士」というタイトルに興味を惹かれて読み始めたところ、ぐんぐんと引き込まれる面白さで、あっという間に読み終わってしまいました。
面白さのポイントは、ふたつ。
ひとつは、上質なミステリー小説であったということ。
もうひとつは、作中で描かれているコーダ(※)の境遇、ろう者・難聴者の暮らしの歴史や現状、手話の種類などなど…数々の驚きの事実がそのエンターテインメントのなかにうまく組み込まれていた点です。
※ コーダ(CODA)
Children of Deaf Adultsの頭文字を取ってCODAという。
耳が聞こえない親、聞こえにくい親から生まれた、または育てられた、「聞こえる」子どものこと。
特に印象的だったのは、同じ日本で暮らしながら、「手話」という日本語とは違う言語を使うろう者の皆さんが独自の文化を持っていること。そして、登場するろう者のキャラクターたちが耳の聞こえないことを「障害」と捉えず、ひとつの個性として受け入れて生きているというところでした。
ろう者や難聴者を日本文化のなかで生きる「かわいそうな存在」として描かない、その内容にとても衝撃を受けた記憶があります。
なぜ、この小説にそんなにも衝撃を受けたのか…。
自問自答するなかで、見えてきたことがあります。
わたしは先天的に右目がほぼ見えません。
生まれつき眼球の大きさが通常より小さく、手術をしても向上する可能性も低いということで、物心ついた頃から右目がほぼ見えない状態で暮らしてきました(色が判る程度の視力です)。
普通に生活する分には周囲から気づかれることも少なく、片目が見えないことが普通だったので、特に不便さを感じてはいませんでした。
そんなある日。
女手ひとつで私を育ててくれた母と「将来なりたい職業」について話していると、こんなことを言われました。
「片目しか見えない状態で産んでしまって本当にごめん。妊娠中もほんとうに気をつけて生活をしていたのに、なんでそうなってしまったのか分からない」
ふだんは気丈に振る舞い、今まで泣いた姿を見せたことがない母の涙。衝撃的で、とても思い出に残っています。その時に、自分を思う母の優しさを感じつつも、違和感があったため、母に伝えました。
「お母さんは”かわいそう”と思って言ってくれているんだろうけど、片目しか見えなくても結構楽しくやっているし、だいたい片目しか見えないのが自分にとっては普通だから、そんな風に謝らないでほしい。お母さんのおかげで、いま十分幸せなので、それを否定するようなことは言わないでね」
その時に思ったのは、これだけ身近にいる人ですら「片目が見えなくても別に普通です」という感覚がちゃんと伝わらないのだな、ということでした。
自分が黙っているだけでは「これは普通です、かわいそうじゃないです」という感覚は周囲に伝わらない、しかし声高に主張することでもない。理解されない一抹の寂しさは抱えながらも、この感覚をしばらく思い出すことはありませんでした。
その思い出と記憶が小説『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』を読むことで蘇り、描かれていたろう者の生きざまとシンクロしたのです。
「わたしたちはわたしたちなりに幸せに生きているので、かわいそうと思わないで大丈夫ですよ」
という気持ちを周囲に投げかけるきっかけになるかもしれない。
これが、わたしが原作小説に心を動かされ、映像化したいと思った最大の理由だと思います。
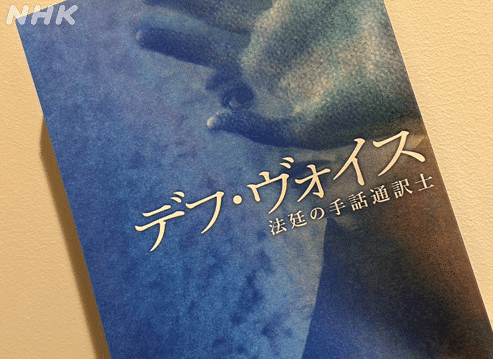
この小説を映像化したい、そしてたくさんの人にコーダやろう者、難聴者の世界を知ってほしい。
そう思い企画をはじめてから最初に仲間になってくださったのは、脚本の高橋美幸さんでした。高橋さんとは以前にも刑事ドラマ作品でご一緒したことがあり、社会的苦境に立たされている方々への目線と物語を紡ぐ筆力がとてもすばらしかったため、今回、プロット開発をご一緒いただけて、とても心強かったです。
素晴らしい原作。ご尽力いただいた高橋さん、渡辺一貴監督。
そして、出演をご快諾いただいた草彅剛さん。
皆さんの力でこの番組をスタートすることができました。
取材の先にあった、広い世界
制作の準備として、まずは原作が描いているコーダ・ろう者・難聴者の世界を取材しました。
手話の監修をお願いした木村晴美さんは、国立障害者リハビリテーションセンター学院の手話通訳学科で手話を教えている方で、毎年多くの手話通訳士を世に送り出しています。
長年、ろうの世界で活躍されてきた木村さんからは、ろうや手話の世界が非常に多角的で複雑である、ということを学びました。
俳優への手話指導を担当いただいた江副悟史さんは、日本ろう者劇団の代表。わたしのろう者のイメージを覆す開放的で大らかなマインドの持ち主でした。
彼のおかげで“手話でコミュニケーションをする楽しさ”を知ることができ、わたしがろう者俳優の方々と距離が近づくきっかけにもなり、作品づくりに大きな影響がありました。
同じく手話指導であり、コーダ考証でもある米内山陽子さんは、自身もコーダです。ふだんは舞台やアニメの脚本を描かれています。
コーダとしての生き方や立ち居振る舞いについて実体験を交えて教えていただきました。米内山さんの実感のこもった意見のおかげで、センシティブな側面のあるコーダの生きづらさを恐れずに描くことができました。
ろう者俳優コーディネートの廣川麻子さんは、ろう者であり、ろう者・難聴者がより多くのエンターテインメントを楽しめるようにアクセシビリティを高めるための活動をされています。
とても広い交友網をお持ちで、「〇〇の施設に取材をしたい」「〇〇さんのお話を聞きたい」というお願いをすべて実現してくださいました。
そのおかげで本当にたくさんの方々に意見を伺うことができました。
また、現役の手話通訳士である高井洋さんからは、手話通訳士として体験されたたくさんのエピソードや視点、思いをお聞きすることができました。
法廷での手話通訳とは具体的にはどのようなものなのか、手話通訳をするうえで大切なこと、苦労や大変なこと…など、高井さんへの取材から着想を得てリアルで繊細なエピソードを脚本に落とし込むことができました。
このような取材を経て、高橋さんが、ろう者や手話を取り巻く歴史の変遷をまとめた膨大な年表と詳細な登場人物の背景を作成して下さり、作品の世界観がぐっと力強く、深くなりました。
コーダ・ろう者・難聴者の世界の奥の深さと複雑さを目の当たりにし、どのようにこの作品を描くべきか、描くことができるのかと日々考え、議論し、形作っていく日々は大変ながらも、とても楽しい作業でした。
オーディションで気づいた「その人の手話」

準備の段階で一番印象に残っているのは、ろう者・難聴者の役を決めるオーディションです。
本企画の大きなポイントのひとつは「ほぼすべてのろう者・難聴者の役を当事者が演じる」という部分ですが、企画当初はそのような予定ではありませんでした。
なるべく当事者に演じていただいた方が良いとは思っていたものの、「数ある配役のうち、何名かは聴者の俳優がろう者・難聴者の役を演じる必要があるのでは?」と思っていたのです。
しかし、たくさんの当事者や関係者の方々から「映画やドラマで聴者がろう者や難聴者の役を演じてきたこと」への意見を聞き、オーディションで実際にお芝居を見るうちに、気持ちが変わってきました。
多くの方が「手話やろう者の世界が映画やドラマで取り上げられることで、知ってもらえる機会になるのだから、キャスティングに対する不満や違和感を発言するのは控えよう」と考え、「ろうや難聴の役を当事者に演じてほしい」という思いを言えずにいたと言います。取材を通して、自分たちの本音を知ってほしい、当事者の声も聞いてほしいという思いをたくさん聞きました。
また、オーディションで演技を拝見するなかで、ろう者・難聴者の役は、なるべく全員を当事者でキャスティングしたい、という方針が固まっていきました。
オーディションには、劇団に所属されている方から、演技に興味のある素人の方、東京から地方に住んでいる方まで総勢80名ほどの本当に多くの方々にご参加いただきました。
わたし自身、手話でのお芝居を見ることがはじめての経験だったのですが、参加した皆さんの熱気がすごかったことをよく覚えています。

一人芝居の台本、二人芝居の台本を用意し、台本の手話翻訳も含めて自由に演じていただきました。
その表現の豊かなこと、
そして、表情と身体全体を使ったお芝居に圧倒されました。
何より、演じることの楽しさやうれしさが全身からみなぎっており、
それが感動的で記憶に残っています。
もっとたくさんの方のお芝居を見てみたいと思ったものです。
オーディションの後、監修の木村さんをはじめ、江副さん、米内山さん、廣川さんと監督、プロデューサー陣で、どの方がどの役に合うかを考えて、キャスティングを決めました。
聴者のわたしからは役に合っていると見えた方でも、木村さんたちから「手話の観点から役と合っていない」などたくさんの意見が出て、びっくりした記憶があります。
例えば、「この方は男性だが、手話が女性的だから、この手話の特徴は指導をしても直すのが難しいかもしれない」という意見があり、手話の奥深さや難しさを知りました。
他にも驚いたことがあります。
手話は大きく「日本手話」「日本語対応手話」という分類があるとされ、
原作でもそのことへの言及があるのですが、オーディションの参加者に聞いてみると、自分の手話がどの手話に分類されるか、または分類されることが適切かどうかわからないという方が多かったのです。
生きてきたバックグラウンドで培われた「その人の手話」があることを実感しました。
今回出演が叶わなかった参加者の皆さんも本当にすばらしいお芝居ができる方ばかりでした。
また別の機会に、お会いしたいと思っております。
加えて、まだ見ぬろう者・難聴者の俳優とも、出会う機会があれば幸いです。
“模擬撮影”で不安を払拭
制作統括として、出演するろう・難聴の方々には「遠慮せずに自分の意見を言ってほしい」という思いがありました。
面白いドラマを作るための”仲間”として出演をお願いしたいという思いがあったので、ドラマのクオリティを上げるために、演技に対するアプローチや撮影環境についての意見があれば、どんどんと言ってもらい、それを踏まえてどんどん改善していきたかったのです。
当然、言語の違いによるコミュニケーションの難しさや慣習の違いなどがあるため、撮影において想定される心配事はたくさんありました。
そこで、その不安を少しでも緩和できるよう、撮影前に「模擬撮影」を行うことにしました。

「模擬撮影」は、スタジオの中に、実際のロケ現場の様子を簡易的に再現し、シミュレーションをすることです。
机などを配置し、撮影・照明・録音のスタッフがセッティング。そして、リハーサル~本番撮影までの一連の流れを体験してもらいました。
そのなかで、ろう・難聴の方々がいる現場として、撮影がスムーズに進められるよう、さまざまな確認と取り決めを行いました。
例えば、
「よーいスタート」という声の合図の代わりに、手をグルグル回すのが「よーい」、その手を下にチョップするのが「スタート」とする
手話指導の江副さんと俳優それぞれに手話通訳を配置
助監督が声がけして俳優たちを現場に連れていく
このように撮影時の細かい部分までスタッフ・キャスト全員で事前に共有できたことは非常に有益だったと思います。

また、模擬撮影当日は太陽の光がまぶしく、俳優たちから手話通訳が見えないことがありました。
その際、「通訳が見えないから撮影場所を変えるのではなく、この撮影場所で通訳が見えるためにはどうすればいいか考えよう」という話し合いを持ちました。このドラマの撮影における優先順位をみんなで共有できたのも大きかったと思います。
『帰る前にメイクを落としますか?』を手話で
このような工夫や、話し合いやすい空気感を作れた結果なのか、撮影はとてもスムーズに進んだという印象があります。
出演された皆さんが遠慮しない、楽しい撮影環境が多少なりとも作れたのではないかと思います。
当初、ろう・難聴の方は、手話を解さない聴者スタッフに話しかけづらいかと思い、トイレの場所など分からないことは特定のスタッフに話しかけてもらうようにしていました。
しかし、撮影終盤ではその必要もなくなるくらい、皆さんチームに溶け込んでいました。

聴者スタッフとろう・難聴の皆さんのコミュニケーションも日ごとに増えていきました。
そうしたなかで、”聴者側が手話を分からなくても、良い関係性が作れるのだな”と感じる出来事がありました。
聴者スタッフが、部署ごとにそれぞれ必要な手話を覚えて、コミュニケーションを取ってくれていたのです。
メイク部さんであれば「(出番が終わって)帰る前にメイク落としますか?」、録音部さんであれば「飛行機が来てるので(本番を収録するのを)ちょっと待っています」など。
ひとつのドラマ制作を通して、一緒に作品をつくる仲間同士が、このようなコミュニケーションを取れるようになっていく過程がとてもうれしく、感動したことを覚えています。

撮影が終わり、クランクアップの花束を受け取った皆さんひとりひとりのうれしそうな表情と、自分の心に湧いた寂しい気持ちが、今も忘れられません。
聴者・ろう者・難聴者が「同じ画面」でドラマを楽しむ
撮影が終わり、いざ編集という段階で一番気にかけたのは、字幕の存在です。
手話セリフは、元々脚本にあったセリフをベースにした木村さん・江副さん・米内山さんの手話翻訳によるもので、それを出演者が演じています。
ただ、手話で表現されている内容のすべてに字幕をつけるわけではなく、元々の脚本のセリフをそのまま入れられる場合と、そうでない場合があります。
字幕には読みやすい文字数と表示時間があり、そこを超える情報量となる場合は整理しなくてはいけないからです。
元々の脚本のセリフを尊重しながら、手話の意味合いも鑑みて、最適な字幕となるように調整していく作業を行いました。

今回は、手話部分だけでなく、日本語のセリフ、きっかけとなる音表現など、すべてに字幕をつけることにしました。
聴者とろう者・難聴者が「全く同じ画面」を見て、同時に楽しんでもらいたいという思いがあったためです。
しかし、見やすく、かつ楽しむための十分な情報を字幕化するのは容易ではありません。
字幕を表示すると、ドラマとして見せたい部分が隠れてしまったり、制作側が意図しない印象を与えてしまったりするおそれがあります。
また、すべての情報を字幕化すると、見慣れていない人(特に聴者)にとっては、見づらいドラマになってしまうかもしれません。
そのため、どうすればいいか、何度も協議を重ねました。
試行錯誤のうえで完成した今回の字幕がどのように視聴者の皆さんに届いたのか。
感想をいただけると、とてもうれしいです。

正解はない。議論を、話し合いを続けよう
このような経緯と思いで作られてきた『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』ですが、聴者とろう者・難聴者に向けたドラマ作りのアプローチとして“完全な正解”だとは思っていません。
制作側としてはベストを尽くして作ってきましたが、出来上がったドラマを見て、またこのような制作の過程を知っていただくなかで、称賛や批判など、さまざまな意見が出てくるかと思います。
わたしは、このドラマをひとつの土台として、聴者とろう者・難聴者にとって”より良いドラマ作り”とは何か、という議論が皆さんとたくさんできると、うれしいです。

今回のドラマ制作を通して一番感じたことは、聴者もろう者も難聴者も、「楽しく一緒に暮らしていきたい」「コミュニケーションの齟齬をなくしていきたい」という共通の気持ちを持っていて、そこに至るアプローチには、色々なやり方があり、意見があり、すれ違いがある。
それを解消していくためには、話し合いや議論がとても大事なのではないか、ということです。
このドラマを見て、聴者とろう者・難聴者のコミュニケーションや手話について、少しでも興味を持ってくださった方がいれば、ぜひ感じたことや思ったことを周りの方とたくさん話していただければ幸いです。
それがきっかけとなって、新しい未来への足がかりとなることを、とても強く望んでいます。

*「デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士」見逃し配信はこちら *
