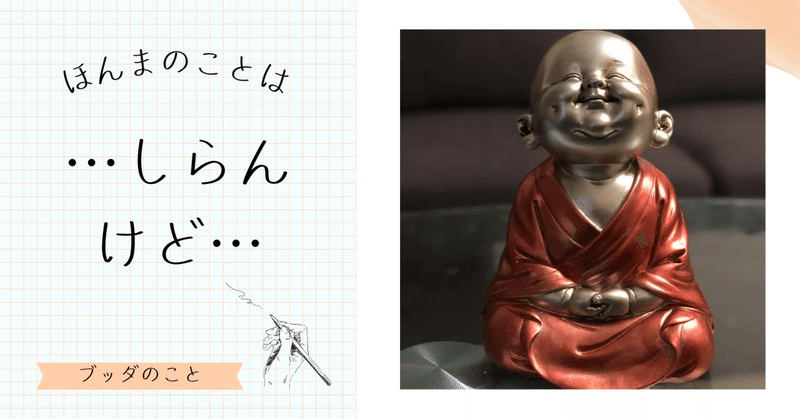
【ブッダ】「マインドフルネス」「サティ」「念」アップデートする仏教
学びたいものがあり過ぎて
中途半端過ぎる学びではありますが、
現状できることとして
『アップデートする仏教』
藤田一照 山下良道
の第三章で眼に留まったもの
を残させて頂きます。
序章 マインドフルネスという切り口
マインドフルネスとサティと念
一照 それで良道さんは、
マインドフルネスの語源である「サティ(sati)」
というのを真正面から、
しかもシステマティックに修行している
本場のビルマに行って学ぼうということで、
とうとう行っちゃったわけだね。
良道 そうですね。
マインドフルネスという英語は、
「サティ」というパーリ語の翻訳です。
そのサティというのがビルマを中心とする
テーラワーダ仏教の実践の中心になっています。
一照 かれらの修行のいちばん核心にあるのが「サティ」、
それを英語でマインドフルネスと呼ぶ。
それは一つのスキルと思っていいわけね。
訓練によって身につけることができるスキル、技術。
良道 そうですね。
サティというものが、要するに気になってしょうがない。
とにかくその気になっているものを、
実際に見に行くというのが主な目的でしたね。
一照 良道さんは日本仏教の中で修行した後、
僕と一緒にアメリカへ行き、
いったんは日本に帰ってきてしばらくやっているうちに、
日本からビルマへ行ったわけですね。
でも、日本の仏教の中には、
その「サティ」というのはないわけじゃない。
良道 ないわけではないけれど、
非常に弱いという気がしてならないのですよ。
サティというのは漢訳経典だと
「念」になるわけですよね。
一照 それは漢字で「念ずる」と書く「念」だね。
良道 では漢訳経典の中での「念」が
本当にマインドフルネス(サティ)の意味で使われてきたか
というと、非常に弱いですよね、そこが。
一照 いま良道さんが言ってるのは、
「いま起きてることに判断を差し挟まずに
はっきりと気がついている」
という意味の「マインドフルネス」ですか。
良道 そうですね。はい。
一照 念仏の念もサティだからね。
サンスクリット語だと「スムルティ」と言うた
良道 そう。
「サティ」というのは疑問の余地なく素晴らしいものだ
というのがテーラーワーダ仏教界の常識です。
ティク・ナット・ハン師もまったく同じ立場です。
だけど、漢字の「念」というのは、
必ずしも「一〇〇%いいもんだ」ということではないのでは。
一照 だから妄念とか、邪念とか、
「妄」や「邪」という漢字と一緒になっている。
良道 まさにそれを言いたかったんだけれども、
道元禅師の最後の著作に
『正法眼蔵 八大人覚』というものがあって、
お釈迦さまの経典を引用しながら、
八つの修行のポイントを話されています。
小欲知足などと並んで、その五番目が
不忘念(ふもうねん)ですね。
一照 「ふぼうねん」とも読むね。
「念を忘れちゃいけない」。
それがまさにサティでしょう。
漢字でよく似てるけど、妄念の「妄」じゃないよ。
「忘れる」の「忘」。
良道 一照さんも知っていると思うけど、
この「不忘念」をめぐる有名な話がありますね。
この『正法眼蔵 八大人覚』の中で引用されているのは、
お釈迦さまの遺言でもある『仏遺教経』です。
二月十五日のお釈迦さまの「涅槃会」の法要では、
『仏遺教経』を読みます。その法要の前に、
お経の勉強会をするのが安泰寺の昔からの習わしでした。
内山興正老師がまだ若いころに
その勉強会で八つあるうちの「不忘念」が担当になった。
「不忘念」。
これはテーラワーダ的には非常に簡単な話です。
「いつもマインドフルを忘れないようにしなさい」
という意味で、「はい、わかりました」となるわけですよ。
ところが、これが仏教の文脈になるとどうなるかというと、
若き日の内山老師ですら勘違いをされた。
一照 ああ、「忘」じゃなくて「妄」に誤解した
というエピソードだね。漢字が似てるもんね。
うっかりすると「不妄念」に見えちゃって
「妄想するな」という意味に取ってしまう。
良道 あのころ内山老師はまだ若い雲水だったので
忙しくて「不忘念がお前の担当だよ」と言われても、
勉強する時間がなくてちらっとだけテクストを見て、
「ああ、はい、わかった」と思って、
不妄念をイメージしてしまった。
それでちょっと時間ができて落ち着いてテクストを読んでみたら、
不妄念ではなくて不忘念ではないですか。
で、びっくり仰天した。
この話はわたしも昔から聞いていたのだけれど、
これは単なる勘違いではすまされないのですよ。
そこには何か歴史的必然性があるわけです。
テーラワーダでマインドフルネスを学び、
それが漢字だと念だとわかって、
この逸話の深い意味がわかりました。
一照 日本仏教の文脈では
そういう勘違いをするのも無理ないということね。
念というものの見方がテーラワーダとはだいぶ違う。
良道 無理もない。
歴史的必然性のある勘違いだった、大げさに言うと。
だからこれはやっぱり「念」というのは、
あくまでも悪いものだということに心理的影響を受けていたわけです。
一照 雑念とかいう表現を使うしね。
良道 妄念とはいかなくても雑念ということですよね。
一照 この場合の念というのは「思考」という意味でしょ。
思念だからね。考え事のこと。
良道 テーラワーダの文脈の中ではなんの疑問もないことが、
見事に歴史的な必然性でもって勘違いのもとになった。
このことからわかるのは、マインドフルネスというのが
もともと日本にもあるのではというのは、その通りだけれども、
必ずしもテーラワーダのような強度では存在していなかったこと
は認めざるを得ないのではないか。
そうなのだけれども、不思議なことに、
わたしも一照さんもやってきた禅の修行というのは
マインドフルネスという観点から見れば、
非常に意味があるわけですよね。
たとえば「応量器」というものがあって⋯⋯。
一照 禅のお坊さんが食事をするときに使う
お椀のセットのことね。
良道 それをたとえば永平寺などの修行道場へ行った場合に、
そのお椀のセットをどうやって並べるか
ということを徹底的に訓練されるわけですね。
一照 食事の作法ということでね。
お箸の持ち方、使い方、お椀の取り方、置き方、
そういうことのすべてを決まった作法でやるようにたたき込まれるのね。
良道 お箸の並べ方も全部決まっている。禅寺の生活というのは
すべて立ち居振る舞いを徹底的に指導されます。
トイレのドアの開け方からして。
そういう修行はいったいなんのためかというと、
実は「マインドフルネスを養うため」。
だからマインドフルネスというものを入れた途端に、
禅寺での修行がすべていきなり深い意味を持つ。
だけれども同時にもしそこに
マインドフルネスというものが入らなかった場合に、
あれは非常に狭い意味での形式主義になってしまうわけですよね。
一照 そうなってくるね。形だけで精神が失われてくる。
外見だけが問題にされて、心がこもらなくて、
ただ決められた形通りに体を動かしているだけ。
そうなると作法というのも本来のスピリットが失われて、
ただ窮屈な形に無理やり従うだけのことになる。
良道 型が強調されるんだけれども、
その型を強調するのはなんのためか?
本来はマインドフルネスを養うためだったんですよね。
だから、「マインドフルネスは日本にもあっただろう」というのは
半分イエスで半分ノーとわたしは言わざるを得ないんですよ。
一照 あったはずのものが、
あるいは本来そういう形で伝わってきたものが、
そのうち外形だけが残って中身がなくなってしまったということだね。
こちらの内容は、
『アップデートする仏教』
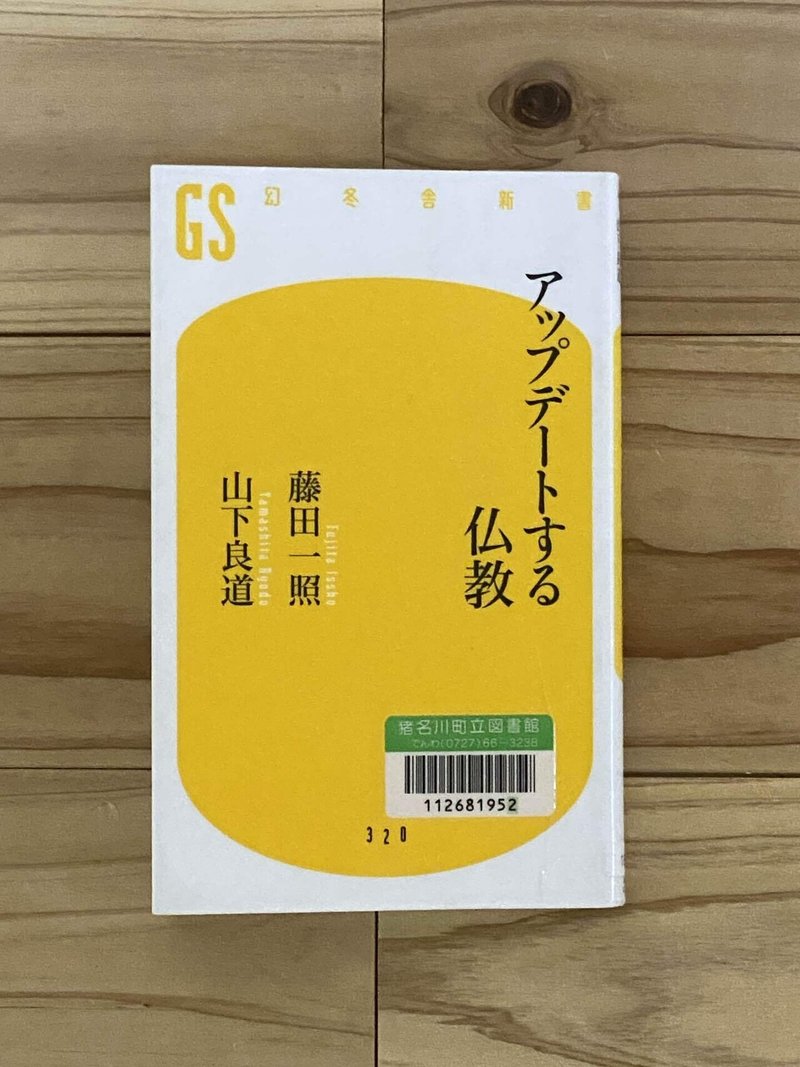
発行 株式会社幻冬舎
著者 藤田一照 山下良道
2013年9月30日発行
を引用させて頂いています。
よろしければ、サポートよろしくお願いします❤ ジュニアや保護者様のご負担が少ない ジュニアゴルファー育成を目指しています❕ 一緒に明るい未来を目指しましょう👍
