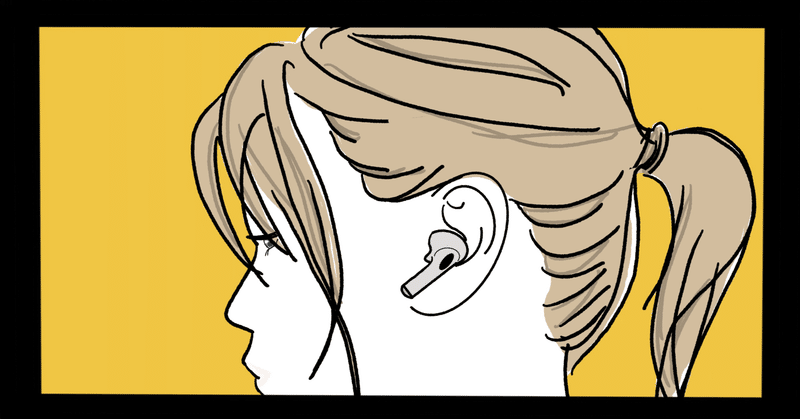
オーディオブックを作らないといけないと思ったこと【雑記】
オーディオブックについて。
小説を書いて誰かに読んでもらう上で、オーディオブックは大事だなと感じたので、その話。
長編の紀行小説 ウツとアフリカのアップロードが終わった。
noteで長いのを載せると大変だな、と。
でも、写真が付けられるのは良い。
旅に行ってから小説の形になるまで、本当に長かった。公開出来てよかった。
今日は一日、オーディオブック作り。
十万字、五時間しゃべり続けたから喉が痛い。
YouTubeで聞けます。
ちなみにYouTubeは自転車について語ってるだけのチャンネルです。
なぜオーディオブックを作らないといけないと思ったか?
なんでオーディオブックなんか作るか?
答えは二つ。
・日本人は小説なんか読んでいるほど暇じゃないってこと。
・あとは声に出して読むことで、文章の変なところなんかが分かる。
この2つが大きい。
あとは、オーディオブック制作には、作品を多くの人に届けたいという欲求も大事です。
長編の朗読って大変だから、モチベーション大事です。
今回の作品はアフリカのチャリティーが一つの大きな目的なので、多くの人に読んでもらって募金を増やしたいと思ったのが、原動力になっています。
素人の長編小説を読むほど暇じゃない
今回の話は面白かったらしく、10万字と長い割に公開して三日経たずに各方面から感想が届きました。ありがたいことです。
長編で感想が届くってすごい。
noteはつい最近始めたが、これまでも何本も小説を書いている。キンドルで出したりもしている。
それでも、わざわざ感想を連絡してくる人ってあんまりいなかった。
そもそも感想って、最後まで読み切らないと言えない。
公開して三日以内に読みきって、しかも感想を伝えたくなる人が現れているっていうのは、実に嬉しい。
でも、現実には小説って本当に読まれない。
みんな忙しい。
ハウツー本とかビジネス本とかは、いくらか読まれるけど、小説は厳しい。
特に長編って、最後まで読まないと良さが分からない。
忍耐力が必要だし、その忍耐を楽しむのも読書の悦びなのですが。
みんな暇じゃない。
もちろん、noteで創作する人なんかは、文章を読むのが好きな人も多いですが。
とはいえ、普通の人は、無名作家の十万字の小説なんて読みませぬ。
有名作家でも読んでもらえる長編はごく一部
現実は厳しいもので、有名作家の作品でも、小説ってそんなに読まれません。
もちろん、アマチュアよりは読まれますけど。
例えば村上春樹でも、僕は五本くらいしか読んでない。世界の終わりとハードボイルドワンダーランドとか読みたいなと思ったけど、途中でやめた。
まあ、僕が読むのが遅くて、あんまりたくさん読めないってこともあるんだけど。
でも、この記事を読んでいる人で、カラマーゾフの兄弟、罪と罰を読んでない人も結構いるんじゃないでしょうか? ドストエフスキーなんて世界で最も素晴らしい小説家の代表作なのに。
かくいう僕もトルストイの戦争と平和は読んでません。ドストエフスキーもカラマーゾフと罪と罰は読んでるけど、他は読んでません。
一番好きな作家である内田百閒先生の阿房列車も全部は読んでません、多分。覚えていない。ちなみに阿呆自転車は、シリーズ1を書いた当時、阿房列車が好き過ぎてタイトルをパクっています。なのに、全部読んだか怪しい。それはさすがに問題な気もしますが。阿房列車、買うかな。
動画でさえ5分以上見られない時代だけど、長編じゃないと伝えられないことは存在する
阿房列車の話はさておき。
小説って読まれない。
YouTubeなんかの動画でさえも五分以上のものは見られない時代ですから。
ツイッターなんか100文字ちょっとでしょう。
インスタなんかもはや文字はおまけ。
写真で一秒で見れるもの。
そりゃ、真摯に受け止めるしかないです。
でも、長編小説や長い文章でしか表現できないことは間違いなく存在します。
長い文章は人類にとって重要です。
書く人は読んでもらう工夫をしないといけないのです。
SNSで公表したり、あれこれ。
オーディオブックは読まれるための一つの工夫です。
オーディオブックなら読まれるか?
さて、問題はオーディオブックなら読んでもらえるか?
答えは半分はイエス、半分はノーでしょう。
読まない人はオーディオブックだろうが何だろうが読まないです。
読む人は文字でも読んでくれます。
そもそも本当におもしろい作品は、何かきっかけさえあれば、オーディオブックじゃなくても読まれます。
そういう意味ではオーディオブックなんて無意味ともいえます。
だけど、読みたいけど時間がないだったり、紙なら読みたいけど、スマホで長い文を読むと目が疲れてしんどい。そういう人も中にはいるわけです。
文なら何でも読む、読書中毒の人にだけ読んでもらえればいいなら、オーディオブックは不必要です。
その作品は読書中毒の人だけに読んでもらえればOKか?
でも、どうでしょう?
その作品は、だれに読んでもらいたいですか?
今回の僕のアフリカの話は、35歳で三歳の子持ちの父親がウツになって、昔のアフリカの自転車旅を思い出しながら、生きる活力をもう一度手に入れる話なのですが。
これ、実際に読んで、感動して感想を送ってくれた人は、
・子持ちの父親
・憂鬱と戦っている人
・自転車が好きな人
・読書が本当に好きで長い文をもりもり読める読書家
でした。
つまり、4つ目の読書家以外は、文が好きってわけでもないんです。
ただし、これって、作品によって違うと思います。
僕も、普段書いている作品は、別に、読書中毒の人にだけ読んでもらえれば良いってことも多いです。
短編とか童話とか。
文学なんて、好きな人間だけのたしなみっていうのも事実なので。
芸術とかって、閉じていて、オタク的な側面はやっぱりあると思います。
それはそれでOKだと思います。
ただですよ。
「これは本当に良い作品が書けた。
世に出したい。
世界に何か良い影響を与えられるかもしれない」
そういう作品が書けたときは話が別でしょう。
作品を世に送り出すという仕事を、著者自身でやる価値がある作品というのは存在すると思います。
そういう時にオーディオブックは有効だと思います。
オーディオブックでの読書ってどうなの? ちゃんと作品を楽しめる?
オーディオブックが意外に普及しそうで普及しない根本って、オーディオブックでも読書がちゃんとできるか?っていう疑問だと思います。
僕の場合、実際の自分自身のプライベートの読書でも、Amazonのオーディブルやキンドルのアレクサ読み上げが増えました。
僕の場合はランニングの時が多い。一時間走れば、結構聞ける。
あとは家事。運転中。
ながら聞きって、聞けてないようで意外と聞けている。細かい部分は聞き流している部分も多いけど、何だかんだ頭に残っている。
精読は難しいかもしれないが、通読は十分出来ますし、読書の楽しみが半減したりしないと思います。
でも、村上春樹なんかはオーディブルで聞いていてちょっときつかった。
ミヒャエルエンデのモモなんかはOKだった。
サピエンス全史なんかは最高だった。
暇と退屈の倫理学も、まあ、行けた。
ライトノベルは全く読まないから分からない。
この辺は作品によったり、読む人によって個人差があるでしょう。
この辺りは、実際に、自分で何冊かオーディオブックを聞いて体験してみないと分からないかもしれません。
過去に紙の本で読んだ作品なんかベターです。
僕は、村上春樹は普通の紙で読むのは好きなのに、オーディオブックではダメでした。
つまり、文で読んで良い本=オーディオブックで面白いとは限らないです。
ただ、少なからず、オーディオブックの読書が好きな人はいます。
社会人やってる限り、みんな仕事や子育てやら忙しいですから。
オーディブル、キンドルのアレクサ読み上げ。技術の進歩とオーディオブック
オーディオブックはとにかく今、技術革新がすごいです。
特にKindleのアレクサ読み上げ。
キンドルのアレクサ読み上げは、AIで文字を読ませるのにすごい。
もちろん、漢字の読み間違えなんかもありますが、最低限はちゃんと読める。アクセントなんかの違和感も少ないです。もちろん、まだまだ人間の朗読の方が上ですけど。
ページが変わるときに止まってしまったり、改善して欲しい点は多いですが、これ、無料で提供してるサービスなのかと驚くレベルで読み上げてくれます。
siriの読み上げはイマイチ。聞きづらい。
キンドルのアレクサ読み上げは本当に優秀だと思います。
オーディブルは当然、プロの朗読だからベスト。
アプリの使い勝手も良いです。
ただ、読みたいタイトルが少なすぎる。自己啓発やビジネス本は多いんだけど。肝心の読みたい話がなかったりする。
あと、本文が読めないので、意味が理解できない時がある。
その点、キンドルはかなりの本が出ている。当然、本文も画面を開いて確認することも出来る。
キンドルとアレクサのコンビは素晴らしい。
理想はオーディブルのラインナップが増えればベストですが。
多分、人間の朗読のラインナップが増えるよりも、AIの読み上げ技術の方が早いかなと思います。
それが実現すると、すべての本に、読み上げは無料で付いてくる状態になります。
多分、十年以内に実現すると思います。
(余談ですが、そうなると、Amazonってすべての本を独占できる可能性が出てきます。
だって、Kindleでしか読み上げてくれないなら、同じ値段ならKindle買うでしょう。
多分、Amazonはそれを分かっているから、ここの開発は継続してるんじゃないかと。
まあ、Alexaは赤字部門とかって聞いたことありますが)
そういうことを考えていくと、オーディオブックが存在する作品かどうかってかなり大きいと思っています。
まあ、そういう意味ではキンドルで出しても良かったんですが。
今回はアフリカへの募金という目標があるので、キンドルの手数料は無駄でしかない。
そうなると、自分でオーディオブック作るしかない。それにキンドルよりもやっぱり人間の朗読の方が良いですから。
とはいえ、オーディオブックも、なんだかんだである程度本が好きな人じゃないと使わないんですが。
著者が自分で読み上げる姿は読者にも熱意が伝わるんじゃないか
読者のために文が読まれる工夫をしているかどうか。
これって結構大事だと思います。
文だけ読ませる自信があるなら、文学賞を狙った方が良い。
文学賞を取って、作品に泊を付けるというのも、ある意味では、読者に読ませる工夫の一種とも言えます。
もし、Kindleの読み上げが、三年以内に劇的に進化したとしても、筆者が自分で自分の作品を朗読して、読者に届けようとしている作品。
これって、やっぱり良い作品だと感じるんじゃないですかね。
どうでしょうね。
でも、全く何もせず、Webの海に投げられている作品よりは、好感を持つんじゃないですかね?
YouTubeで音読で実際に10億円売れた?!
完全に余談で、小説ではないのですが。
僕は、以前、住宅の営業マンをしていたのですが、その時に、YouTubeでの文章の音読のおかげでたくさん家をご契約頂きました。
(まあ、小説にも書いている通り、ウツになって辞めてるんですけど笑)
どういうことかというと、
・オウンドメディアを立ち上げる
・3000字の住宅に関する記事を200本ほど書く
・YouTubeで音読する
・それを見てお客さんがめちゃくちゃ来てくれた
ということです。
家って、一軒何千万円なので、誇張なしで、十億円くらいは売ったと思います。
まあ、音読だけの効果じゃないんですけどね。
住宅についても本当、いろいろ頑張りましたから。
でも、頑張ったって、普通は家を売るって難しいです。
記事だけだと、人間、なかなか読まないですが、動画が付けば、結構見れる。
これは事実です。
まあ、時代的なものもありますよ。
コロナでYouTubeがバズるタイミングだったし、その頃って、他の住宅会社ってほとんどYouTubeしていなかったので。
今は、もうYouTubeだけじゃ家はそこまでは売れないでしょう。
でも、多分、今でも、そこそこ効果はあると思います。
だって、家を建てる人って、家についてリサーチしたいんです。
でも、忙しいから本読んだりって厳しい。
でも、YouTubeなら楽ちんにしかもプロが顔出しでしゃべるし、その人に直接相談できるわけですから。
そして、それをするためには、文章が書けないといけない。
当然、住宅の勉強もしっかりして、知識がないといけない。
さらに、YouTube使いこなせないといけない。
でも、全部できる人間って意外と少ないので。
とにかく。
文章を音声にするっていうのは、一定の効果があると実体験として感じています。
文学や小説にもそのまま応用できるかは、いろいろ他の要素も検討しないといけませんが。
文は音読するだけでも、読者にかなり届きやすくなると言えるんじゃないでしょうか。
音読することで推敲、校正ができる
自分で朗読する大きなメリットとして、推敲、校正の手法としても素晴らしいということです。
どうしたってアマチュアには担当者がいないので、自分で推敲も校正もかけないといけないですから。
推敲と校正の技術って重要です。
音読させるだけなら、キンドルのアレクサ読み上げ以外にも、人工音声はいろいろあります。
最近の技術は本当にすごい。綺麗に読み上げてくれます。
僕なんかのおっさんの声よりも、綺麗な女の子の声の方が聴きやすいですし。途中で噛むこともない。
でも、自分で声に出して読むことで、文の流れを味わうのは、推敲、校正の意味でもすごく有意義です。
特に誰かに聞いてもらうために読むというのは、一人でボソボソ言うよりも良い。
僕は、推敲するときにも、一人でボソボソ呟いて文の通り、流れを確認することがあるんですが、それとはやはり違います。
発音しやすい=良い文章ではないですが。
やはり読もうとして変に引っかかる文章は、読む人には読みづらい。
(もちろん、内田百閒先生のようなガチガチの文体芸術のような文章の場合、読み上げやすさよりも、文章の美しさが重要と言うこともありますが)
そう言いつつ、今回のオーディオブックの朗読の際には、直した方が良いと思ったところを修正できてないのですが。
時間と気力が途切れてしまった。ちょっとそこは課題ですね。
一気に読まずに少しずつ録音、推敲、動画編集した方が良いですね。
あるいはオーディオブック公開用の録音と、推敲用の録音は別にするか。
何にせよもう一段階工程を増やした方が良いですね。
やっぱり体力と気力が途切れてしまった。
今でも喉が痛い。
声優さんってすごいんだなと思いました。
オーディオブックはYouTubeが良いのか?メリットと問題点
今回やってみて機材はマイクを買ったほうが良いなとは思いました。
まあ、それはまた今度の話として。
YouTubeでやるべきか、他の媒体が良いのか。別にオーディオブックなら映像はいりませんから、YouTube以外にも選択肢はあります。
専用アプリとかを追加で入れなくて良い
YouTubeが良いのは、どんな人でもYouTubeはすぐ見れる。YouTubeはほとんどの人が普段から使ってるでしょうから。
別にアプリを入れないといけないとかってハードルがないのは大事です。
キンドルのアレクサ読み上げなんかは、その点良くないです。
キンドル単体では出来ないからです。アレクサアプリも必要です。でも、アレクサのキンドル読み上げって知ってる人が少ない。アレクサのスピーカーがなくても普通にスマホでイヤホンで使えます。でも、知られていない。そもそもアレクサスピーカーもってないのに、アレクサアプリを入れている人はいないでしょう。
履歴で前回見たところの続きから再生してくれる。目次も作れる。
あと、YouTubeは履歴で、前見ていたところから続きを再生できるのも良いです。
概要欄に時間を記述すれば目次も付けられます。
作品によっては目次を付けたいものもあるでしょう。
集客、マーケティング、書籍化的な側面でも強い
すでにチャンネルを持っていたら、そこから小説の宣伝も出来ます。
僕の場合、YouTubeは自転車のチャンネルなので小説好きはあまりいないので、そんなに意味がない気もしますが。
あと、有料で広告をかけることもできます。これがそんなに高くない。
特に書籍化も視野に入れるなら、書籍化した後の集客もできる可能性があります。
これは出版社としても嬉しいでしょう。
集客、マーケティングまでできる作家は当然ながら歓迎されますから。
もちろん、ただ、文章が上手くて良い本が書ける作家でも良いのですが。出版社もビジネスですから。
画面収録で撮れば、文も見える。
これはオーディブルなんかのちゃんとしたオーディオブックなんかでも、そうした方が良いんじゃないかと思います。
本文が見える方が、聞き取りにくい時やすこし戻りたいときなんかにちょっと画面を見て確認できるので便利です。
こうして考えるとYouTubeでやるメリットは多いです。
YouTubeでオーディオブックするデメリットは?
逆にデメリット、問題点は、無料会員だと、広告が入ることと、画面を消して再生できないことでしょう。あと、ダウンロードが出来ない。
画質を低くして、データ量を落としてあげる方が、オーディオブックとしては良いかもしれません。
この辺はユーザー側が有料にすれば問題ないですが、YouTubeも高くはないけど、安くもないですから。無料の人の方が多いでしょう。
対策としては、mp3なんかの音声ファイルも並行して出すことでしょう。
ただ、やっぱりそれも普通の音楽プレイヤーアプリで再生すると、前読んだところの続きから再生とかが出来なかったり、目次が付けられないとか問題点が多いです。
オーディオブック再生に最適なアプリとかがあれば良いですが、やっぱりわざわざアプリをダウンロードしてもらうってハードルは良くないと思います。
そう考えると、アマチュアがオーディオブック出すなら、YouTubeでの配信ってメリットが多いのかなと思います。
文字からYouTube。YouTubeから文字。AI技術で執筆のネタ帳。
完全に余談になりますが。
文字と音声の変換については、僕は結構あれこれ考えることが多いです。
今回のオーディオブックの話は、文字からYouTubeへの方向の変換の話でした。
しかし、逆にYouTubeから文字の変換もありえます。
執筆のネタ帳、メモ代わりに動画を録って、YouTubeにアップしておけば、文字起こしされたメモが勝手に出来上がります。
AI技術の進歩で、自動の文字起こしが劇的に良くなっています。YouTubeの標準機能で文字起こしが搭載されているので、アップした動画はすべて文字起こししてくれています。
もちろん、メモは公開しなくていいですし、あえて公開にしても楽しいかもしれません。
普通の録音アプリと違って、今のスマホカメラはシャッターチャンスを逃さないよう割とすぐに起動できるようになっているのも嬉しいです。
しかも、YouTubeなら容量制限もないです。
ただし、録音、文字起こしで無料で制度が良いものなら、CLOVA NOTEが一番熱いです。精度がすごすぎる。テキストファイルでも出力してくれる。
これは試したことが無い人は一度試してみることをお勧めします。本当にヤバいです。
手書き、タイピング。第三の執筆の方法、しゃべる。
書くというのはとても大事ですが、時間もかかります。
その点、しゃべるというのはやはり速いです。
しゃべるというのを執筆の方法の一つに取り入れたら、すこぶる効果があるんじゃないかと模索しています。
子持ちの35歳のおじさんが書き続けるには、工夫が必要です。
何か思いついたら、ポケットのスマホを出してビデオオンにして、五分しゃべれるだけで、ある程度の文章量になります。
僕の場合、まず手書きでスケッチブックにアイデアを書きます。
その前に、日々の日記帳なんかにあらかじめ断片的な文章を貯めておきます。
そこの部分をしゃべりで入力するって良いんじゃないかなと。毎日、五分くらいならしゃべれますから。
残念ながら、短い文でも書くと十五分くらいはかかってしまう。毎日、十五分は難しい。
動画、あるいは音声をストックしておく。文字起こしがあるので、たまっても、まあまあ、見れる。
ネタが積もってきたら、手書きでスケッチブックにアイデアを自由に書きます。ぐちゃぐちゃに単語が並んで、線でつないだり。絵描いたり、いろいろ。とにかく書きたいことを吐き出します。
そこから、実際に使うものを拾ってマインドマップなんかにしたりガチャガチャやります。
この辺のガチャガチャした作業は手書きが良いと感じています。
スケッチブックに青字のちょっと0.7のPIGMAで書くのが好き。
書きたいことが見えて来たら、Dynalistというアウトライナーに打ち込んで骨を作ります。ここからはタイピングですね。
骨が出来たら、肉を付けていきます。
この肉を付ける過程でもしゃべりは使えるんじゃないかなと目論んでいますが、どうでしょう。
肉が付いたら、一本の流れにして整形していきます。
上手く行かなかったら、アウトライナーに戻ったり、マインドマップなんかを見ます。
完成させます。
で、完成したものを読み上げて、推敲して、オーディオブックもそえて発信する。
こんな流れが当面の狙っていることです。
まあ、これは、僕の勝手な手法ですし、どこまで使えるか、まだまだ実験段階ですが。
AIに文を書かせるのは、まだまだ未来だと思いますが、しゃべっている言葉を文字にさせるのは、すでに実用段階に来ていると思います。
PCやスマホの音声入力はやっぱりまだ少し微妙。ここ何年かで変換精度なんかも劇的に良くなってますが。まだ遅い。
ただ、あと数年したら、劇的に良くなると思いますが、今度は多分、人間の頭の方が追い付かないでしょう。しゃべって書くって別の技術がいります。それはそれで難しい。
音声から文を構築できて、文から音声で人に入力しやすいようにするっていうのは、かなり良いんじゃないかなと。
なので、やっぱり現段階では、ネタのストックで五分ぶつぶつしゃべるというのが、音声→文章のベクトルでしょう。完成したものをオーディオブックにするのが、文章→音声のベクトル。
はい。そんなことを感じました。
3月から大工さんの仕事が忙しそうなので、今後の執筆のためのメモとしての雑記でした。
最初アップした時より随分、長くなって、蛇足も多くなってしまいましたが。
大工さんしながら、コツコツ書くモチベーションにしていきます。
それにしても、オーディオブックの一番の現実的な問題は喉が痛くなることですね。声優さんってすごいですね。十万字を一日で撮ろうとすると大変ですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
