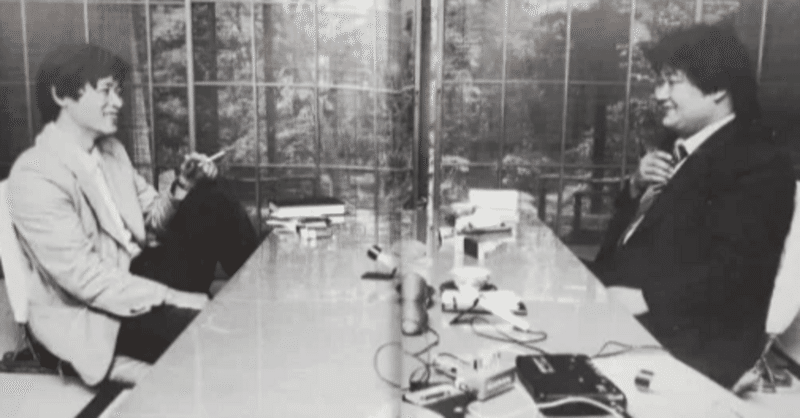
『柄谷行人 中上健次 全対話』 : 正面突破の双騎士
書評:『柄谷行人中上健次全対話』(講談社文芸文庫)
やっぱり柄谷行人は、私に合うなあと思う。何がかというと、要は、馴れ合わないのだ。
それは、人間に対してももちろん、興味の対象に対しても、適当なところで妥協して「うまく立ち回る」というようなことをしない。要は、やりたいことをやりたいだけやるし、そのようにしかやれない、ということである。
無論、空を飛びたくても飛べるわけではなく、そこにはおのずと限界があるのだけれど、その限界を承知のうえで、どこまでできるかに挑まないではいられないという無垢な衝迫を、この人は生きている。
そして、それは盟友であった中上健次も同じことだ。
二人はまるで、仲の良い「いたずら友達」のように、教室を抜け出しては、青空教室の中をとんでもない勢いで駆け回っている、そんな悪童のようである。
とは言え、私は中上健次の方は、あまり読んではいない。1996年頃に『岬』『枯木灘』『地の果て 至上の時』を読んだきりである。
中上健次は、1992年に亡くなっているから、その意味では、中上が最も注目され読まれていた時期だと思うのだが、私が読んだ理由は、そういうことではない。

当時、『産経新聞』の匿名コラム欄である「斜断機」のコーナーに、その匿名批評家が、たしか亡くなったエンタメ作家か誰かのことを「すぐに忘れられる作家だろう」というような趣旨のことを書いていて、その比較対象として、つまり、いつまでも残る作家として中上健次の名前を挙げていたのだ。一一しかし、それで興味を興味を持ったというのでもない。
私は、例によって、その匿名批評家に腹を立てて、読者投稿として、この批評家を批判したのだ。
「死んでから言うな。しかも、匿名で」ということだったのだが、私はこの(編集は入ったが、いちおう)採用された(田中幸一名義の)投稿文で「あなた(匿名批評家)は、今も人気のある中上健次が残ると言っているけれども、そんなことわかるものか。将来的には、どうなっているかなんてことはわからない。評価が逆転してるかもしれないぞ」というような、中上健次について、いささか否定的なことを書いたのである。
ただ、この段階で、私は純文学作家の中上健次については、1冊も読んでいなかったから、否定的なことを書いたからには、いちおう読んでおかないといけないと思い、上のような代表作らしいのを読んだのだ。
だが、結果として、面白いとは思えず、その時の評価が今にまで響いている。
つまり、「いま読めば、評価が変わるかもしれない」という印象が、中上健次に関しては、あまり持てない。
何か本質的なところで「自分には合わない作家だ」という印象が強くあったのだ。
で、その後、中上を読んでいないから、そうした「印象」がどのようなところに由来するものなのか、ハッキリしたことはいえないのだが、その後に読んだ、柄谷行人の言葉の中から、これかなと思うものを挙げるとしたら「中上健次の女性性」といったことになるだろう。
私はおおむね、女性作家を面白いと思えない人間なのだが、言われてみれば、中上の小説には「男性らしさ」が薄く、水分量の高い重さがあったように思えないでもないのである。
あと、今回の対談集の中での中上の言葉としては、「物語」というものへのこだわり、ということがある。
その対談で、中上と柄谷は、1989年当時の、「文学」という制度に激しく反発しているのだが、中上が、「文学」に対抗するものとして、「物語」的な伝統の新たな復権というようなことを、自身試みようとしている、という趣旨のことを語っているのだ。
で、これも、そう言われてみると、私は「物語らしい物語」というのがあまり好きではなく、どちらかといえば、「意味」や「中身」に惹かれるタイプの人間だから、体質的に中上の小説は合わなかったのかな、などと思ったのである。
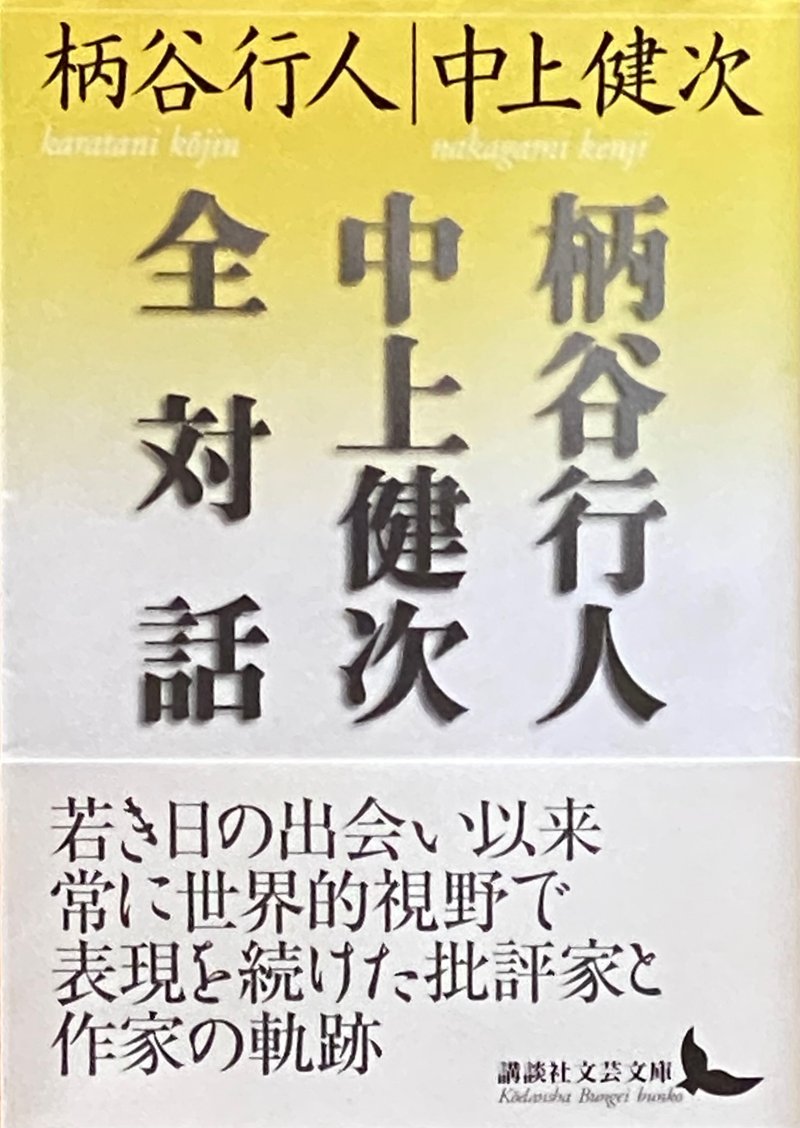
そんなわけで、今回の対談集(時期を異にした、4本の対談と往復書簡)だ。
言うなれば、私に合う柄谷行人と、私に合わない中上健次の対談ということになるわけなのだが、最初に書いたとおり、これらの対談では、両者の、その「悪童」性において、とても共感することができた。
だが、上のように考えてくると、もしかすると、両者は、同じように「悪童」であったとしても、やはり、そのいたずらの仕方に、体質的な違いがあったようにも思える。
それは、どのような「違い」なのかというと、柄谷は、周囲のことなど気にせずに、思いついた方に歩いていってしまうというタイプであり、中上の方は、けっこう周囲を意識して、それに反発するタイプ。つまり、柄谷が「自分の好きなこと以外は、どうでもいい」というタイプなのに対し、中上の方は、他者を強く意識し、それを愛したり憎んだりするが故に反発するタイプだ、というようなことだ。
両者が、こういう性格だから、当然、喧嘩をすることもあったようだが、基本的には、このような「違い」もあったからこそ、結局は生涯の友たり得たのではないか。
どちらもが柄谷タイプだったら、離れていたらそれっきりというようなあっさりした関係になるだろうし、両者が中上タイプだったら、ドロドロの殺し合い的な関係になっていたかもしれないと、そんな印象である。
ともあれ、肝胆相照らす両者による「あいつは馬鹿だ。こいつは何もわかっていない」といったやりとりには、今どきでは目にすることのない「潔さ」がある。
言うからには、当然「それほどのことを、やって見せてくれるんだろうな?」という意地悪い目で見られるのを承知の上で、あえてそれを言う「覚悟と自負」がこの二人にはあり、それが「非日本人的」で、とても痛快なのだ。
今のような「無難に優等生」「無難な正解」しか見当たらないような時代になると、これらの対談は、いっそ「神話時代」のものだとすら思えてくるのである。
○ ○ ○
さて、ここからは、私が共感した、個々の発言について書いていこう。(※()内はルビ)
(1)
『柄谷 小林秀雄の言う歴史は、つまり線的(リニア)だね。彼には隠蔽とか抑圧とか、あるいはその累積された構造が見えない。古代なら古代へ、すぐに直観的に迫れると思っているんだ。本当は一つ一つ、隠蔽された結節点を解きほぐしてしていかなくちゃいけないんだ。
中上 だから小林秀雄は、基本的に「日本的」なものがわからない。物語を熟知していないし、過敏じゃない。それからもう一つ、そうかといって、こんどは交通のレベル、あなたが「小林秀雄論」で、片カナふって言っている知(サイアンス)、その意味での科学とおよそイコールで結べるような知性の部分、これすらもないんです。つまり両方ない。
そうすると、彼の「中庸」とは、すべてそこから導きだされると思うんです。たとえば骨董にしても、半可通ということになります。小林さんの骨董は、物がある、判断停止して疑うことなく信じろという形ですが、所持している物をもし偽物だと言われ、気が動転したなら、せいぜい彼がやれることは、どっかに小林さん自身が書いていたけれども、良寛かなんかの掛軸を偽物だと青山二郎あたりに言われて、(※ 逆に、『頭のいい人は(戦争協力について)たんと反省するがいい。僕は馬鹿だから反省しない』とばかりに、青山二郎を)一刀両断に斬り捨てるとか、そういう形です。
たしかに、それは小林秀雄らしい態度です。ところが、その恰好いいことは、彼のアフォリズムと見まがわれかねないような、ああいう文章の詐術みたいなものと一緒だと思うんですよ。バサーッと全部(※ 小林秀雄の論理的な)ごまかしを斬った(※ 批判した)としても、それだけで、彼の骨董に対する態度は変化しない。玩物の弄ぶべき物が、依然として中庸のまま見えない(※ 具体性を持たない)だけです。
柄谷 それは例えば、「真贋」なんていうのもそうだけれども、要するに正しいか間違っているか、というところで真理を考えている。これはハイデッガーが言っていることだけれども、そういう真理概念ができたのは、プラトンからなんだよね。ギリシャ語の原意では、それは存在するものの「隠れなさ」ということだけど、プラトンにおいて「正しさ」ということに転換している。
小林秀雄は、根本的にプラトニストなんだ。永遠なるイデアを求めている。彼は自分の書いたものを削り、書き加えて、どれもこれも同じようなものにしてしまう。「正しい」ことしか言おうとしない。だから、読むと退屈なんだよ。彼は、永遠であるような文学を刻もうとしているわけだけど、テクストの永遠性があるとしたら、それが多義的で読み変え可能、というところにこそあるんだ。
戦争中に書いたものだって、その通り残しておけばよいのに、一体いつどこで書かれたのかわからないように、書き直してある。彼は永遠たらんとしているけれども、そんな文章はテクストにならない。なぜなら、一つの意味しかないんだからね。読み返せもしない。どれを読んでも同じなんだから。彼のテクストは、意識的に管理されている。
われわれが昔の作品を読むときに、正しいかとか間違っているとかで読みやしない。間違っているとしても、間違い方そのものに意味があるんだ。ところが、小林の作品はそうではない。』(P74〜76)

ここで言われていることも、注釈しだすと切りがないのだが、簡単に言えば、小林秀雄の書いているものの「格好良さ」というのは、「役者の名台詞(あるいは、見栄)」みたいなものだ、ということである。
つまり「小難しい思考や論証抜き」で、「もっともらしい、耳あたりの良い結論」だけを与えてくれる。
だから、ものを考えたくない人には、これはとても便利だし気持ちがいい。
「さすがは小林秀雄、本質を一目で見抜く眼力を持っている」などといって感心するわけなのだが、そんなものは「本質」でもなんでもなく「もっともらしいイメージ」にすぎなくて、要は、存在しない「イデア」でしかないのだ、という話である。
例えば、「本格ミステリとは何か?」というような問いは、イデア論に過ぎない。なぜなら、「本格ミステリ」などというものは、実在しておらず、個々の作品があるだけだからだ。
ただ、それらの作品の中には、いくつかの共通点があり、それらの共通点の中でも特に大切だと思われるものを、ピックアップして定式化したものが、いちおうの「定義」ということになる。「本格ミステリとは、ロジックとトリックの文学である」なんてものも、そうした「意見の一つ」でしかない。
だが、ものを考えない人というのは、多種多様な存在を前にして、それらを考えるなんてことができないので、こうした「もっともらしい定義」を「偉い人」から与えられると、これに飛びついて、これをありがたがる。「自分もそう思ってたんだ!」というわけだ。
だが、こんな人は、何も考えていないだけであり、現にあるものを置き去りにして、ありもしない観念をありがたがり、それを振りまわし、それに振りまわされて生きるしかない、自分の頭をもたない愚か者でしかない。
小林秀雄の文学を、坂口安吾が「教祖の文学」と呼んだのは有名な話だが、その言わんとするところは、これなのだ。
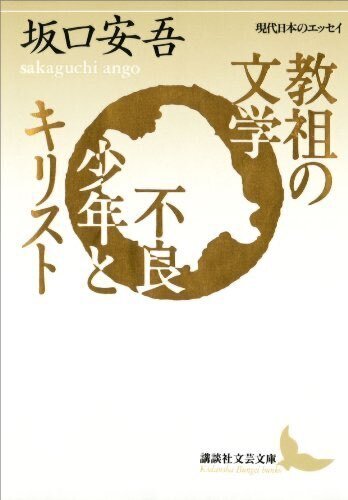
教祖・小林秀雄は、論証抜きに「真理」とやらを語り、信者たちは、それを有り難がって鵜呑みにし、それを担いでまわる。
教祖と同様、彼らには「真贋」つまり「本物と偽物」の二種類しか、世の中にはないと思っている。
世の中にあるものは「比較的正しいものと比較的間違ったものの、無限のグラデュエーション」だなんていう面倒くさい「現実」を見ようとはしない。「白か黒か」の二者択一的な単細胞的思考でしかない。この世の中には「正法か邪法(正統か異端)」しかなくて、我が教祖の語る法門こそが「正法」に決まっており、それ以外はぜんぶ「邪法」に決まっている、というような、度しがたい頭の悪さなのだ。
で、小林秀雄というのは、あらゆる「宗教」と同じで、常に「歴史の改ざん」をしながら、「私は(常に)正しい」とか「私は(間違わない)神である」とやっているような人だから、そんな人の「宗教的文書」など、読むに値しない、ということになるのである。
(2)
『中上 竹田青嗣でも、デビュー作の「金鶴泳論」はすごくいいと思ったよ、面白くって。ところが、そういう人間がずっと書き続けると、だんだんダメになってくるのはなぜだなぜだろう。
柄谷 やっぱり日本的な批評に同化したからでしょう。彼は日本のナショナリストみたいな感じに見える。彼が最もそれに敵対すべきであるのに。江藤淳が昔、俺に言ったことだけれども、批評で最も大事なのはフットワークだね。批評は、いわば運動でしょう。運動は足だからね、フットワークがないと必ず固定しますよ。僕は本来、動くのは嫌いなんだ、面倒くさがりだから。だけど、すごく動いてきたと思う。それ以外ないですよ。運動自体が批評だからさ、柄谷の理論がどうのとを言われても、そんなものはいつでも変わっとるわい、と答える(笑)。』(P152)
竹田青嗣が『日本的な批評に同化』してダメになったというのは、竹田が「在日韓国人二世」であることを踏まえて、語られていることである。
だからこそ、竹田のデビュー作は「金鶴泳論」であり、その頃の竹田には「異物性」という「批評性」があったからこそ面白かったのに、いつの間にか、フッサール現象学の研究者という大学の先生の地位に甘んじて、無難にウケを狙った「解説屋」になったから、批評性が失われて、つまらなくなった、という話である。

最も、私がここを引用したのは、「批評は運動である」というところに、共感したからだ。
およそ、「専門家」だとか「マニア」なんてものには、「批評性」が無い。
彼らにあるのは、「保身」だけであり、「専門」の砦に立てこもって、そこだけは死守しようという、ケチくさい「保守性」だけだから、批評性なんて、無くて当然なのだ。
じっさい、竹田青嗣には批評性がなくても、フッサールその人に批評性があるのは何故かといえば、フッサールのような「先駆者」は、それまでの学問世界の常識に止まらず、みずから討って出て、世界の総体と直に闘おうとしたからであろう。
(3)
『中上 〝柄谷行人を読む〟みたいなセミナーだったな。その過程で、(※ 文芸誌)「文学界」の(※ 対談での)、天皇に関する(※ 俺の)発言が話題になったんだね。浅田(※ 浅田彰)・柄谷対談(「昭和の終焉に」一一「文学界」一九八九年二月号)は、(※ 死にかけていた昭和天皇に額づく多くの日本国民を、「土民」呼ばわりまでして)まさに旧左翼なっちゃったような展開だし、中上と岡野(※ 岡野弘彦)さんと(※ の対談)は、右翼というよりも、〝へへい、(※ 天皇陛下の影響力には)恐れいりやした〟という形になっている。(※ そんなわけで、同志だったはずの)柄谷と中上が、あまり極端に離れすぎているから、それを問題にするというわけで(※ 呼び出されて)さ。なにしろ柄谷ゼミなんだから、俺はつつき回される覚悟で行ったんだ。
柄谷 しかし、学生が「中上VS柄谷」とかで看板を出すかと思ってたら、何もしないし、人数も十人くらいだった。
中上 最後のセミナーだったんだよ。
柄谷 だから、いつもと何も変わらない。静かに話ができてよかった。
中上 彼らはアンダーグラデュエート(※ 大学院生)でしょう。コロンビア大学のアンダーグラデュエートでもあのぐらいにはならないだろうという、世界的に見ても優秀な連中だよ。
柄谷 ふつうはやっぱり、人を呼ぼうとかさ……。
中上 イベントになっちゃう。
柄谷 そう、イベントになるね。ラシュディ(※ が、コーランのパロディ小説『悪魔の詩』を刊行したこと)にしたって、すごい騒ぎになってるけど、ラシュディの仕事は、地味な小さい世界でやってるわけだ。それが表に出ると、突然ものすごい事件になる。だけど今、日本は大きそう(※ な存在に)に見えて、実際に(※ 国際的な広がりを持つ)事件ってないんですよ。だから架空のものを事件にして、人が大勢来たとか、そういう(※ バブルな)感じでしょう。そんな(※ 空疎なから騒ぎをやる)ことで、(※ 世界的に)話が通じてる(※ なんてことがある)はずがないと思うね。小さいところで物を考えることと、国際的であるということとは、ほとんど同じことだと思う。そんな華々しいはずがない。』(P154〜155)
ここで語られていることのポイントの第一点は、私が先日、
『読めない読者大衆によって、〝芥川賞受賞作家だ、直木賞受賞作家だ、ベストセラー作家だ、ジャンルの最前線の作品だ〟などという見えすいた「煽り文句」に飾られた、現役の二流作家ばかりがもて囃され、まんまと売れて、先生ヅラしている』
といった状態を言っているわけである。つまり「田舎者による、田舎のお祭り」のことだ。
これは、オリンピックであれWBCであれ、みんなで一緒に大騒ぎして盛り上がっていれば、自分たちは「世界の中心にいる」というような錯覚の持てる愚かさ、に対する批判である。
(4)
『 中上 ただ、総合雑誌ふうな大仰な振る舞いなんて嘘だよね。総合雑誌の言説なんていうのは、ほとんど甘ったるい通俗的な論理にすぎないものね。
柄谷 そんなもの、読むに値しないね。』(P156)
名指しこそされていないが、ここで言われているのは、この対談の行われた1989年当時、まだ影響力を残していた、岩波書店の『世界』のような総合(論壇)雑誌のこととである。

この雑誌は、その昔(戦後から高度成長期において)、知識人ならみんな読んでいるといった権威を持っていて、この雑誌に寄稿することが「知識人のステータスの証明」のようになっていたほどなのだが、最近では本屋でも目につきにくくなっているし、その存在自体を知らない人も多いのではないだろうか。
私は、たしかまだ『世界』の編集長ではなかった頃の、若い熊谷伸一郎にしつこく噛みついたことがあったのだが、何に噛みついたのかというと、要は「こいつは偽善者」だということである。
外向けにおっしゃることは、なるほどご立派だが、仲間内では馴れ合っているのが、気持ち悪いし、それが「アンフェア」だというような批判だったはずだ。
熊谷が、自分のやってた運動か何かについて「○○さん、番組で取り上げてくれて、いつもありがとう」みたいなことを書いている(たしかツイートしている)のを見つけて、公正中立も客観性もあったもんじゃない「こういう世界なんだな」と、不愉快に思ったのである。
(5)
『柄谷 それは、今の君がやっている熊野大学と繋がっている。その(※ 自分の子供の頃の教育)体験に基づいているのだね。
中上 うん。もう少し自分の問題を整理して言うと、今のロシア、ソビエト(※ の解体と再建)を見てもわかるように、国家がどのように出来上がって、どんなふうに解体していくのか、ということがありますね。しかし僕が見たいのは、それ以前の、ある一つの理想だとか思想だとかいうものですね。それ(※ 理想の国)をどう作っていこうかという熱意、あるいは熱情みたいなもの、と言ってもいい。それが今は(※ 日本では)費えて、何か尻すぼみなっている。
(※ 日本でも)当初は、あのときの子供会の活動とか(※ においてさえ)、教育というものが、ほんとに価値として掲げられていたんですよ。この子たちに教育を与えなくちゃいけないのだ、教育によって人間は変わりうるんだという、自覚と自信みたいなものがあった。それに対して、大人もみんな真面目に考えていた。だから、先生たちが(※ 自分たちの仕事にも、画一化され数値化された)勤務評定を導入され(※ 手足を縛られそうになってい)ると言うので、親たちが、うちの(※ 教育になど興味のない)親までですよ、(※ 日教組の)同盟休校で休校させた。そういう時代の子供でした。
柄谷 戦後民主主義とか言うと嘲笑することが、七〇年代くらいから紋切り型になってきたと思うのだけれど、五〇年代ではそんなことは言えないね。嘲笑はできない。それでは第三世界は絶対に理解できない。』(P189〜190)
これなどもそうだ。今の日本人は、すっかり「負け犬根性」が染みついてしまって「お上に逆らってもダメだ」と諦めるだけではなく、さらには「お上に逆らって、理想を語ろうとする者」を、身の程知らずにも嘲笑して、「我賢し」などと勘違いするような馬鹿ばかりになっている、という現実を批判している。
これは、上の(4)での「熊谷伸一郎批判」と矛盾するように聞こえるかもしれないが、ここ(5)での批判は、「どいつもこいつも信用できない」というようなニヒリズムに発するものではなく、あくまでも「理想」を堅持するからこその、「偽物は許さない」という批判でなければならない、ということだ。
そうでなければ、「第三世界」にはたしかに存在している、「ナイーブなまでの情熱」を、擦れた日本人が、賢しらぶって見誤ることになる、という話である。
○ ○ ○
以上のように、柄谷と中上は、基本「まじめ」なのである。
そんな二人の「盟友」の、打てば響くような対談は、必ずや「闘う人」を励ますものになっていることであろう。
そうでない人には、理解不能ではあろうが、だ。
(2023年8月4日)
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
