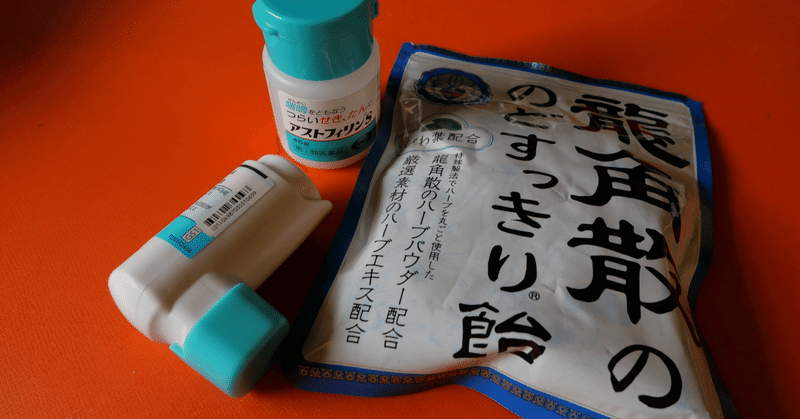
ぜんそくについて 宮古島のきわめて健康コラム
喘息(ぜんそく)は、発作を起こさない人にとってあまり身近に感じない疾患ですが、喘息患者は年々増えており、軽い症状を含めると小児で5%、成人で3%に達するといわれています。また現在、喘息発作で亡くなる人は年間約6000人いるとされ、横ばい傾向にあり、この約10年減少していません。今回は「ぜんそく」について取り上げ、快適な生活を送るための身近な対策についてご紹介しましょう。
ぜんそくの症状
喘息とは、一言で言うと「気管支の炎症」です。
私達は生きていくために呼吸によって空気中の酸素を取り入れ、不要になった二酸化炭素を体外に排出しています。空気の通り道である気道の内側にある粘膜は空気といっしょに吸い込まれてくる異物(ほこり、花粉、チリ、ダニ、細菌、ウイルスなど)を排除するフィルターの働きもあわせ持っています。喘息患者では普通の状態なら何の反応も起こさないちょっとした刺激でも過剰に反応し、気道の粘膜に炎症を生じます。

上記のように空気の通り道である気道が狭くなると息をし
ずらくなり、息切れや喘鳴(ゼンメイ)を起こします。
ぜんめいとは
細くなった気管を空気が無理に通る時の「ゼイゼイ、ヒューヒュー」という音です。胸苦しさを感じたり、痰がたまった状態になり咳が出ることもあります。発作がひどくなると呼吸困難になり苦しくて横になっていられず、前かがみに座って呼吸するようになります。さらには血液中の酸素が少なくなりチアノーゼ(唇や爪、顔の色が紫色になる)をおこします。酸素不足が脳にまで影響を及ぼすと意識がうすれ失神したり、しまいには、窒息状態におちいり喘息死をまねくこともあります。
アレルギー疾患はとかく遺伝や体質だからしょうがないと思われがちですが、喘息は
単に体質だけで起こるのではなく様々な要因が影響し合って引き起こされる多因子性疾患です。起きてしまった発作を抑えることももちろん大切ですが、発作を起こさないようにする予防療法も重要です。発作が起きると気道粘膜に炎症が残り、次の発作の下地となり悪循環を引き起こします。

医師から処方される薬と共に、図を踏まえた上での個々に
合わせた自己管理を行なうことで喘息をコントロールすることができます。
気道粘膜を健康に
ぜんそくの人に共通してみられるのが気管支などの気道が刺激に対し、とても敏感であるということです。かぜをひいたり、たばこや大気汚染などで粘膜が傷つけられていると異物の身体の侵入がたやすくなり、気道は敏感になってしまいます。現在発作のない状態にも継続的に薬をもちいて気道の炎症を抑える予防療法が、行われていますがバランスのとれた食事をとりミネラル、ビタミンの補給を十分に行いましょう。
喘息と心の問題
喘息に限らず、心理的因子、精神的ストレスは、いろんな疾患に悪影響を及ぼします。
喘息発作で起こる呼吸困難は、「息が出来ない=死」をイメージさせ、その恐怖感や不安は、発作を持続させ、また次の発作を誘発します。夜中や明け方に発作は起こりやすく、まわりへ迷惑をかけているといった負い目や治療がなかなかうまく効果を示さない場合には苛立ち、精神的ストレスを強く感じます。ストレスは免疫の働きを狂わせ、アレルギー反応を起こしやすくし、自律神経のバランスを乱し、気管支平滑筋を収縮させたり、気道粘膜の働きの異常をまねきます。人の性格や考え方は当然違うので、治療や病気に対する考え方にもズレがあります。本人、親子を含め周りの協力と理解をコミニュケーションで確認し合い、リラックスすることが心理的負担を軽くします。
環境の整備
子供の喘息は、アレルギー反応によって引き起こされることが多く、
その場合はアレルギーを引き起こす原因となる物質(アレルゲン)
を遠ざける必要があります。小児喘息の約90%のアレルゲンがチリダニであるとされ、最も大きな原因となっています。これらが微粒子となって空気中をただよい、それを吸い込むことによって発作を引き起こします。特に、ハウスダスト(家のほこり)によって引き起こされるぜんそくが、増加傾向にあるのは、最近の家屋が人にとって住み心地の良くなった分、ダニやカビにとっても発育・繁殖がしやすくなっているせいともいえます。寝食の中心の場である住まいの環境を出来る努力からはじめ改善しましょう。

発作時に避ける食事
おもち、もち米が含まれるお菓子、パン、青魚、味の濃い食事、甘すぎるもの、辛すぎるもの、マンゴー、キウイ、パイン、アボカド、カフェインなど
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
