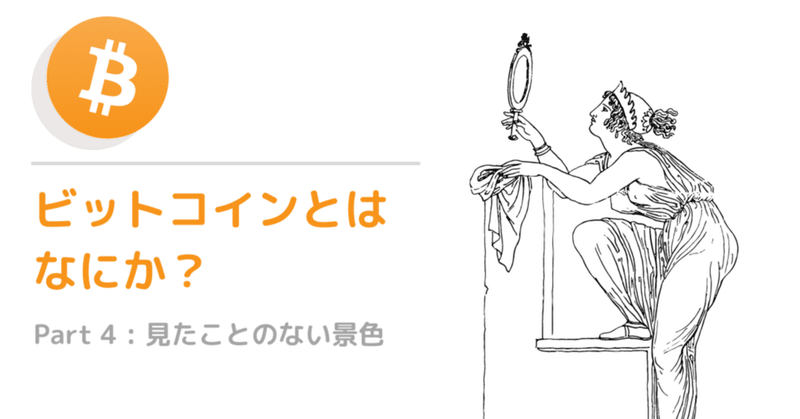
ビットコインってなんだろう?(Part 4)
みなさんこんにちは。ネコバンです。
⚠️補足:これは2022年のアーカイブ記事です
この「ビットコインってなんだろう?」シリーズは、2022年に、自分のブログで掲載していた記事の再掲です。サーバーを借りて、WordPressでサイトを構築して、記事を書いて・・・というスタイルで半年くらい続けましたが、典型的な敗北パターン(収益化の壁&工数の壁にぶつかり)により、続けるのが困難になったため、ブログは閉鎖して、記事だけnoteに引っ越してきました。
いま読み返してみると、ちょっと・・・というところもありますが、手を入れ始めると収拾つかなくなりそうなので、アーカイブ的な位置付けで、押し入れの奥に眠っていたちょっと恥ずかしい昔の日記・・・といった風情で、あえてこのまま再掲させて頂きます。
ちなみに、2023年12月9日現在、ビットコインは冬の季節を乗り越えて、1BTC = 44,000ドルまで回復しており、これから半減期に向けて、さらなるジャンプアップを控えている・・・という、素敵な季節がきています。これを機会に、ビットコインの魅力とその将来性を少しでも感じて頂ければ幸いです。このビッグウェーブを一緒に楽しみましょう!
@はじめに
Part3では、ビットコインがどう世の中に受け入れられたかをお伝えしました。受け入れられた場所には光があり影があり、ビットコインは運命の大波に大きく揺られながら、その長く曲がりくねった旅路を粛々と進んでいきます。歴史としてはちょうどこのあたりが中盤地点となり、いまの我々が知っている仮想通貨の世界に少しずつ近づいて来ているような気がします。それではPart4をお楽しみください。
▶︎ この記事に書いてあることの要点
・ビットコインの成長
・仮想通貨バブルと冬
@2015年
▶︎ 年初の価格:1BTC=34,000円
ビットコインの歴史から外れるのでこれまでスルーしてきましたが、このあたりからアルトコインと呼ばれる、「ビットコイン以外の仮想通貨」が増えていきます。取引価格No2のイーサリアムも、2015年7月30日に正式ローンチされており、ここからイーサリアムをベースにした様々なブロックチェーンのサービスが花開いていきます。
2015年1月6日
Bitstampがハッキングされて約2万BTCが流出2015年5月
ニューヨーク州金融サービス局(NYDFS)が仮想通貨事業資格として「BitLicense」の施行を発表2015年10月
欧州司法裁判所がビットコインの取引はVAT(付加価値税)の課税対象外であると発表
そんな感じで始まった2015年ですが、年始からまたハッキングです。Bitstampはヨーロッパ圏だと最大の老舗取引所で、いまでも人気がありますね。ハッキングされること自体はもちろん不名誉ですが、それによってセキュリティ対策が強化され、よりよいサービス体制になっていくものです。何度もハッキングされる取引所は危ないですが、一度ハッキングされてその後しっかりと立ち直っている取引所は、まったくハッキングされていないところよりも安全なのかも、という考え方もできるかもしれません。
悪名高い?BitLicenseについて。これはニューヨーク市がビットコインビジネスを監督し、その安全性を担保し、ユーザーを保護する目的で施行されました。これによって、申請をして許可を得た業者だけがビットコインを扱うビジネスを展開することができ、市民の安全が確保されるというわけです。しかし実態としては、申請には時間とお金がたっぷりかかり、かつ審査基準も厳しいため、中小の暗号資産企業はニューヨークから出ていくことになり、問題視されるようになりました。直近でもこんなニュースが。
4月27日にロンドンで開催されたクリプト&デジタルアセット・サミットでの基調講演において、ニューヨーク市のエリック・アダムス市長は、ニューヨーク州での仮想通貨規制「ビットライセンス」について、それがイノベーションと経済成長を阻害すると主張"ニューヨーク州は仮想通貨企業にライセンスを求める唯一の州だ。それは高い障壁となっており、競争力を低下させるだけだ。私たちは競争力を維持し続ける必要がある"
このアダムスさんは自分の給料をビットコインで貰っているようで、ニューヨークを暗号資産の中心にしたいという熱い思いをお持ちの方のようです。日本にもこれくらいの思いを持つ議員がいると、面白くなりそうなんですけどね。ちなみに、日本でも、例のMt.Gox事件がきっかけで法整備が進み、金融庁に許可された取引所じゃないと運営が認められません。これによってニューヨークと同じような現象が起こっており、日本から撤退したり、日本を避けて事業展開する国際企業がいるのが実態です。難しいですね。安全面を優先すればイノベーションは起こりにくくなり、イノベーションを優先するとリスクを負うことになり・・・
@2016年
▶︎ 年初の価格:1BTC=51,000円
2016年も恒例イベントである取引所ハッキングから始まります。
2016年3月1日
DMM.comでビットコイン決済を受付開始2016年4月27日
PCゲームのDL販売プラットフォームSteamでビットコイン決済を受付開始
2016年8月2日
Bitfinexがハッキング被害を受けて12万BTCが流出
この流出金額はかなり多いですね。ちなみに取引所のハッキングの際はバウンティ・プログラム(報奨金制度)がよく使われるのですが、この時も、取り戻してくれた人にはその額の5%を支払うという褒賞が提示されました。バウンティ・プログラムは、プログラムのバグ探しや脆弱性探しでも使われることがあり、ホワイトハッカーの活躍の場になってますね。
上の二つは、ビットコイン決済サービスの開始です。ついに・・・という感じですが、いくつかの課題にぶつかり、Steamのほうは翌年には決済サービスを停止してしまいます。
💬 外野スタンドからの声
「ギブアップ早過ぎへんか」
🐈⬛ ネコバン
「そうですね。もうちょっとがんばってほしかったですが、処理にかかる
時間や、その間の価格変動など課題が大きかったようで・・・」
日本でビットコイン決済を受け付けている有名店といえば、ビックカメラ、コジマ電気、ソフマップ、メガネスーパー、といったあたりで、そのほか小店舗、個人店舗や、ECサイトなどでも利用可能なところはありますが、普及しているか?と聞かれれば、2022現時点でも普及はしてるとは言い難いです。理由は上記の通り、やはり価格変動リスクが大きいですかね。直近でもそうですが、価格が1日で数十%変動するのも日常茶飯事なので・・・。また、日本はクレジット決済も浸透している中で、電子マネー決済の普及し始めたところだったので、タイミング的にはちょっとぶつかっちゃった感じです。
@2016年
▶︎ 年初の価格:1BTC=123,000円
BTC価格、ここで一気に上がりましたね!
2017年1月5日
ビットコインが2013年以来の再高値を更新2017年4月1日
改正資金決済法が施行2017年8月1日
ビットコインのブロックチェーンが分裂してBitcoin Cashが誕生2017年8月24日
スケーラビリティ解消のためSegWitが有効化される
この時期、国内のニュースメディアでビットコインが取り上げられるなどで一気に認知が進み、年初の時点で、Mt.Gox事件以来の最高値を更新します。同年の12月8日には1BTC=1,942,438円まで上がり、アルトコイン も含めて仮想通貨バブルの到来です(もちろん、翌年バブルは盛大にはじけるわけですが・・・)。
改正資金決済法は、仮想通貨が「モノやサービス」ではなく、「通貨」であり「決済手段」であることが定められたことになります。これによって、ビットコインを買うたびに必要だった消費税は撤廃されました。当時は、ビットコインを買うときと、ビットコインで何かを買うとき、それぞれ別々で消費税がかかってたんですね。また、取引所も登録制となり、利用者保護の法整備が一気に進むのもこの時期です。
そして、ブロックチェーンの分裂について。経緯はざっくりとこんな感じです。
ビットコインの処理速度の問題が勃発
解決策として、ブロックチェーンのブロックサイズを大きくするかどうかで、開発コミュニティーの方針が分かれる
ブロックサイズを大きくする道を選んだコミュニティーが分裂して、ビットコインキャッシュ(BCH)を構築
うーん。すごいですね。バンドのベーシストが音楽性の違いで脱退して、サイドプロジェクトを正式結成する、みたいな感じでしょうか。ここではまさに思想の違いによる分裂です。処理を早くするには、データを入れる箱であるブロックサイズを大きくすればいいけど、セキュリティリスクを生むことになり、ビットコインを危険に晒すことになる・・・といった議論ですね。ちなみに仮想通貨の世界ではこの分裂のことを「フォーク」と呼び、二種類のフォークがあります。
💡フォークとは?
・ハードフォーク:ルールの範囲を緩和/広げるなどの根本的な路線変更に
踏み切る場合で、ブロックチェーン自体が分裂する
・ソフトフォーク:仕様のアップグレードなど、基本路線はそのまま
なのでブロックチェーン自体は分裂しない
💬 外野スタンドからの声
「あれか、ハードフォークは喧嘩して別居して離婚。
ソフトフォークは協議して基本契約の一部を変更、みたいな感じか」
🐈⬛ ネコバン
「ええと・・・例えが唐突で頭に入ってこないですが、
っていうか、基本契約を結んでる夫婦ってどうなんですか」
仮想通貨のフォークは結構ちょこちょこ発生しているようで、イーサリアムもハードフォーク発生によって、イーサリアムとイーサリアムクラシックに分裂してます。私はどういうわけかこのフォークの概念が好きです。
また、このハードフォークによって本家のビットコインは守られたものの、処理速度の問題は依然として残り続けたため、その対処としてこの「Segwit」という機能が実装化されました。
💡Segwitとは?
Segwitはブロックチェーンのブロックサイズを大きくするのではなく、ブロックに入れるデータそのものを小さくする仕組み。ブロック内の情報である「インプット」、「アウトプット」、「電子署名」のうち、唯一移動が可能な「電子署名」だけを、別の区画で管理することでデータを圧縮し、処理速度を速める
このSegwitは2014年頃から議論され始めましたが、ブロックサイズを大きくするか(ビットコインキャッシュ)、データを小さくするか(Segwit)で長い間もめた末に、やっと達成されたようです。このように、ビットコインは何か仕様変更をする際に開発チームやマイナーの合意を得ることがとても大変なのですが、逆に言うと、簡単に仕様変更できないからこそ安心できるという側面もあります。
@2018年
▶︎ 年初の価格:1BTC=1,700,000円
年初はまだ去年のバブル状態が続いていて、価格はいい感じですが、Coincheckを始めとするいくつかのハッキングによって価格が暴落し、仮想通貨の冬がやってきます。
2018年1月15日
Lightning Networkを利用した初めての取引が行われる2018年1月26日
Coincheckがハッキング被害を受ける2018年1月30年
Facebookで仮想通貨関連の広告が全面禁止2018年3月
Google/Twitterが仮想通貨の広告掲載禁止を発表
まずLightning Networkですが、これは2017年でもお話しした「スケーラビリティ(処理速度)」問題解消のための仕組みのひとつです。先述したSegwitはデータの電子署名部分を、メインのブロックチェーン上ではなく、サイドチェーン上で処理をするという仕組みでしたが、このLightning Networkでは、不特定多数のユーザー同士の送金処理をサイドチェーン上で処理して、その処理をまとめてブロックチェーンに書き込むことで、ブロックチェーン上での処理回数を減らして処理速度を上げるという仕組みです。
とても便利そうですが、SegwitもLightning Networkも、取引所やウォレットサービスがまずその機能に対応する必要があり、すこしずつ浸透が進んでいっている、というのが実態のようです。これから普及していくのかな?
CoincheckのハッキングについてはWikipediaから・・・
2018年1月26日 00:02:13から08:26:13にかけて、コインチェックが保持している暗号資産のうちNEM(ネム)(通貨記号はXEM)建ての顧客資産がクラッキングにより取引所から外部に送金され、さらに別口座に移転されてほぼ100%流出してしまう事態が発生した。…ほとんどの暗号通貨の入出金および売買そして資産の日本円出金もできなくなっていると知った顧客の間で大騒ぎとなり、午後から深夜に至るまで東京都渋谷区の本社前は、顧客数十人、報道陣、警察官、見物人でごった返し、「2億返せ」「どうなっているんだ」などと怒鳴る人もいた
「2億返せ」がいいですね、なかなか壮絶な感じです。
ちなみに、「ハッキングされた」被害者ではあるものの、当時のCoincheckは「ホットウォレット」で顧客の資産が保管されており、その脆弱性を攻撃されたというのが実態となります。
💡ホットウォレット
特徴:インターネットに繋がっている
形態:取引所のウォレット、アプリのウォレット、など
💡コールドウォレット
特徴:インターネットに繋がっていない
形態:USBタイプのハード端末、紙、など
紙、というのはどういうことかと言うと、送金などで必要なウォレットの秘密鍵のアドレスを紙に書いて、金庫などにしまっておくというアナログスタイルです。アナログですが、かなり安全性は高いです。また、この事件以降、ほとんどすべての取引所で、顧客資産はコールドウォレット管理に切り替わっているので、2022年現在ではだいぶ安全になりました。ただ、取引所のハッキングはいまでも続いてますので、万全を尽くすなら、仮想通貨を取引所のウォレットに入れたままにせず、自分の秘密鍵で管理できるウォレット(Metamaskとか)や、ハードタイプのウォレットで管理するほうが良いでしょう。
Facebook、Twitter、Googleの広告禁止については、当時の取引所ハッキングだったり、マネーロンダリンングへの懸念が強まるなどの背景から、禁止に踏み切ったようですが、その後、各社それぞれ解禁、緩和への揺り戻しが起こっています。社会影響が大きい企業は世論にあわせてこういう意思表示をしっかりしますが、なかなか難しいですよね。
@まとめ
Part4は以上です。ふう・・・
💬 外野スタンドからの声
「なんか思ったより長編化してへんか。いつ終わるんやこれ」
🐈⬛ ネコバン
「はい・・・まさかこんなボリュームになるとは、想定外でした。
ちょっとビットコイン舐めてました」
いやほんと、ビットコインというか、仮想通貨の歴史みたいな雰囲気になって収集つかなくなりそうですが、なんとか最後まで走りきりたいと思います。
>Part5に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
