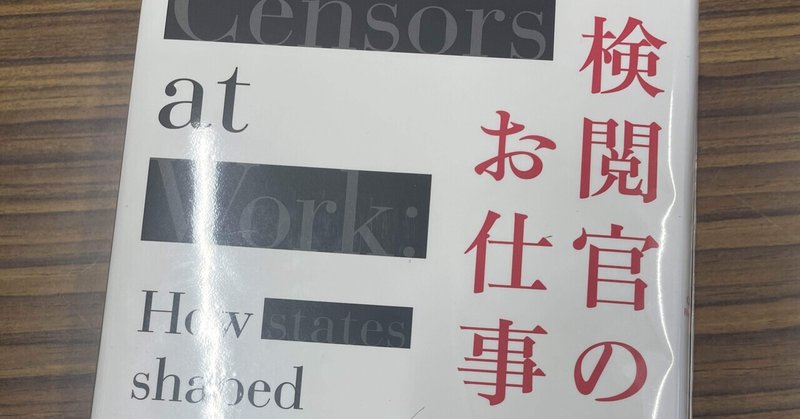
R.ダーントン『検閲官のお仕事』
ロバート・ダーントン [著]ほか. 検閲官のお仕事, みすず書房, 2023.12. 978-4-622-09663-4. https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I033182046
訳者のお一人、上村さんからいただいた。
上村さんはハプスブルクの歴史がご専門なのだが、当該期のメディア史、出版史を専門とされていて、私の学部時代から大学院博士課程までの数少ない同期の一人である。時期もフィールドも若干違っていたが、近代日本はドイツを範としていたし、古典作品の受容に関しては、在学中から上村さんに色々教わっていた(何かの折に、高山樗牛の旧蔵書にレクラム文庫版の『賢者ナータン』がある話をして、院生室でレクラムとかドイツの出版のことを教わったのを未だに僕は覚えている)。
そして、ロバート・ダーントンといえば、フランス革命前後の出版の歴史はもちろん、書物の歴史を研究する上で、その名前を外すことができない人だ。そのダーントンの著作を、上村さんが翻訳される・・・最初この話を知ったときからとても楽しみな本であった。
時期・地域を異にするが、本書ではブルボン朝フランス、英領インド、共産主義下の東ドイツという3つの権威主義的な国家体制下で行われていた検閲を素材に「検閲とは何か」という問いに比較史的に答えようとするものである。ざっくり、18世紀と19世紀と20世紀ということでもあるだろう。
そのなかで描き出されるのは、検閲官が言論を一方的に抑圧したのではなくて、著者たちと交渉したり協力したり何らかの共犯関係を結びながら出版にこぎつけていくプロセスを含んだ検閲の多様性である。
第2部で出てくる、インド大反乱の後のブリテン統治下ベンガルにおける「目録(カタログ)」作成。これは、日本の図書館史のなかで取り上げられてきたことはほぼ無いと思うし、また日本の近代化のなかで日本人が知ることもなかったと思うのだが、納本制度とセットになった監視であるし、また図書館員が検閲に参画していく事例として非常に興味を惹かれた。
近代日本の事例だと千代田図書館に残っている蔵書類がまさに「検閲官のお仕事」を知るための格好の素材となるのだろうが、検閲官の仕事を狭く限定することに警鐘を鳴らしている本書の立場からすると、舞台は、著者の側や、編集者や図書館という空間にも広げていくべきなのかもしれない。
なお、結論で述べられる「検閲制度」とは、どういう体制下でも「意味をめぐる戦い」であって、そのような議論では必ず「読者の反応を考慮することが求められる」といい、それは文学理論家が好んで扱う主題であるという以上に「検閲官にとっては常に現実的な問題であったのだ」(263頁)という記述は、個人的に物凄く巨大な示唆を得た。何か自分の研究の方向性にそのまままっすぐ進めと号令をかけてもらったような。
そのほか、著者ダーントンの文書館に対する没頭するほどの愛情(それは人類学者のフィールドワークに相当するものとされる)も、あちこちから感じられて嬉しくなった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
