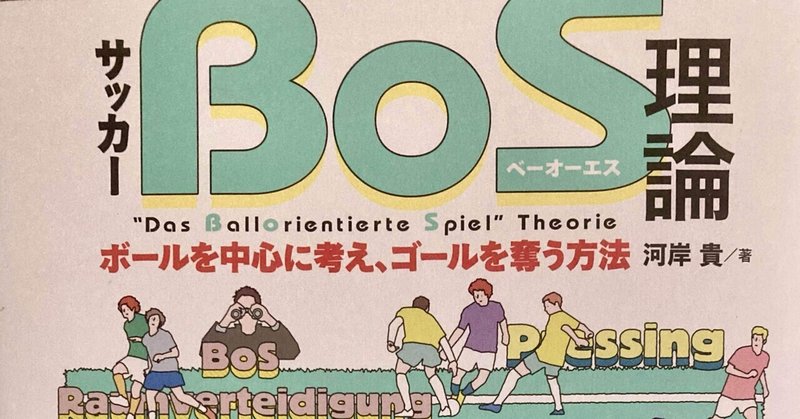
ボールを保持してない時間でもサッカーは「攻撃的」かつ「魅力的」になるのか?―河岸貴『サッカー「BoS理論」』
1.この戦術本に「くらった」
サッカーの戦術に関する本(戦術本)で久しぶりに「くらって」しまった一冊だ。
著者の河岸さんが紹介する「BoS理論」とはドイツで用いられているプレーコンセプトだ。BoSとはDas Ballorientierte Spiel(ダス・バルオリエンティールテ・シュピール)といい、本書では「ボールにオリエンテーションするプレー」と訳されている。オリエンテーションは「方向づけ」というニュアンスであり、「ボールを中心に考えてサッカーをする」というBoS理論の考えを象徴する言葉だ。本書はBoS理論の「ボール奪取」の部分にしぼって書かれている。
戦術本は人によってしっくりくる本とこない本がはっきり分かれる。しっくりくるか否かはその人が読んだ時期はもちろん、知識量や影響を受けたチームと選手などが背景となり形成されるサッカー観に大きく左右されるのだ。
本書は僕にとって非常にしっくりきた本だった。もし「きみにとっての面白いサッカーとは何か?」と聞かれたら「この本に書いてあることだ」と僕は答えるだろう。
なお僕は「ヨーロッパの最先端のトレンドを教えてくれる!僕もこれでトレンドを知ったぞ!」や「日本サッカーにダメだししまくって胸がスッとした!」なんてつまらない理由で「くらった」わけではない。ではどんな理由か。それをこれから明かしていく。
2.目的からの逆算で導かれるボール奪取の論理
本書は様々なシチュエーションにおけるボール奪取のプレーについて解説してる。特徴的なのは、すべてのプレーに対して目的と理由がセットで明確に示されているところだ。
プレーの目的はひとつだけ。「ボールをゴールに入れる」ためだ。あらゆるプレーがこの目的から逆算される形で説明される。
たとえば敵陣でボールを奪われたとき、即座に奪い返そうとするプレーがある。獲られたら獲りかえす。当たり前の話だ。BoS理論ではここに「なぜ自陣に戻らず敵陣でボールを奪いに行くのか」という問いが間にはさまり、理由が明確に提示される。
それは単純明快で、敵陣でボールを奪ったほうが相手ゴールに近いからです。何度でも言いますが、ドイツはボールをゴールに入れることがプレーの中心に据えられています。
ここでも大事にされているのは「ボールをゴールに入れる」という目的だ。目的から逆算して理由を導き出されている。
陣形をコンパクトにした方がいい。このプレー自体がよさげなことはなんとなく分かるはずだ。BoS理論は「なんとなくよさげ」という点をよりはっきりさせている。
なぜコンパクトにしなければいけないのかと言えば、横幅をタイト、縦幅を短くすることによって、必然的に相手がプレーをするスペースを奪うことにつながるからです。プレースペースが狭くなれば狭くなるほど、そのプレーに制限がかかるのは言うまでもありません。ボールに対してコンパクトにすることで相手のプレースペースを奪い、イニシアチブを取ってボールを奪いに行き、奪った場所では数的優位となるので、ゴールチャンスが創出できます。
敵陣でボールを奪う話もコンパクトの話も重要なのは、理由の回答が「こうすればボールを奪えるから」で終わらない点だ。「こうやってボールを奪いゴールに近づくことができて、ゴールできるから」という形が取られてる。「ボールをゴールに入れる」という目的にしっかり重きを置いた説明だ。
僕は「そもそも」という言葉を使うのが、文章や思考のクセになっている。どんな物事でも「目的はなんなの?」ということを真っ先に考えていく。この思考のあり方が軸になっている僕には、「目的と理由」が明確で必ずセットになっている本書のスタンスはとても自分に合っていた。
3.イメージを一致させる言葉の緻密さ
起きている事象を言葉で明確に定義する際に大切なことは「イメージの一致」である。いくら細かく言葉で定義したとて、定義を元にそれぞれの頭に浮かぶイメージが異なれば定義の意味がない。
あるいは当初思い浮かべていたイメージと不一致なのに、言葉の強さに引っ張られて言葉の方をイメージに上書きしてしまう。あたかも初めからそのイメージを見ていたかのように乗っ取られるのだ。
本書はサッカーを見ていてなんとなくふんわりして形で持っていたイメージと見事に一致する言葉を与えてくれる。その緻密さが強みだ。僕はイメージと言葉をつき合わせてすり合わせながら読書することができた。
僕を含めサッカーファンは最近よく「プレスがハマっている」と口にするようになった。ではこの「ハマっている」とはいったいどういう状態か。プレスによってボールを保持している相手が身動きとれずにボールを奪えそうな状態のようなイメージをみなぼんやりと持っているかもしれない。
本書ではこの「ハマっている」にも「ジャストタイミングのアタック」という定義がされている。
では、「ジャストタイミングのアタック」とは、どのようなシチュエーションなのでしょうか?「ジャストタイミングのアタック」を成立させるためにはどのような条件が必要なのでしょうか?それは、バイエルン・ミュンヘンのMFキングスレー・コマン選手が行ったように、ボールが相手に到達すると同時にアタックする選手自身も相手に到達している状況こそが、「ジャストタイミングのアタック」となります。そして、この「ジャストタイミングのアタック」を可能にする基本的条件、目安とは、プレスをかける選手の移動距離がパスの距離に対して2分の1であることです。
「ボールと味方が同じタイミングで相手に到達できる」状況こそ、まさに「ハマっている」状態なのだ。確かに僕らが「ハマっている」と思っている状態を思い出すと、相手にボールが渡った瞬間すぐに奪取したり、ボールが到達する前にカットして奪取している。
4.ボール保持だけが「攻撃的」ではない
本書の「ボールにオリエンテーションする」という発想を読んで、僕はかつてマウリツィオ・サッリやマルコ・ジャンパオロが率いてたときのエンポリ(イタリア)を思い出した。2012~2016年のことだ。エンポリは人口5万人の街がホームの小さなクラブ(プロビンチャ)である。
このときのエンポリはどんな強敵だろうとも、DFラインを非常に高くして極端にコンパクトな陣形でゾーンディフェンスにて高い位置からボール奪取を試みていた。奪った場所によるが一度ボールを保持すると素早く作ったトライアングルの連続によるパス交換でゴールに迫る。それはそれは本当に見ていてわくわくしたサッカーだった。
今とは時代が違う。使っている用語も違う。イタリアとドイツでそもそも国も違う。でも僕は本書を読んであのころ見た面白いサッカーが言葉になって再び現れた感覚になった。
なぜエンポリのサッカーにわくわくしたか。今になって振り返ると「ボールを保持しているときもボール奪取のときも面白くてわくわくして楽しそう」だったからではないだろうか。言葉の定義の仕方を散々褒めたあげく急にふんわりした表現になって恐縮だが、僕の実感はそんな感じだ。
様々なチームを見ていると、ボールを保持しているときはドリブルするもパスするのもとにかく楽しそうでぽんぽんボールが回って面白いチームに出会う。でもその面白いチームの中には、ボール奪取のときにはとにかくしんどそうにしか見えず面白さを感じないチームもいる。まるで罰ゲームのように。
もちろんボールを持っている方が楽しいのはサッカーで当たり前だ。だがボール非保持の時間がどうしても生じるのもサッカーである。「100%支配できればいい」で終わるのではなく、その非保持の時間をどうクリエイティブにデザインするかもサッカーの面白さではないか。
世の中にはボール保持率やチャンス数、得点数だけみて「攻撃的」だと触れ回っているケースもあるらしい。それも一つの考え方だろう。でも本当の「攻撃的」とはボール保持も非保持も攻撃的であることだと僕は思っている。絶えず積極的にボールにオリエンテーションする。これが攻撃的ではないか。「攻撃的」とはボール保持だけにあらず。少なくとも僕の応援するサッカークラブにだけはこうあってほしい。あくまで理想だが。
長くサッカーファンでいると「サッカーファン人生のターニングポイント」になる瞬間に何回か出会う。僕にとってその一つがサッリとジャンパオロのエンポリとの出会いだ。自分にとって「これが面白いサッカーなんだ!」とわくわくした原点を思い出させてくれた一冊である。感謝したい。本書を読み終えたとき、僕のように「ああ、もっとサッカー見たいな」と思う人が一人でも増えれば幸いだ。
【本と出会ったきっかけ】
もともと本の存在は知っていたが、著者の河岸さんと酒井高徳選手(ヴィッセル神戸)の対談動画が非常におもしくて興味がわいたため。
本の購入費に使わせていただきます。読書で得た知識や気づきをまたnoteに還元していきます!サポートよろしくお願いいたします。
