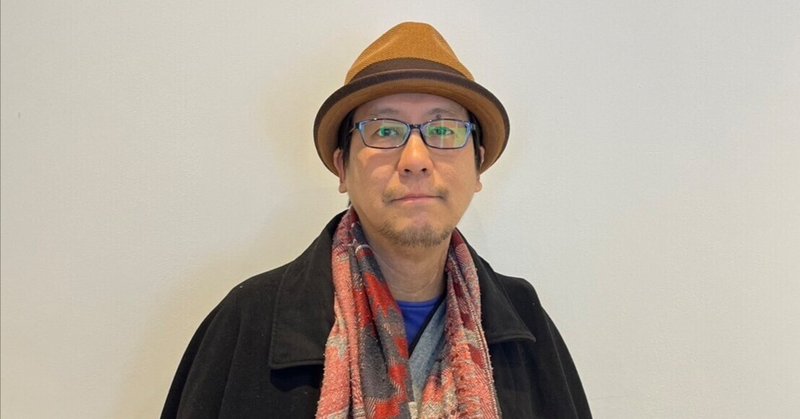
文化系の謎のキャリア・インタビュー11 陸奥賢(むつ・さとし)さん 「目の前のことに向き合い、考え続ける」
(記事担当:坂倉義基)
はじめに
文化系の謎キャリア・インタビュー、坂倉の担当回は、現在コモンズ・デザイナー、観光家、社会実験者として活躍をされている陸奥賢さんにお話を伺った。まわしよみ新聞、直観讀みブックマーカー、当事者研究スゴロクなど様々な「遊び」を作ってきた陸奥さんとは、大学の講義で初めてお会いした。
ちなみに「まわしよみ新聞」とは、興味のある新聞記事を切り抜いたうえで討論しながら壁新聞を作り、話題を共有するワークショップで、2012年に陸奥さんによって考案された。以後子供たちが現代社会について主体的に学ぶ方法として全国に広がり、2017年には第66回読売教育賞のNIE(ニューズペーパーインエデュケーションの略)部門にて、最優秀賞を受賞している人気プロジェクトなのだ。

「直観讀みブックマーカー」とは、読書に偶然性や意外性を取り入れ、読み手が意識しないところで読書の道徳的、理性的な特性をグループで楽しみ、その場で出逢った言葉によって本の栞を作るという、知的なゲームである。

そして「当事者研究スゴロク」は、失敗・挫折・苦労エピソードを話して、その「衝撃レベル」をみんなで評価することで、自分の失敗、挫折、苦労を「大変だと思ってたけど3コマぐらいなんだ」とか「6コマレベルですごいといわれた!」といったように相対化する。やればやるほど、「6コマレベル」を目指したくなるので、どんどんとみんなが、より衝撃の失敗・挫折・苦労エピソードを語りだす……という「弱さの情報開示」が進む効果がある。

私は講義の中で様々な遊びを経験させていただき、遊びを制作する面白さ、難しさを学んだ。そして今回の「謎キャリア」ということを考えたときに、陸奥さんがぴったりだと感じた。現在の陸奥さんを作っているもの、キャリア、考え方などをお答えいただいた。
陸奥賢(むつ・さとし)
観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者。昔は「大阪あそ歩」(観光庁長官表彰受賞)。今は「いわき時空散走」のプロデューサー。他にも大阪七墓巡りプロジェクト、まわしよみ新聞(読売教育賞受賞)、直観読みブックマーカー、当事者研究スゴロク、歌垣風呂(京都文化ベンチャーコンペティション企業賞受賞)、死生観光トランプなどを考察。大阪まち歩き大学学長。慶典院寺町倶楽部世話人。1978年生まれ。
世の中の様々なアルバイトを100個やろうって決めた
―本日はコモンズ・デザイナー、観光家、社会実験者として活躍をされている陸奥賢さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
陸奥賢(以下 陸奥):何でも気軽に聞いてください!
―今回のテーマが「謎キャリア」ということで、プロデュースにまつわる学科の授業がきっかけで陸奥さんを知りました。陸奥さんは大阪市住吉区生まれ、堺市育ちとお聞きしました。学生時代どんな学生でしたか?
陸奥:僕は小学校と中学校しか行ってなくて。成績は良いほうでノートとかは取ったことがなかったんですよ。教科書とか全部見てわかるし覚えちゃうから、ちゃんと覚えたかどうかを確認するテストをやる意味がわからなかった。「テストって何のためにやるんやろう?」「学校って不思議な場所だなぁ」って思ってました。ただ母親が某日蓮系在家教団の二世信者で、めちゃくちゃ活動に熱心な人で、僕もこどもの頃から無理やり信仰を強制されていたんですが、小学校高学年から中学校の時に、その某教団の教えや考え方にいろいろと反発を覚えて、12歳のときに教団の活動や信仰をやめる!と宣言しまして。それで母親や母方の親戚一同との関係が一気におかしくなって、やさぐれていきました。実家に依存しない、自分の生き方を考えざるを得なくなって模索し始めて、それで中学校を卒業したら、すぐにアルバイトをして自分で身銭を稼ぐことを覚えてフリーターになった、という感じです。
―フリーターの間はどんな経験をされましたか?
陸奥:15歳から始めて、最初にやったのが「中華料理T」というお店のアルバイトです。広島出身の店長のお店で、バイト募集の貼紙を見て履歴書を書いて応募しました。15歳やからとくに書くことなかったんですが…(笑)。電話して翌日、店に向かうと、履歴書を持って来たのに何も見ずにメニュー表を渡され、「とりあえずこれ明日までに覚えてきて。長靴買って明日の夕方六時に来て」 と返されました。面接も何もなく、それで一夜漬けでメニュー表を覚えました。
翌日行くと「お!来たか!ちょっと裏回って」と店長に言われてバックヤードに回された。そしたら店長が冷凍エビを持ってきて、「バケツにエビを浸す、そして皮をむく、それをパレットに置いていく。こんな感じや。これやっといて」と言われて、お客さんが店に来ているのにずっとエビの皮をむく作業をやらされて。「あれ?おれ、メニュー表覚えてきたのに注文も取らずに、なんで、こんな作業をずっとやってんねやろ?」とか思いながら30分ぐらいやっていたら、店長が来て、僕のエビの皮剥きの量を見て、「お、自分、真面目やな。合格!」
なんとこれが面接だった。正直、びっくりしましたが、「あ、なるほどな」となったんですわ。それまで9年間、小学校中学校と学校教育を受けてきたけど、世の中というか社会のシステムはこういう風に動いているんだなというのがわかった。学校みたいにテストで「問1」みたいな問題なんてでーへんのよ。世の中は全くそんな風には動いてない。社会に出ると常にテストというか、24時間、問われ続ける。それに対して自分で考えて、行動して、結果を出せば、それが形になり、認められる。そう直観したわけです。
それで学校のテスト勉強、受験勉強よりも実社会、アルバイトのほうがリアルで面白いわ!ってなって勉強のつもりでアルバイトを始めました。世の中、何が求められているのか?を学ぶにはアルバイトのほうがいいと感じて、「世の中の様々なアルバイトを100個やろう!」って決めたんです。色々なバイトを経験し、どのようにして店が構成されているのか?組織の編成とか、業務内容のシステムなどを覚えたらやめるというのを繰り返しました。15~22歳までいろんなアルバイトをやりまくって約70以上のアルバイトを経験しました。結局、100はいってないんですが(笑)、でも、このときの経験は40代の今にもめちゃくちゃ活きてます。アルバイトで様々な業界に触れたから、いまでも、どういう業界の話でも、すぐ「状態」や「流れ」や「雰囲気」などがわかる。これが22歳ぐらいまでだったかな。
―22歳からはどのように過ごされましたか?
陸奥:22歳ときに、あるラジオ局のADのアルバイトが募集されていて、その面接に行きました。面接官のプロデューサーがいろいろと話題豊富な人で映画話や演劇話で盛り上がり、「君は作家向きな人間や」と言われたんです。それで面接官の知り合いの放送作家を紹介され、放送作家さんにアポをとって会いに行きました。こんときに自分が放送作家になったらどんな番組を作りたいのか?というのを10個ほど企画案を考えて持って行ったんです。どれも大した企画案ではなかったですが、意欲が買われたようで、それから一週間も経たないうちに某テレビ局に呼ばれて、いきなり企画会議に参加しました。
そこから27歳ぐらいまでテレビ業界で仕事をしていましたが、当初はベテランの先輩たちの使いぱっしりで、ゴーストライターをしていました。僕は器用なところがあって、いろんな先輩の文章の特徴や特性やクセやギャグを把握して、本人みたいに書くことができたので「ゴーストライターの天才」とか言われました(笑)ただ自分でいざ文章を書くとなった時に自分の文体が分からなくなったんです。自分で書いた記事がこれは○〇先輩っぽいなーとか感じると妙なスランプになってしまい……。給料も安定せず、一気に入るときもあれば全く入らないときもありました。それでいてやたらと忙しいから慢性的な睡眠不足の状態で。あるとき熱が出て「あれ?ちょっと風邪かな?」と思ったら一気に悪化させて高熱が出てマイコプラズマ肺炎になり、倒れてしまったんです。一か月ぐらい仕事を休み、復帰しましたが半年もたたずに再発して。医者にカラダを調べてもらったら白血球数の数値などが異常で、「きみ、免疫力ゼロやで。寝てる?死ぬよ。」といわれ、27歳の時に業界の仕事はすべてやめました。
仕事をやめて、ふと自分のことを振り返ったら、お金もないし、学歴もないし、キャリアもないし、形になった仕事もないし、ほんまに何もないような状態で。大抵の人間だったら焦ると思いますが、僕は結構、平気で(笑)まず初めに名刺を作りました。「ライター、編集、ジャーナリスト」とか大袈裟なことを記載して(笑)それで、いろんな人と会い、名刺交換をして、ブログを立ち上げたりして、そこで当時、僕が興味あった大阪の祭り、関西の祭り、日本全国の祭りを取材して記事をアップしたりしました。そういう活動を続けていると「お祭りブロガー」のようになって、いろんな人からお仕事をいただきました。そのうち東京の出版やウェブメディアの会社、メールマガジンの配信サービスサイトの会社の人たちと知り合い、仲良くなって、仕事をもらったりするようになりました。
オープンソースで仕掛けや遊びを作ってそれをばらまく
―そこから現在のお仕事に繋がっていったということですか?
陸奥:その後、ひょんなことでAll About (オールアバウト)っていうインターネットの専門ガイドでお祭り情報のガイドを募集していることを知って、そのガイドになりました。ところで、お祭りの情報を手に入れるにはどうしたらいいと思う?現地に行く?それもいいんだけどお金がかかるでしょ?なるべく効率よく情報を仕入れたいから、それで情報を得るために日本全国各地の観光協会にリサーチで電話するようになって。そうやって観光業界の人たちと仲良くなっていったんです。そのうち観光を取材するよりも、観光の担い手になりたくなったんです。観光の現場の人たちは意外とメディアについてわかっていないから自分たちのアピールがうまいことできていないと感じてね。それならメディアに関わってきた自分の特性も活かせるのでは?と考えたわけです。
それで、日本全国のいろんな観光のプロジェクトを独自で調べているうちに「コミュニティツーリズム」(※1)という概念というか考え方に出会いました。これは要するに、まち歩きのプロジェクトで自分たちのまちを自分たちで歩いて楽しもうというツアーです。地産地消の観光で、これはおもしろい!と思い、それを堺や大阪でできないか?と考えて活動しはじめました。堺探検クラブというNPOを作ったり、いろんな人と出会っていると大阪市に活動が知られて、それで「大阪あそ歩」(※2)に携わることになりました。港区、築港のまち歩きを作るさいに、そこでアサダワタル先生(坂倉の指導教官/プロデュースゼミ担当)とも出会ってます(笑)
その後、2011年に東日本大震災が起こると、大阪だけで活動するのではなくて、もっと広範囲に、いろんなコミュニティに携わる仕事やプロジェクトがしたいと思い始めました。それで「他者と出逢う」をテーマに僕なりの「遊びの仕組み」を作って、それをオープンソースでばらまくということをはじめました。僕が「コモンズ・デザイン・プロジェクト」と銘打ってやっている「まわしよみ新聞」「直観讀みブックマーカー」「当事者研究スゴロク」「死生観光トランプ」などがそうです。「いつでも、どこでも、だれでもできる」が合言葉で、全部、使用料は無料というか、勝手に自由に使ってもいいですよというプロジェクトです。これを始めたら、ありがたいことに、本当に日本全国の人が、僕の考案した「遊び」を使って、場作りや人作りをしてくれて……。全部、使用料は無料だから、お金にならないし、生活は大変なんですが、でも「こういう変なこと(笑)をやっている陸奥賢という人間は何者だ?」と興味を持つ方も世間にはいて。そういう方々に声をかけられて仕事や企画の依頼などがあったりしました。ただ僕が手掛ける一連のプロジェクトは「他者と出逢う」「人と人を結びつける」というアナログのツールなので、人と出会うことを禁じられたコロナの時は大変でした。あらゆる仕事の依頼がなくなり、止まり、文字通り、お金がなくて死にかけたんですが、いろんな人に寄付などで助けてもらい、そのうちコロナが収まって、なんとか生き延びました。その後、東日本大震災以降、よく仕事で訪れていた福島県いわき市の方から「自転車ツアーのプロデューサーになってくれませんか?」と声がかかり、「いわき時空散走」というプロジェクトを2023年に始めて今に至る……という感じかな。
―遊びを作るときに心がけていることは?
陸奥:僕自身が面白そうと感じるかどうかを大事にしてます。僕自身が熱中しないと遊びにならないですから。熱中できるほどの面白さがないといけないなと常に思ってます。あと「学び」「遊び」ということをよく考えたりもしました。「学」の語源は「まねぶ」からきていますが、「遊」の語源は「それ」だとか。要するに「それていく」「逸脱する」ということです。学びが「守」なら、遊びの本質は「破」であり「離」だと思ってます。自由だと思っている。あとアサダ先生の「日常再編集」(※3)という言葉は好きですよ。まわしよみ新聞はアサダ先生の活動に影響されています。
―どうなったら「面白い」と感じますか?
陸奥:想定したものが変わっていく。逸脱していくと面白いと感じます。いろんな人が携わって可変していくことで新しいものが生まれていく。まわしよみ新聞を経験した人たちが編集の面白さや場づくりの面白さに気づき、そのエッセンスや考え方、方法論を取り入れて、新しいことを模索したりしています。違うことを始める入口や気づきになっている。こういうのは、僕の想像を超えているし、いろんなところに影響を与えているようで嬉しいし、ありがたいですね。ただ、一連のコモンズ・プロジェクトや僕の仕事はすべてそうなんですが、いろんな人たちの言葉や仕事や生き方などが僕に影響を与えてくれて、その結果でできたものなので、自分のものではないという感覚が常にあります。そういう意味でぼくはアーティストな人間ではないと思ってます。自分の仕事、作品にあまり愛着がないんです(笑)。自分の手を離れて、みんなのものになっていったということが嬉しいです。

誰のものでもないし誰のものでもある。
―自身の肩書の観光家、コモンズデザイナーというお仕事について気になったんですけど
陸奥:コミュニティは同質者、同一性の集団といえます。例えば会社の仲間、サークルの仲間、学校、家族、趣味仲間とかね。こうしたコミュニティを作る、考えることはとても大事なことです。人はコミュニティがないと寂しくて死んじゃいますよ(笑)しかしコミュニティ主義の問題は内向きなことです。皆、自分のコミュニティが良ければそれでよいと思っていたりする。でも世の中の問題はコミュニティを超越して、自分のコミュニティ外の人間……つまり他者に対して何ができるか?ということを考える発想、目線を獲得しないといけないのではないかと思うわけです。だから他者を考える時間や、他者と出会う場所を作ろうと思うわけです。コモンズとは異質な人たちが行きかう場所であり、自分とは違うコミュニティの人と出会う場所です。誰のものでもないし、誰のものでもある。
コモンズは「入会地」とか「共有地」とか訳すこともありますが、そもそも果たして世の中に私有のものなんてあるのだろうか?と感じたりもしてます。たとえば日本語はいろんな人が作ってきて、いろんな人が使っている共有財産です。言葉に「これは俺が作ったものだから」なんて権利を主張して私有、占有してしまうと、そこで言葉の世界は終わってしまう。文化というのは常に解放され、他者と共有されることによって育っていくものですよね。自分という人間存在の世界観もいろんなものから影響を受けて構成されており、これは自分が考えたものと思っていても、なにかしらの有形無形の「他者」に影響を受けて生まれてきています。僕が、これまでやってきた活動も、僕という「ろ過」を通してはいるが、結局、それは僕のものではないという感覚があります。もともと社会の構成要素から生まれてきているものだから、それを僕が私有しようというのはおこがましいし、妙なことでは?と思ってます。人間死んだら、なにもあの世に持っていけないですから(笑)私有しているものなんかなにもないです(笑)

―キャリア(お仕事についての考え方)、人生の考え方について、陸奥さんは何を大切にしていますか?
陸奥:自分の仕事は、誰かが見てくれているので、一つ一つ、目の前の仕事を真剣に、大事にする。いろいろと試行錯誤して、形にならないことも多々あります。失敗はアホほどあります(笑)でも、やったことは絶対に自分の経験や糧になって次につながるので。ただモノを作るというだけではない時代になってきているし、売れるものが良いという時代でもなくなってきています。企業活動ももはやお金ではなく地球環境にどれだけ貢献しているか?といったことにシフトしつつある。サスティナブルでないとやっていけない。サスティナブルって、持続可能性って、要するに循環であり、助け合いだと思うんですよ。なるべく人を手助けしたいなあと思ってます。助けて、助けられて、生きる(笑)
―私たち世代へのアドバイスは何かありますか?
陸奥:友達をいっぱい作っておくとよいですよ。僕は全く出世しませんが、僕の周りの人たちはどんどん出世していく人もいて、そういう人たちがありがたいことに僕に仕事をくれたりします(笑)これまでの活動もいろんな人たちと交流してきた賜物です。ひとりでは何もできない。大学、会社、趣味のサークルなど、助け合える人たちをいっぱい作っておくとよいと思います。あと失敗を恐れずに。若いうちの失敗は許されます。でも年をとっても失敗してもいいし、実際に失敗するから(笑)僕はコロナの時は禿げるかと思いました(笑)
―これからの展望ややりたいことはありますか。
陸奥:特に展望はないです。目の前のことをやるだけで。ある意味、いつ死んでもいいなぁという感覚でいます。でも、なるべくサスティナブルな社会を作り、そのバトンを、若い人たちに渡していきたいかな。がんばってください(笑)
―ありがとうございました。
おわりに
今回インタビューを通して感じたことは「しっかり目の前のことを考えてする」ということだ。陸奥さんのこれまでのキャリア、考え方を聞いていると常に考えて行動をされているなと感じた。私自身、現在就職活動を行っている身であり、将来について考える機会が増えている。自分がやりたいことは何なのか、求めるものは何なのか、将来をどのように形成するか。常に思考するということを止めず、向き合っていきたいと強く感じた。
※1 コミュニティ・ツーリズムとは、地域コミュニティが主体となり、地域の歴史や文化、産業、暮らしなどを守りながら、それらを観光コンテンツとしてもアピールし、地域の活性化を目指すツーリズム形態のことをいう。海外ではオーバーツーリズムの緩和にもつながると考えられており、持続可能な旅として近年注目を集めている。CBT(Community Based Tourism)とも呼ばれる。
(出典 https://ideasforgood.jp/glossary/community-based-tourism/
※2「大阪あそ歩」は、大阪あそ歩は2008年に開始された大阪市の地域住民観光事業。「まち歩き」事業の一環で、市民ガイドが大阪市域を案内している。(出典 https://ja.wikipedia.org/wiki/大阪あそ歩)
※3 記事担当の坂倉の指導教官であるアサダワタルが、2010年代に提唱していた考え方。以下のリンク先などを参照。https://www.nettam.jp/column/86/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
