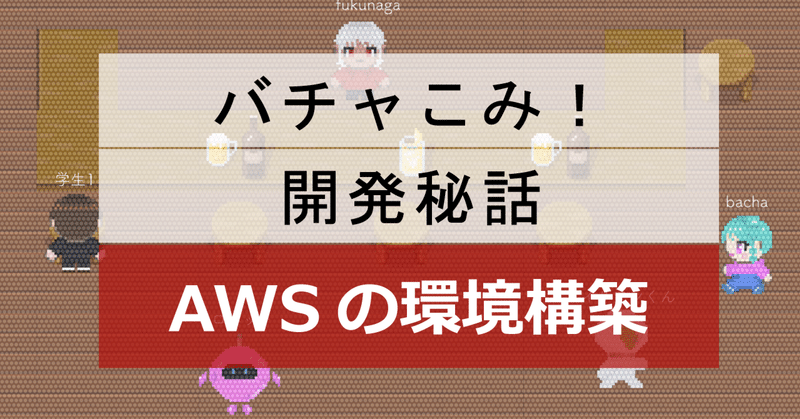
第1回:AWS(Amazon Web Services)とは?
AWSとは?
AWSとは「Amazon Web Services」の頭文字で、Amazonが提供している企業向けのクラウド型のWebサービスのことです。
特徴
クラウド型のサービスは言い換えるとコンピューティングリソースを切り売りすることです。従来のように自前でサーバーやネットワーク機器を購入・設定することなく「使いたいときだけ」リソースを使用し「使った分だけ」料金を支払えばよいのがAWSの特徴です。
最新の技術をリーズナブルに利用できる仕組み
まず、みなさんは「規模の経済」という言葉をご存じでしょうか?
規模の経済とは、
生産の規模が大きくなればなるほど製品1つあたりの平均コストが下がる状況のことです。AWSも大規模なコンピューティングリソースをたくさんのユーザーに切り売りすることで、サービスあたりの単価を低くして提供しているのです。
利用するメリット
サーバーのスペックやストレージの容量変更が思いのまま
実際のAWSサービスの利用状況に応じて、サーバーのスペックを上げたり、逆に下げたりという変更が簡単にできます。過不足のない運用が可能です。
使った分だけ料金が発生する従量課金
AWSのサービスは時間あたり、処理件数あたりのコストによる従量課金制になっており、初期費用はかかりません。無料利用枠が設けられたサービスもあります。
ユーザーの急な増加にも対応
AWSのサービスはオートスケーリングという機能を使ってWebサイトやWebアプリケーションを利用するユーザー数の増減に応じて利用枠を自動調整できます。不特定多数のユーザーが出入りするWebアプリケーションでは、安定してサービスを提供するために必須の技術と言えます。
最後に
江戸時代、越後屋(現在の三越)を日本一の呉服商に押し上げた三井高利(みついたかとし)という人は、それまで格式の高い呉服屋ではご法度とされていた反物の切り売りによって顧客のニーズをつかみ成功したと言われています。当時、反物は基本的に1反という単位で販売され、切って短くなれば価値がなくなってしまうとみなされていました。ところが高利は現金前払いという条件で顧客が欲しい分だけ反物を切り売りし、すぐに仕立てて渡すサービスをはじめました。そして、残った半端な生地はセールで売って損切りする。そのやり方で商品在庫の回転スピードを上げて、常に新しい商品が店頭に並ぶ状況をつくり出しました。三井高利は損して得取れの手法で越後屋を日本一の呉服屋に押し上げたのです。
越後屋とAWSは「切り売り」という販売手法で顧客のニーズをつかみ、どんどん新しいサービスを展開して付加価値を高めていった点が似ていると思います。一般的にはクラウドサービスはコスト削減という切り口で語られることが多いようですが、実際にはビジネス判断の迅速化に真価を発揮するといわれます。AWSの導入もまた「損して得取れ」が本質なのかもしれません。
このシリーズ記事では今後もバチャこみ!を支えるAWSの技術について発信していきたいと思っています。
